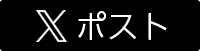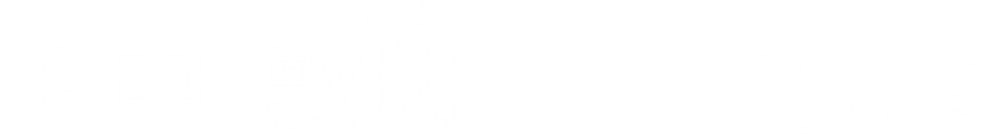2024年06月19日 環境水道委員会
令和 6年第 2回環境水道委員会
環境水道委員会会議録
開催年月日 令和6年6月19日(水)
開催場所 環境水道委員会室
出席委員 8名
三 森 至 加 委員長 山 本 浩 之 副委員長
寺 本 義 勝 委員 木 庭 功 二 委員
筑 紫 るみ子 委員 田 中 敦 朗 委員
高 本 一 臣 委員 西 岡 誠 也 委員
議題・協議事項
(1)議案の審査(2件)
議第 150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」
議第 178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」
(2)所管事務調査
午前10時03分 開会
○三森至加 委員長 ただいまから環境水道委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部において人事異動があっておりますので、順次紹介をお願いいたします。
〔執行部自己紹介〕
○三森至加 委員長 以上で、紹介は終わりました。
これより本日の議事に入ります。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件、その他1件の計2件であります。そのほか、陳情1件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申出のあっております報告7件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎岩本清昭 首席審議員兼総務課長 委員会資料、上下水道局・資料1をお願いいたします。
私からは、議第150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
小学1年生~小学6年生まで、障がいがある子の場合は18歳まで、1日に2時間の範囲内で無給の休暇が取得できる子育て支援時間の導入に伴う規定の整備等を行うため、当該休暇の追加など所要の改正を行うものです。
今議会で交通局及び病院局においても同様の改正が行われます。
資料1、3~6ページに新旧対照表をつけております。
説明は以上でございます。
○三森至加 委員長 次に、議第178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」の説明を求めます。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 私からは、議第178号について御説明いたします。
環境局・資料1を御覧ください。
議第178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」は、地方自治法第289条の規定により、山鹿市と協議し、同法第290条において議決が必要となりますことから、本定例会において議案を提出するものでございます。
資料の3ページ目を御覧ください。
対象となる施設でございますが、北区植木町にあります山鹿植木広域行政事務組合のリサイクルプラザになります。リサイクルプラザについては、山鹿市と植木町の資源物の中間処理を行っていた施設でございますが、平成15年の供用開始以来、長年の稼動により設備が老朽化し、その改修費用に多額の費用がかかることから、令和4年度末をもって閉鎖いたしております。
財産処分についての内容でございますが、対象としては、リサイクルプラザの土地と物品の2点でございます。
まず、土地につきましては、事務組合で建物を解体した後、更地にして熊本市に帰属させるものでございます。また、物品につきましては、2トンダンプ、ショベルローダーやフォークリフト、その他、机、椅子等の事務用品になりまして、こちらは事務組合への帰属となります。
ただいま御説明いたしました財産処分の内容につきましては、山鹿市との協議書として資料の2ページ目にお示しいたしております。
なお、当議案につきましては、山鹿市議会との同文議決案件となります。
また、参考になりますが、リサイクルプラザの跡地利用につきましては、現在、熊本市公文書館建設の検討がなされておりまして、本定例会の予算決算委員会総務分科会において、関連予算の審議と併せ公文書館の整備基本計画(案)について報告予定となってございます。
説明は以上でございます。
○三森至加 委員長 以上で、議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。
ありませんか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
これより、所管事務調査を行います。
執行部より申出のあっております報告7件について、順次説明を聴取いたします。
◎宮邊謙太郎 経営企画課長 環境水道委員会資料、青色の上下水道局をお願いいたします。
私からは、報第14号、水道事業会計及び報第15号、下水道事業会計の予算繰越計算書につきまして、一括して御説明いたします。
資料2の1ページをお願いいたします。
まず、1、令和6年度(2024年度)への繰越額でございます。
表の中央の列、繰越Aでございますが、こちらは地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和5年度の事業予算を令和6年度に繰り越すものでございます。また、表の右側の列、繰越Bでございますが、これは、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越しであり、令和5年度に繰り越していました令和4年度の事業予算をさらに令和6年度に繰り越すものでございますが、今回は該当はございません。表の左側は、繰越Aと繰越Bの合計になります。
次に、繰越しの内容でございますが、水道事業につきましては40件、20億8,744万3,000円でございます。下水道事業につきましては71件、54億13万8,000円でございますが、国の緊急対策に伴う補正予算の関係により、本年2月補正に前倒しした分3億5,173万円が含まれております。
次に、2、繰越の理由でございます。
主な理由ごとに分類しておりますが、件数の割合で多い順に見ますと、水道事業会計につきましては、ア、関係者等との協議に時間を要したものが30%、イ、他工事等の進捗の調整に時間を要したものが30%、ウ、埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したものが23%でございました。また、下水道事業会計につきましては、ア、関係者等との協議に時間を要したものが37%、イ、他工事等の進捗の調整に時間を要したものが22%、ウ、埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したものが18%でございました。
2ページには、水道事業、下水道事業の繰越予算の金額及び件数の推移を掲載しております。
また、3ページ以降は、水道事業会計及び下水道事業会計それぞれの予算繰越計算書と、これらの附属説明資料としまして、繰り越しした事業の一覧を添付しております。繰越しの理由に加え、前払い額、工期や入札の不調、不落の状況も記載しておりますので、御覧いただければと存じますが、工事費の支払いにつきましては、公営企業会計上の取扱いで分かりにくいところがございますので、簡単に御説明いたします。
4ページをお願いいたします。
水道事業会計の繰越計算書でございますが、支払い義務発生額の列でゼロ円となっているところがございます。この支払い義務発生額の欄には、繰越しの対象となりました事業の一部につきまして、完成検査が終了したものが計上されることになっておりますが、実際に全く支払いを行っていないということではございません。
5ページをお願いいたします。
付属説明資料を御覧いただきますと、表中に、うち前払額という列がございます。これは、前払い金の額でございますが、発注しました工事が円滑、適正に行われるよう請求があった分の前払い金を支払っているものでございます。この前払い金につきましては、工事の完成検査を行っておりませんので、額としましては、繰越額に含まれているということでございます。
下水道事業会計の繰越計算書も同様でございます。
説明は以上でございます。
◎戸澤角充 環境推進部長 私からは、熊本市第8次総合計画、令和6年度アクションプランについて御説明させていただきます。
共通資料①をお願いいたします。2ページの図を御覧ください。
熊本市第8次総合計画の基本構想、基本計画につきましては、第1回定例会において議決いただき、4月より本計画をスタートさせたところでございます。本アクションプランは、図の赤囲みになりますが、総合計画を構成するものであり、当該年度の重点事項、各ビジョンにおける主な取組、実施計画の3つで構成し、毎年度策定、公表することとしています。
恐れ入ります、3ページをお願いいたします。
第8次総合計画の着実な推進に向けたマネジメントサイクルを記載しております。年間を通して第8次総合計画に掲げる8つのビジョンについて、事業の進捗状況や行政評価の結果を踏まえた課題の把握、分析を行い、必要な施策展開のための調整や協議・企画・立案を行います。特に、国の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえた新規拡充施策については、当初予算編成時におきまして、十分な検討を行うとともに、必要に応じて補正予算での対応を行うこととしております。また、その検討に当たっては、庁内において緊密な連携の下、課題の共有と調整を図ってまいります。
これらを基本的な考え方としながら、年度当初にアクションプランの策定、行政評価を行い、その結果や当該年度上半期の進捗などを踏まえて、10月以降の次年度予算編成作業において、予算編成方針と次年度アクションプランの重点項目との整合や当初予算のポイントと各ビジョンにおける主な取組との同一化等を図って、次年度以降の取組につなげてまいりたいと考えております。
なお、第8次総合計画に基づく行政評価は、来年度より運用を開始する予定であり、現在その仕組みについて検討を進めているところでございます。
恐れ入ります、6ページをお願いいたします。
重点事項でございます。本市の最重要課題である人口減少への対応に力強く取り組み、希望ある未来を築いていくため、こどもを核としたまちづくりを進めるとともに、半導体関連企業の熊本進出を好機として、地域経済の発展を促進し、魅力あるまちづくりを行っていく必要があることから、令和6年度はこども関連施策の推進と半導体関連企業の熊本進出に伴う諸課題への対応を重点事項として設定しております。
なお、7、8ページに、重点事項についてそれぞれの令和6年度の主なアクション等を記載しております。
次に、9ページ以降でございますが、基本計画に掲げる8つのビジョン及び区における自主自立のまちづくりにおける令和6年度の主な取組を記載しております。環境局の主な取組について御説明させていただきます。
恐れ入ります、18ページをお願いいたします。
ビジョン2、市民に愛され世界に選ばれる、持続可能な発展を実現するまちにおきまして、環境局では、「くまもと水ブランド」の情報発信に努めてまいります。
恐れ入ります、25ページをお願いいたします。
ビジョン5、豊かな環境を未来につなぐまちにおきまして、地下水涵養の促進や水源涵養林の整備、地下水及び公共用水域の水質の監視強化により、引き続き地下水保全に取り組んでまいります。また、環境保全の推進のため、(仮称)環境影響評価条例を制定いたします。最後に、脱炭素の推進として、熊本連携中枢都市圏における脱炭素化事業の加速化や、省エネ家電等を導入する個人、事業所への補助に取り組んでまいります。
環境局からは以上になります。
◎江藤徳幸 総務部長 引き続き、上下水道局分の主な取組を御説明いたします。
資料の31ページをお願いいたします。
ビジョン7、安全で良好な都市基盤が整備されたまちにおける上下水道局の取組としまして、一番下になりますが、水道100周年記念事業を実施いたします。具体的には、令和6年11月27日に通水100周年を迎えることから、感謝・誇り・誓いに信頼を加えた4つのキーワードをコンセプトに、記念式典や併設イベント等の記念事業を実施いたします。また、これらの事業を通じて様々な世代の方たちに、地下水の恩恵を実感していただく持続可能な水道事業の実現に資するよう取り組んでまいります。
次に、共通資料②、第8次総合計画アクションプラン(実施計画)(案)をお願いいたします。
実施計画では、各ビジョンの施策を構成する基本方針ごとに、検証指標や事業等を掲載しております。今後のスケジュールとしましては、本日の御意見を踏まえまして、7月までに策定、公表させていただく予定といたしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◎住谷憲昭 環境政策課長 環境局・資料2を御覧ください。
(仮称)熊本市環境影響評価条例の基本的事項についてでございます。5ページまでは、前回の第1回定例会にて報告させていただきました条例制定の背景や、検討事項等について再度記載しておりますので、追加事項のみ報告させていただきます。
おめくりいただきまして、4ページをお願いいたします。
令和5年度に環境審議会へ諮問し、審議の結果、以下に記載しております①~③を条例の基本的事項として定めることが必要との答申を令和6年3月27日に受領いたしました。令和6年度は、この①~③の具体的検討に加え、④の環境影響評価の調査、予測及び評価の方法について検討してまいります。
続きまして、6ページをお願いいたします。
まず、基本的事項1点目の手続方法についてでございます。本市条例では、図に記載しておりますA~Hの手続、全てを採用する予定でございます。本市が導入を予定しておりますBのスクリーニングとは、事業特性や地域特性、事業実施による環境への影響を考慮し、評価手続を行うかどうか判定するものでございます。手続の課題といたしましては、規模要件のみによる手続の一律義務化により、建て替え等の環境負荷が小さくなる場合でも手続を求めていることや、手続に要する期間が3~4年と長期にわたり、多額な費用が発生するなどの課題がございます。このスクリーニングを導入することにより、手続の要否を適宜判断できることや、事業者に対し環境負荷の低減について検討を促すこと、また、手続が不要となった場合は、事業着手までの期間短縮や費用の削減につながると考えております。熊本県におきましても、本年9月頃をめどに、このスクリーニングを導入する予定とのことでございます。
7ページをお願いいたします。
基本的事項2点目の地域区分についてでございます。自然環境など本市の地域特性に応じて、より環境への配慮が必要な地域として、以下に記載しております①県立自然公園~⑥史跡・名所・天然記念物と6つの地域を指定地域に設定し、一般地域よりも環境配慮を求めることとしております。
8ページをお願いいたします。
基本的事項3点目、対象事業の種類と規模要件でございます。国・熊本県・熊本市それぞれの対象事業を記載しております。熊本県の対象事業は、熊本市域内において事業実施の可能性があるため、全て本市の対象事業とし、加えて大規模建築物等複合事業についても、本市の地域特性を踏まえ対象事業としております。
次の9ページには、大規模建築物を対象事業に追加する必要性について記載しております。本市においては、今後も都市開発により大規模な建築も想定されます。課題といたしましては、大規模建築物が周辺環境に与える影響といたしまして、工事中の騒音、振動、大気汚染や供用が始まった際の景観、日照阻害、電波障害、不具合などが考えられます。対象事業とする効果といたしましては、建築紛争等のトラブルを低減することや、重大な環境影響等の回避に加えまして、事業者に対して必要な措置を求めることができると考えております。
10ページをお願いします。
複合事業を対象事業に追加する必要性についてですが、個別では規模要件に満たない事業であっても、緊密に関連する2つ以上の事業が一体的に実施されることにより、課題に事例を記載しておりますとおり、個別の事業では規模要件25ヘクタール以上を満たさないものでありましても、レクリエーション施設20ヘクタール、土地区画整理事業10ヘクタール、合計30ヘクタールとなり、規模要件以上となる場合がございます。このように一体的に実施される事業や、複数の規模要件未満の切り分け事業のようなアセス逃れの事業に対しまして、複合事業と規定することにより、広く一定の開発行為に対して、適切に環境影響評価を求めることができるようになると考えております。
11ページをお願いします。
次に、本市対象事業の規模要件につきましては、一般地域の規模要件は県条例と同等といたしまして、より環境に配慮すべき指定地域は、原則一般地域の50%規模としております。指定地域の規模要件を強化することで、指定地域から一般地域へ開発が誘導される効果を記載しております。
次の12ページは、事業の種類ごとに一般地域と指定地域の規模要件につきまして、それぞれ記載した一覧表となっております。
13ページをお願いします。
最後に、今後のスケジュールでございますが、現在、環境影響評価技術指針等検討委員会において、条例案の検討を進めており、秋頃をめどにパブリックコメントを実施し、御意見に応じて条例案の修正を行い、令和7年第1回定例会への議案上程を目指し取り組んでいるところでございます。第1回定例会におきまして御承認いただけますならば、この条例は全国の事業者が対象となることから、条例公布後は、広く周知広報を行い、同年10月の条例施行を目指してまいります。
なお、参考資料といたしまして、令和6年3月27日に環境審議会から受領いたしました答申書及び熊本県が条例を制定した際に作成したパンフレット等を添付いたしております。
報告は以上となります。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 私からは、プラスチックの一括回収実証実験について御説明申し上げます。
環境局・資料3を御覧ください。
本市では、プラスチック製容器包装については、分別収集及び再資源化を行っております。一方、プラスチック使用製品については、燃やすごみとして収集し、環境工場で処理を行っているところでございます。
では、プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品の違いは何かということでございますけれども、資料の右側の画像を御覧ください。画像上段のプラスチック製容器包装につきましては、ラーメンの袋や食品トレーなど商品そのもののことではなく、商品の容器や包装のことでございまして、目印としてプラマークがついているものがこれに該当いたしております。一方、プラスチック使用製品につきましては、資料右下の画像になりますが、これまで燃やすごみとして出していただいておりましたスプーンや洗面器、食品タッパーやハンガーなど製品そのものがプラスチックというものがこれに該当いたしております。
概要・目的でございますが、令和4年4月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。この法律によって、市町村に対しプラスチック製品廃棄物の分別収集及び再商品化が求められることとなりました。今回の実証実験では、今後の方針を検討するため、プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品を一括回収し、収集運搬や再資源化等にかかる費用及び事業効果の検証を行うこととしております。
次に、実施内容でございます。実施期間は、令和6年8~9月までの2か月間、実施地区は春日校区で約4,000世帯を対象に行う予定でございます。一括回収の対象品目としては、画像にございますプラスチック製容器包装とプラスチック使用製品となります。また、対象外の品目になりますが、間違いやすい例の一つとして、ペットボトルについて申し上げます。この製品につきましては、キャップとラベル、そしてペットボトル本体に分別できますが、まずキャップとラベルについてはプラスチック製容器包装として、今回の実証実験の際に一括回収いたします。一方ペットボトル本体は、今回の実証実験の対象とはならず、従来どおりペットボトルの日に別途回収させていただきます。
次に、資料の2ページを御覧ください。
上段に実証実験のイメージを記載しております。期間中、春日校区の皆様にはプラスチック製容器包装の収集日に、従来のプラスチック製容器包装に加え、プラスチック使用製品と併せて同一の45リットル以内の透明袋でごみステーションに出していただくことになります。一括回収したプラスチックは、その後、民間施設において選別、再資源化、組成分析などを行います。
スケジュールについては、お示ししているとおりでございまして、実証実験終了後は検証を行い、今後の方針を決定する予定でございます。
最後に、春日校区の皆様へ周知用のリーフレットとしまして、別添の資料3-①を添付いたしております。こちらは、6月下旬~7月にかけまして、自治会の回覧をお願いするとともに、春日校区内の全ての御家庭に配布予定でございます。
説明は以上でございます。
◎戸澤角充 環境推進部長 資料4をお願いいたします。
先月5月18日~25日にインドネシア、バリで開催されました第10回世界フォーラムに参加いたしましたので、御報告させていただきます。
まず、1、フォーラムの概要でございます。本フォーラムは3年に一度、世界中の水関係者が一堂に会し、水と衛生に関わる様々な問題について議論する世界最大の水の国際会議でございます。今回は繁栄を共有するための水というテーマで開催されたところでございます。
恐れ入ります、2、会議等への出席状況を御覧ください。会議開催期間の20~24日において、大西市長が以下の6つの会議に出席いたしました。主なものといたしまして、21日に開催されました、インドネシア政府主催のバンドン・スピリット・ウォーター・サミットでは、各国首脳の発言に対して、市長が本市のこれまでの水保全の取組を踏まえコメントいたしました。また、24日に開催されました水災害リスクを軽減するために必要な資金・ガバナンス・能力開発・制度の最善化に関するセッションでは、市長が健全な水循環と流域防災に向けた熊本市の取組について発表し、世界が学ぶべき事例として高い評価をいただいたところでございます。
恐れ入ります。2ページをお願いいたします。
3番目は、各セッションの様子でございます。
最後に4、総括といたしまして、3つ目の丸の部分でございますが、今後も熊本の貴重な地下水を守るための取組を進めるとともに、本市の取組を世界に発信することで、本市の国内外での認知度向上はもとより、世界の水問題解決に貢献してまいります。
説明は以上でございます。
◎宮邊謙太郎 経営企画課長 環境水道委員会資料、青色の上下水道局・資料3をお願いいたします。
私からは、工業用水道取水2号井の調査結果を御報告いたします。
資料3の1ページをお願いいたします。
まず、工業用水道取水2号井内部調査についてでございます。
1、調査の目的でございますが、令和5年5月、工業用水道の3本の井戸のうち2号井の取水ポンプに故障が発生し、工業用水の供給に支障はなかったものの、2号井が予備水源として重要な役割を持っていたこと、また、施設整備から30年が経過していたことから、井戸本体の劣化も想定し、内部調査を実施したものです。
次に、2、調査の概要でございますが、令和5年第3回定例会で議決いただきました補正予算1,000万円に対し、契約額953万8,940円、調査期間を令和5年12月25日~令和6年2月28日としまして、取水ポンプの引上げ、水中カメラによる井戸内部の調査、井戸内部の清掃を実施いたしました。
3、調査結果でございますが、井戸内部に破損はなく、水質は条例で規定する基準に適合しておりました。また、故障した取水ポンプはメンテナンスにより機能が回復しまして、2号井は当面の運用に支障がないことを確認しました。
次に、「工業用水道使用についてのアンケート」実施についてでございます。
1、実施の目的でございますが、安定した水供給のための設備の維持及び更新計画を検討するため、将来的な使用水量及び水質の条件についてのアンケートを実施したものです。
2ページをお願いいたします。
実施の概要でございますが、城南工業団地入居企業全15社に対し、将来的な使用水量の見込みと受水の水質条件を調査しました。
3、アンケート結果まとめでございますが、将来的な使用水量については、企業の事業活動に左右されるところが大きく、今回、確定できておりません。また、水質については、条例に規定する基準で問題はありませんでした。
次に、工業用水道の今後について(案)でございます。
資料には、今後の流れのイメージを掲載しておりますが、引き続き将来的な水需要量の把握に努め、併せて水需要量、水質に合わせた工業用水道施設の維持及び更新計画を策定し、費用の最小化を図ってまいります。
最後に、参考として、工業用水道の概要を掲載しております。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○三森至加 委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び所管事務について質疑及び意見をお願いします。
◆木庭功二 委員 すみません、説明にはなかったんですけれども、所管ということでちょっと聞かせていただきたいと思います。
令和6年度のアクションプラン(実施計画)(案)の資料98ページになるんですけれども、脱炭素戦略課が所管になるかと思うんですけれども、2番の市有施設LED化整備経費ということで、今年度の予算が約6億9,928万円で計上されているかと思います。それで、本市としては令和2年度から市有施設のLED化を一斉に行うということで、2期的に取り組んでこられたかと思うんですけれども、その中で、公表されているデータによりますと、今、約94%ぐらいの施設がLED化の実施がされましたということでした。これ確認なんですけれども、残りの大体6%の市有施設をこの約6億9,928万円の予算でLED化していくということでよろしかったでしょうか。教えていただければと思います。
◎兼平進一 脱炭素戦略課長 アクションプランに書いておりますLED化の整備経費につきまして、これまで整備してきたLED化の費用についてですけれども、整備の方法としまして、リース方式を採用しておりまして、整備から8年間のリース代を払うこととしております。そのため、このリース代がここの事業費になっているというものでございます。ちなみに、今、市有施設のうち94%がLED化済みということなんですけれども、残りの6%というのが、今後建て替え等が検討されている施設ということで、除外したものでございますので、今後建て替え等のタイミングで検討されていくものでございます。
以上でございます。
◆木庭功二 委員 ありがとうございました。6%は建て替えの施設ですね。今後されていくということでした。ありがとうございます。
水銀に関する水俣条例は策定されまして、2027年までに蛍光灯の製造禁止ということになっているかと思うんですけれども、今後、ほかの自治体でLED化が進んでいないところでは一気にLEDの需要がでてくるかと思いますので、6%ということでありますけれども、その後、LEDの調達に関しては、問題ないというか計画的に進められているということでよろしかったでしょうか。
◎兼平進一 脱炭素戦略課長 市有施設のLED化につきましては、昨年度、令和5年に策定しました熊本市役所脱炭素化イニシアチブプランの中にも、市有施設のLED化ということを掲げておりまして、その進捗につきましては、環境局が中心となって把握していこうと思っております。先ほど94%と話をしましたけれども、ほかにも道路照明であるとか、また学校施設でLED化していないところはまだございますので、その進捗についてはこのプランの進捗の中で把握していきたいと考えております。
以上でございます。
◆木庭功二 委員 御答弁ありがとうございました。
様々市営団地とか学校の施設とか、LED化になることで、皆さん大変喜ばれているところもあるかと思います。今後さらにCO2削減量の公表とか市民の皆様にこれだけの削減ができたとか、電気代のこれだけの削減ができたというような効果についても、しっかり情報公開をしていっていただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
◆筑紫るみ子 委員 令和6年度アクションプラン(案)の8ページの半導体関連企業の熊本進出に伴うというところで、ここに書いてある地下水及び公共用水の監視強化に関連して、実は先日、工業大学の教授の方と二、三人お会いしてお話を聞かせていただいたときに、熊本市はざる田があって、その下に多大な水のプールがあるということで、そこが今はずっと何千年もの間満水だったから、上のざる田、この岩盤の部分が落ちないで、今まで私たちの熊本市にきれいな水が供給されてきたということを聞いて、半導体専門の先生もその中にいらっしゃいまして、今からTSMCさんの第2工場ができていくとなると、相当今の想定量よりももっと使う量が本当は多いんではないかという懸念されていたんですね。そうなると、プールに空洞ができた場合に、上のこの岩盤が支えられていた水がなくなるということで、陥没するおそれもあるので、本当に懸念していると、九州のある何件かの工業大学の教授の方が口をそろえて言われまして、それが一番怖いので、とにかく湛水とかこの涵養事業でいつも下のプールが満タンになっているような施策をきちんと取っていただきたいという要望を言ってくれと言われまして、なので、熊本市が一番影響を受けるということで、その辺も今から重大な施策の一つとしてぜひ頭の隅に入れておいていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○三森至加 委員長 要望だけで。
◆筑紫るみ子 委員 質問というより要望です。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
◆田中敦朗 委員 同じ項目の地下水及び公共用水城の監視強化ということで、新たにPFOS、PFOA等の監視項目を追加するなどということで、PFOS、PFOAのことでちょっとお伺いしたいと思って手を挙げさせていただきました。
井芹川流域の方からPFOS、PFOAが検出されたというところで、今ずっと調査をしていると思うんですけれども、その原因の調査、原因の特定、どこら辺の地域からなど、今の進捗を教えていただければなと思いますけれども。
◎古上藤治 首席審議員兼水保全課長 ただいま御案内いただきました井芹川の方で昨年末、28地点で調査ところ、12地点で超過が見られたということで、それにつきましては、ほぼ上流域で、超過が見られております。
今の調査の状況としましては、その川に流れ込むいわゆる用水路であったり、いろいろな水源といいますか、流れ込みの部分がございまして、そこを今一つ一つ詰めて確認、検査をする作業を進めておるところです。原因究明に向けてという形で今、進めておりますので、こちらまとまり次第、また御報告させていただきたいと思っております。現状は、その調査を行っているということと、あと、現地の聞き取り、地歴調査も併せて行っているところでございます。それぞれ地形等が結構山あり谷ありの場所でもございますので、そういったところ、いろいろな可能性を考えながら、調査を進めているところでございます。いましばらくお待ちください。
◆田中敦朗 委員 前も申し上げたんですけれども、結局職員がやるにも限界があると思うんですよね。また、政令指定都市の中の河川でそういったPFOS、PFOAが検出されたというところで、私としては、前も申し上げたんですけれども、任せられるところは民間に任せたらいいのではないかなと思うんですよね。民間の方に様々な検査とか原因究明の委託をして、そういった調査を進めていただくと。もう一歩進めて、例えば環境省にも協力をお願いして、例えば河川でPFOS、PFOAが検知された場合は、どういった形で検査をすれば、原因特定ができるのかというのをモデルケースにするような方向で話をしていただいて、いろいろな支援をしていただくとか、そういったこともぜひ考えてほしいなと思いまして。
一政令指定都市であればこそ、様々な人員と予算が準備はできるとは思うんですけれども、こういったところがほかの自治体であった場合、その自治体ではちょっともうお手上げのときがあるんではないかなというような懸念もしていまして、ピンチはチャンスというか、熊本市で起こったからこそ、そういった、後に続くであろう様々な環境問題に対しての処方箋として、民間に委託するであるとか、どういった調査をして、どうやって特定していったのかというのも、ほかの自治体の参考になるような形でしっかり残していってほしいなというふうに思いますので、環境省の調査のことと残していってほしいということ、この二つだけお願いしておきます。
以上です。
○三森至加 委員長 ほかに。
◆高本一臣 委員 所管の2番の環境影響評価条例と、3番のプラスチックの実証実験でちょっとお尋ねさせていただきます。
まず、環境影響評価条例、アセス条例ですけれども、ここには記載されていないけれども、前回の資料では、もう既に全都道府県、そして政令市が熊本市を除く19市、その他に2市ということで68の自治体が制定されているということで、環境に非常に関心を今持たれている中で、そういう自治体の中で残念ながら最後というのは非常に思うところもあるんですけれども、一方では最後だからこそ、非常に機能するようなすばらしい条例になってくれればなというふうに思っています。その中で、ちょっと県と市の違いが2つほど追加されていますけれども、例えば面積について、土地区画整理事業や工業団地の造成事業あたりは、県では面積は25ヘクタール以上、それを市としては50%と要件の違いがありました。多分答申書の中でそういう意見が出たと思うんですけれども、それについて、私個人的には、もうちょっと制限をしてもいいのかなと思うんですけれども、その辺についてどういう根拠というか、答申からということなのか、あるいは何かちょっと協議もされたのか、その辺のところをお聞かせください。
◎住谷憲昭 環境政策課長 今、対象事業の規模要件に関する御質問でございますが、こちらにおきましては、本市が6つの指定地域を定めております。一般地域につきましては、熊本県と同様にしておりますが、指定地域については特に制限を設けていきたいということで50%規模、約半分にいたしております。これにつきましても、環境審議会の先生方に御提案いたしまして、先生方と意見を交わしまして、このような形で設定させていただいております。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ということは、指定地域と、この制限の数字あたりは、整合性がとれているという認識でよろしいんですか。
◎住谷憲昭 環境政策課長 お見込みのとおりでございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございます。
例えばですよ、今からパブコメをされますけれども、そういった意見が出たときは、どのように検討し、反映する余地があるのかどうか、その辺もちょっと教えていただければと思います。
◎住谷憲昭 環境政策課長 もちろんパブリックコメントでいただきました御意見、こちらにつきましては、環境審議会技術検討委員会等に報告差し上げまして、必要であれば意見を反映し、修正していきたいと思っております。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございました。
いずれにしても後発ですので、その辺のところもしっかりと考えていただきながら、本当によりよい環境保全をしっかりとしていきながら、開発が駄目とかいうわけではないんですけれども、その辺とうまくバランスが取れて、他都市にはないような、まちづくりに寄与するような条例になることを願っておりますので、期待しています。頑張ってください。
もう一点、続けていいですか。
○三森至加 委員長 どうぞ。
◆高本一臣 委員 すみません。
プラごみの実証実験ですね。まず、前回のお話によると、モデル校区を選ぶのは、大体九十数校区あるうちの平均的な校区とおっしゃったんですけれども、それで春日校区が選ばれたと理解していますが、人口、面積全てというような中で、この選択だったんでしょうか。その辺のところをもう少し詳しく聞かせていただければと思います。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 モデル地区について、どのような形で選定したのかというようなお話でございますけれども、春日校区につきましては、先ほど委員からもございましたとおり、駅周辺地区ということもありまして、マンションだったり一戸建てだったりアパートだったり、住居の形態が偏っていないというところがございます。そして、また住民の年代、ごみを出される年代も偏りがないということでございます。また、世帯数も、今回仙台市を参考にさせていただいているんですけれども、春日校区は1校区だけで4,000世帯ほどございます。ですので、サンプル的にも十分という判断でございます。また、中間処理業者が持込み先になりますけれども、こちらが同じ西区にございます。距離的な面で、収集運搬が大変円滑といったところで、モデル地区としては最適という判断をさせていただきました。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございました。マンションや戸建ての割合、あるいは年代がそれぞれにということで、本当に平均の平均という感じで選ばれたというような理解ですけれども、スケジュールを見ると、この実証実験を行うことによって、来年の1~3月の間に方針を決定されるということですが、仮に予想された実証実験の結果が、想定していたような状況では仮にないとしても、これは必ず将来的にはやっていくというような事業でよろしいんですよね。その辺のところ確認ですけれども。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 委員おっしゃるとおり、先ほど少し触れさせていただきましたけれども、資源循環促進法が施行されたことによりまして、自治体でこのプラ製品の分別収集、そして再商品化が求められているということがございます。そして、また私どもといたしましてもごみの削減、そしてリサイクルの推進、何よりプラスチックごみの対策の一環となるということからも、積極的に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 分かりました。もちろん国の方でそういう法律が施行されたから、やはり進めていくべき事業だと思います。その前の実証実験ということで、現在燃やすごみに含まれているものを今度はプラスチック製容器包装と一緒にするということは、当然そうなってくると、燃やすごみが減量されますよね。今はプラスチック製品の容器は普通の市販の袋ですけれども、燃やすごみの方は有料ごみ袋ということで、環境の観点からもちろん確かにいいんでしょうけれども、一方で本市の収入の一助となっている有料ごみ袋が、この事業を実際やっていくと、間違いなく減少するんではないかなと考えますが、その辺について、なかなかどのぐらい減るとか、まだ分からないとは思うんですけれども、お考えというか、何か対策というのは今のところどうですか。あられますか。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 そこの話になりますと、私どもとしても大変悩ましいところではございます。ごみ量が減れば、当然指定袋の収入が減少していくという相反するところではございます。実際、どのぐらい指定袋の売上げに影響があるかどうかというところも踏まえて、今回の実証実験を通して、コスト面での検証もしていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 今から実証実験を行って、その後に検証ということになっていますから、ちょっと現時点では確かにどのぐらいというのは出てこないと思うんですけれども、今、課長もおっしゃったように、様々な面からそういう検証をしていただかないといけないと思うし、それによって方針を決めるような形にしていただきたいと思います。例えばプラごみ専用の有料ごみ袋を市で作成するとか、いろいろな方法が収入の確保に向けてあると思うんですけれども、さっきの条例と同様に、やはり環境のことも推進していきながら、一方ではそういう貴重な財源である有料ごみ袋の収入確保に向けても、二兎追うものは二兎、ちゃんと確保できるような形でやっていっていただければと思います。いろいろ実証実験の結果も、この後の委員会等でも報告されると思いますので、その辺のところもしっかりと検証して報告していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
議第150号、議第178号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件を可決することに御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、環境水道委員会を閉会いたします。
午前11時05分 閉会
出席説明員
〔環 境 局〕
局長 村 上 慎 一 環境推進部長 戸 澤 角 充
環境政策課長 住 谷 憲 昭 環境政策課副課長 緒 方 美 治
脱炭素戦略課長 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長
古 上 藤 治
水保全課副課長 赤 星 博 興 環境総合センター所長
近 藤 芳 樹
資源循環部長 下錦田 英 夫 廃棄物計画課長 坂 田 文 昭
廃棄物計画課副課長右 山 敬 基 環境施設課長 伊 藤 暢 章
事業ごみ対策課長 菅 本 康 博 事業ごみ対策課副課長
谷 山 祐 喜
浄化対策課長 田 上 真 吾 東部環境工場長 後 藤 滋
〔上下水道局〕
上下水道事業管理者田 中 俊 実 総務部長 江 藤 徳 幸
首席審議員兼総務課長 総務課副課長 西 田 一 也
岩 本 清 昭
経営企画課長 宮 邊 謙太郎 経営企画課副課長 山 下 豊
料金課長 福 島 勝 浩 料金課副課長 北 口 浩 之
給排水設備課長 坂 口 和 高 計画整備部長 藤 本 仁
計画調整課長 福 田 政 昭 計画調整課副課長 神 崎 陽 介
審議員兼技術監理室長 水道整備課長 佐 藤 公 成
末 永 剛
下水道整備課長 渕 上 弘 樹 下水道整備課副課長米 野 武 男
維持管理部長 角 田 俊 一 水道維持課長 島 村 幸 一
下水道維持課長 日 高 輝 下水道維持課副課長宮 本 和 彦
首席審議員兼水運用課長 水運用課副課長 吉 田 浩 史
河 田 誠 二
審議員兼水質管理室長 水再生課長 山 本 孝 壽
濱 野 晃
〔議案の審査結果〕
議第 150号 「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」
………………………………………………………………(可 決)
議第 178号 「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」
………………………………………………………………(可 決)
環境水道委員会会議録
開催年月日 令和6年6月19日(水)
開催場所 環境水道委員会室
出席委員 8名
三 森 至 加 委員長 山 本 浩 之 副委員長
寺 本 義 勝 委員 木 庭 功 二 委員
筑 紫 るみ子 委員 田 中 敦 朗 委員
高 本 一 臣 委員 西 岡 誠 也 委員
議題・協議事項
(1)議案の審査(2件)
議第 150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」
議第 178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」
(2)所管事務調査
午前10時03分 開会
○三森至加 委員長 ただいまから環境水道委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部において人事異動があっておりますので、順次紹介をお願いいたします。
〔執行部自己紹介〕
○三森至加 委員長 以上で、紹介は終わりました。
これより本日の議事に入ります。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件、その他1件の計2件であります。そのほか、陳情1件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申出のあっております報告7件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎岩本清昭 首席審議員兼総務課長 委員会資料、上下水道局・資料1をお願いいたします。
私からは、議第150号「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
小学1年生~小学6年生まで、障がいがある子の場合は18歳まで、1日に2時間の範囲内で無給の休暇が取得できる子育て支援時間の導入に伴う規定の整備等を行うため、当該休暇の追加など所要の改正を行うものです。
今議会で交通局及び病院局においても同様の改正が行われます。
資料1、3~6ページに新旧対照表をつけております。
説明は以上でございます。
○三森至加 委員長 次に、議第178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」の説明を求めます。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 私からは、議第178号について御説明いたします。
環境局・資料1を御覧ください。
議第178号「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」は、地方自治法第289条の規定により、山鹿市と協議し、同法第290条において議決が必要となりますことから、本定例会において議案を提出するものでございます。
資料の3ページ目を御覧ください。
対象となる施設でございますが、北区植木町にあります山鹿植木広域行政事務組合のリサイクルプラザになります。リサイクルプラザについては、山鹿市と植木町の資源物の中間処理を行っていた施設でございますが、平成15年の供用開始以来、長年の稼動により設備が老朽化し、その改修費用に多額の費用がかかることから、令和4年度末をもって閉鎖いたしております。
財産処分についての内容でございますが、対象としては、リサイクルプラザの土地と物品の2点でございます。
まず、土地につきましては、事務組合で建物を解体した後、更地にして熊本市に帰属させるものでございます。また、物品につきましては、2トンダンプ、ショベルローダーやフォークリフト、その他、机、椅子等の事務用品になりまして、こちらは事務組合への帰属となります。
ただいま御説明いたしました財産処分の内容につきましては、山鹿市との協議書として資料の2ページ目にお示しいたしております。
なお、当議案につきましては、山鹿市議会との同文議決案件となります。
また、参考になりますが、リサイクルプラザの跡地利用につきましては、現在、熊本市公文書館建設の検討がなされておりまして、本定例会の予算決算委員会総務分科会において、関連予算の審議と併せ公文書館の整備基本計画(案)について報告予定となってございます。
説明は以上でございます。
○三森至加 委員長 以上で、議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。
ありませんか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
これより、所管事務調査を行います。
執行部より申出のあっております報告7件について、順次説明を聴取いたします。
◎宮邊謙太郎 経営企画課長 環境水道委員会資料、青色の上下水道局をお願いいたします。
私からは、報第14号、水道事業会計及び報第15号、下水道事業会計の予算繰越計算書につきまして、一括して御説明いたします。
資料2の1ページをお願いいたします。
まず、1、令和6年度(2024年度)への繰越額でございます。
表の中央の列、繰越Aでございますが、こちらは地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和5年度の事業予算を令和6年度に繰り越すものでございます。また、表の右側の列、繰越Bでございますが、これは、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越しであり、令和5年度に繰り越していました令和4年度の事業予算をさらに令和6年度に繰り越すものでございますが、今回は該当はございません。表の左側は、繰越Aと繰越Bの合計になります。
次に、繰越しの内容でございますが、水道事業につきましては40件、20億8,744万3,000円でございます。下水道事業につきましては71件、54億13万8,000円でございますが、国の緊急対策に伴う補正予算の関係により、本年2月補正に前倒しした分3億5,173万円が含まれております。
次に、2、繰越の理由でございます。
主な理由ごとに分類しておりますが、件数の割合で多い順に見ますと、水道事業会計につきましては、ア、関係者等との協議に時間を要したものが30%、イ、他工事等の進捗の調整に時間を要したものが30%、ウ、埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したものが23%でございました。また、下水道事業会計につきましては、ア、関係者等との協議に時間を要したものが37%、イ、他工事等の進捗の調整に時間を要したものが22%、ウ、埋設物、土質等の影響によるルート・施工方法・期間の調整に時間を要したものが18%でございました。
2ページには、水道事業、下水道事業の繰越予算の金額及び件数の推移を掲載しております。
また、3ページ以降は、水道事業会計及び下水道事業会計それぞれの予算繰越計算書と、これらの附属説明資料としまして、繰り越しした事業の一覧を添付しております。繰越しの理由に加え、前払い額、工期や入札の不調、不落の状況も記載しておりますので、御覧いただければと存じますが、工事費の支払いにつきましては、公営企業会計上の取扱いで分かりにくいところがございますので、簡単に御説明いたします。
4ページをお願いいたします。
水道事業会計の繰越計算書でございますが、支払い義務発生額の列でゼロ円となっているところがございます。この支払い義務発生額の欄には、繰越しの対象となりました事業の一部につきまして、完成検査が終了したものが計上されることになっておりますが、実際に全く支払いを行っていないということではございません。
5ページをお願いいたします。
付属説明資料を御覧いただきますと、表中に、うち前払額という列がございます。これは、前払い金の額でございますが、発注しました工事が円滑、適正に行われるよう請求があった分の前払い金を支払っているものでございます。この前払い金につきましては、工事の完成検査を行っておりませんので、額としましては、繰越額に含まれているということでございます。
下水道事業会計の繰越計算書も同様でございます。
説明は以上でございます。
◎戸澤角充 環境推進部長 私からは、熊本市第8次総合計画、令和6年度アクションプランについて御説明させていただきます。
共通資料①をお願いいたします。2ページの図を御覧ください。
熊本市第8次総合計画の基本構想、基本計画につきましては、第1回定例会において議決いただき、4月より本計画をスタートさせたところでございます。本アクションプランは、図の赤囲みになりますが、総合計画を構成するものであり、当該年度の重点事項、各ビジョンにおける主な取組、実施計画の3つで構成し、毎年度策定、公表することとしています。
恐れ入ります、3ページをお願いいたします。
第8次総合計画の着実な推進に向けたマネジメントサイクルを記載しております。年間を通して第8次総合計画に掲げる8つのビジョンについて、事業の進捗状況や行政評価の結果を踏まえた課題の把握、分析を行い、必要な施策展開のための調整や協議・企画・立案を行います。特に、国の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえた新規拡充施策については、当初予算編成時におきまして、十分な検討を行うとともに、必要に応じて補正予算での対応を行うこととしております。また、その検討に当たっては、庁内において緊密な連携の下、課題の共有と調整を図ってまいります。
これらを基本的な考え方としながら、年度当初にアクションプランの策定、行政評価を行い、その結果や当該年度上半期の進捗などを踏まえて、10月以降の次年度予算編成作業において、予算編成方針と次年度アクションプランの重点項目との整合や当初予算のポイントと各ビジョンにおける主な取組との同一化等を図って、次年度以降の取組につなげてまいりたいと考えております。
なお、第8次総合計画に基づく行政評価は、来年度より運用を開始する予定であり、現在その仕組みについて検討を進めているところでございます。
恐れ入ります、6ページをお願いいたします。
重点事項でございます。本市の最重要課題である人口減少への対応に力強く取り組み、希望ある未来を築いていくため、こどもを核としたまちづくりを進めるとともに、半導体関連企業の熊本進出を好機として、地域経済の発展を促進し、魅力あるまちづくりを行っていく必要があることから、令和6年度はこども関連施策の推進と半導体関連企業の熊本進出に伴う諸課題への対応を重点事項として設定しております。
なお、7、8ページに、重点事項についてそれぞれの令和6年度の主なアクション等を記載しております。
次に、9ページ以降でございますが、基本計画に掲げる8つのビジョン及び区における自主自立のまちづくりにおける令和6年度の主な取組を記載しております。環境局の主な取組について御説明させていただきます。
恐れ入ります、18ページをお願いいたします。
ビジョン2、市民に愛され世界に選ばれる、持続可能な発展を実現するまちにおきまして、環境局では、「くまもと水ブランド」の情報発信に努めてまいります。
恐れ入ります、25ページをお願いいたします。
ビジョン5、豊かな環境を未来につなぐまちにおきまして、地下水涵養の促進や水源涵養林の整備、地下水及び公共用水域の水質の監視強化により、引き続き地下水保全に取り組んでまいります。また、環境保全の推進のため、(仮称)環境影響評価条例を制定いたします。最後に、脱炭素の推進として、熊本連携中枢都市圏における脱炭素化事業の加速化や、省エネ家電等を導入する個人、事業所への補助に取り組んでまいります。
環境局からは以上になります。
◎江藤徳幸 総務部長 引き続き、上下水道局分の主な取組を御説明いたします。
資料の31ページをお願いいたします。
ビジョン7、安全で良好な都市基盤が整備されたまちにおける上下水道局の取組としまして、一番下になりますが、水道100周年記念事業を実施いたします。具体的には、令和6年11月27日に通水100周年を迎えることから、感謝・誇り・誓いに信頼を加えた4つのキーワードをコンセプトに、記念式典や併設イベント等の記念事業を実施いたします。また、これらの事業を通じて様々な世代の方たちに、地下水の恩恵を実感していただく持続可能な水道事業の実現に資するよう取り組んでまいります。
次に、共通資料②、第8次総合計画アクションプラン(実施計画)(案)をお願いいたします。
実施計画では、各ビジョンの施策を構成する基本方針ごとに、検証指標や事業等を掲載しております。今後のスケジュールとしましては、本日の御意見を踏まえまして、7月までに策定、公表させていただく予定といたしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◎住谷憲昭 環境政策課長 環境局・資料2を御覧ください。
(仮称)熊本市環境影響評価条例の基本的事項についてでございます。5ページまでは、前回の第1回定例会にて報告させていただきました条例制定の背景や、検討事項等について再度記載しておりますので、追加事項のみ報告させていただきます。
おめくりいただきまして、4ページをお願いいたします。
令和5年度に環境審議会へ諮問し、審議の結果、以下に記載しております①~③を条例の基本的事項として定めることが必要との答申を令和6年3月27日に受領いたしました。令和6年度は、この①~③の具体的検討に加え、④の環境影響評価の調査、予測及び評価の方法について検討してまいります。
続きまして、6ページをお願いいたします。
まず、基本的事項1点目の手続方法についてでございます。本市条例では、図に記載しておりますA~Hの手続、全てを採用する予定でございます。本市が導入を予定しておりますBのスクリーニングとは、事業特性や地域特性、事業実施による環境への影響を考慮し、評価手続を行うかどうか判定するものでございます。手続の課題といたしましては、規模要件のみによる手続の一律義務化により、建て替え等の環境負荷が小さくなる場合でも手続を求めていることや、手続に要する期間が3~4年と長期にわたり、多額な費用が発生するなどの課題がございます。このスクリーニングを導入することにより、手続の要否を適宜判断できることや、事業者に対し環境負荷の低減について検討を促すこと、また、手続が不要となった場合は、事業着手までの期間短縮や費用の削減につながると考えております。熊本県におきましても、本年9月頃をめどに、このスクリーニングを導入する予定とのことでございます。
7ページをお願いいたします。
基本的事項2点目の地域区分についてでございます。自然環境など本市の地域特性に応じて、より環境への配慮が必要な地域として、以下に記載しております①県立自然公園~⑥史跡・名所・天然記念物と6つの地域を指定地域に設定し、一般地域よりも環境配慮を求めることとしております。
8ページをお願いいたします。
基本的事項3点目、対象事業の種類と規模要件でございます。国・熊本県・熊本市それぞれの対象事業を記載しております。熊本県の対象事業は、熊本市域内において事業実施の可能性があるため、全て本市の対象事業とし、加えて大規模建築物等複合事業についても、本市の地域特性を踏まえ対象事業としております。
次の9ページには、大規模建築物を対象事業に追加する必要性について記載しております。本市においては、今後も都市開発により大規模な建築も想定されます。課題といたしましては、大規模建築物が周辺環境に与える影響といたしまして、工事中の騒音、振動、大気汚染や供用が始まった際の景観、日照阻害、電波障害、不具合などが考えられます。対象事業とする効果といたしましては、建築紛争等のトラブルを低減することや、重大な環境影響等の回避に加えまして、事業者に対して必要な措置を求めることができると考えております。
10ページをお願いします。
複合事業を対象事業に追加する必要性についてですが、個別では規模要件に満たない事業であっても、緊密に関連する2つ以上の事業が一体的に実施されることにより、課題に事例を記載しておりますとおり、個別の事業では規模要件25ヘクタール以上を満たさないものでありましても、レクリエーション施設20ヘクタール、土地区画整理事業10ヘクタール、合計30ヘクタールとなり、規模要件以上となる場合がございます。このように一体的に実施される事業や、複数の規模要件未満の切り分け事業のようなアセス逃れの事業に対しまして、複合事業と規定することにより、広く一定の開発行為に対して、適切に環境影響評価を求めることができるようになると考えております。
11ページをお願いします。
次に、本市対象事業の規模要件につきましては、一般地域の規模要件は県条例と同等といたしまして、より環境に配慮すべき指定地域は、原則一般地域の50%規模としております。指定地域の規模要件を強化することで、指定地域から一般地域へ開発が誘導される効果を記載しております。
次の12ページは、事業の種類ごとに一般地域と指定地域の規模要件につきまして、それぞれ記載した一覧表となっております。
13ページをお願いします。
最後に、今後のスケジュールでございますが、現在、環境影響評価技術指針等検討委員会において、条例案の検討を進めており、秋頃をめどにパブリックコメントを実施し、御意見に応じて条例案の修正を行い、令和7年第1回定例会への議案上程を目指し取り組んでいるところでございます。第1回定例会におきまして御承認いただけますならば、この条例は全国の事業者が対象となることから、条例公布後は、広く周知広報を行い、同年10月の条例施行を目指してまいります。
なお、参考資料といたしまして、令和6年3月27日に環境審議会から受領いたしました答申書及び熊本県が条例を制定した際に作成したパンフレット等を添付いたしております。
報告は以上となります。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 私からは、プラスチックの一括回収実証実験について御説明申し上げます。
環境局・資料3を御覧ください。
本市では、プラスチック製容器包装については、分別収集及び再資源化を行っております。一方、プラスチック使用製品については、燃やすごみとして収集し、環境工場で処理を行っているところでございます。
では、プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品の違いは何かということでございますけれども、資料の右側の画像を御覧ください。画像上段のプラスチック製容器包装につきましては、ラーメンの袋や食品トレーなど商品そのもののことではなく、商品の容器や包装のことでございまして、目印としてプラマークがついているものがこれに該当いたしております。一方、プラスチック使用製品につきましては、資料右下の画像になりますが、これまで燃やすごみとして出していただいておりましたスプーンや洗面器、食品タッパーやハンガーなど製品そのものがプラスチックというものがこれに該当いたしております。
概要・目的でございますが、令和4年4月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。この法律によって、市町村に対しプラスチック製品廃棄物の分別収集及び再商品化が求められることとなりました。今回の実証実験では、今後の方針を検討するため、プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品を一括回収し、収集運搬や再資源化等にかかる費用及び事業効果の検証を行うこととしております。
次に、実施内容でございます。実施期間は、令和6年8~9月までの2か月間、実施地区は春日校区で約4,000世帯を対象に行う予定でございます。一括回収の対象品目としては、画像にございますプラスチック製容器包装とプラスチック使用製品となります。また、対象外の品目になりますが、間違いやすい例の一つとして、ペットボトルについて申し上げます。この製品につきましては、キャップとラベル、そしてペットボトル本体に分別できますが、まずキャップとラベルについてはプラスチック製容器包装として、今回の実証実験の際に一括回収いたします。一方ペットボトル本体は、今回の実証実験の対象とはならず、従来どおりペットボトルの日に別途回収させていただきます。
次に、資料の2ページを御覧ください。
上段に実証実験のイメージを記載しております。期間中、春日校区の皆様にはプラスチック製容器包装の収集日に、従来のプラスチック製容器包装に加え、プラスチック使用製品と併せて同一の45リットル以内の透明袋でごみステーションに出していただくことになります。一括回収したプラスチックは、その後、民間施設において選別、再資源化、組成分析などを行います。
スケジュールについては、お示ししているとおりでございまして、実証実験終了後は検証を行い、今後の方針を決定する予定でございます。
最後に、春日校区の皆様へ周知用のリーフレットとしまして、別添の資料3-①を添付いたしております。こちらは、6月下旬~7月にかけまして、自治会の回覧をお願いするとともに、春日校区内の全ての御家庭に配布予定でございます。
説明は以上でございます。
◎戸澤角充 環境推進部長 資料4をお願いいたします。
先月5月18日~25日にインドネシア、バリで開催されました第10回世界フォーラムに参加いたしましたので、御報告させていただきます。
まず、1、フォーラムの概要でございます。本フォーラムは3年に一度、世界中の水関係者が一堂に会し、水と衛生に関わる様々な問題について議論する世界最大の水の国際会議でございます。今回は繁栄を共有するための水というテーマで開催されたところでございます。
恐れ入ります、2、会議等への出席状況を御覧ください。会議開催期間の20~24日において、大西市長が以下の6つの会議に出席いたしました。主なものといたしまして、21日に開催されました、インドネシア政府主催のバンドン・スピリット・ウォーター・サミットでは、各国首脳の発言に対して、市長が本市のこれまでの水保全の取組を踏まえコメントいたしました。また、24日に開催されました水災害リスクを軽減するために必要な資金・ガバナンス・能力開発・制度の最善化に関するセッションでは、市長が健全な水循環と流域防災に向けた熊本市の取組について発表し、世界が学ぶべき事例として高い評価をいただいたところでございます。
恐れ入ります。2ページをお願いいたします。
3番目は、各セッションの様子でございます。
最後に4、総括といたしまして、3つ目の丸の部分でございますが、今後も熊本の貴重な地下水を守るための取組を進めるとともに、本市の取組を世界に発信することで、本市の国内外での認知度向上はもとより、世界の水問題解決に貢献してまいります。
説明は以上でございます。
◎宮邊謙太郎 経営企画課長 環境水道委員会資料、青色の上下水道局・資料3をお願いいたします。
私からは、工業用水道取水2号井の調査結果を御報告いたします。
資料3の1ページをお願いいたします。
まず、工業用水道取水2号井内部調査についてでございます。
1、調査の目的でございますが、令和5年5月、工業用水道の3本の井戸のうち2号井の取水ポンプに故障が発生し、工業用水の供給に支障はなかったものの、2号井が予備水源として重要な役割を持っていたこと、また、施設整備から30年が経過していたことから、井戸本体の劣化も想定し、内部調査を実施したものです。
次に、2、調査の概要でございますが、令和5年第3回定例会で議決いただきました補正予算1,000万円に対し、契約額953万8,940円、調査期間を令和5年12月25日~令和6年2月28日としまして、取水ポンプの引上げ、水中カメラによる井戸内部の調査、井戸内部の清掃を実施いたしました。
3、調査結果でございますが、井戸内部に破損はなく、水質は条例で規定する基準に適合しておりました。また、故障した取水ポンプはメンテナンスにより機能が回復しまして、2号井は当面の運用に支障がないことを確認しました。
次に、「工業用水道使用についてのアンケート」実施についてでございます。
1、実施の目的でございますが、安定した水供給のための設備の維持及び更新計画を検討するため、将来的な使用水量及び水質の条件についてのアンケートを実施したものです。
2ページをお願いいたします。
実施の概要でございますが、城南工業団地入居企業全15社に対し、将来的な使用水量の見込みと受水の水質条件を調査しました。
3、アンケート結果まとめでございますが、将来的な使用水量については、企業の事業活動に左右されるところが大きく、今回、確定できておりません。また、水質については、条例に規定する基準で問題はありませんでした。
次に、工業用水道の今後について(案)でございます。
資料には、今後の流れのイメージを掲載しておりますが、引き続き将来的な水需要量の把握に努め、併せて水需要量、水質に合わせた工業用水道施設の維持及び更新計画を策定し、費用の最小化を図ってまいります。
最後に、参考として、工業用水道の概要を掲載しております。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○三森至加 委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び所管事務について質疑及び意見をお願いします。
◆木庭功二 委員 すみません、説明にはなかったんですけれども、所管ということでちょっと聞かせていただきたいと思います。
令和6年度のアクションプラン(実施計画)(案)の資料98ページになるんですけれども、脱炭素戦略課が所管になるかと思うんですけれども、2番の市有施設LED化整備経費ということで、今年度の予算が約6億9,928万円で計上されているかと思います。それで、本市としては令和2年度から市有施設のLED化を一斉に行うということで、2期的に取り組んでこられたかと思うんですけれども、その中で、公表されているデータによりますと、今、約94%ぐらいの施設がLED化の実施がされましたということでした。これ確認なんですけれども、残りの大体6%の市有施設をこの約6億9,928万円の予算でLED化していくということでよろしかったでしょうか。教えていただければと思います。
◎兼平進一 脱炭素戦略課長 アクションプランに書いておりますLED化の整備経費につきまして、これまで整備してきたLED化の費用についてですけれども、整備の方法としまして、リース方式を採用しておりまして、整備から8年間のリース代を払うこととしております。そのため、このリース代がここの事業費になっているというものでございます。ちなみに、今、市有施設のうち94%がLED化済みということなんですけれども、残りの6%というのが、今後建て替え等が検討されている施設ということで、除外したものでございますので、今後建て替え等のタイミングで検討されていくものでございます。
以上でございます。
◆木庭功二 委員 ありがとうございました。6%は建て替えの施設ですね。今後されていくということでした。ありがとうございます。
水銀に関する水俣条例は策定されまして、2027年までに蛍光灯の製造禁止ということになっているかと思うんですけれども、今後、ほかの自治体でLED化が進んでいないところでは一気にLEDの需要がでてくるかと思いますので、6%ということでありますけれども、その後、LEDの調達に関しては、問題ないというか計画的に進められているということでよろしかったでしょうか。
◎兼平進一 脱炭素戦略課長 市有施設のLED化につきましては、昨年度、令和5年に策定しました熊本市役所脱炭素化イニシアチブプランの中にも、市有施設のLED化ということを掲げておりまして、その進捗につきましては、環境局が中心となって把握していこうと思っております。先ほど94%と話をしましたけれども、ほかにも道路照明であるとか、また学校施設でLED化していないところはまだございますので、その進捗についてはこのプランの進捗の中で把握していきたいと考えております。
以上でございます。
◆木庭功二 委員 御答弁ありがとうございました。
様々市営団地とか学校の施設とか、LED化になることで、皆さん大変喜ばれているところもあるかと思います。今後さらにCO2削減量の公表とか市民の皆様にこれだけの削減ができたとか、電気代のこれだけの削減ができたというような効果についても、しっかり情報公開をしていっていただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
◆筑紫るみ子 委員 令和6年度アクションプラン(案)の8ページの半導体関連企業の熊本進出に伴うというところで、ここに書いてある地下水及び公共用水の監視強化に関連して、実は先日、工業大学の教授の方と二、三人お会いしてお話を聞かせていただいたときに、熊本市はざる田があって、その下に多大な水のプールがあるということで、そこが今はずっと何千年もの間満水だったから、上のざる田、この岩盤の部分が落ちないで、今まで私たちの熊本市にきれいな水が供給されてきたということを聞いて、半導体専門の先生もその中にいらっしゃいまして、今からTSMCさんの第2工場ができていくとなると、相当今の想定量よりももっと使う量が本当は多いんではないかという懸念されていたんですね。そうなると、プールに空洞ができた場合に、上のこの岩盤が支えられていた水がなくなるということで、陥没するおそれもあるので、本当に懸念していると、九州のある何件かの工業大学の教授の方が口をそろえて言われまして、それが一番怖いので、とにかく湛水とかこの涵養事業でいつも下のプールが満タンになっているような施策をきちんと取っていただきたいという要望を言ってくれと言われまして、なので、熊本市が一番影響を受けるということで、その辺も今から重大な施策の一つとしてぜひ頭の隅に入れておいていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○三森至加 委員長 要望だけで。
◆筑紫るみ子 委員 質問というより要望です。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
◆田中敦朗 委員 同じ項目の地下水及び公共用水城の監視強化ということで、新たにPFOS、PFOA等の監視項目を追加するなどということで、PFOS、PFOAのことでちょっとお伺いしたいと思って手を挙げさせていただきました。
井芹川流域の方からPFOS、PFOAが検出されたというところで、今ずっと調査をしていると思うんですけれども、その原因の調査、原因の特定、どこら辺の地域からなど、今の進捗を教えていただければなと思いますけれども。
◎古上藤治 首席審議員兼水保全課長 ただいま御案内いただきました井芹川の方で昨年末、28地点で調査ところ、12地点で超過が見られたということで、それにつきましては、ほぼ上流域で、超過が見られております。
今の調査の状況としましては、その川に流れ込むいわゆる用水路であったり、いろいろな水源といいますか、流れ込みの部分がございまして、そこを今一つ一つ詰めて確認、検査をする作業を進めておるところです。原因究明に向けてという形で今、進めておりますので、こちらまとまり次第、また御報告させていただきたいと思っております。現状は、その調査を行っているということと、あと、現地の聞き取り、地歴調査も併せて行っているところでございます。それぞれ地形等が結構山あり谷ありの場所でもございますので、そういったところ、いろいろな可能性を考えながら、調査を進めているところでございます。いましばらくお待ちください。
◆田中敦朗 委員 前も申し上げたんですけれども、結局職員がやるにも限界があると思うんですよね。また、政令指定都市の中の河川でそういったPFOS、PFOAが検出されたというところで、私としては、前も申し上げたんですけれども、任せられるところは民間に任せたらいいのではないかなと思うんですよね。民間の方に様々な検査とか原因究明の委託をして、そういった調査を進めていただくと。もう一歩進めて、例えば環境省にも協力をお願いして、例えば河川でPFOS、PFOAが検知された場合は、どういった形で検査をすれば、原因特定ができるのかというのをモデルケースにするような方向で話をしていただいて、いろいろな支援をしていただくとか、そういったこともぜひ考えてほしいなと思いまして。
一政令指定都市であればこそ、様々な人員と予算が準備はできるとは思うんですけれども、こういったところがほかの自治体であった場合、その自治体ではちょっともうお手上げのときがあるんではないかなというような懸念もしていまして、ピンチはチャンスというか、熊本市で起こったからこそ、そういった、後に続くであろう様々な環境問題に対しての処方箋として、民間に委託するであるとか、どういった調査をして、どうやって特定していったのかというのも、ほかの自治体の参考になるような形でしっかり残していってほしいなというふうに思いますので、環境省の調査のことと残していってほしいということ、この二つだけお願いしておきます。
以上です。
○三森至加 委員長 ほかに。
◆高本一臣 委員 所管の2番の環境影響評価条例と、3番のプラスチックの実証実験でちょっとお尋ねさせていただきます。
まず、環境影響評価条例、アセス条例ですけれども、ここには記載されていないけれども、前回の資料では、もう既に全都道府県、そして政令市が熊本市を除く19市、その他に2市ということで68の自治体が制定されているということで、環境に非常に関心を今持たれている中で、そういう自治体の中で残念ながら最後というのは非常に思うところもあるんですけれども、一方では最後だからこそ、非常に機能するようなすばらしい条例になってくれればなというふうに思っています。その中で、ちょっと県と市の違いが2つほど追加されていますけれども、例えば面積について、土地区画整理事業や工業団地の造成事業あたりは、県では面積は25ヘクタール以上、それを市としては50%と要件の違いがありました。多分答申書の中でそういう意見が出たと思うんですけれども、それについて、私個人的には、もうちょっと制限をしてもいいのかなと思うんですけれども、その辺についてどういう根拠というか、答申からということなのか、あるいは何かちょっと協議もされたのか、その辺のところをお聞かせください。
◎住谷憲昭 環境政策課長 今、対象事業の規模要件に関する御質問でございますが、こちらにおきましては、本市が6つの指定地域を定めております。一般地域につきましては、熊本県と同様にしておりますが、指定地域については特に制限を設けていきたいということで50%規模、約半分にいたしております。これにつきましても、環境審議会の先生方に御提案いたしまして、先生方と意見を交わしまして、このような形で設定させていただいております。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ということは、指定地域と、この制限の数字あたりは、整合性がとれているという認識でよろしいんですか。
◎住谷憲昭 環境政策課長 お見込みのとおりでございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございます。
例えばですよ、今からパブコメをされますけれども、そういった意見が出たときは、どのように検討し、反映する余地があるのかどうか、その辺もちょっと教えていただければと思います。
◎住谷憲昭 環境政策課長 もちろんパブリックコメントでいただきました御意見、こちらにつきましては、環境審議会技術検討委員会等に報告差し上げまして、必要であれば意見を反映し、修正していきたいと思っております。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございました。
いずれにしても後発ですので、その辺のところもしっかりと考えていただきながら、本当によりよい環境保全をしっかりとしていきながら、開発が駄目とかいうわけではないんですけれども、その辺とうまくバランスが取れて、他都市にはないような、まちづくりに寄与するような条例になることを願っておりますので、期待しています。頑張ってください。
もう一点、続けていいですか。
○三森至加 委員長 どうぞ。
◆高本一臣 委員 すみません。
プラごみの実証実験ですね。まず、前回のお話によると、モデル校区を選ぶのは、大体九十数校区あるうちの平均的な校区とおっしゃったんですけれども、それで春日校区が選ばれたと理解していますが、人口、面積全てというような中で、この選択だったんでしょうか。その辺のところをもう少し詳しく聞かせていただければと思います。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 モデル地区について、どのような形で選定したのかというようなお話でございますけれども、春日校区につきましては、先ほど委員からもございましたとおり、駅周辺地区ということもありまして、マンションだったり一戸建てだったりアパートだったり、住居の形態が偏っていないというところがございます。そして、また住民の年代、ごみを出される年代も偏りがないということでございます。また、世帯数も、今回仙台市を参考にさせていただいているんですけれども、春日校区は1校区だけで4,000世帯ほどございます。ですので、サンプル的にも十分という判断でございます。また、中間処理業者が持込み先になりますけれども、こちらが同じ西区にございます。距離的な面で、収集運搬が大変円滑といったところで、モデル地区としては最適という判断をさせていただきました。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 ありがとうございました。マンションや戸建ての割合、あるいは年代がそれぞれにということで、本当に平均の平均という感じで選ばれたというような理解ですけれども、スケジュールを見ると、この実証実験を行うことによって、来年の1~3月の間に方針を決定されるということですが、仮に予想された実証実験の結果が、想定していたような状況では仮にないとしても、これは必ず将来的にはやっていくというような事業でよろしいんですよね。その辺のところ確認ですけれども。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 委員おっしゃるとおり、先ほど少し触れさせていただきましたけれども、資源循環促進法が施行されたことによりまして、自治体でこのプラ製品の分別収集、そして再商品化が求められているということがございます。そして、また私どもといたしましてもごみの削減、そしてリサイクルの推進、何よりプラスチックごみの対策の一環となるということからも、積極的に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 分かりました。もちろん国の方でそういう法律が施行されたから、やはり進めていくべき事業だと思います。その前の実証実験ということで、現在燃やすごみに含まれているものを今度はプラスチック製容器包装と一緒にするということは、当然そうなってくると、燃やすごみが減量されますよね。今はプラスチック製品の容器は普通の市販の袋ですけれども、燃やすごみの方は有料ごみ袋ということで、環境の観点からもちろん確かにいいんでしょうけれども、一方で本市の収入の一助となっている有料ごみ袋が、この事業を実際やっていくと、間違いなく減少するんではないかなと考えますが、その辺について、なかなかどのぐらい減るとか、まだ分からないとは思うんですけれども、お考えというか、何か対策というのは今のところどうですか。あられますか。
◎坂田文昭 廃棄物計画課長 そこの話になりますと、私どもとしても大変悩ましいところではございます。ごみ量が減れば、当然指定袋の収入が減少していくという相反するところではございます。実際、どのぐらい指定袋の売上げに影響があるかどうかというところも踏まえて、今回の実証実験を通して、コスト面での検証もしていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
◆高本一臣 委員 今から実証実験を行って、その後に検証ということになっていますから、ちょっと現時点では確かにどのぐらいというのは出てこないと思うんですけれども、今、課長もおっしゃったように、様々な面からそういう検証をしていただかないといけないと思うし、それによって方針を決めるような形にしていただきたいと思います。例えばプラごみ専用の有料ごみ袋を市で作成するとか、いろいろな方法が収入の確保に向けてあると思うんですけれども、さっきの条例と同様に、やはり環境のことも推進していきながら、一方ではそういう貴重な財源である有料ごみ袋の収入確保に向けても、二兎追うものは二兎、ちゃんと確保できるような形でやっていっていただければと思います。いろいろ実証実験の結果も、この後の委員会等でも報告されると思いますので、その辺のところもしっかりと検証して報告していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○三森至加 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
議第150号、議第178号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件を可決することに御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○三森至加 委員長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、環境水道委員会を閉会いたします。
午前11時05分 閉会
出席説明員
〔環 境 局〕
局長 村 上 慎 一 環境推進部長 戸 澤 角 充
環境政策課長 住 谷 憲 昭 環境政策課副課長 緒 方 美 治
脱炭素戦略課長 兼 平 進 一 首席審議員兼水保全課長
古 上 藤 治
水保全課副課長 赤 星 博 興 環境総合センター所長
近 藤 芳 樹
資源循環部長 下錦田 英 夫 廃棄物計画課長 坂 田 文 昭
廃棄物計画課副課長右 山 敬 基 環境施設課長 伊 藤 暢 章
事業ごみ対策課長 菅 本 康 博 事業ごみ対策課副課長
谷 山 祐 喜
浄化対策課長 田 上 真 吾 東部環境工場長 後 藤 滋
〔上下水道局〕
上下水道事業管理者田 中 俊 実 総務部長 江 藤 徳 幸
首席審議員兼総務課長 総務課副課長 西 田 一 也
岩 本 清 昭
経営企画課長 宮 邊 謙太郎 経営企画課副課長 山 下 豊
料金課長 福 島 勝 浩 料金課副課長 北 口 浩 之
給排水設備課長 坂 口 和 高 計画整備部長 藤 本 仁
計画調整課長 福 田 政 昭 計画調整課副課長 神 崎 陽 介
審議員兼技術監理室長 水道整備課長 佐 藤 公 成
末 永 剛
下水道整備課長 渕 上 弘 樹 下水道整備課副課長米 野 武 男
維持管理部長 角 田 俊 一 水道維持課長 島 村 幸 一
下水道維持課長 日 高 輝 下水道維持課副課長宮 本 和 彦
首席審議員兼水運用課長 水運用課副課長 吉 田 浩 史
河 田 誠 二
審議員兼水質管理室長 水再生課長 山 本 孝 壽
濱 野 晃
〔議案の審査結果〕
議第 150号 「熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について」
………………………………………………………………(可 決)
議第 178号 「山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について」
………………………………………………………………(可 決)