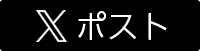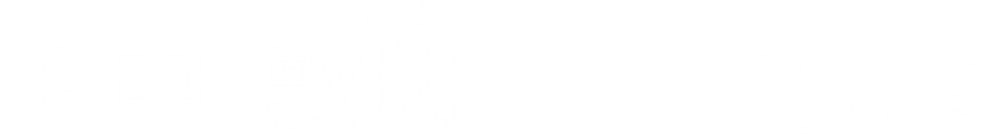2024年10月31日 その他
令和6年10月31日地域公共交通に関する特別委員会
地域公共交通に関する特別委員会会議録
開催年月日 令和6年10月31日(木)
開催場所 特別委員会室
出席委員 12名
田 中 敦 朗 委員長 平 江 透 副委員長
木 庭 功 二 委員 村 上 誠 也 委員
古 川 智 子 委員 中 川 栄一郎 委員
島 津 哲 也 委員 齊 藤 博 委員
井 本 正 広 委員 藤 山 英 美 委員
上 野 美恵子 委員 上 田 芳 裕 委員
議題・協議事項
(1)持続可能な地域公共交通の実現に向けた諸問題に関する調査
午前 9時58分 開会
○田中敦朗 委員長 ただいまから地域公共交通に関する特別委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可します。
◎井芹和哉 交通事業管理者 おはようございます。
まず、1点目でございますが、本日、前回に引き続きまして、運行管理課長の松尾が体調不良により本委員会を欠席しておりますこと、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、運行管理課からはこれまで同様、説明員として運行管理副課長の荒木が出席しております。どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、2点目でございますけれども、去る10月2日に、銀座通り歩道橋交差点におきまして、市電が信号冒進、いわゆる信号無視のインシデントを引き起こしてしまいました。後ほど原因や対策等については、詳細な報告をさせていただきますが、度重なる事故やインシデントの発生を受け、局を挙げて再発防止に取り組んでいる中、また、九州運輸局より改善指示がなされた直後に、このようなインシデントを引き起こしてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
今後、本事案につきましても、外部検証委員会での検証の対象とし、最終報告での安全対策に反映させてまいりたいと考えております。
市電を御利用いただいております皆様をはじめ、市民の皆様に対しましては、立て続けの事故、トラブルにより御心配、御迷惑をおかけしており、改めて深くおわび申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。
以上でございます。
○田中敦朗 委員長 発言は終わりました。
これより本日の議事に入ります。
本日は、「本市のあるべき地域公共交通について」、意見陳述人の意見を聴取するためお集まりいただきました。
意見陳述人におかれましては、大変御多忙の中、本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
委員会を代表いたしましてお礼を申し上げますとともに、忌憚のない御意見をお述べいただきますようにお願い申し上げる次第であります。
それでは、調査の方法についてお諮りいたします。
調査の方法といたしましては、まず意見陳述人の意見聴取を行った後、意見陳述人に対する質疑を行い、次に執行部より「公共交通に関する住民アンケートについて」、「次期地域公共交通計画の策定に向けた取組について」説明を聴取し、一括して質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
これより、意見陳述人として、熊本学園大学経済学部溝上章志教授より、意見聴取を行います。
意見陳述人は、意見の開陳をお願いいたします。
◎溝上章志 意見陳述人 皆様、おはようございます。
この場に呼んでいただきまして大変光栄でございますけれども、これだけカメラもあるので少し緊張しておりますが、3年半前までは熊本大学におりまして、退職して熊本学園大学の方で働かせていただいています。それまで都市計画審議会の会長とか、あるいは公共交通協議会の副会長等を務めさせていただきまして、ここにおられる方、委員の皆さんの中には何人か御一緒させていただいたこと大変光栄に思います。
今日は、皆さんの御期待に添えるかどうか分かりませんけれども、私が考えている公共交通、特に熊本市の交通混雑緩和と地域公共交通再生を両立させて改善していくような方法と、その筋道についてお話ししたいと思います。
これは私の自己紹介なんですけれども、今半分以上申し上げましたけれども、年取ってきたので少し体力をつけなきゃいけないということで、もともとテニスが好きなんですけれども、今膝を痛めておりまして、しばらく休憩中に自転車のツーリングを始めまして、その体力と脚力維持のために大学のジムでトレーニング等をやっております。
昨年4月にしまなみ海道往復、今年の春に浜名湖一周、実は明後日からまた1泊2日で瀬戸内海に行く予定です。つまらない話ですが、皆さんも健康が大事だと思いますし、自転車というのはこれからお話しします車というプライベートな、それも非常に面積等を占有し、かつエネルギー効率も悪いものとは違う乗り物の一つとして、これからどんどん自転車の利用の促進を図っていただければということもあって、こういうことを始めました。
今日は、熊本都市圏における交通混雑の実態、この辺りはいろいろなところで皆さん御存じかと思いますが、ちょっと視点を変えた話をさせていただきます。
それと交通混雑というのがどういう原因で発達しているのかと、それを緩和するためにはこういうふうにしたらいいと、これは理論的な話なんですけれども、少しそういうことを話させていただいた後、一方、公共交通というのはどういう状況になっていて、どんな課題があるか、あるいは後でお話ししますが、熊本市のバスを中心とした公共交通政策というのは、日本で最先端のことをしているんですけれども、これが皆さんにあまり認知されていなくて、とはいうものの、これも限界に来ているために、どういうふうにしたらいいかという話を、その4番の公共交通再生のための政策ということでお話しさせていただきます。
その中には、国までも動かした熊本の公共交通政策というのがありまして、これは市議会及び市の職員の方が長年にわたって国を動かしてきた例をお話ししますが、それ以上のことができなくなったために、6番の公共交通再生のためには、もっと本質的な議論をしなきゃいけないということにつなげさせていただきたいというふうに思います。
まず最初、熊本都市圏における交通混雑の実態ですけれども、これは、皆さんよく別の資料等で御覧になっているかと思いますが、黒いところが徒歩の速度ですね、赤いところがママチャリぐらいですね。寒色系になると早く走れるということなんですが、東バイパスの内側と、特に中心部ですね、ここではママチャリ以下の速度でしか移動できないと。東バイパスと交差する幹線道路ですね、8放射だけではなくていろいろあるんですけれども、そういうところでも赤、あるいは濃い赤ですね、そういうのが起こっております。
それと右上のTSMC、あるいは光の森辺りですね、この辺りも他の郊外部に比べると暖色系の区間が非常に多くなっていて、これはちょっと前なので、今はTSMC周辺ではもっと赤くなっているんではないかというふうに思います。
左の表は、これは名古屋、大阪、東京23区以外を除いた政令市の中心部の交通混雑を示す平均速度ですね。道路上の平均速度、それと公共交通の利用率を示したものですけれども、熊本市はよく政令市で一番混雑が激しい。速度から見ると16.1㎞/hで最も激しいわけですが、実は激しいのは自動車の利用率、一番右側の列を見ていただくと、自動車の利用率が高い都市ほど速度が遅くなっているということが見られると思います。
この公共交通の利用率なんですけれども、人口等調べる国勢調査、熊本都市圏の交通の状況を調べるパーソントリップ調査というのがあるんですが、15年おきに、母都市が50万人以上の都市圏で実施されていますけれども、直近ですね、これは平成24年が64.4%ということで、丸で囲んである紫部分が車の利用率ですが、これでも驚くべき数字なんですけれども、実は昨年行われた最近の最新の情報では、67%までまた拡大しているという状況です。この熊本都市圏における車の利用率の増加は、天井を知らない状況になってきています。
実際にどんな乗り物が使われているかということなんですが、左側は都心部で、青いのは市電ですね、緑色がJR、あるいは熊本電鉄なわけですけれども、結構ここに書いてある数字はその断面の利用者数ですけれども、それとオレンジ色は車の利用です。中心部はもちろん市電等があったり、豊肥本線がありますので、緑とか青の部分があって頑張ってはいるんですけれども、放射方向だけを見る、つまり、そういうところがない方向はほとんど車が利用されておりまして、それが郊外に行くと、御代志、これは合志市ですね、あるいは菊陽町辺り、ほとんど緑色の線が薄く見えるのが豊肥線ですけれども、そのほかは全部車が使われているという状況です。
では、この交通混雑、あるいは今のような車の利用が起こっているのは何でかと、それを緩和するためにどんな対策が取られたらいいかということを少しお話しします。
これは交通流シミュレーション、シミュレーターなんですけれども、我々が開発したものですが、今上から車が流れていて、ボトルネックと書いてあるところで急に車線数が少なくなったような状況を想定してください。
これランダムにある間隔で流れてきているんですけれども、あるときからその間隔が狭くなってくる。つまりたくさん流れてくると、今後ろの方に待ち行列ができて、どんどん待ち行列が上流側に遡及していっていますよね。これが渋滞といわれるもので、実は上から流れている交通需要がこのボトルネックでさばき切れる最大の量、これよりも大きくなった時点でその超過分が上流部分へ滞留していく現象を工学的には渋滞といいます。
渋滞、渋滞というと何か速度が遅くなったりとか、最終的に現象としてはそういうことなんですけれども、こういうことが原因なんですね。これを解消しないことには、渋滞というのは解消できない。つまり上流から流れている車の量と、きゅっと小さくなっているボトルネックですね、ここの容量、この相対関係で交通混雑というのは決まるということです。
これを模式的に表したのがこの図でして、ある断面を単位時間、1時間なら1時間に通過する車の台数のことをよく交通情報センターなんかで、「交通渋滞が非常に激しくなっています」というようなアナウンスがあると思います。
例えば「浄行寺交差点では、交通量が非常に多いために、速度が低下して交通渋滞が激しくなっています」というふうな言い方をしますが、これは工学的に誤りです。交通量というのは、ある断面を単位時間に通過する車の台数ですから、完全に止まってしまうぐらい車が上から流れてくると、交通量は単位時間に1台も流れませんからゼロになります。
ですから、これでいうと、上の方からずっと自由速度、これは制限速度だと思っていただいて結構ですが、横軸が交通量なんですけれども、交通の量がどんどん増えてくると、当然速度は前に車がいますからだんだん遅くなってくるんですけれども、その断面では容量といわれる交通量ですね、それ以上の交通量というのは流れ得ないわけですね。それでも速度はどんどん下がるぐらい上から流れてくると、速度はどんどん下がると同時に交通量は減っていきます。そして完全に止まるぐらいぎゅうぎゅう詰めになったときは、あそこのゼロに落ち着くわけですね。
ですから、この絵をいつも頭に入れといていただいて、今我々が直面しているのは限界速度というところと、容量の交点、要するに一番出っ張ったところですね。あの辺りの近傍で交通混雑というのが議論されなけりゃいけないということです。
多いのは、上流からの交通の需要。車の台数であって、渋滞が進むと交通量、単位時間当たりにある断面を流れる台数は減少します。ですから、ちょっと言い方は変なんですけれども、今上流から流れてくる車の台数が多くなったので交通混雑が激しくなっていますが、交通量は減っていますと。これが工学的に正しい言い方ですね。
だから、上流からの交通需要というのを減らさないことには、駄目だと。つまり相対関係なわけです。キャパシティーと上から流れてくる車のですね。
実際、熊本市中央区を1つの道路区間というふうに考える。これはマクロな見方なんですけれども、縦軸が平均速度、横軸が時間帯の交通量ですね。これを先ほどの絵と同じように取ってみると、やはりぽこっと出ていまして、それより出たところからだんだん下に下がってきていますね。それも速度がゼロに向かって下がってきている形をしています。
それで、さっき言いましたように、あそこの尖ったところあたりを着目して、上から流れている交通量は大体今800台で満杯になっています。断面が1時間に800台が上限だということなんですけれども、それから例えば1割、700台ぐらいになると、縦軸を見ていただくと、12~13㎞/hだった速度が一遍に17~18㎞/hに上がります。つまり、物すごく急激に交通の状態が変化していって、ちょっとでも交通量が減る、上から流れてくる車の台数が減れば、速度は物すごく改善するということなんで、試算してみますと、上流からの車の流れが1割減ると、速度は33%上がって、渋滞による損失時間は大体半減するというふうなことが理論的に、実証的にも分かります。この言葉というのはよく聞かれていると思いますが、これについてはまた後でちょっと話します。
実際には、交通渋滞は解消しちゃ駄目ですね。交通緩和する、あるいはマネジメントするという考え方が大事です。例えば物を買うときに、めちゃくちゃ安くなったらみんなたくさん買いますよね。高くなったら買うのはやめようかという人も出てきます。そのように交通混雑が解消されると、またその道を使おうという人がどんどん増えていきます。
ところが、ある程度のレベルで管理する、マネジメントすると、それ相応の利用のされ方がされるということで、交通混雑の真の目的というのは、解消ではなくて緩和マネジメントです。その上で、ある程度の混雑と共存し合いながら、モビリティー、この言葉もよく聞かれると思います。移動可能性という日本語英語なんですけれども、移動の自由とか可能性、これを高めてやるというような施策が大事で、交通渋滞を解消するとかということを言っていては駄目です。
実は、道路を造るとこんなことも起きる場合があります。
左上の図が簡単なネットワークだと思ってください。AからBへ6台の車が流れるような場合ですね。上側が経路1、下側が経路2とします。5+10χと書いてあるのは車が、χというのはそこを通る台数なんですけれども、それが増えると時間は長くなりますよね。だって、少し混雑してきますから。つまり流れる車が多くなると、5+10χだけ時間がかかるというのが全ての道路区間に書かれています。
こういうところに、AからBへ6台流れたときにはどういう流れ方になるかというと、それがその下の絵です。上の経路を使うと、上の経路に3、下の経路に3、併せて6流れると、ちょうど35+63の98分ですか、下の経路を使ったとしても、63+35の98分、誰一人として今使っている経路から別の経路へ動こうとしません。なぜかというと、その人が動いたために、動いた経路は必ず1台増えますから、時間が余計かかるようになりますし、動かれた経路というのは1台いなくなりますから、短くなります。そうすると、誰かが必ず動いた元の経路へ帰ってきます。毎日そういうことやっていると、あっちが近いというのを知っていますからね。
そうすると、最終的にどういう状態で均衡するかというと、3台、3台が流れてどの経路を使っても時間が同じような状態になるはずです。恐らく今世の中というのはそういうふうになっているはずです。誰かが1人移れば、そちらの方は必ず時間が長くなりますから。こういうのがナッシュ均衡といいますけれども、そういう状態でなっているはずです。
それが右側の上のように、1から2へ新しい道路ができたとします。そうすると、経路3という、Aから1行って、2行ってBへ行く経路ができるんですが、こうするとさっき言ったような、誰一人して経路を変えない、そして使っている経路は、所要時間は同じになるような状態を計算しますと、右下のようになって、経路1に2、経路2に2、経路3に2、全部で6人が流れるようになります。
こうすると、全ての時間は107分で等しくなりますが、これを全部足した都市全体の便利さ加減ですね、総走行時間といいますけれども、これを比較してみると、道路を造る前が588分だったのが、道路を造って流れ方が変わったために、本当だったら全体的にも便利になって総走行時間というのは減るんではないかと期待できるんですが、計算してみると642分になります。
つまり道路を整備すると都市圏全体、システム全体の効率が悪くなるという場合もこうやって出てくるわけですね。もちろん先ほど言いましたように人は誰として今よりも短い時間へ移らない、長い時間へ移らないというルールが成り立ったら、初めて成り立つんですけれども、そのルールというのはそう不合理ではないはずですから、我々研究者としては、そういう流れ方を熊本都市圏で行われるとすれば、どこの断面が何台流れているというのを計算してみます。我々の部門では、これは当然の考え方です。これをプレイスのパラドックスといいます。
もっというと、エエっ!!こんなことまで起きるの!?ということを御紹介します。
左上が車と、車1台当たりの平均費用です。横軸が車の台数で、縦軸が1人当たりの平均費用ですけれども、車が多くなれば1人当たりの平均費用というのは当然高くなるので、右上がりのカーブになります。
右のグラフは公共交通の利用者で、これは軸が反対向きになっていますけれども、左側へ公共交通の利用者が増えると、1人当たりの公共交通の費用はどうなるかという絵ですが、誰も乗っていないときにバス1台買うとめちゃめちゃお金がかかりますので、初期投資の分だけぼっこんと上に上がります。しかし、それが2人乗ってくれる、3人乗ってくれる、どんどん増えてくると、1人当たりの費用というのはだんだん下がっていきます。
これを同じところに重ねます。それで自動車のゼロ、公共交通のゼロ、ここからここの幅の人たちが今都市圏で移動するというふうに考えてください。そうすると、どういうことが起こるかというと、当然車を使っても、公共交通を使っても、1人の費用が等しくなるような比率で、自動車の利用者と公共交通の利用者は決まるはずですよね。どっちかが高かったら必ず低い方に動くはずですから。
そうすると、どこで決まるかというと、ここで決まります。よく経済学で需要供給の交点でというのが、この場合は相互の費用の交点で決まります。そうすると、ここが道路整備前の交通であって、これより左側が自動車を使う人、これより右側を使う人が公共交通を使う人の数です。そのときの費用というのは、この横軸にあるあの高さになります。
ところが、例えばもともとの道路を2車線だったのを4車線に拡幅した場合を想定しましょうか。そうすると、1人当たりの費用は通りやすくなりますから下がりますね。そうすると、この費用曲線というのは、この赤いふうに右側へシフトします。同じ費用でもたくさんの人が通れるということですね。あるいはたくさん通っても、費用はあまりかからないというような曲線になります。
では、出来上がった後、どうなるかというと、先ほど言いましたように、この2つの曲線の交点で決まるはずですから、ここへ移動します。ここが新たな均衡点なんですけれども、ここというのはどういうことかというと、道路整備後の均衡交通量はこの赤のところになりますので、これより左側が車を利用する人、これより右側が公共交通を利用する人、そしてそのときの費用というのは、実はさっきよりも高いところで決まってしまうと。
つまり、ここの緑色の幅が道路整備によって自動車利用者が増加した分であるし、それによって費用もこれだけ増加するというふうなことも理論上は起こります。これはダウンズ・トムソンのパラドックスといいます。パラドックスではここかなと思っていたら、えらい違うから起こったという意味ですけれども、そういうことが起こる場合もあります。
これは必ず起こるわけではありません。かなりの条件が整っていないと起こりませんけれども、今のような場合も実際に観測されるし、理論上はちゃんと計算できます。なので、道路を造ったら駄目と言っているわけではなくて、造るときにはこういうことが起こるんだよということを考えながら、いろいろやっていく必要があるかなというふうに思います。
先ほどからいいますように、上流から流れてくる車の量とボトルネック容量の相対関係、これが重要なので、要するにどういう対策が必要になってくるかというと、容量を増やす、つまり供給を増やすか、需要を減らすか、これしかないわけですね。それが縦軸です。
横軸は、すぐできるものと短期間で費用も安くできるものと、時間もお金もかかるもの、2×2の4つの実施例に分けて、今までどんなことがやられてきたかというのを示したのがこれなんですけれども、もともと全く海外から、戦後視察団が来て、日本の道路網というのはどうなっているんだということで一生懸命やったのがこの道路施設整備ですね。それとか、熊本でもかなり立体化されているところありますし、幹線のバイパスをどんどん整備してきたと。これは造れや造れ、つまり道路を増やしたり広げる施策です。
ところが、これも市民意識が高まって、あるいは公害の問題とか、用地が高くて買えないとか、時間がかかって市民に迷惑をかける。いろいろな問題があって、このやり方というのはかなり上限が見えてきたので、今度は供給サイドも今あるシステムを上手に使って疎通能力をもう少し上げてあげようというようなことがやられ始めました。それがこの上でして、今あるものを上手に使おう方策ですね。
例えば信号制御をうまくやってやると。皆さん水道町の交差点でぼーっと信号を見ていただくと、何分かおきに周期がどんどん変わります。それは御存じないかもしれませんけれども、暇だったらみてください。それだけたくさん流すために県警は交通制御を物すごくやっています。しかし、これも面的に制御するとめちゃくちゃ大変なわけですね。あっちをよくすればこっちが駄目になります。ここをよくすれば次も駄目になります。これをいろいろ考えながら今一生懸命やられているんですけれども、これも限界です。
つまり、上手に使おう方策というのももう限界が出てきているので、つまり供給、あるいは容量サイドをいろいろ考えるともうなかなか難しい状態になってきているので、今はこっちへ移っていて、需要サイドを、車の利用を少し減らしていこう、あるいは管理していこうというマネジメントしていこうというのが主要な考え方で、世界はもうこれです。「元から絶たなきゃ駄目!」というのはちょっと大げさなんですけれども、需要を少し管理してあげるということですね。
実は、そのほかにも皆さん御存じだと思います。混雑料金制を導入するとか、官民民営化とか、PFI等を使って道路を民営化するとか、あるいはもっと大事なのは、その都市計画そのものとリンクして都市の構造を変えていくというふうなことが本質的な総合対策なんです。こういうのがありますけれども、そこまでいくと時間も物すごくかかるので、今はここの交通需要マネジメントといわれる短期で需要サイドをコントロールする、マネジメントするというのが進められています。
よく考えてみると、解決する課題は実は交通混雑の緩和だけではないなと、それを引き受ける公共交通をどう再生させていくか、この2つを両方一緒に考えないと問題は解決しないんだなというのが分かると思います。
交通混雑と渋滞の緩和と公共交通再生を同時に実現するにはどうしたらいいかということを考える必要があって、ややもするとひどい交通混雑を緩和するには道路を造ればいいとか、交差点の改良をすればいいとか、よく最近出てきているようですが、高速道路を造ればいいとか、そういうふうな話にいってしまうんですけれども、そうではなくて、実は公共交通をどう再生させてお互いがよくなるにはどうしたらいいかということを考える必要があります。
1番としては、先ほど言いました道路整備や疎通能力拡大、これは日本のこれまでの主流でやってきたわけですけれども、やっても逆に自動車の利用が増えたりする場合が先ほど言ったようなことで起こります。実際には御存じのように、東バイパスというのは北バイパスをつないだり、整備をしたんですけれども、だんだん車というのは増えてきている。日本でも十指に入るぐらいの交通量が流れているわけですね。6~7万台ですかね。そういうふうに思ったように働かない場合があります。
では、解の2として、公共交通や自転車に転換して車を少し減らしたり、あるいは管理する。管理するというと、何か強制的にやらされるんで何とかあまりよくありませんけれども、例えば皆さん、ナビゲーションシステムなんかも、あれは同時に同じ交差点にみんなが集まるから渋滞が起こるんで、時間をずらしたり、あるいはそこは満杯だから違う経路を通ったらというふうにアドバイスをすれば、実はかなり緩和できるんですね。そういうのも含めて管理、マネジメントといいます。
だけれども、それだけでは車の量は減りませんので、公共交通にこういう問題の諸元となっている車の需要を少し転換してもらおうというのが、1つの非常に有効な解であろうと。実はこれが世界のトレンドであって、熊本市、私たちが目指す解決策ではないかと私は今考えています。
今、県も採用していただいている、市長は前回の選挙の公約にも入れられていたんではないかと思いますけれども、この合言葉ですね。「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」。これは実は熊本だけではなくて、日本中でよく言われている言葉になってきました。
実際、64%が車を使っているわけですから、その1割ですね、6%ぐらいが車から公共交通機関に移れば、先ほど言いましたとがったところの速度の変化ですね、800台が700台、これ6%以下ですけれども、ぐっと速度が上がります。そうすると、渋滞はほぼ半減します。それと同時に6%、今の公共交通機関の利用にして6%ぐらいですから、車から6%移ると12%になります。ということは、倍増するわけですね。
実は、この言葉というのは上っ面だけを言っているように思いますが、実はとても論理的なんです。そのためには計画をする人たち、利用する人たち、あるいは財政担当者、あるいは有権者の方たちがどういうことをしたらいいかということを考えてみますと、計画をちゃんとやることですね。渋滞とか遅延とかを改善するためには、一番重要なのはバス等が遅れるために乗るのがいやだという方がかなりいますので、バスレーンとか、バス優先信号みたいなものをどんどん導入してあげて、遅延とか渋滞の改善に貢献すると。
それと、実は公共交通を潜在的に利用したい、あるいは利用してもいいなと思っている人がいるにもかかわらず、うまい働きかけができていないために、乗ってみると本当は便利なんですよ。そういう人たちに適切に利用促進を働きかけるような、これはモビリティマネジメントといいますけれども、データに基づいて潜在的な需要に働きかけて、そしてそれに合わせるような適切なサービスの水準に持っていくというふうなことをやることですね。
これが非常に重要な計画であるし、利用者はどういう情報がほしいかというと、例えば歩いて駅まで行って、駅から幹線に乗って、それからバスに乗り換えて職場に行くということを考える場合、どうしても幹線の電車、バス、駅までの徒歩を別々に考えて、一貫した利便性というものを享受できていないということですね。
ところが、これをスマホ1本で、何分で行って何時のものに乗り換えれば、何分で待ち時間があって結局何分で着きます。ましてやそれが予約制ができたり、あるいは料金が一気通貫で支払えるというふうなことができればきっと乗る人もっと増えると思いますね。MaaSといいますけれども、そういうのをどんどん提供していくことですね。
これも最後に話をしますが、そういうことというのは実は熊本市もかなり先進的にやられていますが、それでもなかなかうまくいかないようなことが起きているので、その場合にはもっと行政というかな、自治体が働きかける必要があるというので、これも最後にお話ししたいと思います。
公共交通はこの辺簡単に話をしますが、2008年にはこの4社、熊本市交通局のバス部門ありましたけれども、2018年にはこの交通局がなくなって、民間に全部移譲したわけですね。代わりに出てきたのが面的な移譲先である都市バスでして、都市バスは非常にいい働きをしているんではないかと私は思います。
これは予算補助ですね、一番多かった頃は平成25年ぐらいですかね、この緑色のところが自主運行系統に対する補助額ですので、17億円ぐらいですね、補助をしていたときがあります。これは熊本市の一般会計からの繰り入れですので、このほかに運行補助として2億円ぐらい入れていたはずなので、当時は20億円ぐらいの補助をやっていましたが、その後、都市バスに全部移譲された頃を中心に少なくなって、今はもうこのぐらいですね。これ平成30年ですから、今はもっと少なくなっているはずです。うまく機能してきたなと私は思っています。
当時は先ほど言いましたように、最盛期の4分の1しか公共バスを使わないと、昭和46年ぐらいが多分最盛期だったと思います。その4分の1ですね。直近10年間でも3割ぐらい減ると。それと先ほど言いましたように、運行補助が2億円ぐらいで、そのほかに一般会計からの繰入れが十数億円ありましたので、それとここにありますように、2003年に九州産交が経営破綻して産業再生機構から支援を受けたり、熊本電鉄も私的整理に入ったり、熊本バスも地域経済活性化支援機構によって支援を受けるというふうに、今ある熊本の都市バス以外は全て一度はつぶれる、支援の仕方はいろいろ違いますけれども、1回つぶれたということで、バスサービスの改善と運用を抜本的に考え直さなければいけない時期というのが出てきました。
それに対して、公共交通再生のための政策として、2008年から熊本市のバスのあり方検討協議会という今の地域公共交通協議会の前身に当たるものなんですけれども、これは大西市長の前の市長が我々に諮問して答申したものですが、私が思うにこれは画期的なんですね。
その上の方を見ていただきますと、「熊本市営バス事業を民間事業者に全面移譲すると共に」、これ全面移譲ですね。「バス事業を市民の生活交通を確保する重要な行政サービスの一環と位置付けます」と言っています。
つまりこれはごみの収集とか、水道の供給とか、それと同じような行政サービスの一環とみなしますというふうに言っています。そして行政は市民に対してモビリティー水準、移動可能性の水準を確保することにだから責任を持ちますよと、そのかわり適切にバス運営にはコミットしていくということを中心にした市長からの諮問に対して、我々のこの協議会でこういう答申をしたら、市長は、ではこれで今後のバス、あるいは公共交通の政策はやっていきましょうということで決まって、それがずっと今根底にあって進められているわけですね。
これは画期的です。どこの自治体に行っても、バス事業を公共サービスの一環と位置づけているということを文書に示しているところは多分ないと思います。その例がこの公共交通基本条例ですね。これは前文、目的のところを抜粋していますけれども、「移動する権利を有するとの理念を尊重」する。移動する権利を認めるとは言っていません、これやると立田山の上に私が住む、居住は自由ですから、立田山の上で見晴らしがよくて環境のいいところ住みたい。だけれども、移動の権利を与えると、そこへバスを引いてくださいという権利に対して義務が生じますから、それを実行しなきゃいけないので、その気持ちは分かるから移動する権利を有する理念は尊重する。そのような政策を進めていきます。そのような地域社会を実現していきますということを言っています。
これはよく参照されるフランス交通法典ですね、Code des Transportsと言われるんですけれども、これはもう同じような表現です。フランスは移動の自由が認められていると、権利として認められているということを間違って言う人がいますが、そんなことは書いてありません。これと同じような表現です。ただ、やはりその重視の仕方が全然違うということですね。
そのためには、自動車から公共交通への転換を推進して、公共交通を基軸とした多核連携のまちづくりを推進していきましょうと。そのためには市、市民、事業者、あるいは商業者とかが参画して一緒に働いていきましょうということを言っています。これは本当に中身も高い、理想だけではなくて中身も非常に高い公共交通基本条例の目的、前文だと思います。
これを実行するために、通常条例とか法律というのは目的があって、その後、言葉の定義がありますが、この定義もちゃんとされていまして、地域を3つに分けますと、その3つはバス事業者が自主的にサービスするエリアと、それだと赤字だからやれない。
しかし、地域の住民が協議会をつくって、自分のところにこういう路線を引いてくださいという不便地域と、これはバス停から500メートルから1,000メートルぐらいの間のエリアですね。これをつないだ不便地域、そして1キロより離れたところ、これは空白地域、この3つに分けてあります。そして、それぞれの地域にそこに合った適切な公共交通機関をサービスする。つまり一人も漏れは出さないといっているんだから、3つに分けてそれぞれに必ず適切な公共交通機関をサービスしているわけですね。こんなところ日本中ないです。
例えば西鉄の例をいうとよくないですけれども、あそこもやはり独占企業でかなり熊本のバスに比べると経営状況はいいんですけれども、赤字のところはぱっと切ります。そうすると、そこは完全に空白地帯になって何もない状態です。ところが、熊本市の場合、そこにあった公共交通を必ず導入しているわけですね。
ここにそこのメンバーおられると思いますけれども、それがどういうものかといいますと、この自主的にサービスするエリアですね。とはいっても、今収支率が6~7割なので、赤字でも実は民間事業者は提供してくれているんですね。主にこういう仕組みでやっています。
右上のようにいろいろなところから都心へ、今でもこういうところ結構ありますけれども、路線が長くて街の中へ全部バスが入ってくるような仕組みを、右下のように適切な乗換え拠点を造ってそこから都心までは高速で大量の交通機関に任せて、その周辺部の枝のところですね、フィーダーといいますけれども、ここで往復をたくさんできるようになりますから、活躍してもらってサービスを上げるというような仕組みにしましょうということですね。これをゾーンシステムといいますが、これ熊本市の場合、今東西南北ですね、一応これで路線を編成していっています。成功しているところ、あまりうまくいっていないところいろいろありますけれども、考え方はこうで、都市圏全域をこんな考え方で再編し直しているというのは多分あまりないと思います。
それと2番目ですね、不便地域、500メートルから1,000メートルのエリアですね、ここは緑色の矢印で示しているように、地域が支えるコミュニティバスですね。ゆうゆうバスですが、これは地域の方たちに路線とか止まる停留所みたいなものを議論してもらって、ここに走らせてくださいという申請をしていただくと。そうすると、市は提供します。ただし、7割までは赤字でも補填しますけれども、3割は自分たちで稼いでくださいという最初の契約を結んであります。
もしこれ何でも出すといったら青天井ですから何もしなくても空バスがどんどん走らなければいけなということになりますから、3割は自分たちで稼いでください。それは別に乗車料金だけではなくて、例えば通る沿線のスーパーとかお医者さんとか、そういうところから基金をもらってもいいし、とにかく自分たちで支え合うような路線を造ってくださいということですね。
ところが、残念なことに最初5路線、9系統でしたかね、ありましたけれども、この3月31日に最後の植木循環ですね、これも廃止になってしまいました。全てなくなってしまいます。
では、その地域どうなるか。それは先ほど言いましたように、不便地域から空白地域になるわけですね。これが普通のところはならないです。でも、これは、熊本市は絶対に提供するといっているわけですから、次のランクの空白地域になります。
空白地域はどうやっているかというと、これは乗合タクシーですね。これは全面的に行政が経費を負担するということです。ただし、御存じのように、最寄りの乗換えのバス停までしか走りません。それと定時です。定路線です。
私、前から言っているんだけれども、定時と定路線なんてバスが小さくなっただけだから、利便性上がらないからオンデマンドにしろと言っているんですけれども、あるいはエリアを自由に動き回るようなですね。ただ、ここの走っているところは、どこも谷間なんですね。谷筋なんですよ。ですから、左右へ動き回ることはできないし、バス事業者もそうですけれども、タクシー事業者も人員が全然足らないので、ここに専念することがなかなかできないということで、今はこういう状況になっています。
ただ、この実態を見ると、一番下の1.19という数字は平均の乗合率で、タクシーには平均1.19人しか乗っていない。つまりマイタクシーになってしまっています。それとグレーのハッチがかかったところはやめたと、要らんと言われるところもあったり、グレーのところから色がついたり、数字が出たりしているところは、新規にコミュニティバス、つまりゆうゆうバスが走っていたところが、この乗合タクシーに変わっていったところです。非常にダイナミックに変わっています。
その典型が乗合タクシーをやった、最初はゆうゆうバスが走っていたけれども、これでもこれが廃止になって乗合タクシーにしようと思ったけれども、それよりも先ほど言いました、ここは谷筋ではないので、天明あたりですけれども、面的なサービスができるということでリアルタイム・オンデマンド乗合タクシーですね、チョイソコくまもと西南が今非常に高齢者を中心に利用者が増えていて、今の面的なリアルタイム・オンデマンド型の面的なサービス、これが非常に成功している例です。
今のように、熊本市というのは、実は置いてきぼりを絶対に全然してないんですよ。濃淡はありますけれども、成功しているところ、そうではないところ、でも理念としては非常によくできているところだと思っています。
それで、実はこういう動きというのは国までも動かしていまして、これは随分前ですけれども、私、熊本大学にいたところに、当時は市営バスと産交バスと電鉄バスが熊本大学の前から都心まで行っていたんですけれども、市営バスは産交バスと電鉄バスに移譲しましたので2つになりました。だけれども、時刻表はそれぞれ別々にあったんですね。でも、我々乗るのは、黄色いバスだろうが、青いバスだろうが関係なくて、とにかく都心に行ければいいわけなので、それを今何時だからこっちは駄目、こっちは多分あるなというふうなことで、とても不便だったのを1枚のバス時刻表にしていただいた例です。
これは一目で分かります。色が違って、赤が電鉄バスで黒が産交バスだけで、私は電鉄バスしか乗らないなんていう人は多分あまりいないと思うので、これで十分というか、こっちの方がよほどいいわけですね。
もっとすごいのは右側でして、これは日銀前から宇土方面への路線ですけれども、全ての会社の路線を1枚の路線図に書いてあるわけです。こんなこと日本中探しても多分ないと思います。必ず時刻表と路線図のセット、書き方が違うから同じバス停が書いてあっても全然イメージができないですけれども、これは一目で分かる。これは実は国が、これはカルテルなんですね。でも、これは当時からやっていました。後でちょっと紹介します。
それともっと非常に便利なんですけれども、バスきたくまさんですね。これは地震でループ型の時刻表示が壊れちゃったので、こういうふうな携帯で見られるようなものになったわけですけれども、県下全域で同一のバスロケーションシステムが使えるというのは、多分熊本市ぐらいしかないんではないですか、最近は変わってきているかもしれませんけれども、地震の復興費用でこれに入れ替えることができました。とても便利です。でも、残念なことにうちの学生さんに聞くと知らない子がいっぱいいます。
こういうことをいっぱいやってきて、この赤が課題だったのに対して、青色の解決を促したということは、熊本市の交通政策課の方たちが頻繁に国の方に行って、こういうことをやりたいんだけれども、今こういう制約があるけれどもどうにかならないかということで、いろいろそれを緩和していただいた例で、その一番の成果が赤で書いてある令和2年11月27日のバス事業の独占禁止法の特例法ですね。これを認めさせたことです。
御存じのように、路線を別の会社同士で調整し合ったり、運行頻度を調整し合ったりするのも完全カルテルだったんで、今まで一切認められていなかったんですけれども、先ほどの時刻表を一緒にしたりとか、路線図を一緒にしたりとかする、法律に触れるぎりぎりのことをずっとやりながら、最終的にバス路線網の調整、それと運行費の適正化を幾つかの会社の中で相談してやるということまでは認めてもらえるようなことになりました。
最終的には、皆さんも御存じだと思いますが、ソウルなんていうのは100社ぐらいあるんですけれども、バスの色3つしかありませんね。幹線部分とフィーダー部分と都市間ですね。それぞれは別の会社ですけれども、機能に合わせて色も一緒にしてあるわけです。財布も一個です。全部集めてそれを提供している、当時ですから今ちょっと変わっているかもしれませんけれども、代キロですね、サービスのレベルに提供しているサービスのレベルに合わせて配分するというふうにしています。
日本のこの独禁法の特例法では、お金のことについては一切まだ触れません。将来的には、そういうことができるようになるとかなりいろいろなことができるかなと思います。
彼らがやったのは、今言いました重複区間等の最適化ですね。それと経営資源を余ったところから別の会社へ回すというようなこともやっていまして、この共同経営推進室ですけれども、ここが偉いのは計画を市民に訴えて、実際にやってその成果を評価して公開するということをちゃんとやっているところです。
その例が次のページなんですけれども、これは第1期の成果なんですが、収益性も改善していますし、運転士数も5.5人余らせることができたと。そして車両数も4.6台余らせることができたと。それによって足らないところへ、あるいは新しい路線へこのバスとか、運転士さんを回しています。別の会社がやるところですね。出向みたいな形だと思うんですけれども、そういうことまでやっています。これはほかのところに聞くと、口が開いたら戻らないぐらいびっくりされます。
こういうことを一生懸命やってきたわけですけれども、実はそれでも限界。バスだけでのことですけれども、共同経営推進室バス会社5社でいろいろな検討をされていまして、経営効率をいろいろなことを工夫してやられているんだけれども、経営努力の結果上の限界もだんだん見えてきたから、さらなるいろいろな組織との連携によって公共交通全体の在り方を考える必要があるんではないかということで。その仲間に入っていただいているのがもちろん県、市ですが、そのほかに熊本市の交通局と幾つかのタクシー会社が合併した地域交通ホールディングス、タクシーの会社としてはTaKuRooという名前で走っていますが、そこです。
そこで、一番下にあるように、エリア全体の最適路線網への転換を図りつつ、そのほか、タクシーも含めた、あるいは市電も含めた公的機関が、公共交通に責任を持つような体制が取れないだろうかというふうなことを市の方へ今いろいろ相談されているんではないかと思います。
よく見て考えてみると、左の2枚がバス・市電の収支率です。実は熊本市というのは頑張っていまして、バス5社の収支率83%ですね。市電も86%、赤字なんですけれども、頑張っておられます。
ところが、欧米の収支率がその真ん中のグラフなんですが、ロンドンなんていうのは125%、つまり黒字なんですが、そのほかのフランスですね、ドイツ、ベルギー、とにかくヨーロッパの国ですね、棒グラフを見てもらうと、ほとんどの国が30%~60%の間です、収支率。つまり、7割~4割はどこかから補填していただいているんですね。これが常識で、ロンドン、イギリスは例外です。
それに比べると、熊本市のバスも市電も頑張っておられるということです。それでも先ほども申し上げたように、これ限界という状態になっていますから、これをどうにかしなきゃいけない。何かいい方法ないかなと思って右側の表を見てもらうと、実は交通に関する行政予算を地域交通、公共交通と思っていただいていいと思いますが、道路と予算額を比較してみるとかなり差がありまして、地域交通への予算は道路予算のほんの3%ぐらいしか過ぎません。だから、道路予算の5%をバスの地域交通の方へ回してもらうと、マイナス10億円ですね、この赤字が解消できます。
こういうふうに、もう少し道路と地域公共交通ですね、そこがいろいろ相談をしていただいて、利用者あるいは都市交通全体としての利便性とか、そういうものが上がるような工夫というのはできないことはないんではないかというふうに思います。
どんなことがやられるかといいかというと、これは公共交通だけの話なんですが、今までバスを走らせたりするのに、バスの路線網の計画とそれを実際に走らせる人と、お金のやり取りというのは全部分離されていたんですね。これは共同経営推進室になる間ですけれども、計画は行政が立てて、事業者が走らせて、お金のやり取り、補助金を中心とした補助金のあたりを運営してやるということであって、これが実は、ほとんどがバス事業者が全部やっていたわけです。
ところが、外国は先ほど言いましたように、右側のように計画をするのは熊本市を中心としたもの、それと第三者機関が真ん中にいて、ちゃんと走っているかどうか、あるいは補助金の申請とか、それの配分とかをやるし、バス事業者は運行に徹するというような、要するに計画と運営と運行を分離したような組織体系、これがヨーロッパを中心としたところのやり方です。
今、共同経営推進室は大体このような形になって、熊本市はなりつつありますが、一番下のところはバス事業者だけなんですけれども、ここが今後先ほどちょっと申し上げた地域公共ホールディングスみたいなタクシー事業者とか、非常に今便利で皆さん利用者が増えていますチャリチャリですね、ああいうところがこの下にぶら下がってもらえるととても便利になる。ここを御存じかと思いますけれども、MaaSオペレーターとして位置づけてくると、これは完全な熊本MaaSになります。
そしてさらに、これに先ほど言いましたお金のやり取りとか、今は触っちゃいけない部分もありますけれども、あと料金の設定の仕方ですね、そういうところまで踏み込むと、これも聞かれたことがあると思いますけれども、ドイツを中心としてあります運輸連合ですね、こういうのに実はなるんです。直前まで熊本市の場合来ています。どうにかここへ持っていくのがいいんではないかなと思います。
とはいうものの、そういうことをするときに、ちょっと井芹事業管理者には申し訳ないですけれども、目に余る交通局と書いていますが、ちょっともう少し公共交通協議会とか、共同経営制バスですね、あるいはタクシーのところに協力をしていただきたいと思う具体例が、私、どうしても均一料金と昔からワンコインだから便利だといいますけれども、180円でワンコインではないですよね。100円とか500円だったらワンコインでできますけれども、それを言われるのがよく分からんし、それは本当に妥当なのか、合理的なのか、これもう一回ちゃんと考えてもらいたい。ICカード変わりますけれども、とにかくタッチ決済でできるわけですから、自動的に課金をされるわけですね。そのときにコインで出すときに便利な額、そんなもの関係ないではないですかということですね。
それと競合して走っています健軍・益城方面ですね、これは料金がバス路線と全然違うと。もう少し何かうまく調整されるといいんではないかと。
それと、一時期快速運転をしたらどうだということで、物理的になかなか難しいというのは分かりますけれども、バスとしては市電と、先ほど言いましたゾーンバスシステムといって乗換え拠点から都心までは大量で高速の乗り物にするということで、その代表格が市電です。今度3両編成の高容量の車両がどんどん入っていきますから、高速で大量が可能になっていきます。そこは、本当はバス会社に任せたいと思われているんですね。それよりも郊外部分のフィーダー部分でたくさん人を健軍なら健軍とか、神水なら神水に集めてくる作業をしたい。
それと快速運転すると、市電の中であまり乗っていないところあるんですね。そこは飛ばしますから、高速になるんですね。では、誰がその飛ばした駅の近くの人たちはどうするのか、バスがそこはちゃんと拾っていきますと言ってくれているのに、それがなかなかうまくいかないというのがちょっと残念だなと。
それと今もそうですけれども、VISAタッチですね、これは降りるときだけにしかしませんけれども、何で乗るときにタッチさせないんだろうと。どこから乗ってどこへ下りたという、それが何時何分に乗って、何時何分に降りたという宝の山のデータ、これを全部放棄してしまっている。一言入れるときに誰かに相談されなかったのかな。いっぱいありますからやめます。
下から2つ目ですね、上下分離ですね、これとても大きな改革だと思います。ところが、経営計画書を読みましたけれども、需要をどうやってその後獲得していくのか、上下分離を使うことによってそれがどういうふうに機能するのかということは、一切書かれていなくて帳簿だけが載っているという状況で、別にあるんだと思いますけれども、それがあまり聞こえてこないのがとても残念です。
都市軸というのは、物すごく大事なんですね。今、人が住んでいるところに軸をつくって、軸と言っていればいいんではないんです。軸というのは、そこの沿道をどういうふうな土地利用も含めて考えていくかというのが大事で、その軸によってそこに沿道に高収益、あるいは高機能の施設を配置して、そこを使う人たちが増えることによって、またその軸の乗り物、公共交通を使う利用者も増やしていくということのサイクルをつくることが都市軸をつくることなんですけれども、そういうのが全然あまり見えていないと。今度の健軍からの延伸ですね、私はぜひやっていただきたいんです。
それにとどまらずに、まだまだ軸として街の形をうまくやっていく軸というのは、まだたくさんあるはずですね。そこには市電は無理かもしれないけれども、例えばBRTみたいなものをどんどん導入して、もちろんそのためにはバスレーンが必要ですけれども、そういうことをやって軸を形づくると同時に、都市の形を形づくっていく、そういうことを一緒にやっていくという、そういう執行が必要だろう。それの一番大事な市電をお持ちの交通局には、もう少し協調あるいは連携していただけるといいかなというふうに思います。
それをするときに、これは最後になりますけれども、ややもすると熊本市だけの話になってしまうんですが、広域地方政府組織、これがとても必要だと思います。
例えば消防とか、水道というのは、広域事務組織がありますよね。それと同じように、熊本市だけではなくて都市圏なんですね。益城町のことも考えないといけないし、ましてや今非常に注目されている菊陽町とか合志市とか、あるいは南の方もそうですけれども、そういうところを一緒に考えるような広域地方政府、世界で一番住みやすい街1位のポートランドですね。ここではメトロという組織がありますし、パリはパリ市だけではなくて都市圏というメトロポールという組織になっています。そこでは交通の計画、料金の設定、課税、これも全部基礎自治体ではなくて、メトロポールとか、メトロという広域地方政府が行っています。そういうのが今後は必要になってくるかなというふうに思います。
3番目は、PSOと、これは例えば熊本市ではバスは最低15分に1本、これぐらいのネットワークでという計画を立てたら、それをやる人を入札に応じてというやり方ですね。今は自主的に各事業者がネットワーク、もちろん市と調整しながらやられていますけれども、赤字になったら補填するというやり方なんですが、PSOというのは、パブリックサービスオブリゲーションと言って、その入札に応じるときにこれぐらいのお金でやります。その代わり提示された契約は必ず守りますというやり方ですね。これはヨーロッパでは当たり前です。
だから、世界に3つか4つ大きな会社があるんですけれども、イギリスの会社がベルギーで走っているとか、そんなの当たり前なんですね。この契約さえ満足すればいいわけですから。利用者は誰がやっていようと、実は関係ない。だからといって、熊本市ですぐやれとは言いませんよ。だって、長い歴史の中で地権者の方とか、投資されている方の関係がありますから、一挙にそういうのは難しいのは分かっているんですけれども、こういう考え方も視野に入れながら、サービスの向上に、それともちろんこれだったらやると言っているんですから、その会社は経営的にもそれはできるわけですね。そういうことを了知させてもらいたいなと。
つまり、地域公共交通維持改善のための本質的議論というのは、こういうところまで入っていかないといけないので、今こそ熊本市でこういうことが始まればいいなというふうに思いますし、実は日本中が熊本市が次何やるかをとても期待しています。
この辺にしておきますかね。ちょっと1時間になっちゃいましたので、あと計画の立て方もいろいろ考えなきゃいけないんですけれども、これはちょっと飛ばしましょう。
真ん中だけやりますかね。今までは需要がこうなるから、こういうふうな施設整備をしなきゃいけないというような需要追随型の開発だったんですけれども、もう需要なんて伸びるはずはないんですね、人口がこれだけ減ってきていますから。では、こういうところを着地点に置いて、そうするためにはどうやって行ったらいいかなというふうに後ろ向きに計画を、後ろ向きといったらマイナスのように見えますけれども、目標を定めてそれに到達するような最適な計画はどうあるべきかということを考えるのが今のやり方なんですね。
これはまだ日本の場合なかなかやられていないんですけれども、ヨーロッパではもうこれは当たり前です。バックキャスティング型の計画のやり方ですね。これも今の交通マスタープラン、パーソントリップ調査の分析とマスタープランの作成が今年、来年中に行われますが、こういうやり方で進めていきたいなと思っていますけれども、今後、熊本市でも立案されるようないろいろな計画というのは、こういう形でないとうまくいかないんではないかというふうに思っています。
ちょっと長くなりました。御清聴ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 ありがとうございました。
以上で、意見陳述人からの意見の開陳は終わりました。
それでは、意見陳述人に対する質疑をお願いいたします。
なお、念のために申し上げますが、意見陳述人は委員長の許可を得て発言し、委員に対する質疑はできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、委員の方々お願いいたします。
◆上野美恵子 委員 溝上先生には、今日は大変貴重なお話ありがとうございました。
私も公共交通の委員会等々で、ほかの委員会でも御一緒させていただいたこともございまして、今日また改めて勉強になりました。
あらかた前半のところは本当に私、考えていたことと一致点が多くて、とてもうれしかったです。
ちょっと分からないところがあったのでお尋ねしたいんですけれども、さっき大変厳しいというふうにおっしゃった目に余る交通局の非協調というページがありましたが、ここのところで丸ポチの1点目の「ICカード導入後も全線180円均一運賃とすることの妥当性、合理性」という、この点の指摘があったんですけれども、先生としては、ではどういうふうにしたらいいとか、お考えをお持ちであればもう少し教えていただけないでしょうか。
◎溝上章志 意見陳述人 電子決済になっているわけだから距離制にすればいいんですよ。何の問題もないと思います。だから、バスと同じようなやり方にすればいいんだと思います。長く乗ったら高くなる。今均一運賃ですけれどもね。
ちょっと聞いたところによると、ゾーン運賃にしたいというふうなお考えもあるようですが、何でゾーン運賃にするのかの理由もよく分かりません。そしてそれがバスと共通のゾーン運賃だったらまだ分かるんですけれども、市電だけがやりそうな感じになっていて、そのあたりの話がどうなっているのかもよく分からないうちに、何かいろいろな料金システムを考えられているらしいんですけれども、それは置いといて、とにかくICカード等があるわけですから、距離運賃、バスと同じ距離制にすればいいんではないかというふうに思います。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
そうしたときに長年熊本市は均一料金で来ているので、遠いところから中心部に出てくるときにすごい安い料金で来られるので、市電をうれしく利用できるというか、やはり公共交通を優先して使おうという意思が働いていたと思うんですよね。
その前のところで私も共感したんですけれども、今後、要するによそからのかなり距離があるところからの車の流れを中心に抑えていく、なくすではなくて抑えていくためには、一定そういうところからの車で来る方たちに公共交通を利用していただくというふうにしたらいいんだなと思ったんですけれども、そうなると、例えば路線が決まってはいますものの、今均一で安くできている人たちが距離制によって若干高くなる部分が出てくると思うので、そうなった場合にどうなのかな。
むしろさっき先生が前段でおっしゃったように、今の公共交通を今後車からもうちょっとシフトして利用促進していくためには、今までは公が補助をしていくという考えだったんだけれども、もっと支えていくというふうな側面が必要ではないかという御指摘があったと思ったんですけれども、そういうふうにするならば、市電の均一料金を一定部分引き上げていくような変更の仕方というよりは、バスをもっとちょっと離れた距離からでも安価で利用できるような、そういう工夫の方が利用者側からするならば、バスにもっとたくさん乗ろうというふうになったりしないかなと思ったんですけれども。
◎溝上章志 意見陳述人 その考え方も一つあると思います。今はだから、同じところを走っているにもかかわらず、システムが違っていることが一番問題で、バスの料金のシステムと市電のシステムを共通にして、バスと市電の区間は全部180円にバスもできればいいんですけれども、恐らくそうすると今よりももっとバス会社の経営状態は悪くなると思います。
そこに例えば市が赤字分をもっと補填すればいいではないか、それもありますけれども、そのコンセンサスというのはなかなかまだ取れていないような気がしますから、とにかく料金の問題にしろ、とても難しいわけです。難しいというか、ほかとのことを考えないといけないし、収入・支出、財政のことも考えないといけないので、少なくとも今、あまり抵抗なくやれるのは、全体的に下げて距離制にする。市電も距離制にするけれども、バスも全体的に下げて車へ戻っていく人をできるだけ下げる。できれば、バスも安くなったから公共交通機関、車からバスにも乗ろうという人を増やす。そういうことが大事かなと思いますね。料金の問題とても大事だと思います。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
最初の公共交通に対する財政的な何か問題というところで、補助を出してあげられるというのはでなくて、もっと公共交通を支えていく、利用を徹底的に促進していくという立場に立った財政的な支えというか、それが必要なんではないかなと私、お話を聞いて思ったもんですから、何ページだったかな、道路との予算の比較とかもありましたけれども、もう少し車を調整していくというふうな発想の方に重きを置いて、道路中心から公共交通の予算配分というのを先生がさっきおっしゃったように、比率を増やしていく必要があるなというふうに感じました。
◎溝上章志 意見陳述人 基本的に私も同じ意見です。ただ、料金の設定の仕方はこれから皆さんで考えていただきたいと思います。
それと、ただ、赤字の補填をしてあげればいいんではないかという発想から、やはり今おっしゃったように、積極的な投資といったらいけないけれども、事業者ではどうしてもできないことがあるんですよ。
例えば、先ほども健軍を乗換えの拠点にしようとする考え方非常にいいと思うんですね。ところが、木山とか、長嶺とか南の方からそこへバスが入ってきて、止めるところがない。回転する場所がないんですね。これを自分で車庫とか、回転場を民間事業者造れと、これは無理です。そういうふうな、要するに物的な投資で施設の投資、こういうのは行政が率先してやっていただくというのがとても大事だということで、赤字補填だけにとどまらないような公共交通サービス全体のサービス水準を上げるための投資、そういうのは積極的にやっていただきたいというふうに、同じように思っています。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございました。
私もそう思います。
○田中敦朗 委員長 ほかにありませんか。
◆藤山英美 委員 溝上先生、お世話になりました。いろいろな視点から御指摘をいただきました。
ちょっと今の上野委員の関連ですけれども、市電の150円均一運賃というのは、私が提案して実現させていただきました。なぜかというと、その当時は、定期券以外は整理券を取ってほとんど現金だったんですよね。運転手さんの精算のときの苦労を考えて、そして執行部に聞いたんですけれども、150円均一だったらとんとんという話もあったもんですから、それでは働き方もあるからということでやって、バス事業者の方には申し訳なかったんですけれども、そういう採用をしていただきました。今のようなICカードでやれば距離制でもよかったかと思っておりますけれども、その当時は現金決済だったもんですから、そういう提案をいたしました。
そして産交さんは私の地域ですけれども、180円のことで路線の見直しを相当されているんです。だから、電車通りは激減しております。そして地域の中に、何本も路線を造られたんですね。私もコロナのときはあまり利用しなかったんですけれども、その後、乗ってみると結構利用がありますので、今までバス停まで歩く距離が長かったところに路線ができたもんですから、かなりの利用が高くなって、そしてほとんどがいろいろな経路を通して県庁経由で合流するようになっているんですね。結構利用はあって、本当にバス事業者のそういう努力というのは感じております。
しかし、空白といいますか、なかなかバスを利用できないところを今後どうするかというのは、先生の御指摘のとおりだと思いますので、そういう利用が公共交通でできれば、もっとよくなって自家用車の利用も減ってくるんではないかなという思いはあります。ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 そのほか質疑はございませんか。
◆齊藤博 委員 今日は、先生ありがとうございました。
ちょっと先生の御見解を改めてお尋ねをしたいと思いますが、公共交通全体での不具合のページにライトレールの宇都宮駅の御紹介があっておりますけれども、いわゆるLRTといわれるもの。この熊本市の今の公共交通の現状も踏まえる中で、BRT、バス・ラピッド・トランジット、この可能性というのは、先生どのようにお考えなのか、可能となれるような素質があるのかどうなのか、ちょっとそこの御見解を聞かせていただければと思いますが。
◎溝上章志 意見陳述人 BRTというのは、バス・ラピッド・トランジットなので、連接車両を走らせたらBRTと思っていらっしゃる方がおられますけれども、決してそうではなくて、ラピッドではないと、速くないと駄目です。速く走るためには、車に邪魔されないようにしないと駄目なので、やはり専用レーンがどうしても必要になると思いますね。専用レーンを増やすということは、普通のバスにとっても速度が上がります。
ただ、需要が多いところは連接車両で高速で走らせないといけない。それが実は先ほど言いました都市軸に当たるところで、今、市の方で一生懸命計画、あるいはもう実行されるんではないかと思うんですけれども、産業道路ですね、東バイパスから大江の交差点辺りまでですかね。あそこを5車線化して上りか下りかだけをバスレーンにして、連接車両を走らせる。それだけでは多分まだ不十分で、本当は長嶺あたりまで延ばさないと駄目だと思うんですけれども、そういうところにBRTというのは非常に役に立つだろうと思います。
だから、そういう路線を積極的に造っていく、そして沿道の土地利用とか施設配置を適切にしていって利用者をさらに多くして、都市としての機能を向上させると同時に、交通軸での利用者を増やしていくということをどんどんやっていくところですね。
これは、今言いました産業道路だけでなくて、実は南熊本駅のところがとてももったいないんですよね。JRで南の方から、八代の方から来たら、都心に行くには今新水前寺駅をみんな使われていますけれども。もうあそこは混雑で市電も満杯、乗れない状態。実はその前の駅で降りて、国道266号線ですね、今のところまだそんなに混雑はしていません。もともとあそこは市電が走っていたところですから、あそこの両側をできればLRT、でもLRTが難しかったらBRTですね、そういうふうにして活用されれば、南熊本の利用価値物すごく上がると思います。
今はないことはないですけれども、熊本バスが一生懸命やられていますけれども、まだ何というかな、ブレイクスルーになるほどの斬新さとか、利便性の向上というのがやはり見られないですよね。あそこなんかは、次にやるところとしては非常にいいところではないかなと思います。
先ほど言いましたように、2両編成の連接車両を走らせたらBRTということではないとだけちょっと記憶にとどめていただいて、とにかく速く、定時性を持って走らせる、それも高頻度で。そのようなバスシステムのことをBRTということですね。たくさん可能性のある路線はあると思います。
○田中敦朗 委員長 そのほか質疑はございませんか。
いいですか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 それでは、ほかに質疑がなければ、以上で意見陳述人に対する質疑を終了いたします。
本日は大変お忙しい中、本委員会に御出席いただき、また貴重な御意見を述べていただきまして、本当に溝上先生ありがとうございました。心から感謝申し上げます。
本委員会といたしましては、本日いただきました御意見を今後の調査に十分に生かしてまいりたいと考えております。
本日は大変ありがとうございました。
どうぞ御退席ください。
〔溝上章志意見陳述人 退席〕
○田中敦朗 委員長 以上で、意見陳述人からの意見聴取を終了します。
次に、「公共交通に関する住民アンケートについて」、「次期地域公共交通計画の策定に向けた取組について」、執行部の説明を求めます。
◎大川望 交通企画課長 それでは、資料1をお願いいたします。
「公共交通に関する住民アンケートについて」でございます。
地域公共交通計画の策定に向けましては、市民の方々、地域の特性に応じた施策を講じることが当然必要でございます。市民等の公共交通に対するニーズ等を把握するためにアンケートを実施するものでございます。
2、アンケートの概要でございますが、対象といたします市町村にお住いの方々でございますが、記載のとおりでございますけれども、例えば山鹿市であったり、玉名市であったり、やはり植木にお住いの方々であったり、河内にお住いの方々というのは、市域を超えたところでの生活圏域等も考えられますので、そういった地域住民の方々の御意見というところも加味して調査をかけたいというふうに思ってございます。
方法につきましては、WEBアンケートと記載をしてございますけれども、各世代、いろいろな世代の方からの御意見を賜りたいというふうに考えてございますので、しっかりと聞き取りができるようにWEBアンケート以外の方法についても検討いたしたいと思ってございます。
調査の時期につきましては、12月頃を想定してございます。
3ですけれども、アンケートに盛り込む視点というところでございますが、大きくは記載のとおりの考えでございますけれども、各委員の方からはこういった切り口での意見を聞くとよいだろうとか、そういったお気づきの点ございましたらば、御意見をいただきたいというふうに考えてございます。
また、取りまとめましたアンケート結果につきましては、本委員会にまた御報告を差し上げたいと考えてございます。
続けて、資料は都-1をお願いいたします。
ICリプレイスについてでございます。
昨日、9月30日ですが、バス事業者の方が記者会見等を開きまして、報道等でも御承知かと思いますけれども、決済手段の機器入替の時期というものがはっきりと示されたところでございます。
図示してございますとおり、全国交通系ICカードについては、11月15日をもって利用ができなくなるというところでございます。
また、最下段でございますが、タッチ決済、緑色で付しておりますが、この環境が3月上旬から利用が開始できるということになってございます。
この間、機器入替後、3か月ちょっとかかるというところでございますが、この間につきましては、くまモンのICカード、または現金という支払い手段のみというところになりますので、それに対します周知であったり、また、タッチ決済を体験いただく、またはくまモンのICカードをいかにお手元に届けるかというふうな活動も、バス事業者が中心になって行っているところでございますが、行政といたしましても、どのような取組が必要かというワーキンググループみたいなものを週に何回も開催をしておりまして、取組を進めているというところでございます。
真ん中、まず、周知広報の点でございますが、例えばポスター掲示、バス車内のみならず市本庁舎であるとか、サクラマチの建物でのポスターによる周知であったり、また、バス会社も5社ございますので、それぞれのホームページというとなかなか情報が得にくいというのがございますので、特設のホームページをバス事業者の方が開発をいたしまして、市のホームページからもリンクを張るなど一元化したホームページを開設するなどの方法を取ってございます。
また、11月の市政だよりでございますけれども、これは熊本県下全域の市町村の行政広報紙において、11月号でアナウンスをしたというようなところも取り組んでいるところでございます。
また、利用促進策につきましては、タッチ決済、新しい環境に少しでも慣れていただこうという視点から、市電に御協力をいただいておりますけれども、タッチ決済の上限割引というものを12月末まで。また、右側でございますが、「渋滞なくそう!半額パス」ということで、これはくまモンのICカードを媒体といたしまして、オフピーク時間、9時以降の御利用に対して料金が半額になるということで、こちらは直近の情報ではございますけれども、6,000枚以上の売上げといいますか、枚数が発行されたということで非常に好評をいただいておりますが、こういった形で円滑に移行ができるような準備というものを続けているという状況でございます。
報告は以上でございます。
◎徳田隆宏 移動円滑推進課長 資料都-2をお願いいたします。
10月29日に、上熊本駅における交通結節機能強化に向けた第2回の協議会を開催いたしましたので、その内容について御報告いたします。
本協議会につきましては、合志市、菊陽町方面へのさらなる半導体の集積によりまして渋滞の悪化が懸念されることから、自動車交通から公共交通への転換を図ることでこの解決を図るため、上熊本駅において市電と電鉄の対面乗換えなど交通結節機能強化について検討を進めているところでございます。
第2回協議会につきましては、各社から様々な意見をいただきました。
主な意見を御紹介しますと、合志市長からは、渋滞対策として上熊本駅の結節や電鉄の機能強化は必要だが、下段の表の⑩にあるような居住の誘導など電鉄沿線のまちづくりについても併せて取り組むべき。熊本電鉄からは、下段の④電鉄と市電の相互乗り入れを進めてほしい。大西市長からは、現状電鉄と市電の乗換えは1日80人程度、運行本数もピーク時2本と少ない状況、下の表の①にあるような離合駅の設置などにより、電鉄の運行本数の増加や快速列車の運行など利便性を高めまして、利用客数を増加させる取組も必要ではないかと、これらの意見をいただいたところでございます。
このような御意見を踏まえまして、上熊本駅の結節機能強化だけではく、2枚目の絵にございますように、熊本電鉄の機能強化並びに沿線のまちづくりについても取り組むなど、赤の太線で示すような電鉄を軸とした新たな公共交通ネットワークの構築について検討を進めることになりました。
具体的には、熊本都市圏共通の目標であります「車1割削減、公共交通2倍、渋滞半減」に向けまして、最下段の表にあるような施策について検討を進めていきたいと考えております。
まずは、各施策に関する現状や課題、効果等について整理し、各施策の優先順位、取組の時間軸、役割分担等をまとめた基本構想の策定に取り組みたいと考えております。
今年度は、協議会の専門部会において基本構想の内容を検討、令和7年度からは具体的な基本構想に向けて検討を進めていきたいと考えております。
続きまして、資料都-3をお願いいたします。
JR新水前寺駅高架下(高森線上り方面)のバス停の設置について御説明します。
先日、10月17日に第1回の地元説明会を行いましたので御報告いたします。
説明会には9名が参加され、主に側道の通行止めや左折レーンの短縮による周辺交通への影響が心配、実証実験でしっかり確認をしてほしいとの意見をいただいたところでございます。
これらの御意見を踏まえまして、11月から12月にかけて計画を現地におおむね再現する実証実験等を実施したいと考えております。
令和7年1月には、実証実験の結果報告について、第2回地元説明会を開催したいと考えております。
説明は以上でございます。
◎大江田真宏 移動円滑推進課市電延伸室長 資料都-4、市電延伸に伴う都市計画に係る説明会の開催状況についてでございます。
第3回定例会にて、市電延伸関連の予算議決いただきましたことを受けまして、都市計画決定に向けた手続として住民説明会を実施いたしましたので、御報告させていただきます。
資料上段の概要を御覧ください。
説明会は10月5日から計4回開催いたしまして、合計165名の方々に御参加いただきました。内訳を下の表に記載しておりますが、最も影響の大きい東区につきましては健軍文化ホール、そして各区から集まりやすい場所として、市民会館シアーズホーム夢ホールにて各2回ずつ合計4回実施いたしました。
右のグラフに参加された方々の属性を記載しておりますが、まず、住まい別につきましては、やはり東区の方々が約7割ということで一番参加をいただいたところでございます。
また、年代別につきましては、50代の方が24%と最も多いということではございますが、10代から80代まで様々な幅広い年齢層の方々に御参加いただいたところでございます。
中段に、説明会での主な意見について記載をしております。
項目としましては、都市計画に関すること、そして(仮称)東町線の整備に関すること、今後のまちづくりに関することについて御意見をいただいております。
まず、都市計画に関する意見としましては、整備方面、整備ルート、そして一部単線化の経緯のほか、自動車が減るのであれば車線を減らしてもいいのではないかといったような御提案もいただきました。
また、(仮称)東町線の整備に関することとしましては、事業費約141億円の事業費が高いのではないか、その事業費で採算性が合うのかなどといったような御意見、また、市電の利用者数の増加、そして自動車が2,000台減るといったような整備効果の根拠に関する御意見もいただいたところでございます。
また、まちづくりに関することとしましては、市電延伸を契機とした地域の活性化など周辺のまちづくりに関する御意見のほか、交通結節の機能強化に関する御意見について意見をいただいたところでございます。
今回は、都市計画決定に向けた住民説明会ということではございましたが、今後も地域の集まり、商店街等々の集まりもございますので、そういった集まりに積極的に参加しまして、地域の方々と意見交換を行いながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
最後に、下段の今後のスケジュールについてでございます。
都市計画関連につきましては、12月の都市計画審議会、そして1月の都市計画決定の告示に向けて手続を進めてまいります。
また、実施設計関連としまして、今回いただきました補正予算を基に、本年度中に実施設計の契約ができるよう発注手続を準備してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 資料交-1をお願いいたします。
熊本市電の運賃改定について御説明をさせていただきます。
市電の運賃改定につきましては、今年6月25日の第2回定例会で一度御報告をさせていただきまして、その際にアンケート結果等を踏まえまして、また改定額が決まりましたら御報告させていただきますと言っていたものの御報告になります。
まず、1の概要でございますが、2点上げております。
経営状況の悪化ということで、乗車人員については、コロナ禍前まで回復していないという状況でありますし、乗務員等の処遇改善、あるいは物価高騰等により収支が悪化しているという状況でございます。
また、今後の収支見込みにつきましても、現在の180円で換算をしますと、上物法人の単年度収支が初年度から赤字ということになっています。また、ちょっと記載はしておりませんけれども、これは上物法人に限ったことではございませんで、下物事業者との合算、上下合算で見た場合でも、収支というのは非常に厳しい状況でございまして、数百万円から数千万円程度の利益しか出ない。年によってはマイナスになる年もあるということで、上下一体で見ても非常に厳しい状況になるというふうな見込みでございます。
2の運賃改定に関するアンケート結果についてでございますが、今年8月末から9月13日まで実施したアンケート結果を記載しております。
まず、1つ目の「運賃値上げについてどう感じるか」という回答に対しましては、「値上げはやむを得ない」とお答えいただいた方が70%という結果でございました。
2つ目の「運賃を値上げする場合、許容できる運賃額は幾らか」という質問に対しましては、「200円」と答えられた方が61.8%と最も多くなっておりまして、210円以上でも構わないと答えられた方も16.6%という結果でございました。
3点目の「どのような運賃制度が利用しやすいですか」という問いに対しましては、現在市電で採用しております「均一制がいい」と答えられた方が76.8%とその多くを占めたという結果でございました。
これらの結果をもちまして、200円への運賃改定をさせていただきたいと考えております。
次のページをお願いいたします。
運賃改定により得られる効果でございますが、まず、収支面としまして、令和6年度の当初予算ベースに試算をしますと、今回の180円から200円への改定によりまして、年間で約1億6,300万円程度増収になる見込みでございます。これらをそこにちょっと例示させていただいておりますけれども、これまで不十分であった経費等に充当させていただきたいと考えております。
1つ目に上げておりますのが、乗務員等の雇用環境・処遇の改善ということで、現在の会計年度任用職員につきましては、上下分離移行後、すぐに全て正規職員化したいと考えております。また、正規職員に対しましては、新たに扶養手当、住居手当、勤勉手当といった手当を支給していきたいと思っております。
これらによりまして、平均の年収につきましては、約96万円ほど増える見込みとなっております。
2点目に上げさせていただいておりますのが、安全確保に向けた設備投資ということで、まず車両につきましては、令和10年度まで新規車両毎年度2編成ずつ導入していきたいと考えております。レール交換、軌条交換につきましても、交換の計画を見直しまして更新を加速化させていきたいと考えています。電停のバリアフリー化も推進を着実に進めてまいりたいと思っております。
なお、この②に書いてある部分につきましては、直接的には下物事業者が企業会計で負担をしていく部分になりますので、直接運賃が当たるというところではございませんが、上物、下物分かれた場合は、下物事業者に上物事業者から施設の使用料が入る形にあります。その施設の使用料は、運賃収入を基に払われることになりますので、今回大事な部分でございますので、例示として上げさせていただいているものでございます。
その下(2)のスムーズな乗降、分かり易さのところでございますけれども、200円ということになりますので、硬貨を準備をしやすくなりますし、両替が減少とすると見込んでおりますので、スムーズな降車につながるものと考えています。
また、県外等から来られる初めて乗車される方々にとっても、非常に分かりやすい運賃体系になるものと考えております。
次のページをお願いいたします。
最後に、スケジュールでございますが、今回の特別委員会、それから12月の都市整備委員会で御報告をさせていただいた後、来年3月に条例改正の議案を出させていただきまして、議決いただきましたならば、国への申請、認可、それから周知広報を得まして、できましたら来年6月にこの運賃の改定をさせていただければということで考えております。
説明は以上でございます。
○田中敦朗 委員長 以上で説明は終わりました。
それでは、ただいまの説明に関して質疑及び御意見等をお願いいたします。
◆上野美恵子 委員 たくさん報告がありましたけれども、今ほどおっしゃいました資料交-1の熊本市電の運賃改定について大変重要なことだと思いますのでお尋ねをさせていただきます。
1つは、さっき説明で経営状況の悪化ということと、今後の収支見通しの健全化を図っていくというような趣旨がるる述べられたかと思います。これについて厳しいかもしれないけれども、さっき溝上先生のお話の中で、要するに上下分離をするに当たっての経営計画、これがまだまだ不十分ではないかという御指摘があったんですね。やはりさっきの説明だと、財政面からの交通局、交通事業としての収支、財政という視点から、今回20円上げるというふうな提案がなされているというふうに私たちは理解をするんですよね。
ですけれども、さっきの溝上先生のお話をずっと聞いていまして、先生がこの計画そのものがもうちょっと何か中身が不十分ではないかとおっしゃったのは、交通事業というのがやはり今後の公共交通の中で果たしていく役割等々を考えたときに、利用者の立場に立って利用促進につながっていくものなのか、それと合わせて経営的にも安定したものになっていくというふうに、多面的に効果のある事業の方向が見えてくる提案であってほしいなというふうに思ったんですよね。
でも、何か経営、経営という、そういうふうな説明であったかと思うので、ちょっと何かそれが納得いかなかったのと、それからこれまで交通事業に多分今年度までは来ていたと思いますけれども、基準外の運行支援金というのが1億数千万円来ていたかと思います。
この資料によりますと、今度の改定によって1億6,300万円程度の増収になるということで、何か支援金がさっき報告では減るんではないかというお話がありましたが、その分に相当する額が上がるわけですから、だったらもう少し交通局と一般会計、本庁の方とよく話をして、交通事業の今後の在り方の中でどうあるべきかという点についての検討等が必要ではなかったのかなと思ったんですけれども、その点についての御説明お願いしていいでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 まず1点目の御質問なんですけれども、経営面ばかりが目立ってというところであったかと思いますけれども、ちょっとお答えにはなかったんですけれども、まず、これまでも一応交通局の方では、利便性向上策として様々取り組んできたと考えております。昨年度から実施しておりますタッチ決済、QRコード決済、そういったものの導入もそうでございますし、コロナ禍でいろいろとイベント列車的な乗客誘致を図るようなイベントというのを全部休止していましたけれども、そういったものも全て復活させていきまして、乗客誘致に向けた取組というのも一応交通局としては着実に行ってきているというふうに考えております。
それと2点目の基準外補助運行支援金についてでございますが、コロナ禍に影響を受けた部分、それから近年は物価上昇等に対する支援としまして、令和2年度から一般会計への基準外繰り出しといった形で受けておりまして、今年度も基準外繰出金額としては、1億4,200万円ほど受けるということになっております。
来年度以降につきましては、予算編成等もまだ確定をしておりませんので、その中で来年度以降の収支状況を見ながら財政当局の方とお話をさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 利便性向上とか考えているというふうにおっしゃって、それは当然ですよね。それもないと何か公共交通としての役割上、それはちょっと問題かと思うんですけれども、実際値上げになった分について「増収分をこれまで投資が不充分であった下記の経費に充てる」というふうにさっき詳しく説明していただいた①の乗務員等の雇用環境・処遇の改善、そしてまた直接的では、上下分離になった場合は直接ならないけれども、安全確保に向けた整備の投資ということで、これ下物になる部分だと思うんですけれども、中身を見ると、これというのは何かもうちょっと基本的に交通事業を拡充させていく中でやるべき部分であって、運賃の値上げでやることかなと。
そこのところがやはり溝上先生もおっしゃった、今市電とか、そういう軌道だけではなくて、バスも含めて公共交通という分野が大変苦戦をしている中で、今までは補助を出していたけれども、もっともっと抜本的に投資的な形ででもいいから支えていくということがないと、本当の意味での公共交通の抜本的な利用の促進とか、拡充にはなっていかないんではないかという御指摘があったかと思ったんですけれども。
それからするなら、補助金でも不十分だというふうに専門家が指摘をしているときに、補助金は削って、そして利用者の負担を増やして、そして当然何かもうちょっと公共交通を公が支えるというのであれば、公がもっと支えるべきであろうその基本的な部分ですね、これは今やることではなくて、ずっと必要だったことですよね。後から出るインシデントが多発をしているとかということにもつながるような職員さんたちの問題とかもありますけれども、そういうことのために値上げをするというのは、やはりどうかなと思うんですよね。
さっき私、先生が均一ではなくて段階的な料金にと言ったときに、増えるのかなと思ったから増えるんですかと聞いたら、いや、それはあくまでも段階を設けても、料金そのものはやはり抑えていくというふうなことを助言としておっしゃいましたけれども、今そういう発想で市電にしても、何にしても、公共交通の利用促進を図っていかなければならないときに、利用者の負担を増やすという発想というのは、やはりちょっと逆行ではないかなと思うんですよね。
そしてさっき上げた後に来年度上下分離して、その収支を見た上で財政局と話をしていくとおっしゃいましたよね。でも、それというのは後先が逆ではないんですか。今するべきではないんですか。公共交通の利用促進に逆行するから、今この補助金継続が必要なんですということは、今財政当局に折衝すべきことであって、値上げの前にすることだと私思ったんですよね、井芹事業管理者。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの御質問ですけれども、まず、先ほどもありましたように、この今回高度化計画ということでここ数年ずっと検討を重ねてきており、また、適宜議会の方にも御説明をしてきたかというふうに思ってございますけれども、その高度化計画の中では、当然お金だけの話ではなくて、そもそも高度化計画というのはお金だけの話ではありませんで、その趣旨といいますのは、その定時制の確保だったり、速達性とか、快適性とか、安全性とか、そういった利用促進につながることというのが計画の大前提であって、交通局の方としても先ほども課長の方から内容等については若干触れておりましたけれども、当然多両編成車両の導入であるとか、軌道の施設の整備であるとか、バリアフリーであるとかといったことも合わせてやるということで整理をしてきたところでございます。
ただ、その際に、今までできていなかったところが、乗務員関係につきまして御承知のとおり、非正規の職員が乗務員の大半を占めているというところ、これはどうにかしないといけないというところで、運賃値上げと併せて上下分離をすることによってきちんと処遇を改善していくということに今検討しているというところでございまして、先ほど溝上先生からもありましたが、全体的なバス、均一料金は市電だけでいかがなものかというようなお話もありましたけれども、その全体的な議論というものは当然必要だと思っておりますので、そこについてはまた適宜全体の話として進めさせていただきたいと思いますけれども、あくまでも今回は上下分離ということに関しての運賃改定ということで御理解いただければというふうに思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 上下分離は、私はこれまで執行部の方の説明をずっと聞いてくる中で、いい面をすごく協調して言ってこられたんですよね。でも上下分離のためと、今、事業管理者がおっしゃったけれども、だったら利用者負担を上げるために上下分離するようなふうになってしまいやしませんか。だって、上下分離をするに先立ってですよ、今この時点で値上げをするという、しかも一般会計からの補助金は一旦引き上げるかもしれないと。
だったら、要するに利便性だ、何だということをおっしゃるけれども、でも、それというのは公共交通の利用促進を図っていく、もっと街を元気にしていく、そのために公共交通が元気に役割を果たしていくということの中での市電であるわけだから、やはりさっきおっしゃったように、補助ということよりは、むしろもっと公共交通を全面に出して応援するための投資こそ必要だという時期に、補助金は引き上げて、そして利用者負担は高くして。でも、これまで私思うに、いろいろな事業者の協力もあって市電の無料の日であるとか、100円均一運賃とか、いろいろな利用促進日というのが設けられましたよね。それというのは、すごく利用に効果があったと思うんですよ。たくさん利用がありましたという報告を受けたので。
ということは、やはりいろいろな要因があるけれども、利用者側からすれば、それは安全運行とか環境整備は本当に当たり前のこと、基本的なこと、何があろうとそれはもともとあって当然のもの、それは利便性ではなくて基本ですよね。そしてやはり利用者からいうならば、安価で利用できる、そしてできれば早く目的地に利便性よく着いてくれるというふうな、そう考えたときには、やはりその安く乗れるときにたくさんの利用があるということは、料金的なものを安くしていけば、要するに利用者が増えるということですよね。
ここの地域公共交通に関する特別委員会というのは、それは市電に限らずバスも含めて、公共交通を利用促進するために私たちは集まって議論しているんですよ。それなのに値上げをするというのは、今この時期にすることかと思ったんですよ。だって逆行でしょう、ただならたくさん乗る、安いときもたくさん乗る、それなのに、いや、収支があれですから値上げしますというのは、やはり間違っていると思いますよ。
大体財政局としてここに今おられますけれども、公共交通の利用促進についてどのようにお考えなんですか、今上下分離して値上げを提案しているときに、補助金を引き上げるかもしれないというその発想というのは、逆行していると思うんですけれども、どのようにお考えなんですか。
◎原口誠二 財政局長 繰出金につきましては、これまでも交通局の経営計画等々を見習って、委員御承知のとおり、基準内の繰り出しでありますとか、基準外の繰り出しを行ってきたところでございます。
今回につきましては、上下分離に移行するという中で、なかなか今後の見通しが見通せない状況の中での局の予算の見通しだというふうに聞き及びますので、繰り出しについて今のところ引き上げるとかどうとか、そのところを全部決定したところではございません。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 では、1点聞いておきますけれども、さっき溝上先生の方から、やはり公共交通を今後発展させていくためには、補助を出しているというふうな、そういう小さいなものではなくて、部分的にしてあげているということではなくて、やはりその事業の発展のために、公共交通に対する投資的なものとしてもっと基本的に、抜本的に支えていく、公が支えるという、そういうことも必要ではないかという御指摘があったと思ったんですけれども、その考え方についてはどのように受け止めておられますか。
◎原口誠二 財政局長 一般会計からの繰り出しでございますので、これは中央公営企業の繰出金の考え方、またもう一方では、本市の基幹交通軸を担う重要な交通機関であること、また、市電が持ちます定時性、速達性、輸送力の高い交通手段としての考え方、そして市のシンボルとしての交通の市電の在り方、歴史等を考慮して、総トータルで、市政の中で繰り出しの考え方は御議論をいただいて決定していくものと考えております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 私は補助金の繰り出し方を聞いたんではなくて、公共交通に対する公の支え方についての基本的な考えを聞いたつもりだったんですけれども、何かちょっと補助金をどう出すかの質問ではなかったんです。公共交通を公の財政がどう支えていくのかという、その考え方を聞いたんです。補助金ではなくて。
○田中敦朗 委員長 投資的な観点を持つのか持たないのかということですか。
◆上野美恵子 委員 そうそう、溝上先生がこれからの公共交通の発展のためには、今までは補助金だったけれども、もっと投資的な視点での支えが必要ではないでしょうかと提起をされたから、その点についての考え方はどうなんですかと聞いたんです。
◎原口誠二 財政局長 これは先ほどの陳述人の御意見の中での委員の御質問と思いますので、それぞれの委員の方々のお考えの議論を聞いた中での考え方をまとめるところだと考えております。
◆上野美恵子 委員 ちょっと分かりませんでした。
○田中敦朗 委員長 財政局として、公共交通に関して投資的な側面に関して今後検討するのかしないのかというふうな質問ですよね。
◆上野美恵子 委員 考え方だよね、そうそう。今のおっしゃった考えが。
○田中敦朗 委員長 その考え方があるのかないのか。
◆上野美恵子 委員 今のは、何か答弁と違うと思います。
○田中敦朗 委員長 ですので、そういった考えがあるのかないのかというのを公共交通の……
◆上野美恵子 委員 溝上先生のその指摘を局長はどう受け止めたのと聞いているんです。
◎原口誠二 財政局長 先生の御意見としては、今後の将来的な公共交通の維持、促進、市電の考え方での御意見だったと思います。現時点で今後の投資的に考え方を持って繰り出しをどうするのかということでは、現時点では上下分離を今後導入するに当たって、本日この時点で投資的経費において重点的に投入していきますというお答えは差し控えたいと思います。
以上です。
◆上野美恵子 委員 ちょっと答えではなかったんですけれども、やはり財政局というところは予算を査定していくところです。熊本市にはいろいろな大事な事業がたくさんあるので、取捨選択しながら何が一番必要かなということを考えていく。
でも、私は今日溝上先生のお話を聞いて、熊本市が公共交通の分野においては、かなり一生懸命取り組んで実績も上げて、国も動かしてそしてやっているということをお話されたなというふうに受け止めたんですよね。もちろん先生独自のお考えですからそれを受け止めるのは私も違う、あなたと私も違う、一人一人受け止め方違うと思います。だけれども、財政をつかさどる財政局長はどう受け止められたのかなと私は思ったから、お尋ねしたんですよね。
やはりいろいろな学者の先生のお考えはあろうかと思いますけれども、さっき厳しい面で交通局に対して計画についての熟度が足りない的な御指摘もあったんですけれども、やはり目先の経営だけではなくて、本当に公共交通を支える一つの大きな事業として市電の役割を果たしていく、その面に立って利用者の方に気軽にたくさん利用してもらって、そのことによって少しでも収益が、経営がよくなっていく、そういう好循環がある市電事業にしていくためには、補助金は分からないと局長言っているのでできれば出していただきたいですけれども、不透明な中でもらえるかもしれんし、もらえんかもしれんけれども、上げる順番がちょっと違うんではないかなというふうに私は思います。
だったら、上下分離をするに当たって上げるんだったら、上下分離なんかせんければよかったたいねと、結局は上物が民間になるということで、より今まで以上に独立採算制を市としては求めていくんだなというふうに見えますもの。だけれども、溝上先生はそれはバスであろうが、市電であろうが、公共交通なんだから、市民の足を支えるということで、もっともっと公が支えていくべきではないでしょうかと私は今日問題提起をしていただいたと思うんですよね。
そういう中で、今回20円とはいえ、そしてさっき今からタッチ決済とか、いろいろなそんなものが増えてくるんだから、端数がついていようがいまいが、別に200円ちゃりんちゃりんと入れる人ばかりではない。むしろクレジットとかタッチ決済とかでやる人の方が多いんだから、だったら端数がついているなんてこと全然マイナスないわけだから、そこに上げるということよりも、むしろ将来を見据えてどうしたらバスと一体化をして、バスも市電も含めてもっと利用者の皆さんが利用しやすいような料金体形になっていくのかということを長期的なスパンで考えながら、そうでもって今、ではどうしようかというふうに、そういうふうな視点で提案をしていただけたらいいなと思うけれども。
何か目先の経営がどうでは、こうでは、これでいけばペイできますとか、使い道は正規職員がどうですかと、そんなこと前々からの話でしょう、今頃になってすることでもないわけだから、ちょっとこの20円の1億6,300万円というこの値上げというのは、本当に公共交通の利用促進、公共交通の発展を考えてやっているのかについて、私はとても疑問です。とても賛成できません。
何回聞いても、財政局の答えも何かあまりぱっとしないし、井芹交通事業管理者もさっきの答えではちょっと私も納得できませんけれども、何か展望が見えないんですよ。と思いますよ。だから、そのことを溝上先生もおっしゃったんではないんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 まず、公共交通の利用促進という観点では、これは非常に重要なことだと思います。市電だけではなくてバスも含めて公共交通に乗っていただくという施策については、これは非常に大事な視点であります。
そこで、ワンコインとか、均一運賃とか、代キロという話もありましたが、私はやはり分かりやすいまず運賃と連携した、ほかの公共交通機関と連携できる運賃というのが大事だというふうに思っています。そこについては今、バス会社とも一緒に話していますが、上野委員、ちょっと後先がというお話もありましたけれども、要は溝上先生の話の中でも一気通貫な料金とかという説明もありましたが、やはりそういう利便性の高い料金と分かりやすい料金だろうというふうに思っています。
上野委員の方からは、先ほど100円ウィークの話もされましたけれども、やはりそういう意味で料金施策というのは非常に重要だというふうには思っております。それはきちんとバス会社とも含めて、都市建設局とも含めて、そこについてはきちんと話をしていきたいですし、検討していこうとしていっているところでございますが、改めて、とはいえ今現在置かれている交通局の立場といたしましては、利便性、先ほど説明しましたけれども、快適性とか、定時性とか、速達性とかという、その本来市電が持っている今の機能をより高めていくには、やはり職場環境も含めて、乗務員の環境も含めた対応が必要だろうというふうに、対策が急務だというふうに思っています。
本当に最近安全への面で皆様に御迷惑、御心配をおかけして本当に申し訳なく思っておりますけれども、そういうのを解決するのもやはりまずはそこだろうというふうに思っています。一つの企業として、バス会社もそれぞれバス会社一つの企業でございますので、そこで企業努力をしております。
うちは今現在、交通局は熊本市の組織ではありますけれども、だからといって全て税金で、この段階で全て税金でというのは、やはりちょっと違うのかなと。そこについては、やはりそれぞれの事業者の事業の採算性というものについては、あくなき追及をしていくべきだというふうに思っておりますので、それが200円で向こう30年間黒字が確保できるという今試算が立っておりますので、やはりそこについては、まずは大変申し訳ございませんが、御理解をいただいて、その上で料金施策と乗りやすい決済手段等については、一緒にやっていきたいというふうに思っているところです。
すみません、ちょっと説明足らないところもあるかと思いますけれども、まずはそういった点を御理解いただきたいというふうに思ってございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 全てを税金でという言葉使われたからすごく違和感があったんですけれども、私は何も全てを税金でと言っているわけではなくて、利用者が利用できる、もっと公共交通に乗り換えようという気分になるような、値上げはそれに逆行するんではないかという指摘をしたんであって、そして今回で言うなら、やはり1億何千万円かの財政の基準外の支援金、それを上下分離になっても、この御時世だから応援していただくというふうにすることの方が、熊本市という自治体が公共交通に対して本当に利用者のために頑張っているよねというふうに、そういう姿が見えるんではないかというふうに思ったから聞いたんですよね。
やはりちょっといろいろ言われても、今この時期にバスのことをいうんだったら、本当にバスがもっと利用しやすくなるようなそういう料金についての検討と合わせて、電車とどうするのかということなんかを含めて、それを話し合ったときに、では、電車運賃はということをおっしゃった方がいいし、今上下分離の直前に値上げということが、やはりすごくまずいというふうに私は思っているんですよ。
だから、何かすごく一面的に上下に分かれるから、経営が優先しているんではないかなというふうに見えてしまう。それでは、やはりさっきの先生の指摘みたいに、目に余る交通局の非協調というふうに指摘をされたら残念ではないですか。そうならないように頑張っていただきたいという、私からの最大限のエールです。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆古川智子 委員 私からも、200円への運賃改定についてです。
御説明をいただいて、今日も溝上先生のお話を聞いて、最初説明があったときは、この交通局上下分離ということで、今度上物の戦略、乗りやすさ、料金体系、分かりやすさ、そういったところで市電に乗っていただくことを一番に考えて、そこを訴えられていくのかなというふうに思いました。
今日の意見陳述人の話も聞いていく中で、全体的な公共交通の在り方として、公共交通とまたそれに合わせて道路というところも考えていかなきゃいけない。そして公共交通の中でも電車、それからバス、その分配率も考えていかなきゃいけないとなると、バスとやはり電車の料金の差額が本当にそれでいいのかということも、ちょっと考えなければいけないなというふうに正直なところ私が思って受け止めたところです。
電車さえよければということであれば、もちろん200円でいいのかもしれません。ただ、全体的なバスも生き残りをかけていかなければいけない。持続可能性を全体で見ていかなければいけないとなると、本当に今後まちづくり、地域核、そういったところも含めて、どこがバスのそれぞれが核となっていくかにもよっても、考えなければいけないことは大きくなっていくとは思うんですけれども。バスの生き残り、それから電車の生き残り、そしてまたは公共交通以外の道路との共存といったところを考えていくと、ちょっと長期的な目線で考えていく。また、タイミングが今後出てくるかもしれないなというふうに思っているところです。
これに関しては、今すぐ回答を求めるものではなく、私はもう求めません。今日は特別委員会、それから今度は常任委員会でも話合いがなされる中で、ちょっとそういったところを執行部の中でも、もう一度本当にこの前進の仕方でいいのかといったところをちょっともんでほしいなというところで、私、今回要望とさせていただきます。
以上です。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆上野美恵子 委員 最初説明していただきました公共交通に関する住民アンケート、今度お取りになるということで説明がありまして、WEBアンケートが主ですけれども、それだけでは不十分だという御認識のようで、地域での対面聞き取りによる調査も想定するという説明がありました。
私も本当にWEBアンケートだけだったら、なかなかそこに答えが出せないという方がおられるので、聞き取り等々の別のやり方を併せてなさるということについてはいいことだと思いますが、そのやり方というのが十分効果のあるやり方にしていかないといけないんではないかなと思うんですよ。どんなふうなやり方でWEBアンケートではない部分についてはやっていこうと思っているのか、少し詳細を教えてください。
◎大川望 交通企画課長 委員おっしゃるとおりでして、どうやって取っていくかの分については、様々多分やり方はいろいろあるとは思っておりまして、今考えているのは、例えば11月30日に公共交通利用促進キャンペーンというものが、これは毎年、年に1回、交通事業者さんを中心としてやるイベントのようなものがございます。そういったときに、御来場の方々に対してしっかりと対面でヒアリングをしていったりとか、どこかの場所とかでチラシを配るような形ではないんでしょうけれども、そういった機会を捉えて直接的にお話を聞いたりであるとか、紙媒体だけを送り付けてというふうなやり方もあるんでしょうけれども、それではなかなか上手にいかないというところもあると思いますので、いろいろな方法をちょっと織り交ぜながら、御意見をいただけたらなというふうには考えているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 やはりアンケートというのが、いろいろな方たちが多様な意見がきちんと集まるということがすごく大事だと思うんですよね。そういう意味では、公平に意見を述べられる場がどんなふうに提供されるかということがすごく大事だと思うので、ウェブの難点というのは、ウェブをしない人たちがアクセスできないというのが難点なので、それの補完するものが直接であったり、何だろうということになるんですよね。
なので、ちょっと今おっしゃった部分ではなくて、もう少し、もう一工夫が必要ではないかなと私は思います。少なくともこうすれば、この点について回答できますよという、意見を述べたい人はもっと自由に述べてください。でも、ウェブができない人も回答ができるようなものを工夫した方がいいなというふうに思いました。
もう一つは、アンケートをするに当たって、3番にアンケートに盛り込む視点の、まず丸ポチの1に書いてあるんですけれども、「公共交通の現状を認識いただいた上で回答をできる」というのがありました。これもとても大事な点だと思ったんですけれども、要するによく分からないのに解答するというのは、書く方も難しいし、答える方も難しいと思うので、一定現状についての何か情報提供しないといけないと思うので、資料とかを一緒に、アンケートと一緒につけて公表するのか、違った形で何か情報提供するのか、そこのところを教えてください。
◎大川望 交通企画課長 手法につきましては、資料のようなものでできるだけ分かりやすくというふうに思っております。資料のようなもので、いわゆる前語りといいますか、今現状こうなんですよというようなものを少し御理解いただくようなものを先に、設問より前に設定をいたしまして、そこから、では、お尋ねしますというような形で流していきたいと。
ですので、例えばウェブ上であれば、問いの前に図示したりであるとか、文言で補足をするような形で、できるだけ分かりやすくというふうな形で考えているところです。
以上です。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
こういうアンケートがあるということは、市政だよりには載るんですよね。市政だよりには。
◎大川望 交通企画課長 そうですね、広く周知するために、すみません、市政だよりは、今私の中ではまだまだちょっとそこまで思い立っていなかったところもございますので、しっかりと周知をするために市政だよりも活用していきたいと思います。ありがとうございます。
◆上野美恵子 委員 公共交通の住民アンケートすごく大事だと思うんですよ。とても大事だと思うんですよね。だからこそ、市政だよりは基本なのでぜひ、ホームページはもちろん載せられるでしょうから、市政だよりの方にも載せていただきたいなと思います。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆齊藤博 委員 ICリプレイスについてちょっと確認でお尋ねをいたしますが、くまモンのICカードと現金しか使えない、いわゆる全国交通系ICカードがもう11月16日以降から使えないということでありますので、現金で払う方、それからくまモンのICカードで決済していただく方ということになるんだろうと思います。
確認なんですが、くまモンのICカードを例えばバスの中で買おうとする場合には、従前も可能だったかと思いますが、引き続き買っていただけることができるのかどうか、ちょっと確認でお尋ねいたします。
◎大川望 交通企画課長 従前どおり、バスの車内でもくまモンのICカードは買うことができます。
以上です。
◆齊藤博 委員 金額は幾らになりますか。
◎大川望 交通企画課長 販売額は2,000円のお支払いをいただきまして、デポジットが500円ございますので、1,500円分のご利用額という形での発行になります。
以上です。
◆齊藤博 委員 需要が一定増えるだろうと思いますので、不足が出なかったりとか、スムーズに購入いただけるような体制をバス会社さんにはぜひ整えていただくように、行政の方からも遺漏なくお伝えをいただきたいと思います。
それと併せて、もう11月の中旬以降から、要は現金とくまモンのICカードしか使えませんというようなことになります。恐らくちょっと簡単に想定できるのが、現金もちょうど持たない、あるいはもちろんくまモンのICカードなんて持っていない、クレジットカードしかないとか、あるいは10カードしかないというような、例えば出張者の方であるとか、そういう意味では、今現金持っていない方結構いらっしゃいますので、そういう方にどのような形で対応するのか。今日はいいですよなんていうことは基本的にはできないと思います。
ですから、例えばバスの運転手さんごとで対応が違ったとかいうようなことは、これは困難を招く一因ともなりかねないと。いろいろな想定を、バス事業者さんが考えることなのかもしれませんが、やはり行政サービスとしての公共交通機関ということで、そういった対応にしっかりお答えできるような体制を各バス会社さんにもぜひ行政の方からも問合せをいただければと思いますが。そこはいかがでございますでしょうか。
◎大川望 交通企画課長 確かに委員おっしゃるとおり、不測の事態といいますか、払えないという状況に陥るというのは、当然あり得ると、十分にあり得るというふうに考えてございます。
当然、我々市としてもバス事業者さんに対してはそのような対応についても想定をして、また、なった場合にはしっかりと御利用者さんに対して接遇をというか、対応をお願いするというところは、重ねて申し上げるというところはやっていきたいというふうに考えてございます。ちなみになんですけれども、今現状においてのバス事業者におかれては、当然ちょっと財布を忘れてしまったとかというような方も、現状においても当然いらっしゃいます。
そういったときには、まず運転手さんに対してお客様の方から今日ちょっと支払えないんですという旨を申し出ていただくと、運転手さんは一つ紙券みたいなものを配りまして、後払い券という呼び方をするようなんですが、そこにお名前であったり、連絡先であったり、または金額ですね、これを御記載いただいて、お客さんとその運転士が複写式なんでしょうか、物理的に両方とも同じ情報を持っておくと。次に乗るときに、御利用者さんの方から、前回こういうふうな形で後払いになりましたのでという形で合算してお支払いいただくと、そういった対応をもう既に取っていただいているところもございます。ただ、先ほど申し上げたとおり、併せて交通事業者の方にはまた申し伝えをしておこうと思っております。ありがとうございます。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 分かりやすい御回答ありがとうございました。
混乱を招かないように、そして何か不測の事態が起こったときに、重複しますけれども、サービスの在り方がまちまちにならないように、ぜひバス事業者さんと共有をしていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 13時を目途にと思っておりますので、質疑は円滑に回せるようにお願いいたします。
◆井本正広 委員 すみません、決算手段の件でちょっと1点お聞きしたいんですが、バスの方はタッチ決済について3月から導入されて、これは多分距離によって金額が違うから、乗るときと降りるときとタッチされると思います。
先ほど溝上先生の方から御指摘もありましたけれども、市電の方は今タッチ決済、降りるとき1回ですよね、これはやはり乗降、どこからどこまで乗ったという情報を取るためにも、最初と最後というような形にした方がいいんではないかなとは思うんですけれども、そのためには機器を追加しないといけないのかもしれないんですが、その辺についてはどんな状況なんでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 委員がおっしゃられましたとおり、仮に乗り降りで取る場合は、今の乗るところに機器がございませんので、そういった経費負担が新たに発生するというところがございます。
溝上教授からもありましたけれども、ODデータですね、これにつきましては、現在、交通局で全国交通系ICカード、こちらが約半数利用されていますけれども、こちらの方で取っておりますので、このデータを持って十分だというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆井本正広 委員 ただ、交通系ICカードの場合は、今も同一金額でも2回タッチされますよね。要はそれだけでいいというんであればそれでいいんですけれども、将来的にタッチ決済の方に移行していくような状況ではないかなというふうに思いますので、この辺については、一度金額との検討とかした方がいいんではないなと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○田中敦朗 委員長 答弁要らないですか。
◆井本正広 委員 はい。
○田中敦朗 委員長 では、検討して井本委員に報告お願いします。
そのほか質疑ありませんか。
◆上野美恵子 委員 上熊本駅における交通結節機能強化について、専門部会についての検討の報告がありましたが、さっきの説明だと、なかなか熊本電鉄の運行本数が少ないこととか、実際の乗り継ぎとかも少ないので、結節の強化といった場合に、現状ではちょっと難しい課題がたくさんあるのかなというふうに私は認識をしています。
この問題で専門部会で検討が進められていくので、何というのかな、市民というか、住民の意見とか、利用者の声とか、そういうのは専門部会にどのような形で集められていくのか、反映されていくのかということと、大事なことなので何か機会を見て市民の方々については、こういう問題についての情報提供というのをする場面があってもいいのかなと思ったんですけれども、それについての何かお考えがあれば教えてください。
◎徳田隆宏 移動円滑推進課長 現在、この上熊本の交通結節機能強化につきましては、合志市、本市交通局、熊本電鉄と、あとそこに県を加えて専門部会で検討を行っているところでございます。市民の声につきましては、こういった専門部会での検討内容につきまして、本市の交通の協議会であるとか、様々な機会を捉えて意見を伺っていきたいなというふうに考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 十分になさっていただくようにお願いしておきます。
それから、4番目の市電の延伸についての説明会の開催についての御報告がありましたけれども、これで終わりということではないと思うんですけれども、結構ずっと議論もあったし、私たちは報告を聞いてきているので、情報も持っている側としては分かるんですけれども、一般の市民の方たちからすれば、なかなかまだ中身についてよく伝わっていないという方々も多いのではないかなというふうな、そういう御意見をお持ちの方に何人かお会いしました。
だから、まだまだ伝わっていないんだな、説明会の後に会ったんですけれども、だから、行った人は分かったかもしれない、意見も言ったかもしれないけれども、だから、この問題は継続的にいろいろな機会を活用して情報提供とか、いろいろ意見聞いたり、説明したりする場面というのが必要かなというふうに思ったんですけれども、今後のことについて何かお考えがあれば教えてください。
◎大江田真宏 移動円滑推進課市電延伸室長 今委員が言われたとおり、説明会の中でもこれまで議会で御議論いただきました整備形態ですとか、ルートですとか、その事業の効果に関する意見というのが、結構住民説明会の中でも多うございました。
そういったことから、私どもとしましても、改めて計画内容、検討経緯も含めて住民の方々へ丁寧な説明、情報発信というのが必要だなというふうに感じたところでございます。
今後は、地域の例えば校区の集まりですとか、商店街の集まり等に積極的に参加していく中で、意見交換しながら事業を進めていきたいと、そして情報発信していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 やはり事業費的にもかなりかかっていくものでもありますし、市民の理解というのが何よりかなというふうに思ったので、疑問持っているけれども、説明会に行くという人は本当に多くないんですよね。思っているけれども行かない人が大半だと思うので、そういう方たちに御納得いただくような手立てというのが必要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 次に、報告2件の説明を求めます。
◎荒木敏雄 運行管理副課長 資料交-2をお願いいたします。
銀座通り歩道橋交差点における信号冒進(インシデント)についてでございます。
発生日は、令和6年10月2日でございます。
経緯といたしましては、左下のところにあります市役所前電停から花畑町電停の方に向かって進行した電車が、交差点に進入する際、右上の方の写真になりますけれども、電車信号が進行可能な黄色矢印、白抜きのところになります。黄色矢印の信号が出ていない状態、上側の方になりまして、その状態で進行したものです。運転士の方は、右折車に気を取られてそのまま進行したと申しております。
右側の方で、2の発生原因でございます。
運転士が電車信号の確認を怠ったもの。
3番、再発防止策についてです。
全運転士に対しまして、本事案を周知しました。また、当該事案運転士に関しましては、1週間電車を下ろして再教育を行いました。また、全運転士に対しまして、「信号よし」などの確認呼称の徹底を指示しております。
また、毎朝出勤したときの点呼時の際には、進行信号と停止信号の信号写真をランダムに掲げて、反射的に確認呼称をすることで故障の意識づけというのを実施しております。
最後に、全運転士のドライブレコーダーを確認いたしまして、指導後の確認というのも行っております。
資料交-2に関しては以上です。
続きまして、資料交-3をお願いいたします。
保安監査結果に対する改善報告についてでございます。
度重なるインシデント等を受けまして、7月と8月に実施されました九州運輸局からの緊急保安監査での改善指示が9月20日に出されまして、1か月後の10月21日に改善報告書(中間報告)という形で提出いたしました。
内容といたしましては、安全管理体制の再構築及び4つの改善指示事項についての改善措置の状況というものを報告したものです。
1番の方が、こちらが九州運輸局の中で一番重点的な項目と考えられている項目でして、安全管理体制の再構築ということになります。指示内容といたしましては、現在の安全管理体制を検証いたしまして、安全統括管理者(以下「安統管」)といいますけれども、そちらを中心とした安全管理体制の再構築というものを指示されたものです。
問題点といたしまして、現在の安統管が営業所長との兼務でありまして、全体を統括する上で職位が不十分などとなっております。
改善措置に関しましては、次のページを御覧ください。
上の方の①番、安全統括管理者を専任とするとともに、位置づけを強化いたします。こちらの方は11月1日、明日からを考えております。
②番、安全対策に係る推進セクションを新設、こちらの方は年明けの1月からを予定しております。
現行の体制といたしましては、左側の方になっております。現在、中心に安統管とありますけれども、安統管は営業所長が兼任しておりますが、組織的には運行管理課長の下の主幹級の職員になりまして、しかも運転関係しか把握できていない状況にございます。安統管には、運転のみならず、施設、車両を統括することが求められますので、職位が不十分であると指摘されたものです。
見直し後が、右側の方になります。真ん中よりちょっと上のところに、専任の安統管を設置いたします。部長級の任期付職員で市のOBを考えております。
下の方には管理班といって、運転管理する部門がありますけれども、そちらの方に安全対策係というのを設置いたします。
一番下のところに安全対策係の事業内容といたしまして、運転管理者を補佐し、運転士の育成、指導・教育、資質管理などのほか、運転施設、車両各部門の情報共有と連携を計画実施する役割を担うものとしております。
戻っていただきまして、資料交-3の4つの指示事項でございます。
①番、運転知識・技能の保有状況の管理ということで、指示内容といたしまして、必要な教育、技能が確認できていなかった運転士が乗務していたことを受けまして、適切な教育の実施、技能の管理というものを指示されております。
問題点といたしまして、運転管理者等の制度への認識・知識不足、引継ぎが不十分、関連規定が不明確などが考えられます。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、対象運転士に教育いたしまして、知識・技能の確認を実施するなどとしております。
恒久対策といたしまして、関連規定の改正、改正後の規定の教育を実施するなどとしております。
②番、視力要件等適性の管理についてでございます。
指示内容といたしまして、視力要件を満たさない運転士が1週間程度要件を充足しない状態で乗務していたことを受けて、適正な管理を指示されたものでございます。
問題点といたしまして、運転管理者等の制度への認識、知識不足などと考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置としまして、対象運転士の視力要件を確認いたしました。また。改めて全運転士への視力要件の周知を行いました。
恒久対策といたしまして、①番と同じく規定の改正、改正後の規定の教育を実施などとしております。
③番、点呼の不備についてでございます。
指示内容といたしまして、不適切な点呼簿への記録、点呼完了前に点呼完了と記載したり、また、チェック漏れの状態で確認印が押してあったりなどといったことを受けまして、適切な点呼実施を指示されたものでございます。
問題点といたしまして、点呼執行者などの点呼の目的、実施方法などに関する理解、認識不足と考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、点呼執行者や乗務員への教育を行います。
また、恒久対策といたしまして、①、②と同じく内規の策定、点呼結果のダブルチェック、複数人点呼、今出勤した運転士を複数にまとめて点呼しておりますけれども、それを一人一人の個人点呼に変更するなどと考えております。
④番、軌道整備上の不備についてでございます。
指示内容といたしまして、レールの数値に一部基準値の超過というのが見られましたけれども、こちらは1年以上整備が未実施であったことから、必要な整備等の見直しを指示されたものでございます。
問題点といたしまして、超過箇所での整備計画の未作成、また施設管理者の知識不足などと考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、早急に整備計画というものを策定いたしまして、今年度と来年度にかけまして、超過箇所の整備を完了させますとともに、完了までの間、超過箇所を重点的に監視することといたします。
恒久対策といたしまして、施設管理者交代時の教育と定期的な勉強会を実施したいと考えております。
説明は以上です。
○田中敦朗 委員長 ただいまの報告に対し何かお尋ね等はございますか。
◆上野美恵子 委員 今、市電のインシデントに関わることで2件の報告がありました。
1点お尋ねしたいのは、国の保安監査結果が9月20日に出されて、その間、交通局でいろいろ協議がなされて、中間報告を出されたと思うんですけれども、まさに中間報告を作っておられる真っ最中の10月2日に、銀座通り交差点でのインシデントが発生をしたという、時系列からするとそうなるんですよね。そのことについてどう受け止めておられますでしょうか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今、上野委員おっしゃられたとおりでありまして、9月20日にいただいて、その内容等について精査している間に10月2日起こったわけでございまして、冒頭御説明しましたが、銀座通りの交差点で信号に関することで、これについては、今年5月2日からもう既に信号冒進という観点では3回目となります。インシデントでない案件も含めますと、4回目になろうかというふうに思ってございます。
運輸局からの改善指示のさなかというところもございますが、そもそも論として今年度に信号冒進というものが何件も起こっている。内容についてはやはり、これについては見落としといいますか、確認不足というところでありまして、そこについては本当にこの特別委員会もそうですけれども、職員の再教育等もやっていますとか、本当にきちんとやっていたにもかかわらず、こういうことが起こったということについては、本当に申し訳なく思っております。
そこはもう、ただ機械的な不備とかということであれば別ですけれども、やはり安全運転するための運転士の見落としとかというのは、本当にあってはならないことですので、ここがもう本当に繰り返し基本に忠実にということと併せて、ふだんの運転等についても添乗監査であるとか、ドライブレコーダーを使った監査であるとか、要は個人ごとの運転のくせというものも、原因の一つには内在しているのかなというふうに思ってございますので、そういったことについてもいろいろな手段を使って、個人個人に運転の動作というものを再確認して徹底をさせていきたいというふうに思ってございます。本当に申し訳ございませんでした。
◆上野美恵子 委員 陳謝ということではなくて、やはり何というかな、定期的な安全監査ではなくて、インシデントがすごく続いてきたと。そういう中でのやはり監査が入って、そして指摘事項が出て、これがまずかったんではないんですかということが示された後に、交通局としてどうしようと、これではいけないんではないか、どの点を改善しようかというそのさなかに次のインシデントが起こるということは、事業者の方からはきちんと対策を、信号冒進も幾つもあったんだからやっていたんだけれどもというふうにあったけれども、でも実際はそれが繰り返し起こっているということについて、私はとても危機感がありました。
だから、ちょっともう言っても一緒なんですけれども、とても今の時点では中間報告出されて改善点は書いてありますけれども、今後、それをどう進捗を見守っていくのかということが私は大事であろうというふうに思っています。
なので、本当に国の指摘事項というのは、どれを見ても日常業務の中でこういう基本的なことを、細かいことがチェックができていなかったのかなというのでは驚いたんですよね。視力にしても、何にしてもですね。
だから、インシデントをなくして、本当に安全運行ができていくようにするためには、今中間報告が出ていますけれども、もちろん多分最終的な報告というのもつくられるでしょうし、それにとどまらずに定期的にいろいろな形で安全運行に関する取組状況というのは、見える形で事業管理者としても確認する。チェック機関である私たちも、確認できるというふうにやっていかないとなくなっていかないんではないかなというふうに思いました。今回中間報告が出されていましたけれども、今後そういう形でこちらとのやり取りもさせていただきながら、改善の方向に向かっていかれるようにお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの御意見、もっともだというふうに思ってございますので、御報告をさせていただきながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 そのほかありますか。
◆齊藤博 委員 ちょっと素朴な質問1つだけ。
保安監査結果に対する改善報告、見直し案で組織というのはすごく大事な、結果として大切なんだろう思います。特に安統管を専任で配置すると。なかなか安統管、御人材が今局内にはいらっしゃらないというふうなことも踏まえた上で、令和7年1月からこの見直し案になると。それまでの今の現行は安全管理体制、安統管のポジションを誰が務めるのかとか、これ全く変わらないでこのままいくんですか。そこをちょっと教えてください。
要は、今年中の安全管理体制として組織はこのままでいくんですか、どうなんでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理副課長 ちょっと説明が不足していたかと思いますけれども、安統管に関しては、明日から就任をしていただこうかと思っております。その後に、安全管理に係るセクションというのを来年1月から考えておりまして、その中ではやはり局内で人選をしたりだとか、関係規定を整えたりだとか、そういったところに2か月程度見ているところでございます。
以上でございます。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 本日は、意見陳述人に御意見をいただきました。
様々な御指摘、御意見をいただきました。当然その御意見はこちら、公共交通に関する特別委員会でございますので、熊本市役所がどのようにそれを受け止めたのか、そして今後、次期の地域公共交通計画についてどのように反映させていくのか、そういったものに対しては、真摯に取り組んでいただきたいというふうに思います。
委員の方からもそういった御意見がありました。一つ一つ交通局にせよ、都市建設局にせよ、関係する部署は、それに対して自分たちの回答を持った上で計画に臨んでいただきたいなというふうに思います。
それでは、ほかにないようであれば、本日の調査はこの程度にとどめ、これをもちまして、地域公共交通に関する特別委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後 0時47分 閉会
出席説明員
〔意見陳述人〕
熊本学園大学経済学部教授
溝 上 章 志
〔政 策 局〕
局長 三 島 健 一 総括審議員 村 上 英 丈
総合政策部長 黒 木 善 一 政策企画課長 松 永 直 樹
〔財 政 局〕
局長 原 口 誠 二 財務部長 濱 田 真 和
財政課長 津 川 正 樹
〔都市建設局〕
局長 秋 山 義 典 技監 上 野 幸 威
都市政策部長 高 倉 伸 一 都市政策課長 飯 田 考 祐
交通政策部長 迫 本 昭 交通政策部主席審議員
濱 口 佳 久
交通企画課長 大 川 望 移動円滑推進課長 徳 田 隆 宏
移動円滑推進課市電延伸室長 自転車利用推進課長酒 井 伸 二
大江田 真 宏
〔中央区役所〕
区長 土 屋 裕 樹 区民部長 大 田 就 久
〔東区役所〕
区長 本 田 昌 浩 区民部長 橋 本 裕 光
〔西区役所〕
区長 石 坂 強 区民部長 田 島 千花子
〔南区役所〕
区長 本 田 正 文 区民部長 東 野 正 明
〔北区役所〕
区長 吉 住 和 征 区民部長 岡 本 智 美
〔交 通 局〕
交通事業管理者 井 芹 和 哉 次長 松 本 光 裕
総務課長 吉 岡 秀 一 運行管理副課長 荒 木 敏 雄
地域公共交通に関する特別委員会会議録
開催年月日 令和6年10月31日(木)
開催場所 特別委員会室
出席委員 12名
田 中 敦 朗 委員長 平 江 透 副委員長
木 庭 功 二 委員 村 上 誠 也 委員
古 川 智 子 委員 中 川 栄一郎 委員
島 津 哲 也 委員 齊 藤 博 委員
井 本 正 広 委員 藤 山 英 美 委員
上 野 美恵子 委員 上 田 芳 裕 委員
議題・協議事項
(1)持続可能な地域公共交通の実現に向けた諸問題に関する調査
午前 9時58分 開会
○田中敦朗 委員長 ただいまから地域公共交通に関する特別委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可します。
◎井芹和哉 交通事業管理者 おはようございます。
まず、1点目でございますが、本日、前回に引き続きまして、運行管理課長の松尾が体調不良により本委員会を欠席しておりますこと、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、運行管理課からはこれまで同様、説明員として運行管理副課長の荒木が出席しております。どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、2点目でございますけれども、去る10月2日に、銀座通り歩道橋交差点におきまして、市電が信号冒進、いわゆる信号無視のインシデントを引き起こしてしまいました。後ほど原因や対策等については、詳細な報告をさせていただきますが、度重なる事故やインシデントの発生を受け、局を挙げて再発防止に取り組んでいる中、また、九州運輸局より改善指示がなされた直後に、このようなインシデントを引き起こしてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
今後、本事案につきましても、外部検証委員会での検証の対象とし、最終報告での安全対策に反映させてまいりたいと考えております。
市電を御利用いただいております皆様をはじめ、市民の皆様に対しましては、立て続けの事故、トラブルにより御心配、御迷惑をおかけしており、改めて深くおわび申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。
以上でございます。
○田中敦朗 委員長 発言は終わりました。
これより本日の議事に入ります。
本日は、「本市のあるべき地域公共交通について」、意見陳述人の意見を聴取するためお集まりいただきました。
意見陳述人におかれましては、大変御多忙の中、本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
委員会を代表いたしましてお礼を申し上げますとともに、忌憚のない御意見をお述べいただきますようにお願い申し上げる次第であります。
それでは、調査の方法についてお諮りいたします。
調査の方法といたしましては、まず意見陳述人の意見聴取を行った後、意見陳述人に対する質疑を行い、次に執行部より「公共交通に関する住民アンケートについて」、「次期地域公共交通計画の策定に向けた取組について」説明を聴取し、一括して質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
これより、意見陳述人として、熊本学園大学経済学部溝上章志教授より、意見聴取を行います。
意見陳述人は、意見の開陳をお願いいたします。
◎溝上章志 意見陳述人 皆様、おはようございます。
この場に呼んでいただきまして大変光栄でございますけれども、これだけカメラもあるので少し緊張しておりますが、3年半前までは熊本大学におりまして、退職して熊本学園大学の方で働かせていただいています。それまで都市計画審議会の会長とか、あるいは公共交通協議会の副会長等を務めさせていただきまして、ここにおられる方、委員の皆さんの中には何人か御一緒させていただいたこと大変光栄に思います。
今日は、皆さんの御期待に添えるかどうか分かりませんけれども、私が考えている公共交通、特に熊本市の交通混雑緩和と地域公共交通再生を両立させて改善していくような方法と、その筋道についてお話ししたいと思います。
これは私の自己紹介なんですけれども、今半分以上申し上げましたけれども、年取ってきたので少し体力をつけなきゃいけないということで、もともとテニスが好きなんですけれども、今膝を痛めておりまして、しばらく休憩中に自転車のツーリングを始めまして、その体力と脚力維持のために大学のジムでトレーニング等をやっております。
昨年4月にしまなみ海道往復、今年の春に浜名湖一周、実は明後日からまた1泊2日で瀬戸内海に行く予定です。つまらない話ですが、皆さんも健康が大事だと思いますし、自転車というのはこれからお話しします車というプライベートな、それも非常に面積等を占有し、かつエネルギー効率も悪いものとは違う乗り物の一つとして、これからどんどん自転車の利用の促進を図っていただければということもあって、こういうことを始めました。
今日は、熊本都市圏における交通混雑の実態、この辺りはいろいろなところで皆さん御存じかと思いますが、ちょっと視点を変えた話をさせていただきます。
それと交通混雑というのがどういう原因で発達しているのかと、それを緩和するためにはこういうふうにしたらいいと、これは理論的な話なんですけれども、少しそういうことを話させていただいた後、一方、公共交通というのはどういう状況になっていて、どんな課題があるか、あるいは後でお話ししますが、熊本市のバスを中心とした公共交通政策というのは、日本で最先端のことをしているんですけれども、これが皆さんにあまり認知されていなくて、とはいうものの、これも限界に来ているために、どういうふうにしたらいいかという話を、その4番の公共交通再生のための政策ということでお話しさせていただきます。
その中には、国までも動かした熊本の公共交通政策というのがありまして、これは市議会及び市の職員の方が長年にわたって国を動かしてきた例をお話ししますが、それ以上のことができなくなったために、6番の公共交通再生のためには、もっと本質的な議論をしなきゃいけないということにつなげさせていただきたいというふうに思います。
まず最初、熊本都市圏における交通混雑の実態ですけれども、これは、皆さんよく別の資料等で御覧になっているかと思いますが、黒いところが徒歩の速度ですね、赤いところがママチャリぐらいですね。寒色系になると早く走れるということなんですが、東バイパスの内側と、特に中心部ですね、ここではママチャリ以下の速度でしか移動できないと。東バイパスと交差する幹線道路ですね、8放射だけではなくていろいろあるんですけれども、そういうところでも赤、あるいは濃い赤ですね、そういうのが起こっております。
それと右上のTSMC、あるいは光の森辺りですね、この辺りも他の郊外部に比べると暖色系の区間が非常に多くなっていて、これはちょっと前なので、今はTSMC周辺ではもっと赤くなっているんではないかというふうに思います。
左の表は、これは名古屋、大阪、東京23区以外を除いた政令市の中心部の交通混雑を示す平均速度ですね。道路上の平均速度、それと公共交通の利用率を示したものですけれども、熊本市はよく政令市で一番混雑が激しい。速度から見ると16.1㎞/hで最も激しいわけですが、実は激しいのは自動車の利用率、一番右側の列を見ていただくと、自動車の利用率が高い都市ほど速度が遅くなっているということが見られると思います。
この公共交通の利用率なんですけれども、人口等調べる国勢調査、熊本都市圏の交通の状況を調べるパーソントリップ調査というのがあるんですが、15年おきに、母都市が50万人以上の都市圏で実施されていますけれども、直近ですね、これは平成24年が64.4%ということで、丸で囲んである紫部分が車の利用率ですが、これでも驚くべき数字なんですけれども、実は昨年行われた最近の最新の情報では、67%までまた拡大しているという状況です。この熊本都市圏における車の利用率の増加は、天井を知らない状況になってきています。
実際にどんな乗り物が使われているかということなんですが、左側は都心部で、青いのは市電ですね、緑色がJR、あるいは熊本電鉄なわけですけれども、結構ここに書いてある数字はその断面の利用者数ですけれども、それとオレンジ色は車の利用です。中心部はもちろん市電等があったり、豊肥本線がありますので、緑とか青の部分があって頑張ってはいるんですけれども、放射方向だけを見る、つまり、そういうところがない方向はほとんど車が利用されておりまして、それが郊外に行くと、御代志、これは合志市ですね、あるいは菊陽町辺り、ほとんど緑色の線が薄く見えるのが豊肥線ですけれども、そのほかは全部車が使われているという状況です。
では、この交通混雑、あるいは今のような車の利用が起こっているのは何でかと、それを緩和するためにどんな対策が取られたらいいかということを少しお話しします。
これは交通流シミュレーション、シミュレーターなんですけれども、我々が開発したものですが、今上から車が流れていて、ボトルネックと書いてあるところで急に車線数が少なくなったような状況を想定してください。
これランダムにある間隔で流れてきているんですけれども、あるときからその間隔が狭くなってくる。つまりたくさん流れてくると、今後ろの方に待ち行列ができて、どんどん待ち行列が上流側に遡及していっていますよね。これが渋滞といわれるもので、実は上から流れている交通需要がこのボトルネックでさばき切れる最大の量、これよりも大きくなった時点でその超過分が上流部分へ滞留していく現象を工学的には渋滞といいます。
渋滞、渋滞というと何か速度が遅くなったりとか、最終的に現象としてはそういうことなんですけれども、こういうことが原因なんですね。これを解消しないことには、渋滞というのは解消できない。つまり上流から流れている車の量と、きゅっと小さくなっているボトルネックですね、ここの容量、この相対関係で交通混雑というのは決まるということです。
これを模式的に表したのがこの図でして、ある断面を単位時間、1時間なら1時間に通過する車の台数のことをよく交通情報センターなんかで、「交通渋滞が非常に激しくなっています」というようなアナウンスがあると思います。
例えば「浄行寺交差点では、交通量が非常に多いために、速度が低下して交通渋滞が激しくなっています」というふうな言い方をしますが、これは工学的に誤りです。交通量というのは、ある断面を単位時間に通過する車の台数ですから、完全に止まってしまうぐらい車が上から流れてくると、交通量は単位時間に1台も流れませんからゼロになります。
ですから、これでいうと、上の方からずっと自由速度、これは制限速度だと思っていただいて結構ですが、横軸が交通量なんですけれども、交通の量がどんどん増えてくると、当然速度は前に車がいますからだんだん遅くなってくるんですけれども、その断面では容量といわれる交通量ですね、それ以上の交通量というのは流れ得ないわけですね。それでも速度はどんどん下がるぐらい上から流れてくると、速度はどんどん下がると同時に交通量は減っていきます。そして完全に止まるぐらいぎゅうぎゅう詰めになったときは、あそこのゼロに落ち着くわけですね。
ですから、この絵をいつも頭に入れといていただいて、今我々が直面しているのは限界速度というところと、容量の交点、要するに一番出っ張ったところですね。あの辺りの近傍で交通混雑というのが議論されなけりゃいけないということです。
多いのは、上流からの交通の需要。車の台数であって、渋滞が進むと交通量、単位時間当たりにある断面を流れる台数は減少します。ですから、ちょっと言い方は変なんですけれども、今上流から流れてくる車の台数が多くなったので交通混雑が激しくなっていますが、交通量は減っていますと。これが工学的に正しい言い方ですね。
だから、上流からの交通需要というのを減らさないことには、駄目だと。つまり相対関係なわけです。キャパシティーと上から流れてくる車のですね。
実際、熊本市中央区を1つの道路区間というふうに考える。これはマクロな見方なんですけれども、縦軸が平均速度、横軸が時間帯の交通量ですね。これを先ほどの絵と同じように取ってみると、やはりぽこっと出ていまして、それより出たところからだんだん下に下がってきていますね。それも速度がゼロに向かって下がってきている形をしています。
それで、さっき言いましたように、あそこの尖ったところあたりを着目して、上から流れている交通量は大体今800台で満杯になっています。断面が1時間に800台が上限だということなんですけれども、それから例えば1割、700台ぐらいになると、縦軸を見ていただくと、12~13㎞/hだった速度が一遍に17~18㎞/hに上がります。つまり、物すごく急激に交通の状態が変化していって、ちょっとでも交通量が減る、上から流れてくる車の台数が減れば、速度は物すごく改善するということなんで、試算してみますと、上流からの車の流れが1割減ると、速度は33%上がって、渋滞による損失時間は大体半減するというふうなことが理論的に、実証的にも分かります。この言葉というのはよく聞かれていると思いますが、これについてはまた後でちょっと話します。
実際には、交通渋滞は解消しちゃ駄目ですね。交通緩和する、あるいはマネジメントするという考え方が大事です。例えば物を買うときに、めちゃくちゃ安くなったらみんなたくさん買いますよね。高くなったら買うのはやめようかという人も出てきます。そのように交通混雑が解消されると、またその道を使おうという人がどんどん増えていきます。
ところが、ある程度のレベルで管理する、マネジメントすると、それ相応の利用のされ方がされるということで、交通混雑の真の目的というのは、解消ではなくて緩和マネジメントです。その上で、ある程度の混雑と共存し合いながら、モビリティー、この言葉もよく聞かれると思います。移動可能性という日本語英語なんですけれども、移動の自由とか可能性、これを高めてやるというような施策が大事で、交通渋滞を解消するとかということを言っていては駄目です。
実は、道路を造るとこんなことも起きる場合があります。
左上の図が簡単なネットワークだと思ってください。AからBへ6台の車が流れるような場合ですね。上側が経路1、下側が経路2とします。5+10χと書いてあるのは車が、χというのはそこを通る台数なんですけれども、それが増えると時間は長くなりますよね。だって、少し混雑してきますから。つまり流れる車が多くなると、5+10χだけ時間がかかるというのが全ての道路区間に書かれています。
こういうところに、AからBへ6台流れたときにはどういう流れ方になるかというと、それがその下の絵です。上の経路を使うと、上の経路に3、下の経路に3、併せて6流れると、ちょうど35+63の98分ですか、下の経路を使ったとしても、63+35の98分、誰一人として今使っている経路から別の経路へ動こうとしません。なぜかというと、その人が動いたために、動いた経路は必ず1台増えますから、時間が余計かかるようになりますし、動かれた経路というのは1台いなくなりますから、短くなります。そうすると、誰かが必ず動いた元の経路へ帰ってきます。毎日そういうことやっていると、あっちが近いというのを知っていますからね。
そうすると、最終的にどういう状態で均衡するかというと、3台、3台が流れてどの経路を使っても時間が同じような状態になるはずです。恐らく今世の中というのはそういうふうになっているはずです。誰かが1人移れば、そちらの方は必ず時間が長くなりますから。こういうのがナッシュ均衡といいますけれども、そういう状態でなっているはずです。
それが右側の上のように、1から2へ新しい道路ができたとします。そうすると、経路3という、Aから1行って、2行ってBへ行く経路ができるんですが、こうするとさっき言ったような、誰一人して経路を変えない、そして使っている経路は、所要時間は同じになるような状態を計算しますと、右下のようになって、経路1に2、経路2に2、経路3に2、全部で6人が流れるようになります。
こうすると、全ての時間は107分で等しくなりますが、これを全部足した都市全体の便利さ加減ですね、総走行時間といいますけれども、これを比較してみると、道路を造る前が588分だったのが、道路を造って流れ方が変わったために、本当だったら全体的にも便利になって総走行時間というのは減るんではないかと期待できるんですが、計算してみると642分になります。
つまり道路を整備すると都市圏全体、システム全体の効率が悪くなるという場合もこうやって出てくるわけですね。もちろん先ほど言いましたように人は誰として今よりも短い時間へ移らない、長い時間へ移らないというルールが成り立ったら、初めて成り立つんですけれども、そのルールというのはそう不合理ではないはずですから、我々研究者としては、そういう流れ方を熊本都市圏で行われるとすれば、どこの断面が何台流れているというのを計算してみます。我々の部門では、これは当然の考え方です。これをプレイスのパラドックスといいます。
もっというと、エエっ!!こんなことまで起きるの!?ということを御紹介します。
左上が車と、車1台当たりの平均費用です。横軸が車の台数で、縦軸が1人当たりの平均費用ですけれども、車が多くなれば1人当たりの平均費用というのは当然高くなるので、右上がりのカーブになります。
右のグラフは公共交通の利用者で、これは軸が反対向きになっていますけれども、左側へ公共交通の利用者が増えると、1人当たりの公共交通の費用はどうなるかという絵ですが、誰も乗っていないときにバス1台買うとめちゃめちゃお金がかかりますので、初期投資の分だけぼっこんと上に上がります。しかし、それが2人乗ってくれる、3人乗ってくれる、どんどん増えてくると、1人当たりの費用というのはだんだん下がっていきます。
これを同じところに重ねます。それで自動車のゼロ、公共交通のゼロ、ここからここの幅の人たちが今都市圏で移動するというふうに考えてください。そうすると、どういうことが起こるかというと、当然車を使っても、公共交通を使っても、1人の費用が等しくなるような比率で、自動車の利用者と公共交通の利用者は決まるはずですよね。どっちかが高かったら必ず低い方に動くはずですから。
そうすると、どこで決まるかというと、ここで決まります。よく経済学で需要供給の交点でというのが、この場合は相互の費用の交点で決まります。そうすると、ここが道路整備前の交通であって、これより左側が自動車を使う人、これより右側を使う人が公共交通を使う人の数です。そのときの費用というのは、この横軸にあるあの高さになります。
ところが、例えばもともとの道路を2車線だったのを4車線に拡幅した場合を想定しましょうか。そうすると、1人当たりの費用は通りやすくなりますから下がりますね。そうすると、この費用曲線というのは、この赤いふうに右側へシフトします。同じ費用でもたくさんの人が通れるということですね。あるいはたくさん通っても、費用はあまりかからないというような曲線になります。
では、出来上がった後、どうなるかというと、先ほど言いましたように、この2つの曲線の交点で決まるはずですから、ここへ移動します。ここが新たな均衡点なんですけれども、ここというのはどういうことかというと、道路整備後の均衡交通量はこの赤のところになりますので、これより左側が車を利用する人、これより右側が公共交通を利用する人、そしてそのときの費用というのは、実はさっきよりも高いところで決まってしまうと。
つまり、ここの緑色の幅が道路整備によって自動車利用者が増加した分であるし、それによって費用もこれだけ増加するというふうなことも理論上は起こります。これはダウンズ・トムソンのパラドックスといいます。パラドックスではここかなと思っていたら、えらい違うから起こったという意味ですけれども、そういうことが起こる場合もあります。
これは必ず起こるわけではありません。かなりの条件が整っていないと起こりませんけれども、今のような場合も実際に観測されるし、理論上はちゃんと計算できます。なので、道路を造ったら駄目と言っているわけではなくて、造るときにはこういうことが起こるんだよということを考えながら、いろいろやっていく必要があるかなというふうに思います。
先ほどからいいますように、上流から流れてくる車の量とボトルネック容量の相対関係、これが重要なので、要するにどういう対策が必要になってくるかというと、容量を増やす、つまり供給を増やすか、需要を減らすか、これしかないわけですね。それが縦軸です。
横軸は、すぐできるものと短期間で費用も安くできるものと、時間もお金もかかるもの、2×2の4つの実施例に分けて、今までどんなことがやられてきたかというのを示したのがこれなんですけれども、もともと全く海外から、戦後視察団が来て、日本の道路網というのはどうなっているんだということで一生懸命やったのがこの道路施設整備ですね。それとか、熊本でもかなり立体化されているところありますし、幹線のバイパスをどんどん整備してきたと。これは造れや造れ、つまり道路を増やしたり広げる施策です。
ところが、これも市民意識が高まって、あるいは公害の問題とか、用地が高くて買えないとか、時間がかかって市民に迷惑をかける。いろいろな問題があって、このやり方というのはかなり上限が見えてきたので、今度は供給サイドも今あるシステムを上手に使って疎通能力をもう少し上げてあげようというようなことがやられ始めました。それがこの上でして、今あるものを上手に使おう方策ですね。
例えば信号制御をうまくやってやると。皆さん水道町の交差点でぼーっと信号を見ていただくと、何分かおきに周期がどんどん変わります。それは御存じないかもしれませんけれども、暇だったらみてください。それだけたくさん流すために県警は交通制御を物すごくやっています。しかし、これも面的に制御するとめちゃくちゃ大変なわけですね。あっちをよくすればこっちが駄目になります。ここをよくすれば次も駄目になります。これをいろいろ考えながら今一生懸命やられているんですけれども、これも限界です。
つまり、上手に使おう方策というのももう限界が出てきているので、つまり供給、あるいは容量サイドをいろいろ考えるともうなかなか難しい状態になってきているので、今はこっちへ移っていて、需要サイドを、車の利用を少し減らしていこう、あるいは管理していこうというマネジメントしていこうというのが主要な考え方で、世界はもうこれです。「元から絶たなきゃ駄目!」というのはちょっと大げさなんですけれども、需要を少し管理してあげるということですね。
実は、そのほかにも皆さん御存じだと思います。混雑料金制を導入するとか、官民民営化とか、PFI等を使って道路を民営化するとか、あるいはもっと大事なのは、その都市計画そのものとリンクして都市の構造を変えていくというふうなことが本質的な総合対策なんです。こういうのがありますけれども、そこまでいくと時間も物すごくかかるので、今はここの交通需要マネジメントといわれる短期で需要サイドをコントロールする、マネジメントするというのが進められています。
よく考えてみると、解決する課題は実は交通混雑の緩和だけではないなと、それを引き受ける公共交通をどう再生させていくか、この2つを両方一緒に考えないと問題は解決しないんだなというのが分かると思います。
交通混雑と渋滞の緩和と公共交通再生を同時に実現するにはどうしたらいいかということを考える必要があって、ややもするとひどい交通混雑を緩和するには道路を造ればいいとか、交差点の改良をすればいいとか、よく最近出てきているようですが、高速道路を造ればいいとか、そういうふうな話にいってしまうんですけれども、そうではなくて、実は公共交通をどう再生させてお互いがよくなるにはどうしたらいいかということを考える必要があります。
1番としては、先ほど言いました道路整備や疎通能力拡大、これは日本のこれまでの主流でやってきたわけですけれども、やっても逆に自動車の利用が増えたりする場合が先ほど言ったようなことで起こります。実際には御存じのように、東バイパスというのは北バイパスをつないだり、整備をしたんですけれども、だんだん車というのは増えてきている。日本でも十指に入るぐらいの交通量が流れているわけですね。6~7万台ですかね。そういうふうに思ったように働かない場合があります。
では、解の2として、公共交通や自転車に転換して車を少し減らしたり、あるいは管理する。管理するというと、何か強制的にやらされるんで何とかあまりよくありませんけれども、例えば皆さん、ナビゲーションシステムなんかも、あれは同時に同じ交差点にみんなが集まるから渋滞が起こるんで、時間をずらしたり、あるいはそこは満杯だから違う経路を通ったらというふうにアドバイスをすれば、実はかなり緩和できるんですね。そういうのも含めて管理、マネジメントといいます。
だけれども、それだけでは車の量は減りませんので、公共交通にこういう問題の諸元となっている車の需要を少し転換してもらおうというのが、1つの非常に有効な解であろうと。実はこれが世界のトレンドであって、熊本市、私たちが目指す解決策ではないかと私は今考えています。
今、県も採用していただいている、市長は前回の選挙の公約にも入れられていたんではないかと思いますけれども、この合言葉ですね。「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」。これは実は熊本だけではなくて、日本中でよく言われている言葉になってきました。
実際、64%が車を使っているわけですから、その1割ですね、6%ぐらいが車から公共交通機関に移れば、先ほど言いましたとがったところの速度の変化ですね、800台が700台、これ6%以下ですけれども、ぐっと速度が上がります。そうすると、渋滞はほぼ半減します。それと同時に6%、今の公共交通機関の利用にして6%ぐらいですから、車から6%移ると12%になります。ということは、倍増するわけですね。
実は、この言葉というのは上っ面だけを言っているように思いますが、実はとても論理的なんです。そのためには計画をする人たち、利用する人たち、あるいは財政担当者、あるいは有権者の方たちがどういうことをしたらいいかということを考えてみますと、計画をちゃんとやることですね。渋滞とか遅延とかを改善するためには、一番重要なのはバス等が遅れるために乗るのがいやだという方がかなりいますので、バスレーンとか、バス優先信号みたいなものをどんどん導入してあげて、遅延とか渋滞の改善に貢献すると。
それと、実は公共交通を潜在的に利用したい、あるいは利用してもいいなと思っている人がいるにもかかわらず、うまい働きかけができていないために、乗ってみると本当は便利なんですよ。そういう人たちに適切に利用促進を働きかけるような、これはモビリティマネジメントといいますけれども、データに基づいて潜在的な需要に働きかけて、そしてそれに合わせるような適切なサービスの水準に持っていくというふうなことをやることですね。
これが非常に重要な計画であるし、利用者はどういう情報がほしいかというと、例えば歩いて駅まで行って、駅から幹線に乗って、それからバスに乗り換えて職場に行くということを考える場合、どうしても幹線の電車、バス、駅までの徒歩を別々に考えて、一貫した利便性というものを享受できていないということですね。
ところが、これをスマホ1本で、何分で行って何時のものに乗り換えれば、何分で待ち時間があって結局何分で着きます。ましてやそれが予約制ができたり、あるいは料金が一気通貫で支払えるというふうなことができればきっと乗る人もっと増えると思いますね。MaaSといいますけれども、そういうのをどんどん提供していくことですね。
これも最後に話をしますが、そういうことというのは実は熊本市もかなり先進的にやられていますが、それでもなかなかうまくいかないようなことが起きているので、その場合にはもっと行政というかな、自治体が働きかける必要があるというので、これも最後にお話ししたいと思います。
公共交通はこの辺簡単に話をしますが、2008年にはこの4社、熊本市交通局のバス部門ありましたけれども、2018年にはこの交通局がなくなって、民間に全部移譲したわけですね。代わりに出てきたのが面的な移譲先である都市バスでして、都市バスは非常にいい働きをしているんではないかと私は思います。
これは予算補助ですね、一番多かった頃は平成25年ぐらいですかね、この緑色のところが自主運行系統に対する補助額ですので、17億円ぐらいですね、補助をしていたときがあります。これは熊本市の一般会計からの繰り入れですので、このほかに運行補助として2億円ぐらい入れていたはずなので、当時は20億円ぐらいの補助をやっていましたが、その後、都市バスに全部移譲された頃を中心に少なくなって、今はもうこのぐらいですね。これ平成30年ですから、今はもっと少なくなっているはずです。うまく機能してきたなと私は思っています。
当時は先ほど言いましたように、最盛期の4分の1しか公共バスを使わないと、昭和46年ぐらいが多分最盛期だったと思います。その4分の1ですね。直近10年間でも3割ぐらい減ると。それと先ほど言いましたように、運行補助が2億円ぐらいで、そのほかに一般会計からの繰入れが十数億円ありましたので、それとここにありますように、2003年に九州産交が経営破綻して産業再生機構から支援を受けたり、熊本電鉄も私的整理に入ったり、熊本バスも地域経済活性化支援機構によって支援を受けるというふうに、今ある熊本の都市バス以外は全て一度はつぶれる、支援の仕方はいろいろ違いますけれども、1回つぶれたということで、バスサービスの改善と運用を抜本的に考え直さなければいけない時期というのが出てきました。
それに対して、公共交通再生のための政策として、2008年から熊本市のバスのあり方検討協議会という今の地域公共交通協議会の前身に当たるものなんですけれども、これは大西市長の前の市長が我々に諮問して答申したものですが、私が思うにこれは画期的なんですね。
その上の方を見ていただきますと、「熊本市営バス事業を民間事業者に全面移譲すると共に」、これ全面移譲ですね。「バス事業を市民の生活交通を確保する重要な行政サービスの一環と位置付けます」と言っています。
つまりこれはごみの収集とか、水道の供給とか、それと同じような行政サービスの一環とみなしますというふうに言っています。そして行政は市民に対してモビリティー水準、移動可能性の水準を確保することにだから責任を持ちますよと、そのかわり適切にバス運営にはコミットしていくということを中心にした市長からの諮問に対して、我々のこの協議会でこういう答申をしたら、市長は、ではこれで今後のバス、あるいは公共交通の政策はやっていきましょうということで決まって、それがずっと今根底にあって進められているわけですね。
これは画期的です。どこの自治体に行っても、バス事業を公共サービスの一環と位置づけているということを文書に示しているところは多分ないと思います。その例がこの公共交通基本条例ですね。これは前文、目的のところを抜粋していますけれども、「移動する権利を有するとの理念を尊重」する。移動する権利を認めるとは言っていません、これやると立田山の上に私が住む、居住は自由ですから、立田山の上で見晴らしがよくて環境のいいところ住みたい。だけれども、移動の権利を与えると、そこへバスを引いてくださいという権利に対して義務が生じますから、それを実行しなきゃいけないので、その気持ちは分かるから移動する権利を有する理念は尊重する。そのような政策を進めていきます。そのような地域社会を実現していきますということを言っています。
これはよく参照されるフランス交通法典ですね、Code des Transportsと言われるんですけれども、これはもう同じような表現です。フランスは移動の自由が認められていると、権利として認められているということを間違って言う人がいますが、そんなことは書いてありません。これと同じような表現です。ただ、やはりその重視の仕方が全然違うということですね。
そのためには、自動車から公共交通への転換を推進して、公共交通を基軸とした多核連携のまちづくりを推進していきましょうと。そのためには市、市民、事業者、あるいは商業者とかが参画して一緒に働いていきましょうということを言っています。これは本当に中身も高い、理想だけではなくて中身も非常に高い公共交通基本条例の目的、前文だと思います。
これを実行するために、通常条例とか法律というのは目的があって、その後、言葉の定義がありますが、この定義もちゃんとされていまして、地域を3つに分けますと、その3つはバス事業者が自主的にサービスするエリアと、それだと赤字だからやれない。
しかし、地域の住民が協議会をつくって、自分のところにこういう路線を引いてくださいという不便地域と、これはバス停から500メートルから1,000メートルぐらいの間のエリアですね。これをつないだ不便地域、そして1キロより離れたところ、これは空白地域、この3つに分けてあります。そして、それぞれの地域にそこに合った適切な公共交通機関をサービスする。つまり一人も漏れは出さないといっているんだから、3つに分けてそれぞれに必ず適切な公共交通機関をサービスしているわけですね。こんなところ日本中ないです。
例えば西鉄の例をいうとよくないですけれども、あそこもやはり独占企業でかなり熊本のバスに比べると経営状況はいいんですけれども、赤字のところはぱっと切ります。そうすると、そこは完全に空白地帯になって何もない状態です。ところが、熊本市の場合、そこにあった公共交通を必ず導入しているわけですね。
ここにそこのメンバーおられると思いますけれども、それがどういうものかといいますと、この自主的にサービスするエリアですね。とはいっても、今収支率が6~7割なので、赤字でも実は民間事業者は提供してくれているんですね。主にこういう仕組みでやっています。
右上のようにいろいろなところから都心へ、今でもこういうところ結構ありますけれども、路線が長くて街の中へ全部バスが入ってくるような仕組みを、右下のように適切な乗換え拠点を造ってそこから都心までは高速で大量の交通機関に任せて、その周辺部の枝のところですね、フィーダーといいますけれども、ここで往復をたくさんできるようになりますから、活躍してもらってサービスを上げるというような仕組みにしましょうということですね。これをゾーンシステムといいますが、これ熊本市の場合、今東西南北ですね、一応これで路線を編成していっています。成功しているところ、あまりうまくいっていないところいろいろありますけれども、考え方はこうで、都市圏全域をこんな考え方で再編し直しているというのは多分あまりないと思います。
それと2番目ですね、不便地域、500メートルから1,000メートルのエリアですね、ここは緑色の矢印で示しているように、地域が支えるコミュニティバスですね。ゆうゆうバスですが、これは地域の方たちに路線とか止まる停留所みたいなものを議論してもらって、ここに走らせてくださいという申請をしていただくと。そうすると、市は提供します。ただし、7割までは赤字でも補填しますけれども、3割は自分たちで稼いでくださいという最初の契約を結んであります。
もしこれ何でも出すといったら青天井ですから何もしなくても空バスがどんどん走らなければいけなということになりますから、3割は自分たちで稼いでください。それは別に乗車料金だけではなくて、例えば通る沿線のスーパーとかお医者さんとか、そういうところから基金をもらってもいいし、とにかく自分たちで支え合うような路線を造ってくださいということですね。
ところが、残念なことに最初5路線、9系統でしたかね、ありましたけれども、この3月31日に最後の植木循環ですね、これも廃止になってしまいました。全てなくなってしまいます。
では、その地域どうなるか。それは先ほど言いましたように、不便地域から空白地域になるわけですね。これが普通のところはならないです。でも、これは、熊本市は絶対に提供するといっているわけですから、次のランクの空白地域になります。
空白地域はどうやっているかというと、これは乗合タクシーですね。これは全面的に行政が経費を負担するということです。ただし、御存じのように、最寄りの乗換えのバス停までしか走りません。それと定時です。定路線です。
私、前から言っているんだけれども、定時と定路線なんてバスが小さくなっただけだから、利便性上がらないからオンデマンドにしろと言っているんですけれども、あるいはエリアを自由に動き回るようなですね。ただ、ここの走っているところは、どこも谷間なんですね。谷筋なんですよ。ですから、左右へ動き回ることはできないし、バス事業者もそうですけれども、タクシー事業者も人員が全然足らないので、ここに専念することがなかなかできないということで、今はこういう状況になっています。
ただ、この実態を見ると、一番下の1.19という数字は平均の乗合率で、タクシーには平均1.19人しか乗っていない。つまりマイタクシーになってしまっています。それとグレーのハッチがかかったところはやめたと、要らんと言われるところもあったり、グレーのところから色がついたり、数字が出たりしているところは、新規にコミュニティバス、つまりゆうゆうバスが走っていたところが、この乗合タクシーに変わっていったところです。非常にダイナミックに変わっています。
その典型が乗合タクシーをやった、最初はゆうゆうバスが走っていたけれども、これでもこれが廃止になって乗合タクシーにしようと思ったけれども、それよりも先ほど言いました、ここは谷筋ではないので、天明あたりですけれども、面的なサービスができるということでリアルタイム・オンデマンド乗合タクシーですね、チョイソコくまもと西南が今非常に高齢者を中心に利用者が増えていて、今の面的なリアルタイム・オンデマンド型の面的なサービス、これが非常に成功している例です。
今のように、熊本市というのは、実は置いてきぼりを絶対に全然してないんですよ。濃淡はありますけれども、成功しているところ、そうではないところ、でも理念としては非常によくできているところだと思っています。
それで、実はこういう動きというのは国までも動かしていまして、これは随分前ですけれども、私、熊本大学にいたところに、当時は市営バスと産交バスと電鉄バスが熊本大学の前から都心まで行っていたんですけれども、市営バスは産交バスと電鉄バスに移譲しましたので2つになりました。だけれども、時刻表はそれぞれ別々にあったんですね。でも、我々乗るのは、黄色いバスだろうが、青いバスだろうが関係なくて、とにかく都心に行ければいいわけなので、それを今何時だからこっちは駄目、こっちは多分あるなというふうなことで、とても不便だったのを1枚のバス時刻表にしていただいた例です。
これは一目で分かります。色が違って、赤が電鉄バスで黒が産交バスだけで、私は電鉄バスしか乗らないなんていう人は多分あまりいないと思うので、これで十分というか、こっちの方がよほどいいわけですね。
もっとすごいのは右側でして、これは日銀前から宇土方面への路線ですけれども、全ての会社の路線を1枚の路線図に書いてあるわけです。こんなこと日本中探しても多分ないと思います。必ず時刻表と路線図のセット、書き方が違うから同じバス停が書いてあっても全然イメージができないですけれども、これは一目で分かる。これは実は国が、これはカルテルなんですね。でも、これは当時からやっていました。後でちょっと紹介します。
それともっと非常に便利なんですけれども、バスきたくまさんですね。これは地震でループ型の時刻表示が壊れちゃったので、こういうふうな携帯で見られるようなものになったわけですけれども、県下全域で同一のバスロケーションシステムが使えるというのは、多分熊本市ぐらいしかないんではないですか、最近は変わってきているかもしれませんけれども、地震の復興費用でこれに入れ替えることができました。とても便利です。でも、残念なことにうちの学生さんに聞くと知らない子がいっぱいいます。
こういうことをいっぱいやってきて、この赤が課題だったのに対して、青色の解決を促したということは、熊本市の交通政策課の方たちが頻繁に国の方に行って、こういうことをやりたいんだけれども、今こういう制約があるけれどもどうにかならないかということで、いろいろそれを緩和していただいた例で、その一番の成果が赤で書いてある令和2年11月27日のバス事業の独占禁止法の特例法ですね。これを認めさせたことです。
御存じのように、路線を別の会社同士で調整し合ったり、運行頻度を調整し合ったりするのも完全カルテルだったんで、今まで一切認められていなかったんですけれども、先ほどの時刻表を一緒にしたりとか、路線図を一緒にしたりとかする、法律に触れるぎりぎりのことをずっとやりながら、最終的にバス路線網の調整、それと運行費の適正化を幾つかの会社の中で相談してやるということまでは認めてもらえるようなことになりました。
最終的には、皆さんも御存じだと思いますが、ソウルなんていうのは100社ぐらいあるんですけれども、バスの色3つしかありませんね。幹線部分とフィーダー部分と都市間ですね。それぞれは別の会社ですけれども、機能に合わせて色も一緒にしてあるわけです。財布も一個です。全部集めてそれを提供している、当時ですから今ちょっと変わっているかもしれませんけれども、代キロですね、サービスのレベルに提供しているサービスのレベルに合わせて配分するというふうにしています。
日本のこの独禁法の特例法では、お金のことについては一切まだ触れません。将来的には、そういうことができるようになるとかなりいろいろなことができるかなと思います。
彼らがやったのは、今言いました重複区間等の最適化ですね。それと経営資源を余ったところから別の会社へ回すというようなこともやっていまして、この共同経営推進室ですけれども、ここが偉いのは計画を市民に訴えて、実際にやってその成果を評価して公開するということをちゃんとやっているところです。
その例が次のページなんですけれども、これは第1期の成果なんですが、収益性も改善していますし、運転士数も5.5人余らせることができたと。そして車両数も4.6台余らせることができたと。それによって足らないところへ、あるいは新しい路線へこのバスとか、運転士さんを回しています。別の会社がやるところですね。出向みたいな形だと思うんですけれども、そういうことまでやっています。これはほかのところに聞くと、口が開いたら戻らないぐらいびっくりされます。
こういうことを一生懸命やってきたわけですけれども、実はそれでも限界。バスだけでのことですけれども、共同経営推進室バス会社5社でいろいろな検討をされていまして、経営効率をいろいろなことを工夫してやられているんだけれども、経営努力の結果上の限界もだんだん見えてきたから、さらなるいろいろな組織との連携によって公共交通全体の在り方を考える必要があるんではないかということで。その仲間に入っていただいているのがもちろん県、市ですが、そのほかに熊本市の交通局と幾つかのタクシー会社が合併した地域交通ホールディングス、タクシーの会社としてはTaKuRooという名前で走っていますが、そこです。
そこで、一番下にあるように、エリア全体の最適路線網への転換を図りつつ、そのほか、タクシーも含めた、あるいは市電も含めた公的機関が、公共交通に責任を持つような体制が取れないだろうかというふうなことを市の方へ今いろいろ相談されているんではないかと思います。
よく見て考えてみると、左の2枚がバス・市電の収支率です。実は熊本市というのは頑張っていまして、バス5社の収支率83%ですね。市電も86%、赤字なんですけれども、頑張っておられます。
ところが、欧米の収支率がその真ん中のグラフなんですが、ロンドンなんていうのは125%、つまり黒字なんですが、そのほかのフランスですね、ドイツ、ベルギー、とにかくヨーロッパの国ですね、棒グラフを見てもらうと、ほとんどの国が30%~60%の間です、収支率。つまり、7割~4割はどこかから補填していただいているんですね。これが常識で、ロンドン、イギリスは例外です。
それに比べると、熊本市のバスも市電も頑張っておられるということです。それでも先ほども申し上げたように、これ限界という状態になっていますから、これをどうにかしなきゃいけない。何かいい方法ないかなと思って右側の表を見てもらうと、実は交通に関する行政予算を地域交通、公共交通と思っていただいていいと思いますが、道路と予算額を比較してみるとかなり差がありまして、地域交通への予算は道路予算のほんの3%ぐらいしか過ぎません。だから、道路予算の5%をバスの地域交通の方へ回してもらうと、マイナス10億円ですね、この赤字が解消できます。
こういうふうに、もう少し道路と地域公共交通ですね、そこがいろいろ相談をしていただいて、利用者あるいは都市交通全体としての利便性とか、そういうものが上がるような工夫というのはできないことはないんではないかというふうに思います。
どんなことがやられるかといいかというと、これは公共交通だけの話なんですが、今までバスを走らせたりするのに、バスの路線網の計画とそれを実際に走らせる人と、お金のやり取りというのは全部分離されていたんですね。これは共同経営推進室になる間ですけれども、計画は行政が立てて、事業者が走らせて、お金のやり取り、補助金を中心とした補助金のあたりを運営してやるということであって、これが実は、ほとんどがバス事業者が全部やっていたわけです。
ところが、外国は先ほど言いましたように、右側のように計画をするのは熊本市を中心としたもの、それと第三者機関が真ん中にいて、ちゃんと走っているかどうか、あるいは補助金の申請とか、それの配分とかをやるし、バス事業者は運行に徹するというような、要するに計画と運営と運行を分離したような組織体系、これがヨーロッパを中心としたところのやり方です。
今、共同経営推進室は大体このような形になって、熊本市はなりつつありますが、一番下のところはバス事業者だけなんですけれども、ここが今後先ほどちょっと申し上げた地域公共ホールディングスみたいなタクシー事業者とか、非常に今便利で皆さん利用者が増えていますチャリチャリですね、ああいうところがこの下にぶら下がってもらえるととても便利になる。ここを御存じかと思いますけれども、MaaSオペレーターとして位置づけてくると、これは完全な熊本MaaSになります。
そしてさらに、これに先ほど言いましたお金のやり取りとか、今は触っちゃいけない部分もありますけれども、あと料金の設定の仕方ですね、そういうところまで踏み込むと、これも聞かれたことがあると思いますけれども、ドイツを中心としてあります運輸連合ですね、こういうのに実はなるんです。直前まで熊本市の場合来ています。どうにかここへ持っていくのがいいんではないかなと思います。
とはいうものの、そういうことをするときに、ちょっと井芹事業管理者には申し訳ないですけれども、目に余る交通局と書いていますが、ちょっともう少し公共交通協議会とか、共同経営制バスですね、あるいはタクシーのところに協力をしていただきたいと思う具体例が、私、どうしても均一料金と昔からワンコインだから便利だといいますけれども、180円でワンコインではないですよね。100円とか500円だったらワンコインでできますけれども、それを言われるのがよく分からんし、それは本当に妥当なのか、合理的なのか、これもう一回ちゃんと考えてもらいたい。ICカード変わりますけれども、とにかくタッチ決済でできるわけですから、自動的に課金をされるわけですね。そのときにコインで出すときに便利な額、そんなもの関係ないではないですかということですね。
それと競合して走っています健軍・益城方面ですね、これは料金がバス路線と全然違うと。もう少し何かうまく調整されるといいんではないかと。
それと、一時期快速運転をしたらどうだということで、物理的になかなか難しいというのは分かりますけれども、バスとしては市電と、先ほど言いましたゾーンバスシステムといって乗換え拠点から都心までは大量で高速の乗り物にするということで、その代表格が市電です。今度3両編成の高容量の車両がどんどん入っていきますから、高速で大量が可能になっていきます。そこは、本当はバス会社に任せたいと思われているんですね。それよりも郊外部分のフィーダー部分でたくさん人を健軍なら健軍とか、神水なら神水に集めてくる作業をしたい。
それと快速運転すると、市電の中であまり乗っていないところあるんですね。そこは飛ばしますから、高速になるんですね。では、誰がその飛ばした駅の近くの人たちはどうするのか、バスがそこはちゃんと拾っていきますと言ってくれているのに、それがなかなかうまくいかないというのがちょっと残念だなと。
それと今もそうですけれども、VISAタッチですね、これは降りるときだけにしかしませんけれども、何で乗るときにタッチさせないんだろうと。どこから乗ってどこへ下りたという、それが何時何分に乗って、何時何分に降りたという宝の山のデータ、これを全部放棄してしまっている。一言入れるときに誰かに相談されなかったのかな。いっぱいありますからやめます。
下から2つ目ですね、上下分離ですね、これとても大きな改革だと思います。ところが、経営計画書を読みましたけれども、需要をどうやってその後獲得していくのか、上下分離を使うことによってそれがどういうふうに機能するのかということは、一切書かれていなくて帳簿だけが載っているという状況で、別にあるんだと思いますけれども、それがあまり聞こえてこないのがとても残念です。
都市軸というのは、物すごく大事なんですね。今、人が住んでいるところに軸をつくって、軸と言っていればいいんではないんです。軸というのは、そこの沿道をどういうふうな土地利用も含めて考えていくかというのが大事で、その軸によってそこに沿道に高収益、あるいは高機能の施設を配置して、そこを使う人たちが増えることによって、またその軸の乗り物、公共交通を使う利用者も増やしていくということのサイクルをつくることが都市軸をつくることなんですけれども、そういうのが全然あまり見えていないと。今度の健軍からの延伸ですね、私はぜひやっていただきたいんです。
それにとどまらずに、まだまだ軸として街の形をうまくやっていく軸というのは、まだたくさんあるはずですね。そこには市電は無理かもしれないけれども、例えばBRTみたいなものをどんどん導入して、もちろんそのためにはバスレーンが必要ですけれども、そういうことをやって軸を形づくると同時に、都市の形を形づくっていく、そういうことを一緒にやっていくという、そういう執行が必要だろう。それの一番大事な市電をお持ちの交通局には、もう少し協調あるいは連携していただけるといいかなというふうに思います。
それをするときに、これは最後になりますけれども、ややもすると熊本市だけの話になってしまうんですが、広域地方政府組織、これがとても必要だと思います。
例えば消防とか、水道というのは、広域事務組織がありますよね。それと同じように、熊本市だけではなくて都市圏なんですね。益城町のことも考えないといけないし、ましてや今非常に注目されている菊陽町とか合志市とか、あるいは南の方もそうですけれども、そういうところを一緒に考えるような広域地方政府、世界で一番住みやすい街1位のポートランドですね。ここではメトロという組織がありますし、パリはパリ市だけではなくて都市圏というメトロポールという組織になっています。そこでは交通の計画、料金の設定、課税、これも全部基礎自治体ではなくて、メトロポールとか、メトロという広域地方政府が行っています。そういうのが今後は必要になってくるかなというふうに思います。
3番目は、PSOと、これは例えば熊本市ではバスは最低15分に1本、これぐらいのネットワークでという計画を立てたら、それをやる人を入札に応じてというやり方ですね。今は自主的に各事業者がネットワーク、もちろん市と調整しながらやられていますけれども、赤字になったら補填するというやり方なんですが、PSOというのは、パブリックサービスオブリゲーションと言って、その入札に応じるときにこれぐらいのお金でやります。その代わり提示された契約は必ず守りますというやり方ですね。これはヨーロッパでは当たり前です。
だから、世界に3つか4つ大きな会社があるんですけれども、イギリスの会社がベルギーで走っているとか、そんなの当たり前なんですね。この契約さえ満足すればいいわけですから。利用者は誰がやっていようと、実は関係ない。だからといって、熊本市ですぐやれとは言いませんよ。だって、長い歴史の中で地権者の方とか、投資されている方の関係がありますから、一挙にそういうのは難しいのは分かっているんですけれども、こういう考え方も視野に入れながら、サービスの向上に、それともちろんこれだったらやると言っているんですから、その会社は経営的にもそれはできるわけですね。そういうことを了知させてもらいたいなと。
つまり、地域公共交通維持改善のための本質的議論というのは、こういうところまで入っていかないといけないので、今こそ熊本市でこういうことが始まればいいなというふうに思いますし、実は日本中が熊本市が次何やるかをとても期待しています。
この辺にしておきますかね。ちょっと1時間になっちゃいましたので、あと計画の立て方もいろいろ考えなきゃいけないんですけれども、これはちょっと飛ばしましょう。
真ん中だけやりますかね。今までは需要がこうなるから、こういうふうな施設整備をしなきゃいけないというような需要追随型の開発だったんですけれども、もう需要なんて伸びるはずはないんですね、人口がこれだけ減ってきていますから。では、こういうところを着地点に置いて、そうするためにはどうやって行ったらいいかなというふうに後ろ向きに計画を、後ろ向きといったらマイナスのように見えますけれども、目標を定めてそれに到達するような最適な計画はどうあるべきかということを考えるのが今のやり方なんですね。
これはまだ日本の場合なかなかやられていないんですけれども、ヨーロッパではもうこれは当たり前です。バックキャスティング型の計画のやり方ですね。これも今の交通マスタープラン、パーソントリップ調査の分析とマスタープランの作成が今年、来年中に行われますが、こういうやり方で進めていきたいなと思っていますけれども、今後、熊本市でも立案されるようないろいろな計画というのは、こういう形でないとうまくいかないんではないかというふうに思っています。
ちょっと長くなりました。御清聴ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 ありがとうございました。
以上で、意見陳述人からの意見の開陳は終わりました。
それでは、意見陳述人に対する質疑をお願いいたします。
なお、念のために申し上げますが、意見陳述人は委員長の許可を得て発言し、委員に対する質疑はできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、委員の方々お願いいたします。
◆上野美恵子 委員 溝上先生には、今日は大変貴重なお話ありがとうございました。
私も公共交通の委員会等々で、ほかの委員会でも御一緒させていただいたこともございまして、今日また改めて勉強になりました。
あらかた前半のところは本当に私、考えていたことと一致点が多くて、とてもうれしかったです。
ちょっと分からないところがあったのでお尋ねしたいんですけれども、さっき大変厳しいというふうにおっしゃった目に余る交通局の非協調というページがありましたが、ここのところで丸ポチの1点目の「ICカード導入後も全線180円均一運賃とすることの妥当性、合理性」という、この点の指摘があったんですけれども、先生としては、ではどういうふうにしたらいいとか、お考えをお持ちであればもう少し教えていただけないでしょうか。
◎溝上章志 意見陳述人 電子決済になっているわけだから距離制にすればいいんですよ。何の問題もないと思います。だから、バスと同じようなやり方にすればいいんだと思います。長く乗ったら高くなる。今均一運賃ですけれどもね。
ちょっと聞いたところによると、ゾーン運賃にしたいというふうなお考えもあるようですが、何でゾーン運賃にするのかの理由もよく分かりません。そしてそれがバスと共通のゾーン運賃だったらまだ分かるんですけれども、市電だけがやりそうな感じになっていて、そのあたりの話がどうなっているのかもよく分からないうちに、何かいろいろな料金システムを考えられているらしいんですけれども、それは置いといて、とにかくICカード等があるわけですから、距離運賃、バスと同じ距離制にすればいいんではないかというふうに思います。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
そうしたときに長年熊本市は均一料金で来ているので、遠いところから中心部に出てくるときにすごい安い料金で来られるので、市電をうれしく利用できるというか、やはり公共交通を優先して使おうという意思が働いていたと思うんですよね。
その前のところで私も共感したんですけれども、今後、要するによそからのかなり距離があるところからの車の流れを中心に抑えていく、なくすではなくて抑えていくためには、一定そういうところからの車で来る方たちに公共交通を利用していただくというふうにしたらいいんだなと思ったんですけれども、そうなると、例えば路線が決まってはいますものの、今均一で安くできている人たちが距離制によって若干高くなる部分が出てくると思うので、そうなった場合にどうなのかな。
むしろさっき先生が前段でおっしゃったように、今の公共交通を今後車からもうちょっとシフトして利用促進していくためには、今までは公が補助をしていくという考えだったんだけれども、もっと支えていくというふうな側面が必要ではないかという御指摘があったと思ったんですけれども、そういうふうにするならば、市電の均一料金を一定部分引き上げていくような変更の仕方というよりは、バスをもっとちょっと離れた距離からでも安価で利用できるような、そういう工夫の方が利用者側からするならば、バスにもっとたくさん乗ろうというふうになったりしないかなと思ったんですけれども。
◎溝上章志 意見陳述人 その考え方も一つあると思います。今はだから、同じところを走っているにもかかわらず、システムが違っていることが一番問題で、バスの料金のシステムと市電のシステムを共通にして、バスと市電の区間は全部180円にバスもできればいいんですけれども、恐らくそうすると今よりももっとバス会社の経営状態は悪くなると思います。
そこに例えば市が赤字分をもっと補填すればいいではないか、それもありますけれども、そのコンセンサスというのはなかなかまだ取れていないような気がしますから、とにかく料金の問題にしろ、とても難しいわけです。難しいというか、ほかとのことを考えないといけないし、収入・支出、財政のことも考えないといけないので、少なくとも今、あまり抵抗なくやれるのは、全体的に下げて距離制にする。市電も距離制にするけれども、バスも全体的に下げて車へ戻っていく人をできるだけ下げる。できれば、バスも安くなったから公共交通機関、車からバスにも乗ろうという人を増やす。そういうことが大事かなと思いますね。料金の問題とても大事だと思います。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
最初の公共交通に対する財政的な何か問題というところで、補助を出してあげられるというのはでなくて、もっと公共交通を支えていく、利用を徹底的に促進していくという立場に立った財政的な支えというか、それが必要なんではないかなと私、お話を聞いて思ったもんですから、何ページだったかな、道路との予算の比較とかもありましたけれども、もう少し車を調整していくというふうな発想の方に重きを置いて、道路中心から公共交通の予算配分というのを先生がさっきおっしゃったように、比率を増やしていく必要があるなというふうに感じました。
◎溝上章志 意見陳述人 基本的に私も同じ意見です。ただ、料金の設定の仕方はこれから皆さんで考えていただきたいと思います。
それと、ただ、赤字の補填をしてあげればいいんではないかという発想から、やはり今おっしゃったように、積極的な投資といったらいけないけれども、事業者ではどうしてもできないことがあるんですよ。
例えば、先ほども健軍を乗換えの拠点にしようとする考え方非常にいいと思うんですね。ところが、木山とか、長嶺とか南の方からそこへバスが入ってきて、止めるところがない。回転する場所がないんですね。これを自分で車庫とか、回転場を民間事業者造れと、これは無理です。そういうふうな、要するに物的な投資で施設の投資、こういうのは行政が率先してやっていただくというのがとても大事だということで、赤字補填だけにとどまらないような公共交通サービス全体のサービス水準を上げるための投資、そういうのは積極的にやっていただきたいというふうに、同じように思っています。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございました。
私もそう思います。
○田中敦朗 委員長 ほかにありませんか。
◆藤山英美 委員 溝上先生、お世話になりました。いろいろな視点から御指摘をいただきました。
ちょっと今の上野委員の関連ですけれども、市電の150円均一運賃というのは、私が提案して実現させていただきました。なぜかというと、その当時は、定期券以外は整理券を取ってほとんど現金だったんですよね。運転手さんの精算のときの苦労を考えて、そして執行部に聞いたんですけれども、150円均一だったらとんとんという話もあったもんですから、それでは働き方もあるからということでやって、バス事業者の方には申し訳なかったんですけれども、そういう採用をしていただきました。今のようなICカードでやれば距離制でもよかったかと思っておりますけれども、その当時は現金決済だったもんですから、そういう提案をいたしました。
そして産交さんは私の地域ですけれども、180円のことで路線の見直しを相当されているんです。だから、電車通りは激減しております。そして地域の中に、何本も路線を造られたんですね。私もコロナのときはあまり利用しなかったんですけれども、その後、乗ってみると結構利用がありますので、今までバス停まで歩く距離が長かったところに路線ができたもんですから、かなりの利用が高くなって、そしてほとんどがいろいろな経路を通して県庁経由で合流するようになっているんですね。結構利用はあって、本当にバス事業者のそういう努力というのは感じております。
しかし、空白といいますか、なかなかバスを利用できないところを今後どうするかというのは、先生の御指摘のとおりだと思いますので、そういう利用が公共交通でできれば、もっとよくなって自家用車の利用も減ってくるんではないかなという思いはあります。ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 そのほか質疑はございませんか。
◆齊藤博 委員 今日は、先生ありがとうございました。
ちょっと先生の御見解を改めてお尋ねをしたいと思いますが、公共交通全体での不具合のページにライトレールの宇都宮駅の御紹介があっておりますけれども、いわゆるLRTといわれるもの。この熊本市の今の公共交通の現状も踏まえる中で、BRT、バス・ラピッド・トランジット、この可能性というのは、先生どのようにお考えなのか、可能となれるような素質があるのかどうなのか、ちょっとそこの御見解を聞かせていただければと思いますが。
◎溝上章志 意見陳述人 BRTというのは、バス・ラピッド・トランジットなので、連接車両を走らせたらBRTと思っていらっしゃる方がおられますけれども、決してそうではなくて、ラピッドではないと、速くないと駄目です。速く走るためには、車に邪魔されないようにしないと駄目なので、やはり専用レーンがどうしても必要になると思いますね。専用レーンを増やすということは、普通のバスにとっても速度が上がります。
ただ、需要が多いところは連接車両で高速で走らせないといけない。それが実は先ほど言いました都市軸に当たるところで、今、市の方で一生懸命計画、あるいはもう実行されるんではないかと思うんですけれども、産業道路ですね、東バイパスから大江の交差点辺りまでですかね。あそこを5車線化して上りか下りかだけをバスレーンにして、連接車両を走らせる。それだけでは多分まだ不十分で、本当は長嶺あたりまで延ばさないと駄目だと思うんですけれども、そういうところにBRTというのは非常に役に立つだろうと思います。
だから、そういう路線を積極的に造っていく、そして沿道の土地利用とか施設配置を適切にしていって利用者をさらに多くして、都市としての機能を向上させると同時に、交通軸での利用者を増やしていくということをどんどんやっていくところですね。
これは、今言いました産業道路だけでなくて、実は南熊本駅のところがとてももったいないんですよね。JRで南の方から、八代の方から来たら、都心に行くには今新水前寺駅をみんな使われていますけれども。もうあそこは混雑で市電も満杯、乗れない状態。実はその前の駅で降りて、国道266号線ですね、今のところまだそんなに混雑はしていません。もともとあそこは市電が走っていたところですから、あそこの両側をできればLRT、でもLRTが難しかったらBRTですね、そういうふうにして活用されれば、南熊本の利用価値物すごく上がると思います。
今はないことはないですけれども、熊本バスが一生懸命やられていますけれども、まだ何というかな、ブレイクスルーになるほどの斬新さとか、利便性の向上というのがやはり見られないですよね。あそこなんかは、次にやるところとしては非常にいいところではないかなと思います。
先ほど言いましたように、2両編成の連接車両を走らせたらBRTということではないとだけちょっと記憶にとどめていただいて、とにかく速く、定時性を持って走らせる、それも高頻度で。そのようなバスシステムのことをBRTということですね。たくさん可能性のある路線はあると思います。
○田中敦朗 委員長 そのほか質疑はございませんか。
いいですか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 それでは、ほかに質疑がなければ、以上で意見陳述人に対する質疑を終了いたします。
本日は大変お忙しい中、本委員会に御出席いただき、また貴重な御意見を述べていただきまして、本当に溝上先生ありがとうございました。心から感謝申し上げます。
本委員会といたしましては、本日いただきました御意見を今後の調査に十分に生かしてまいりたいと考えております。
本日は大変ありがとうございました。
どうぞ御退席ください。
〔溝上章志意見陳述人 退席〕
○田中敦朗 委員長 以上で、意見陳述人からの意見聴取を終了します。
次に、「公共交通に関する住民アンケートについて」、「次期地域公共交通計画の策定に向けた取組について」、執行部の説明を求めます。
◎大川望 交通企画課長 それでは、資料1をお願いいたします。
「公共交通に関する住民アンケートについて」でございます。
地域公共交通計画の策定に向けましては、市民の方々、地域の特性に応じた施策を講じることが当然必要でございます。市民等の公共交通に対するニーズ等を把握するためにアンケートを実施するものでございます。
2、アンケートの概要でございますが、対象といたします市町村にお住いの方々でございますが、記載のとおりでございますけれども、例えば山鹿市であったり、玉名市であったり、やはり植木にお住いの方々であったり、河内にお住いの方々というのは、市域を超えたところでの生活圏域等も考えられますので、そういった地域住民の方々の御意見というところも加味して調査をかけたいというふうに思ってございます。
方法につきましては、WEBアンケートと記載をしてございますけれども、各世代、いろいろな世代の方からの御意見を賜りたいというふうに考えてございますので、しっかりと聞き取りができるようにWEBアンケート以外の方法についても検討いたしたいと思ってございます。
調査の時期につきましては、12月頃を想定してございます。
3ですけれども、アンケートに盛り込む視点というところでございますが、大きくは記載のとおりの考えでございますけれども、各委員の方からはこういった切り口での意見を聞くとよいだろうとか、そういったお気づきの点ございましたらば、御意見をいただきたいというふうに考えてございます。
また、取りまとめましたアンケート結果につきましては、本委員会にまた御報告を差し上げたいと考えてございます。
続けて、資料は都-1をお願いいたします。
ICリプレイスについてでございます。
昨日、9月30日ですが、バス事業者の方が記者会見等を開きまして、報道等でも御承知かと思いますけれども、決済手段の機器入替の時期というものがはっきりと示されたところでございます。
図示してございますとおり、全国交通系ICカードについては、11月15日をもって利用ができなくなるというところでございます。
また、最下段でございますが、タッチ決済、緑色で付しておりますが、この環境が3月上旬から利用が開始できるということになってございます。
この間、機器入替後、3か月ちょっとかかるというところでございますが、この間につきましては、くまモンのICカード、または現金という支払い手段のみというところになりますので、それに対します周知であったり、また、タッチ決済を体験いただく、またはくまモンのICカードをいかにお手元に届けるかというふうな活動も、バス事業者が中心になって行っているところでございますが、行政といたしましても、どのような取組が必要かというワーキンググループみたいなものを週に何回も開催をしておりまして、取組を進めているというところでございます。
真ん中、まず、周知広報の点でございますが、例えばポスター掲示、バス車内のみならず市本庁舎であるとか、サクラマチの建物でのポスターによる周知であったり、また、バス会社も5社ございますので、それぞれのホームページというとなかなか情報が得にくいというのがございますので、特設のホームページをバス事業者の方が開発をいたしまして、市のホームページからもリンクを張るなど一元化したホームページを開設するなどの方法を取ってございます。
また、11月の市政だよりでございますけれども、これは熊本県下全域の市町村の行政広報紙において、11月号でアナウンスをしたというようなところも取り組んでいるところでございます。
また、利用促進策につきましては、タッチ決済、新しい環境に少しでも慣れていただこうという視点から、市電に御協力をいただいておりますけれども、タッチ決済の上限割引というものを12月末まで。また、右側でございますが、「渋滞なくそう!半額パス」ということで、これはくまモンのICカードを媒体といたしまして、オフピーク時間、9時以降の御利用に対して料金が半額になるということで、こちらは直近の情報ではございますけれども、6,000枚以上の売上げといいますか、枚数が発行されたということで非常に好評をいただいておりますが、こういった形で円滑に移行ができるような準備というものを続けているという状況でございます。
報告は以上でございます。
◎徳田隆宏 移動円滑推進課長 資料都-2をお願いいたします。
10月29日に、上熊本駅における交通結節機能強化に向けた第2回の協議会を開催いたしましたので、その内容について御報告いたします。
本協議会につきましては、合志市、菊陽町方面へのさらなる半導体の集積によりまして渋滞の悪化が懸念されることから、自動車交通から公共交通への転換を図ることでこの解決を図るため、上熊本駅において市電と電鉄の対面乗換えなど交通結節機能強化について検討を進めているところでございます。
第2回協議会につきましては、各社から様々な意見をいただきました。
主な意見を御紹介しますと、合志市長からは、渋滞対策として上熊本駅の結節や電鉄の機能強化は必要だが、下段の表の⑩にあるような居住の誘導など電鉄沿線のまちづくりについても併せて取り組むべき。熊本電鉄からは、下段の④電鉄と市電の相互乗り入れを進めてほしい。大西市長からは、現状電鉄と市電の乗換えは1日80人程度、運行本数もピーク時2本と少ない状況、下の表の①にあるような離合駅の設置などにより、電鉄の運行本数の増加や快速列車の運行など利便性を高めまして、利用客数を増加させる取組も必要ではないかと、これらの意見をいただいたところでございます。
このような御意見を踏まえまして、上熊本駅の結節機能強化だけではく、2枚目の絵にございますように、熊本電鉄の機能強化並びに沿線のまちづくりについても取り組むなど、赤の太線で示すような電鉄を軸とした新たな公共交通ネットワークの構築について検討を進めることになりました。
具体的には、熊本都市圏共通の目標であります「車1割削減、公共交通2倍、渋滞半減」に向けまして、最下段の表にあるような施策について検討を進めていきたいと考えております。
まずは、各施策に関する現状や課題、効果等について整理し、各施策の優先順位、取組の時間軸、役割分担等をまとめた基本構想の策定に取り組みたいと考えております。
今年度は、協議会の専門部会において基本構想の内容を検討、令和7年度からは具体的な基本構想に向けて検討を進めていきたいと考えております。
続きまして、資料都-3をお願いいたします。
JR新水前寺駅高架下(高森線上り方面)のバス停の設置について御説明します。
先日、10月17日に第1回の地元説明会を行いましたので御報告いたします。
説明会には9名が参加され、主に側道の通行止めや左折レーンの短縮による周辺交通への影響が心配、実証実験でしっかり確認をしてほしいとの意見をいただいたところでございます。
これらの御意見を踏まえまして、11月から12月にかけて計画を現地におおむね再現する実証実験等を実施したいと考えております。
令和7年1月には、実証実験の結果報告について、第2回地元説明会を開催したいと考えております。
説明は以上でございます。
◎大江田真宏 移動円滑推進課市電延伸室長 資料都-4、市電延伸に伴う都市計画に係る説明会の開催状況についてでございます。
第3回定例会にて、市電延伸関連の予算議決いただきましたことを受けまして、都市計画決定に向けた手続として住民説明会を実施いたしましたので、御報告させていただきます。
資料上段の概要を御覧ください。
説明会は10月5日から計4回開催いたしまして、合計165名の方々に御参加いただきました。内訳を下の表に記載しておりますが、最も影響の大きい東区につきましては健軍文化ホール、そして各区から集まりやすい場所として、市民会館シアーズホーム夢ホールにて各2回ずつ合計4回実施いたしました。
右のグラフに参加された方々の属性を記載しておりますが、まず、住まい別につきましては、やはり東区の方々が約7割ということで一番参加をいただいたところでございます。
また、年代別につきましては、50代の方が24%と最も多いということではございますが、10代から80代まで様々な幅広い年齢層の方々に御参加いただいたところでございます。
中段に、説明会での主な意見について記載をしております。
項目としましては、都市計画に関すること、そして(仮称)東町線の整備に関すること、今後のまちづくりに関することについて御意見をいただいております。
まず、都市計画に関する意見としましては、整備方面、整備ルート、そして一部単線化の経緯のほか、自動車が減るのであれば車線を減らしてもいいのではないかといったような御提案もいただきました。
また、(仮称)東町線の整備に関することとしましては、事業費約141億円の事業費が高いのではないか、その事業費で採算性が合うのかなどといったような御意見、また、市電の利用者数の増加、そして自動車が2,000台減るといったような整備効果の根拠に関する御意見もいただいたところでございます。
また、まちづくりに関することとしましては、市電延伸を契機とした地域の活性化など周辺のまちづくりに関する御意見のほか、交通結節の機能強化に関する御意見について意見をいただいたところでございます。
今回は、都市計画決定に向けた住民説明会ということではございましたが、今後も地域の集まり、商店街等々の集まりもございますので、そういった集まりに積極的に参加しまして、地域の方々と意見交換を行いながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
最後に、下段の今後のスケジュールについてでございます。
都市計画関連につきましては、12月の都市計画審議会、そして1月の都市計画決定の告示に向けて手続を進めてまいります。
また、実施設計関連としまして、今回いただきました補正予算を基に、本年度中に実施設計の契約ができるよう発注手続を準備してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 資料交-1をお願いいたします。
熊本市電の運賃改定について御説明をさせていただきます。
市電の運賃改定につきましては、今年6月25日の第2回定例会で一度御報告をさせていただきまして、その際にアンケート結果等を踏まえまして、また改定額が決まりましたら御報告させていただきますと言っていたものの御報告になります。
まず、1の概要でございますが、2点上げております。
経営状況の悪化ということで、乗車人員については、コロナ禍前まで回復していないという状況でありますし、乗務員等の処遇改善、あるいは物価高騰等により収支が悪化しているという状況でございます。
また、今後の収支見込みにつきましても、現在の180円で換算をしますと、上物法人の単年度収支が初年度から赤字ということになっています。また、ちょっと記載はしておりませんけれども、これは上物法人に限ったことではございませんで、下物事業者との合算、上下合算で見た場合でも、収支というのは非常に厳しい状況でございまして、数百万円から数千万円程度の利益しか出ない。年によってはマイナスになる年もあるということで、上下一体で見ても非常に厳しい状況になるというふうな見込みでございます。
2の運賃改定に関するアンケート結果についてでございますが、今年8月末から9月13日まで実施したアンケート結果を記載しております。
まず、1つ目の「運賃値上げについてどう感じるか」という回答に対しましては、「値上げはやむを得ない」とお答えいただいた方が70%という結果でございました。
2つ目の「運賃を値上げする場合、許容できる運賃額は幾らか」という質問に対しましては、「200円」と答えられた方が61.8%と最も多くなっておりまして、210円以上でも構わないと答えられた方も16.6%という結果でございました。
3点目の「どのような運賃制度が利用しやすいですか」という問いに対しましては、現在市電で採用しております「均一制がいい」と答えられた方が76.8%とその多くを占めたという結果でございました。
これらの結果をもちまして、200円への運賃改定をさせていただきたいと考えております。
次のページをお願いいたします。
運賃改定により得られる効果でございますが、まず、収支面としまして、令和6年度の当初予算ベースに試算をしますと、今回の180円から200円への改定によりまして、年間で約1億6,300万円程度増収になる見込みでございます。これらをそこにちょっと例示させていただいておりますけれども、これまで不十分であった経費等に充当させていただきたいと考えております。
1つ目に上げておりますのが、乗務員等の雇用環境・処遇の改善ということで、現在の会計年度任用職員につきましては、上下分離移行後、すぐに全て正規職員化したいと考えております。また、正規職員に対しましては、新たに扶養手当、住居手当、勤勉手当といった手当を支給していきたいと思っております。
これらによりまして、平均の年収につきましては、約96万円ほど増える見込みとなっております。
2点目に上げさせていただいておりますのが、安全確保に向けた設備投資ということで、まず車両につきましては、令和10年度まで新規車両毎年度2編成ずつ導入していきたいと考えております。レール交換、軌条交換につきましても、交換の計画を見直しまして更新を加速化させていきたいと考えています。電停のバリアフリー化も推進を着実に進めてまいりたいと思っております。
なお、この②に書いてある部分につきましては、直接的には下物事業者が企業会計で負担をしていく部分になりますので、直接運賃が当たるというところではございませんが、上物、下物分かれた場合は、下物事業者に上物事業者から施設の使用料が入る形にあります。その施設の使用料は、運賃収入を基に払われることになりますので、今回大事な部分でございますので、例示として上げさせていただいているものでございます。
その下(2)のスムーズな乗降、分かり易さのところでございますけれども、200円ということになりますので、硬貨を準備をしやすくなりますし、両替が減少とすると見込んでおりますので、スムーズな降車につながるものと考えています。
また、県外等から来られる初めて乗車される方々にとっても、非常に分かりやすい運賃体系になるものと考えております。
次のページをお願いいたします。
最後に、スケジュールでございますが、今回の特別委員会、それから12月の都市整備委員会で御報告をさせていただいた後、来年3月に条例改正の議案を出させていただきまして、議決いただきましたならば、国への申請、認可、それから周知広報を得まして、できましたら来年6月にこの運賃の改定をさせていただければということで考えております。
説明は以上でございます。
○田中敦朗 委員長 以上で説明は終わりました。
それでは、ただいまの説明に関して質疑及び御意見等をお願いいたします。
◆上野美恵子 委員 たくさん報告がありましたけれども、今ほどおっしゃいました資料交-1の熊本市電の運賃改定について大変重要なことだと思いますのでお尋ねをさせていただきます。
1つは、さっき説明で経営状況の悪化ということと、今後の収支見通しの健全化を図っていくというような趣旨がるる述べられたかと思います。これについて厳しいかもしれないけれども、さっき溝上先生のお話の中で、要するに上下分離をするに当たっての経営計画、これがまだまだ不十分ではないかという御指摘があったんですね。やはりさっきの説明だと、財政面からの交通局、交通事業としての収支、財政という視点から、今回20円上げるというふうな提案がなされているというふうに私たちは理解をするんですよね。
ですけれども、さっきの溝上先生のお話をずっと聞いていまして、先生がこの計画そのものがもうちょっと何か中身が不十分ではないかとおっしゃったのは、交通事業というのがやはり今後の公共交通の中で果たしていく役割等々を考えたときに、利用者の立場に立って利用促進につながっていくものなのか、それと合わせて経営的にも安定したものになっていくというふうに、多面的に効果のある事業の方向が見えてくる提案であってほしいなというふうに思ったんですよね。
でも、何か経営、経営という、そういうふうな説明であったかと思うので、ちょっと何かそれが納得いかなかったのと、それからこれまで交通事業に多分今年度までは来ていたと思いますけれども、基準外の運行支援金というのが1億数千万円来ていたかと思います。
この資料によりますと、今度の改定によって1億6,300万円程度の増収になるということで、何か支援金がさっき報告では減るんではないかというお話がありましたが、その分に相当する額が上がるわけですから、だったらもう少し交通局と一般会計、本庁の方とよく話をして、交通事業の今後の在り方の中でどうあるべきかという点についての検討等が必要ではなかったのかなと思ったんですけれども、その点についての御説明お願いしていいでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 まず1点目の御質問なんですけれども、経営面ばかりが目立ってというところであったかと思いますけれども、ちょっとお答えにはなかったんですけれども、まず、これまでも一応交通局の方では、利便性向上策として様々取り組んできたと考えております。昨年度から実施しておりますタッチ決済、QRコード決済、そういったものの導入もそうでございますし、コロナ禍でいろいろとイベント列車的な乗客誘致を図るようなイベントというのを全部休止していましたけれども、そういったものも全て復活させていきまして、乗客誘致に向けた取組というのも一応交通局としては着実に行ってきているというふうに考えております。
それと2点目の基準外補助運行支援金についてでございますが、コロナ禍に影響を受けた部分、それから近年は物価上昇等に対する支援としまして、令和2年度から一般会計への基準外繰り出しといった形で受けておりまして、今年度も基準外繰出金額としては、1億4,200万円ほど受けるということになっております。
来年度以降につきましては、予算編成等もまだ確定をしておりませんので、その中で来年度以降の収支状況を見ながら財政当局の方とお話をさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 利便性向上とか考えているというふうにおっしゃって、それは当然ですよね。それもないと何か公共交通としての役割上、それはちょっと問題かと思うんですけれども、実際値上げになった分について「増収分をこれまで投資が不充分であった下記の経費に充てる」というふうにさっき詳しく説明していただいた①の乗務員等の雇用環境・処遇の改善、そしてまた直接的では、上下分離になった場合は直接ならないけれども、安全確保に向けた整備の投資ということで、これ下物になる部分だと思うんですけれども、中身を見ると、これというのは何かもうちょっと基本的に交通事業を拡充させていく中でやるべき部分であって、運賃の値上げでやることかなと。
そこのところがやはり溝上先生もおっしゃった、今市電とか、そういう軌道だけではなくて、バスも含めて公共交通という分野が大変苦戦をしている中で、今までは補助を出していたけれども、もっともっと抜本的に投資的な形ででもいいから支えていくということがないと、本当の意味での公共交通の抜本的な利用の促進とか、拡充にはなっていかないんではないかという御指摘があったかと思ったんですけれども。
それからするなら、補助金でも不十分だというふうに専門家が指摘をしているときに、補助金は削って、そして利用者の負担を増やして、そして当然何かもうちょっと公共交通を公が支えるというのであれば、公がもっと支えるべきであろうその基本的な部分ですね、これは今やることではなくて、ずっと必要だったことですよね。後から出るインシデントが多発をしているとかということにもつながるような職員さんたちの問題とかもありますけれども、そういうことのために値上げをするというのは、やはりどうかなと思うんですよね。
さっき私、先生が均一ではなくて段階的な料金にと言ったときに、増えるのかなと思ったから増えるんですかと聞いたら、いや、それはあくまでも段階を設けても、料金そのものはやはり抑えていくというふうなことを助言としておっしゃいましたけれども、今そういう発想で市電にしても、何にしても、公共交通の利用促進を図っていかなければならないときに、利用者の負担を増やすという発想というのは、やはりちょっと逆行ではないかなと思うんですよね。
そしてさっき上げた後に来年度上下分離して、その収支を見た上で財政局と話をしていくとおっしゃいましたよね。でも、それというのは後先が逆ではないんですか。今するべきではないんですか。公共交通の利用促進に逆行するから、今この補助金継続が必要なんですということは、今財政当局に折衝すべきことであって、値上げの前にすることだと私思ったんですよね、井芹事業管理者。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの御質問ですけれども、まず、先ほどもありましたように、この今回高度化計画ということでここ数年ずっと検討を重ねてきており、また、適宜議会の方にも御説明をしてきたかというふうに思ってございますけれども、その高度化計画の中では、当然お金だけの話ではなくて、そもそも高度化計画というのはお金だけの話ではありませんで、その趣旨といいますのは、その定時制の確保だったり、速達性とか、快適性とか、安全性とか、そういった利用促進につながることというのが計画の大前提であって、交通局の方としても先ほども課長の方から内容等については若干触れておりましたけれども、当然多両編成車両の導入であるとか、軌道の施設の整備であるとか、バリアフリーであるとかといったことも合わせてやるということで整理をしてきたところでございます。
ただ、その際に、今までできていなかったところが、乗務員関係につきまして御承知のとおり、非正規の職員が乗務員の大半を占めているというところ、これはどうにかしないといけないというところで、運賃値上げと併せて上下分離をすることによってきちんと処遇を改善していくということに今検討しているというところでございまして、先ほど溝上先生からもありましたが、全体的なバス、均一料金は市電だけでいかがなものかというようなお話もありましたけれども、その全体的な議論というものは当然必要だと思っておりますので、そこについてはまた適宜全体の話として進めさせていただきたいと思いますけれども、あくまでも今回は上下分離ということに関しての運賃改定ということで御理解いただければというふうに思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 上下分離は、私はこれまで執行部の方の説明をずっと聞いてくる中で、いい面をすごく協調して言ってこられたんですよね。でも上下分離のためと、今、事業管理者がおっしゃったけれども、だったら利用者負担を上げるために上下分離するようなふうになってしまいやしませんか。だって、上下分離をするに先立ってですよ、今この時点で値上げをするという、しかも一般会計からの補助金は一旦引き上げるかもしれないと。
だったら、要するに利便性だ、何だということをおっしゃるけれども、でも、それというのは公共交通の利用促進を図っていく、もっと街を元気にしていく、そのために公共交通が元気に役割を果たしていくということの中での市電であるわけだから、やはりさっきおっしゃったように、補助ということよりは、むしろもっと公共交通を全面に出して応援するための投資こそ必要だという時期に、補助金は引き上げて、そして利用者負担は高くして。でも、これまで私思うに、いろいろな事業者の協力もあって市電の無料の日であるとか、100円均一運賃とか、いろいろな利用促進日というのが設けられましたよね。それというのは、すごく利用に効果があったと思うんですよ。たくさん利用がありましたという報告を受けたので。
ということは、やはりいろいろな要因があるけれども、利用者側からすれば、それは安全運行とか環境整備は本当に当たり前のこと、基本的なこと、何があろうとそれはもともとあって当然のもの、それは利便性ではなくて基本ですよね。そしてやはり利用者からいうならば、安価で利用できる、そしてできれば早く目的地に利便性よく着いてくれるというふうな、そう考えたときには、やはりその安く乗れるときにたくさんの利用があるということは、料金的なものを安くしていけば、要するに利用者が増えるということですよね。
ここの地域公共交通に関する特別委員会というのは、それは市電に限らずバスも含めて、公共交通を利用促進するために私たちは集まって議論しているんですよ。それなのに値上げをするというのは、今この時期にすることかと思ったんですよ。だって逆行でしょう、ただならたくさん乗る、安いときもたくさん乗る、それなのに、いや、収支があれですから値上げしますというのは、やはり間違っていると思いますよ。
大体財政局としてここに今おられますけれども、公共交通の利用促進についてどのようにお考えなんですか、今上下分離して値上げを提案しているときに、補助金を引き上げるかもしれないというその発想というのは、逆行していると思うんですけれども、どのようにお考えなんですか。
◎原口誠二 財政局長 繰出金につきましては、これまでも交通局の経営計画等々を見習って、委員御承知のとおり、基準内の繰り出しでありますとか、基準外の繰り出しを行ってきたところでございます。
今回につきましては、上下分離に移行するという中で、なかなか今後の見通しが見通せない状況の中での局の予算の見通しだというふうに聞き及びますので、繰り出しについて今のところ引き上げるとかどうとか、そのところを全部決定したところではございません。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 では、1点聞いておきますけれども、さっき溝上先生の方から、やはり公共交通を今後発展させていくためには、補助を出しているというふうな、そういう小さいなものではなくて、部分的にしてあげているということではなくて、やはりその事業の発展のために、公共交通に対する投資的なものとしてもっと基本的に、抜本的に支えていく、公が支えるという、そういうことも必要ではないかという御指摘があったと思ったんですけれども、その考え方についてはどのように受け止めておられますか。
◎原口誠二 財政局長 一般会計からの繰り出しでございますので、これは中央公営企業の繰出金の考え方、またもう一方では、本市の基幹交通軸を担う重要な交通機関であること、また、市電が持ちます定時性、速達性、輸送力の高い交通手段としての考え方、そして市のシンボルとしての交通の市電の在り方、歴史等を考慮して、総トータルで、市政の中で繰り出しの考え方は御議論をいただいて決定していくものと考えております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 私は補助金の繰り出し方を聞いたんではなくて、公共交通に対する公の支え方についての基本的な考えを聞いたつもりだったんですけれども、何かちょっと補助金をどう出すかの質問ではなかったんです。公共交通を公の財政がどう支えていくのかという、その考え方を聞いたんです。補助金ではなくて。
○田中敦朗 委員長 投資的な観点を持つのか持たないのかということですか。
◆上野美恵子 委員 そうそう、溝上先生がこれからの公共交通の発展のためには、今までは補助金だったけれども、もっと投資的な視点での支えが必要ではないでしょうかと提起をされたから、その点についての考え方はどうなんですかと聞いたんです。
◎原口誠二 財政局長 これは先ほどの陳述人の御意見の中での委員の御質問と思いますので、それぞれの委員の方々のお考えの議論を聞いた中での考え方をまとめるところだと考えております。
◆上野美恵子 委員 ちょっと分かりませんでした。
○田中敦朗 委員長 財政局として、公共交通に関して投資的な側面に関して今後検討するのかしないのかというふうな質問ですよね。
◆上野美恵子 委員 考え方だよね、そうそう。今のおっしゃった考えが。
○田中敦朗 委員長 その考え方があるのかないのか。
◆上野美恵子 委員 今のは、何か答弁と違うと思います。
○田中敦朗 委員長 ですので、そういった考えがあるのかないのかというのを公共交通の……
◆上野美恵子 委員 溝上先生のその指摘を局長はどう受け止めたのと聞いているんです。
◎原口誠二 財政局長 先生の御意見としては、今後の将来的な公共交通の維持、促進、市電の考え方での御意見だったと思います。現時点で今後の投資的に考え方を持って繰り出しをどうするのかということでは、現時点では上下分離を今後導入するに当たって、本日この時点で投資的経費において重点的に投入していきますというお答えは差し控えたいと思います。
以上です。
◆上野美恵子 委員 ちょっと答えではなかったんですけれども、やはり財政局というところは予算を査定していくところです。熊本市にはいろいろな大事な事業がたくさんあるので、取捨選択しながら何が一番必要かなということを考えていく。
でも、私は今日溝上先生のお話を聞いて、熊本市が公共交通の分野においては、かなり一生懸命取り組んで実績も上げて、国も動かしてそしてやっているということをお話されたなというふうに受け止めたんですよね。もちろん先生独自のお考えですからそれを受け止めるのは私も違う、あなたと私も違う、一人一人受け止め方違うと思います。だけれども、財政をつかさどる財政局長はどう受け止められたのかなと私は思ったから、お尋ねしたんですよね。
やはりいろいろな学者の先生のお考えはあろうかと思いますけれども、さっき厳しい面で交通局に対して計画についての熟度が足りない的な御指摘もあったんですけれども、やはり目先の経営だけではなくて、本当に公共交通を支える一つの大きな事業として市電の役割を果たしていく、その面に立って利用者の方に気軽にたくさん利用してもらって、そのことによって少しでも収益が、経営がよくなっていく、そういう好循環がある市電事業にしていくためには、補助金は分からないと局長言っているのでできれば出していただきたいですけれども、不透明な中でもらえるかもしれんし、もらえんかもしれんけれども、上げる順番がちょっと違うんではないかなというふうに私は思います。
だったら、上下分離をするに当たって上げるんだったら、上下分離なんかせんければよかったたいねと、結局は上物が民間になるということで、より今まで以上に独立採算制を市としては求めていくんだなというふうに見えますもの。だけれども、溝上先生はそれはバスであろうが、市電であろうが、公共交通なんだから、市民の足を支えるということで、もっともっと公が支えていくべきではないでしょうかと私は今日問題提起をしていただいたと思うんですよね。
そういう中で、今回20円とはいえ、そしてさっき今からタッチ決済とか、いろいろなそんなものが増えてくるんだから、端数がついていようがいまいが、別に200円ちゃりんちゃりんと入れる人ばかりではない。むしろクレジットとかタッチ決済とかでやる人の方が多いんだから、だったら端数がついているなんてこと全然マイナスないわけだから、そこに上げるということよりも、むしろ将来を見据えてどうしたらバスと一体化をして、バスも市電も含めてもっと利用者の皆さんが利用しやすいような料金体形になっていくのかということを長期的なスパンで考えながら、そうでもって今、ではどうしようかというふうに、そういうふうな視点で提案をしていただけたらいいなと思うけれども。
何か目先の経営がどうでは、こうでは、これでいけばペイできますとか、使い道は正規職員がどうですかと、そんなこと前々からの話でしょう、今頃になってすることでもないわけだから、ちょっとこの20円の1億6,300万円というこの値上げというのは、本当に公共交通の利用促進、公共交通の発展を考えてやっているのかについて、私はとても疑問です。とても賛成できません。
何回聞いても、財政局の答えも何かあまりぱっとしないし、井芹交通事業管理者もさっきの答えではちょっと私も納得できませんけれども、何か展望が見えないんですよ。と思いますよ。だから、そのことを溝上先生もおっしゃったんではないんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 まず、公共交通の利用促進という観点では、これは非常に重要なことだと思います。市電だけではなくてバスも含めて公共交通に乗っていただくという施策については、これは非常に大事な視点であります。
そこで、ワンコインとか、均一運賃とか、代キロという話もありましたが、私はやはり分かりやすいまず運賃と連携した、ほかの公共交通機関と連携できる運賃というのが大事だというふうに思っています。そこについては今、バス会社とも一緒に話していますが、上野委員、ちょっと後先がというお話もありましたけれども、要は溝上先生の話の中でも一気通貫な料金とかという説明もありましたが、やはりそういう利便性の高い料金と分かりやすい料金だろうというふうに思っています。
上野委員の方からは、先ほど100円ウィークの話もされましたけれども、やはりそういう意味で料金施策というのは非常に重要だというふうには思っております。それはきちんとバス会社とも含めて、都市建設局とも含めて、そこについてはきちんと話をしていきたいですし、検討していこうとしていっているところでございますが、改めて、とはいえ今現在置かれている交通局の立場といたしましては、利便性、先ほど説明しましたけれども、快適性とか、定時性とか、速達性とかという、その本来市電が持っている今の機能をより高めていくには、やはり職場環境も含めて、乗務員の環境も含めた対応が必要だろうというふうに、対策が急務だというふうに思っています。
本当に最近安全への面で皆様に御迷惑、御心配をおかけして本当に申し訳なく思っておりますけれども、そういうのを解決するのもやはりまずはそこだろうというふうに思っています。一つの企業として、バス会社もそれぞれバス会社一つの企業でございますので、そこで企業努力をしております。
うちは今現在、交通局は熊本市の組織ではありますけれども、だからといって全て税金で、この段階で全て税金でというのは、やはりちょっと違うのかなと。そこについては、やはりそれぞれの事業者の事業の採算性というものについては、あくなき追及をしていくべきだというふうに思っておりますので、それが200円で向こう30年間黒字が確保できるという今試算が立っておりますので、やはりそこについては、まずは大変申し訳ございませんが、御理解をいただいて、その上で料金施策と乗りやすい決済手段等については、一緒にやっていきたいというふうに思っているところです。
すみません、ちょっと説明足らないところもあるかと思いますけれども、まずはそういった点を御理解いただきたいというふうに思ってございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 全てを税金でという言葉使われたからすごく違和感があったんですけれども、私は何も全てを税金でと言っているわけではなくて、利用者が利用できる、もっと公共交通に乗り換えようという気分になるような、値上げはそれに逆行するんではないかという指摘をしたんであって、そして今回で言うなら、やはり1億何千万円かの財政の基準外の支援金、それを上下分離になっても、この御時世だから応援していただくというふうにすることの方が、熊本市という自治体が公共交通に対して本当に利用者のために頑張っているよねというふうに、そういう姿が見えるんではないかというふうに思ったから聞いたんですよね。
やはりちょっといろいろ言われても、今この時期にバスのことをいうんだったら、本当にバスがもっと利用しやすくなるようなそういう料金についての検討と合わせて、電車とどうするのかということなんかを含めて、それを話し合ったときに、では、電車運賃はということをおっしゃった方がいいし、今上下分離の直前に値上げということが、やはりすごくまずいというふうに私は思っているんですよ。
だから、何かすごく一面的に上下に分かれるから、経営が優先しているんではないかなというふうに見えてしまう。それでは、やはりさっきの先生の指摘みたいに、目に余る交通局の非協調というふうに指摘をされたら残念ではないですか。そうならないように頑張っていただきたいという、私からの最大限のエールです。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆古川智子 委員 私からも、200円への運賃改定についてです。
御説明をいただいて、今日も溝上先生のお話を聞いて、最初説明があったときは、この交通局上下分離ということで、今度上物の戦略、乗りやすさ、料金体系、分かりやすさ、そういったところで市電に乗っていただくことを一番に考えて、そこを訴えられていくのかなというふうに思いました。
今日の意見陳述人の話も聞いていく中で、全体的な公共交通の在り方として、公共交通とまたそれに合わせて道路というところも考えていかなきゃいけない。そして公共交通の中でも電車、それからバス、その分配率も考えていかなきゃいけないとなると、バスとやはり電車の料金の差額が本当にそれでいいのかということも、ちょっと考えなければいけないなというふうに正直なところ私が思って受け止めたところです。
電車さえよければということであれば、もちろん200円でいいのかもしれません。ただ、全体的なバスも生き残りをかけていかなければいけない。持続可能性を全体で見ていかなければいけないとなると、本当に今後まちづくり、地域核、そういったところも含めて、どこがバスのそれぞれが核となっていくかにもよっても、考えなければいけないことは大きくなっていくとは思うんですけれども。バスの生き残り、それから電車の生き残り、そしてまたは公共交通以外の道路との共存といったところを考えていくと、ちょっと長期的な目線で考えていく。また、タイミングが今後出てくるかもしれないなというふうに思っているところです。
これに関しては、今すぐ回答を求めるものではなく、私はもう求めません。今日は特別委員会、それから今度は常任委員会でも話合いがなされる中で、ちょっとそういったところを執行部の中でも、もう一度本当にこの前進の仕方でいいのかといったところをちょっともんでほしいなというところで、私、今回要望とさせていただきます。
以上です。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆上野美恵子 委員 最初説明していただきました公共交通に関する住民アンケート、今度お取りになるということで説明がありまして、WEBアンケートが主ですけれども、それだけでは不十分だという御認識のようで、地域での対面聞き取りによる調査も想定するという説明がありました。
私も本当にWEBアンケートだけだったら、なかなかそこに答えが出せないという方がおられるので、聞き取り等々の別のやり方を併せてなさるということについてはいいことだと思いますが、そのやり方というのが十分効果のあるやり方にしていかないといけないんではないかなと思うんですよ。どんなふうなやり方でWEBアンケートではない部分についてはやっていこうと思っているのか、少し詳細を教えてください。
◎大川望 交通企画課長 委員おっしゃるとおりでして、どうやって取っていくかの分については、様々多分やり方はいろいろあるとは思っておりまして、今考えているのは、例えば11月30日に公共交通利用促進キャンペーンというものが、これは毎年、年に1回、交通事業者さんを中心としてやるイベントのようなものがございます。そういったときに、御来場の方々に対してしっかりと対面でヒアリングをしていったりとか、どこかの場所とかでチラシを配るような形ではないんでしょうけれども、そういった機会を捉えて直接的にお話を聞いたりであるとか、紙媒体だけを送り付けてというふうなやり方もあるんでしょうけれども、それではなかなか上手にいかないというところもあると思いますので、いろいろな方法をちょっと織り交ぜながら、御意見をいただけたらなというふうには考えているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 やはりアンケートというのが、いろいろな方たちが多様な意見がきちんと集まるということがすごく大事だと思うんですよね。そういう意味では、公平に意見を述べられる場がどんなふうに提供されるかということがすごく大事だと思うので、ウェブの難点というのは、ウェブをしない人たちがアクセスできないというのが難点なので、それの補完するものが直接であったり、何だろうということになるんですよね。
なので、ちょっと今おっしゃった部分ではなくて、もう少し、もう一工夫が必要ではないかなと私は思います。少なくともこうすれば、この点について回答できますよという、意見を述べたい人はもっと自由に述べてください。でも、ウェブができない人も回答ができるようなものを工夫した方がいいなというふうに思いました。
もう一つは、アンケートをするに当たって、3番にアンケートに盛り込む視点の、まず丸ポチの1に書いてあるんですけれども、「公共交通の現状を認識いただいた上で回答をできる」というのがありました。これもとても大事な点だと思ったんですけれども、要するによく分からないのに解答するというのは、書く方も難しいし、答える方も難しいと思うので、一定現状についての何か情報提供しないといけないと思うので、資料とかを一緒に、アンケートと一緒につけて公表するのか、違った形で何か情報提供するのか、そこのところを教えてください。
◎大川望 交通企画課長 手法につきましては、資料のようなものでできるだけ分かりやすくというふうに思っております。資料のようなもので、いわゆる前語りといいますか、今現状こうなんですよというようなものを少し御理解いただくようなものを先に、設問より前に設定をいたしまして、そこから、では、お尋ねしますというような形で流していきたいと。
ですので、例えばウェブ上であれば、問いの前に図示したりであるとか、文言で補足をするような形で、できるだけ分かりやすくというふうな形で考えているところです。
以上です。
◆上野美恵子 委員 ありがとうございます。
こういうアンケートがあるということは、市政だよりには載るんですよね。市政だよりには。
◎大川望 交通企画課長 そうですね、広く周知するために、すみません、市政だよりは、今私の中ではまだまだちょっとそこまで思い立っていなかったところもございますので、しっかりと周知をするために市政だよりも活用していきたいと思います。ありがとうございます。
◆上野美恵子 委員 公共交通の住民アンケートすごく大事だと思うんですよ。とても大事だと思うんですよね。だからこそ、市政だよりは基本なのでぜひ、ホームページはもちろん載せられるでしょうから、市政だよりの方にも載せていただきたいなと思います。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
◆齊藤博 委員 ICリプレイスについてちょっと確認でお尋ねをいたしますが、くまモンのICカードと現金しか使えない、いわゆる全国交通系ICカードがもう11月16日以降から使えないということでありますので、現金で払う方、それからくまモンのICカードで決済していただく方ということになるんだろうと思います。
確認なんですが、くまモンのICカードを例えばバスの中で買おうとする場合には、従前も可能だったかと思いますが、引き続き買っていただけることができるのかどうか、ちょっと確認でお尋ねいたします。
◎大川望 交通企画課長 従前どおり、バスの車内でもくまモンのICカードは買うことができます。
以上です。
◆齊藤博 委員 金額は幾らになりますか。
◎大川望 交通企画課長 販売額は2,000円のお支払いをいただきまして、デポジットが500円ございますので、1,500円分のご利用額という形での発行になります。
以上です。
◆齊藤博 委員 需要が一定増えるだろうと思いますので、不足が出なかったりとか、スムーズに購入いただけるような体制をバス会社さんにはぜひ整えていただくように、行政の方からも遺漏なくお伝えをいただきたいと思います。
それと併せて、もう11月の中旬以降から、要は現金とくまモンのICカードしか使えませんというようなことになります。恐らくちょっと簡単に想定できるのが、現金もちょうど持たない、あるいはもちろんくまモンのICカードなんて持っていない、クレジットカードしかないとか、あるいは10カードしかないというような、例えば出張者の方であるとか、そういう意味では、今現金持っていない方結構いらっしゃいますので、そういう方にどのような形で対応するのか。今日はいいですよなんていうことは基本的にはできないと思います。
ですから、例えばバスの運転手さんごとで対応が違ったとかいうようなことは、これは困難を招く一因ともなりかねないと。いろいろな想定を、バス事業者さんが考えることなのかもしれませんが、やはり行政サービスとしての公共交通機関ということで、そういった対応にしっかりお答えできるような体制を各バス会社さんにもぜひ行政の方からも問合せをいただければと思いますが。そこはいかがでございますでしょうか。
◎大川望 交通企画課長 確かに委員おっしゃるとおり、不測の事態といいますか、払えないという状況に陥るというのは、当然あり得ると、十分にあり得るというふうに考えてございます。
当然、我々市としてもバス事業者さんに対してはそのような対応についても想定をして、また、なった場合にはしっかりと御利用者さんに対して接遇をというか、対応をお願いするというところは、重ねて申し上げるというところはやっていきたいというふうに考えてございます。ちなみになんですけれども、今現状においてのバス事業者におかれては、当然ちょっと財布を忘れてしまったとかというような方も、現状においても当然いらっしゃいます。
そういったときには、まず運転手さんに対してお客様の方から今日ちょっと支払えないんですという旨を申し出ていただくと、運転手さんは一つ紙券みたいなものを配りまして、後払い券という呼び方をするようなんですが、そこにお名前であったり、連絡先であったり、または金額ですね、これを御記載いただいて、お客さんとその運転士が複写式なんでしょうか、物理的に両方とも同じ情報を持っておくと。次に乗るときに、御利用者さんの方から、前回こういうふうな形で後払いになりましたのでという形で合算してお支払いいただくと、そういった対応をもう既に取っていただいているところもございます。ただ、先ほど申し上げたとおり、併せて交通事業者の方にはまた申し伝えをしておこうと思っております。ありがとうございます。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 分かりやすい御回答ありがとうございました。
混乱を招かないように、そして何か不測の事態が起こったときに、重複しますけれども、サービスの在り方がまちまちにならないように、ぜひバス事業者さんと共有をしていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
○田中敦朗 委員長 13時を目途にと思っておりますので、質疑は円滑に回せるようにお願いいたします。
◆井本正広 委員 すみません、決算手段の件でちょっと1点お聞きしたいんですが、バスの方はタッチ決済について3月から導入されて、これは多分距離によって金額が違うから、乗るときと降りるときとタッチされると思います。
先ほど溝上先生の方から御指摘もありましたけれども、市電の方は今タッチ決済、降りるとき1回ですよね、これはやはり乗降、どこからどこまで乗ったという情報を取るためにも、最初と最後というような形にした方がいいんではないかなとは思うんですけれども、そのためには機器を追加しないといけないのかもしれないんですが、その辺についてはどんな状況なんでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 委員がおっしゃられましたとおり、仮に乗り降りで取る場合は、今の乗るところに機器がございませんので、そういった経費負担が新たに発生するというところがございます。
溝上教授からもありましたけれども、ODデータですね、これにつきましては、現在、交通局で全国交通系ICカード、こちらが約半数利用されていますけれども、こちらの方で取っておりますので、このデータを持って十分だというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆井本正広 委員 ただ、交通系ICカードの場合は、今も同一金額でも2回タッチされますよね。要はそれだけでいいというんであればそれでいいんですけれども、将来的にタッチ決済の方に移行していくような状況ではないかなというふうに思いますので、この辺については、一度金額との検討とかした方がいいんではないなと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○田中敦朗 委員長 答弁要らないですか。
◆井本正広 委員 はい。
○田中敦朗 委員長 では、検討して井本委員に報告お願いします。
そのほか質疑ありませんか。
◆上野美恵子 委員 上熊本駅における交通結節機能強化について、専門部会についての検討の報告がありましたが、さっきの説明だと、なかなか熊本電鉄の運行本数が少ないこととか、実際の乗り継ぎとかも少ないので、結節の強化といった場合に、現状ではちょっと難しい課題がたくさんあるのかなというふうに私は認識をしています。
この問題で専門部会で検討が進められていくので、何というのかな、市民というか、住民の意見とか、利用者の声とか、そういうのは専門部会にどのような形で集められていくのか、反映されていくのかということと、大事なことなので何か機会を見て市民の方々については、こういう問題についての情報提供というのをする場面があってもいいのかなと思ったんですけれども、それについての何かお考えがあれば教えてください。
◎徳田隆宏 移動円滑推進課長 現在、この上熊本の交通結節機能強化につきましては、合志市、本市交通局、熊本電鉄と、あとそこに県を加えて専門部会で検討を行っているところでございます。市民の声につきましては、こういった専門部会での検討内容につきまして、本市の交通の協議会であるとか、様々な機会を捉えて意見を伺っていきたいなというふうに考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 十分になさっていただくようにお願いしておきます。
それから、4番目の市電の延伸についての説明会の開催についての御報告がありましたけれども、これで終わりということではないと思うんですけれども、結構ずっと議論もあったし、私たちは報告を聞いてきているので、情報も持っている側としては分かるんですけれども、一般の市民の方たちからすれば、なかなかまだ中身についてよく伝わっていないという方々も多いのではないかなというふうな、そういう御意見をお持ちの方に何人かお会いしました。
だから、まだまだ伝わっていないんだな、説明会の後に会ったんですけれども、だから、行った人は分かったかもしれない、意見も言ったかもしれないけれども、だから、この問題は継続的にいろいろな機会を活用して情報提供とか、いろいろ意見聞いたり、説明したりする場面というのが必要かなというふうに思ったんですけれども、今後のことについて何かお考えがあれば教えてください。
◎大江田真宏 移動円滑推進課市電延伸室長 今委員が言われたとおり、説明会の中でもこれまで議会で御議論いただきました整備形態ですとか、ルートですとか、その事業の効果に関する意見というのが、結構住民説明会の中でも多うございました。
そういったことから、私どもとしましても、改めて計画内容、検討経緯も含めて住民の方々へ丁寧な説明、情報発信というのが必要だなというふうに感じたところでございます。
今後は、地域の例えば校区の集まりですとか、商店街の集まり等に積極的に参加していく中で、意見交換しながら事業を進めていきたいと、そして情報発信していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 やはり事業費的にもかなりかかっていくものでもありますし、市民の理解というのが何よりかなというふうに思ったので、疑問持っているけれども、説明会に行くという人は本当に多くないんですよね。思っているけれども行かない人が大半だと思うので、そういう方たちに御納得いただくような手立てというのが必要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 次に、報告2件の説明を求めます。
◎荒木敏雄 運行管理副課長 資料交-2をお願いいたします。
銀座通り歩道橋交差点における信号冒進(インシデント)についてでございます。
発生日は、令和6年10月2日でございます。
経緯といたしましては、左下のところにあります市役所前電停から花畑町電停の方に向かって進行した電車が、交差点に進入する際、右上の方の写真になりますけれども、電車信号が進行可能な黄色矢印、白抜きのところになります。黄色矢印の信号が出ていない状態、上側の方になりまして、その状態で進行したものです。運転士の方は、右折車に気を取られてそのまま進行したと申しております。
右側の方で、2の発生原因でございます。
運転士が電車信号の確認を怠ったもの。
3番、再発防止策についてです。
全運転士に対しまして、本事案を周知しました。また、当該事案運転士に関しましては、1週間電車を下ろして再教育を行いました。また、全運転士に対しまして、「信号よし」などの確認呼称の徹底を指示しております。
また、毎朝出勤したときの点呼時の際には、進行信号と停止信号の信号写真をランダムに掲げて、反射的に確認呼称をすることで故障の意識づけというのを実施しております。
最後に、全運転士のドライブレコーダーを確認いたしまして、指導後の確認というのも行っております。
資料交-2に関しては以上です。
続きまして、資料交-3をお願いいたします。
保安監査結果に対する改善報告についてでございます。
度重なるインシデント等を受けまして、7月と8月に実施されました九州運輸局からの緊急保安監査での改善指示が9月20日に出されまして、1か月後の10月21日に改善報告書(中間報告)という形で提出いたしました。
内容といたしましては、安全管理体制の再構築及び4つの改善指示事項についての改善措置の状況というものを報告したものです。
1番の方が、こちらが九州運輸局の中で一番重点的な項目と考えられている項目でして、安全管理体制の再構築ということになります。指示内容といたしましては、現在の安全管理体制を検証いたしまして、安全統括管理者(以下「安統管」)といいますけれども、そちらを中心とした安全管理体制の再構築というものを指示されたものです。
問題点といたしまして、現在の安統管が営業所長との兼務でありまして、全体を統括する上で職位が不十分などとなっております。
改善措置に関しましては、次のページを御覧ください。
上の方の①番、安全統括管理者を専任とするとともに、位置づけを強化いたします。こちらの方は11月1日、明日からを考えております。
②番、安全対策に係る推進セクションを新設、こちらの方は年明けの1月からを予定しております。
現行の体制といたしましては、左側の方になっております。現在、中心に安統管とありますけれども、安統管は営業所長が兼任しておりますが、組織的には運行管理課長の下の主幹級の職員になりまして、しかも運転関係しか把握できていない状況にございます。安統管には、運転のみならず、施設、車両を統括することが求められますので、職位が不十分であると指摘されたものです。
見直し後が、右側の方になります。真ん中よりちょっと上のところに、専任の安統管を設置いたします。部長級の任期付職員で市のOBを考えております。
下の方には管理班といって、運転管理する部門がありますけれども、そちらの方に安全対策係というのを設置いたします。
一番下のところに安全対策係の事業内容といたしまして、運転管理者を補佐し、運転士の育成、指導・教育、資質管理などのほか、運転施設、車両各部門の情報共有と連携を計画実施する役割を担うものとしております。
戻っていただきまして、資料交-3の4つの指示事項でございます。
①番、運転知識・技能の保有状況の管理ということで、指示内容といたしまして、必要な教育、技能が確認できていなかった運転士が乗務していたことを受けまして、適切な教育の実施、技能の管理というものを指示されております。
問題点といたしまして、運転管理者等の制度への認識・知識不足、引継ぎが不十分、関連規定が不明確などが考えられます。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、対象運転士に教育いたしまして、知識・技能の確認を実施するなどとしております。
恒久対策といたしまして、関連規定の改正、改正後の規定の教育を実施するなどとしております。
②番、視力要件等適性の管理についてでございます。
指示内容といたしまして、視力要件を満たさない運転士が1週間程度要件を充足しない状態で乗務していたことを受けて、適正な管理を指示されたものでございます。
問題点といたしまして、運転管理者等の制度への認識、知識不足などと考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置としまして、対象運転士の視力要件を確認いたしました。また。改めて全運転士への視力要件の周知を行いました。
恒久対策といたしまして、①番と同じく規定の改正、改正後の規定の教育を実施などとしております。
③番、点呼の不備についてでございます。
指示内容といたしまして、不適切な点呼簿への記録、点呼完了前に点呼完了と記載したり、また、チェック漏れの状態で確認印が押してあったりなどといったことを受けまして、適切な点呼実施を指示されたものでございます。
問題点といたしまして、点呼執行者などの点呼の目的、実施方法などに関する理解、認識不足と考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、点呼執行者や乗務員への教育を行います。
また、恒久対策といたしまして、①、②と同じく内規の策定、点呼結果のダブルチェック、複数人点呼、今出勤した運転士を複数にまとめて点呼しておりますけれども、それを一人一人の個人点呼に変更するなどと考えております。
④番、軌道整備上の不備についてでございます。
指示内容といたしまして、レールの数値に一部基準値の超過というのが見られましたけれども、こちらは1年以上整備が未実施であったことから、必要な整備等の見直しを指示されたものでございます。
問題点といたしまして、超過箇所での整備計画の未作成、また施設管理者の知識不足などと考えております。
改善措置といたしまして、暫定措置といたしまして、早急に整備計画というものを策定いたしまして、今年度と来年度にかけまして、超過箇所の整備を完了させますとともに、完了までの間、超過箇所を重点的に監視することといたします。
恒久対策といたしまして、施設管理者交代時の教育と定期的な勉強会を実施したいと考えております。
説明は以上です。
○田中敦朗 委員長 ただいまの報告に対し何かお尋ね等はございますか。
◆上野美恵子 委員 今、市電のインシデントに関わることで2件の報告がありました。
1点お尋ねしたいのは、国の保安監査結果が9月20日に出されて、その間、交通局でいろいろ協議がなされて、中間報告を出されたと思うんですけれども、まさに中間報告を作っておられる真っ最中の10月2日に、銀座通り交差点でのインシデントが発生をしたという、時系列からするとそうなるんですよね。そのことについてどう受け止めておられますでしょうか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今、上野委員おっしゃられたとおりでありまして、9月20日にいただいて、その内容等について精査している間に10月2日起こったわけでございまして、冒頭御説明しましたが、銀座通りの交差点で信号に関することで、これについては、今年5月2日からもう既に信号冒進という観点では3回目となります。インシデントでない案件も含めますと、4回目になろうかというふうに思ってございます。
運輸局からの改善指示のさなかというところもございますが、そもそも論として今年度に信号冒進というものが何件も起こっている。内容についてはやはり、これについては見落としといいますか、確認不足というところでありまして、そこについては本当にこの特別委員会もそうですけれども、職員の再教育等もやっていますとか、本当にきちんとやっていたにもかかわらず、こういうことが起こったということについては、本当に申し訳なく思っております。
そこはもう、ただ機械的な不備とかということであれば別ですけれども、やはり安全運転するための運転士の見落としとかというのは、本当にあってはならないことですので、ここがもう本当に繰り返し基本に忠実にということと併せて、ふだんの運転等についても添乗監査であるとか、ドライブレコーダーを使った監査であるとか、要は個人ごとの運転のくせというものも、原因の一つには内在しているのかなというふうに思ってございますので、そういったことについてもいろいろな手段を使って、個人個人に運転の動作というものを再確認して徹底をさせていきたいというふうに思ってございます。本当に申し訳ございませんでした。
◆上野美恵子 委員 陳謝ということではなくて、やはり何というかな、定期的な安全監査ではなくて、インシデントがすごく続いてきたと。そういう中でのやはり監査が入って、そして指摘事項が出て、これがまずかったんではないんですかということが示された後に、交通局としてどうしようと、これではいけないんではないか、どの点を改善しようかというそのさなかに次のインシデントが起こるということは、事業者の方からはきちんと対策を、信号冒進も幾つもあったんだからやっていたんだけれどもというふうにあったけれども、でも実際はそれが繰り返し起こっているということについて、私はとても危機感がありました。
だから、ちょっともう言っても一緒なんですけれども、とても今の時点では中間報告出されて改善点は書いてありますけれども、今後、それをどう進捗を見守っていくのかということが私は大事であろうというふうに思っています。
なので、本当に国の指摘事項というのは、どれを見ても日常業務の中でこういう基本的なことを、細かいことがチェックができていなかったのかなというのでは驚いたんですよね。視力にしても、何にしてもですね。
だから、インシデントをなくして、本当に安全運行ができていくようにするためには、今中間報告が出ていますけれども、もちろん多分最終的な報告というのもつくられるでしょうし、それにとどまらずに定期的にいろいろな形で安全運行に関する取組状況というのは、見える形で事業管理者としても確認する。チェック機関である私たちも、確認できるというふうにやっていかないとなくなっていかないんではないかなというふうに思いました。今回中間報告が出されていましたけれども、今後そういう形でこちらとのやり取りもさせていただきながら、改善の方向に向かっていかれるようにお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの御意見、もっともだというふうに思ってございますので、御報告をさせていただきながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 そのほかありますか。
◆齊藤博 委員 ちょっと素朴な質問1つだけ。
保安監査結果に対する改善報告、見直し案で組織というのはすごく大事な、結果として大切なんだろう思います。特に安統管を専任で配置すると。なかなか安統管、御人材が今局内にはいらっしゃらないというふうなことも踏まえた上で、令和7年1月からこの見直し案になると。それまでの今の現行は安全管理体制、安統管のポジションを誰が務めるのかとか、これ全く変わらないでこのままいくんですか。そこをちょっと教えてください。
要は、今年中の安全管理体制として組織はこのままでいくんですか、どうなんでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理副課長 ちょっと説明が不足していたかと思いますけれども、安統管に関しては、明日から就任をしていただこうかと思っております。その後に、安全管理に係るセクションというのを来年1月から考えておりまして、その中ではやはり局内で人選をしたりだとか、関係規定を整えたりだとか、そういったところに2か月程度見ているところでございます。
以上でございます。
○田中敦朗 委員長 そのほかありませんか。
(発言する者なし)
○田中敦朗 委員長 本日は、意見陳述人に御意見をいただきました。
様々な御指摘、御意見をいただきました。当然その御意見はこちら、公共交通に関する特別委員会でございますので、熊本市役所がどのようにそれを受け止めたのか、そして今後、次期の地域公共交通計画についてどのように反映させていくのか、そういったものに対しては、真摯に取り組んでいただきたいというふうに思います。
委員の方からもそういった御意見がありました。一つ一つ交通局にせよ、都市建設局にせよ、関係する部署は、それに対して自分たちの回答を持った上で計画に臨んでいただきたいなというふうに思います。
それでは、ほかにないようであれば、本日の調査はこの程度にとどめ、これをもちまして、地域公共交通に関する特別委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後 0時47分 閉会
出席説明員
〔意見陳述人〕
熊本学園大学経済学部教授
溝 上 章 志
〔政 策 局〕
局長 三 島 健 一 総括審議員 村 上 英 丈
総合政策部長 黒 木 善 一 政策企画課長 松 永 直 樹
〔財 政 局〕
局長 原 口 誠 二 財務部長 濱 田 真 和
財政課長 津 川 正 樹
〔都市建設局〕
局長 秋 山 義 典 技監 上 野 幸 威
都市政策部長 高 倉 伸 一 都市政策課長 飯 田 考 祐
交通政策部長 迫 本 昭 交通政策部主席審議員
濱 口 佳 久
交通企画課長 大 川 望 移動円滑推進課長 徳 田 隆 宏
移動円滑推進課市電延伸室長 自転車利用推進課長酒 井 伸 二
大江田 真 宏
〔中央区役所〕
区長 土 屋 裕 樹 区民部長 大 田 就 久
〔東区役所〕
区長 本 田 昌 浩 区民部長 橋 本 裕 光
〔西区役所〕
区長 石 坂 強 区民部長 田 島 千花子
〔南区役所〕
区長 本 田 正 文 区民部長 東 野 正 明
〔北区役所〕
区長 吉 住 和 征 区民部長 岡 本 智 美
〔交 通 局〕
交通事業管理者 井 芹 和 哉 次長 松 本 光 裕
総務課長 吉 岡 秀 一 運行管理副課長 荒 木 敏 雄