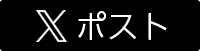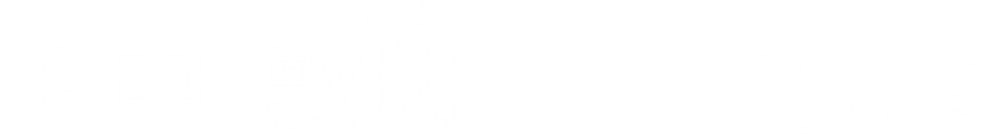2025年01月27日 その他
令和7年1月27日地域公共交通に関する特別委員会
地域公共交通に関する特別委員会会議録
開催年月日 令和7年1月27日(月)
開催場所 特別委員会室
出席委員 12名
田 中 敦 朗 委員長 平 江 透 副委員長
木 庭 功 二 委員 村 上 誠 也 委員
古 川 智 子 委員 中 川 栄一郎 委員
島 津 哲 也 委員 齊 藤 博 委員
井 本 正 広 委員 藤 山 英 美 委員
上 野 美恵子 委員 上 田 芳 裕 委員
議題・協議事項
(1)持続可能な地域公共交通の実現に向けた諸問題に関する調査
午前10時30分 開会
○田中敦朗 委員長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから地域公共交通に関する特別委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可します。
◎井芹和哉 交通事業管理者 おはようございます。
まず、おわびでございます。
昨年12月21日に、大江5丁目交差点において、またも市電が信号冒進、いわゆる信号無視をするインシデントが発生いたしました。
また、12月31日には、熊本城市役所前停留所から花畑町停留所方面に向かう区間で、脱線という重大事故を引き起こしてしまいました。
さらに、運行再開後、脱線箇所付近のレール幅に広がりが確認されましたことから、緊急に軌道の修正する工事が必要と判断をいたしまして、1月15日から2日間区間運休をいたしました。
後ほど原因や対応につきましては、詳細な報告をさせていただきますが、度重なる事故やインシデントの発生を受け、局を挙げて再発防止に取り組んでいる中、また、インシデント等外部委員会での最終取りまとめの時期に前後して、このような事態を引き起こしてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
市電を御利用いただいている皆様をはじめ、市民の皆様に対しましては、年末年始の外出に御不便をおかけし、また、度重なる運行トラブルにより大変御迷惑と御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
それから、次に御報告でございます。
去る1月1日付の人事異動により、交通局運行管理課に北添副課長が着任いたしました。同時に、安全管理体制をより強固なものにするため、北添と同じく異動でまいった事務職員2名と運輸職員4名の計6名で構成する安全対策チームを運行管理課内に新設いたしました。安全対策を専門部署で一体的に実施する体制とすることで、より効果的な安全対策とノウハウの蓄積による人材育成を図り、一日も早い熊本市電の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○田中敦朗 委員長 発言は終わりました。
これより本日の議題に入ります。
本日は、執行部より申出のありました信号冒進(インシデント)について、熊本城・市役所前停留場付近の軌道の不備について、インシデント等外部検証委員会の最終報告について、市電延伸事業について説明聴取を行うため、お集まりいただきました。
それでは、調査の方法についてお諮りいたします。
調査の方法といたしましては、まず、執行部から説明を聴取した後、質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
それでは、執行部の説明を求めます。
◎荒木敏雄 運行管理課長 資料交-1をお願いいたします。
12月21日、土曜日に発生した信号冒進(インシデント)についてでございます。
経緯は、左下に書いております。場所が、交通局前電停から味噌天神電停に向かって発車した電車が、デイリーストアがある交差点、鎮西高校から出てくるところになりますけれども、そちらの交差点に差しかかったところで冒進したものでございます。
経緯といたしまして、信号が赤だったために、停止線の約80メートル手前から速度調整しながら、約25メートル手前でブレーキ操作を開始したものです。しかしながら、イチョウの落葉の影響により滑走しまして、横断歩道を越え、停止線約33メートルの交差点内で停止したものです。鎮西高校から出てくる自動車には、支障のない位置で停止したものでございます。
運転士は、滑走によるものであるため信号冒進とは考えず、指令への報告は行っておりませんでした。外部からの通報を受け、ドラレコで事実を確認したものでございます。けが人は発生しておりません。
右側2番、発生原因でございますけれども、イチョウの落葉の影響により滑走し、適切な位置に停止できなかったものでございます。
3番、再発防止策といたしまして、全運転士、監督に対して事案を周知、また、滑走が発生する12月、1月におきまして点呼等で周知いたしました。
また、運転士によるレール状況の報告、滑りやすいだとか、イチョウの葉っぱが落ちるだとかというところを、無線で指令に上げるということを徹底しております。
加えまして、以前からやっておったんですけれども、滑り止めの砂まきというのを始発前の5時ぐらいからと、当日も朝方に1回まいておりました。そういったもので、滑走を防止してまいりたいと思っております。
また、落葉が大量にある場合は、速やかに営業所から出向いて撤去してまいりたいと思っております。
さらに、全運転士に対して以下の2点を周知しておりまして、1点が落葉を確認した場合、早めのブレーキ操作を行うこと、2点目が滑走や信号冒進が発生した際、運転指令への報告を徹底することというのを指示しております。
交-1に関しては以上です。
続きまして、資料交-2をお願いいたします。
熊本城・市役所前停留所付近の軌道の不備についてでございます。
2項目ございまして、1番として12月31日、大みそかに発生した脱線事故(重大事故)でございます。
左側に経緯を書いておりますけれども、熊本城・市役所前電停から花畑町電停に向けて出発した電車が脱線したものでございます。乗客30名、乗務員2名にけがはございませんでした。
運転士が脱線を確認し、運転指令に報告の上、乗客を車外に誘導しております。脱線直後から水道町、辛島町間を上下線ともに区間運休しまして、レールの補修工事を行った上で試運転を行い、1月3日の始発から全線で運行を再開しております。
右上が現場の状況写真になります。奥の市役所方面から写真手前の花畑町方面に電車が進行している際に、「脱線痕」と書いてある緑色の矢印で示したところ辺りで脱線をしておりまして、進行方向の左側10センチぐらいずれたところをずっと走行しているというものでございます。
舗装を剥いだときの状況が右側の絵で描いておりまして、枕木の上にレールが乗っておって、そのレールを止めるのが犬釘という大きなくぎで止めているんですけれども、そちらが完全にずれて25ミリの隙間があって、完全にレールを抑えられていない状況というのが確認できました。
この要因といたしまして、軌間が基準値から最大で39ミリメートル超過していたというものでございます。
2番の発生原因でございますけれども、レール幅が基準値を超えた箇所があり、右カーブで左側に遠心力が加わりまして脱線につながったと推定しております。
次のページの資料を見ていただきますと、絵の左側のところが今回の12月31日の脱線箇所でございまして、右側の市役所方面から進行してきたときに、やや右カーブになっておりまして、それで左側、図でいう下の方に遠心力がかかりまして、脱線したものでございます。
また、この絵で緑の十字のところのポイントが青点線の横にありますけれども、そちらが脱線の3週間前、12月7日にレール整正、レールの幅を狭める工事というのを行っておりまして、その間隔が近すぎるということで、その間にレールのひずみが生じまして、また、車両の通過の振動によって徐々に広がったものと推定しております。
資料にお戻りいただきまして、3番、対策についてでございます。
広がった軌間というのを狭めるようにレール整正工事を実施、また加えてレールのひずみ、影響がないように円を切る形でレールを切断しまして、レールの長さを調整しております。
施工後もレール変位を定期的に観測いたしまして、変位が見られないことを確認できるまで、運行時上限15キロというのを設けております。
また、全面的な改修、下地から全部やり換える軌条交換というのを今年秋~冬にかけて実施する予定としております。
こちらに関しましては、先ほどの図の1月15日、16日の整正箇所も、同じく交差点部分のところは軌条交換を実施したいと考えております。
資料交-2の2枚目をお願いいたします。
1月15日、16日発生のレール緊急整正工事でございます。
先ほどの図の左側が大みそかの脱線箇所でございまして、その右側、市役所に近いところの交差点というのが今回の整正工事の場所になります。
図で描いておりますように、黄色の吹き出しに書いておりますように、1月7日、レール幅の広がりというのを確認しております。ただ、脱線箇所で見られたようなレールの動きだとか、レール横の舗装に車輪が接触した痕というのがございませんでしたことから、早急に脱線につながる状況ではないと局内で判断しておりました。
それで徐行運転に加えまして、運転士が通行中に異音、振動等が感じられた場合にはすぐ報告するように、また併せて自動車の通行や市電の通行を妨げない工法というのを合わせて検討しておりました。
1週間後の1月14日、再度検測いたしまして、また、夜間に実際に電車での試運転というのを実施したものの、このままだと安全性が100%確保できないと考えまして、自動車や市電の通行を妨げない工法で実施するのは困難と判断したものでございます。
そこで区間運休しまして、全対象区間の舗装を剥ぎ取った上で、整正する工法の選択を決定したものです。
1月15日始発から先ほどの大みそかの分と同じく水道町、辛島町間を区間運休いたしまして、緊急整正工事を実施しました。試運転後に1月17日の始発から全線運行再開しております。
3番、1月22日九州運輸局からの指摘事項及び今後の対応についてでございます。
この2回の工事等を受けまして、九州運輸局から文書で「軌道の安全輸送の確保について」というのが発出されております。もともと9月20日に改善指示が出ておりまして、それに加えまして指摘が2点ございました。
1番としまして、全線の軌道について安全性を再確認すること、2番といたしまして、軌道の維持管理の方法について検証を行うとともに、この2件の背後要因を含めた原因究明と再発防止策を策定すること。
今後の対策といたしましては、番号が対応しておりますけれども、1番といたしまして、今年度内に現時点で軌間拡大が確認されている5か所は、整正工事を実施するとともに、全線の軌道の検測を実施いたします。
また、その検測の結果、問題がある箇所に関しましては、早急に整正工事を実施したいと思っております。
②維持管理の方法についてでございますけれども、検測間隔の基準の見直し、今20メートル間隔で測定しておりますけれども、それを半分の10メートル間隔に狭める等を検討してまいりたいと思っております。こちらは、運輸局と相談して決定したいと思っております。
交-2の説明は以上です。
続きまして、交-3をお願いいたします。
インシデント等外部検証委員会の最終報告についてでございます。
1月10日に、検証委員会から市長に最終報告書が提出されました。6回にわたる会議での検証と対策、会長と委員が局職員に取られたアンケートの調査結果を踏まえた提言というのがなされました。それを受けまして、今後のインシデント等の再発防止に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
左側1番、課題と対策でございます。
ひし形で課題、四角囲みで対策を書いております。
ジャンルといたしまして、人、もの、環境、管理の4つに分けておりまして、人の代表的なところでいきますと、一番上の基本ルールの不徹底、指導・教育等の効果確認不足の対策といたしまして、初期教育の充実、個人教習の強化と効率的な効果確認等を行ってまいりたいと思っております。
続きまして、ものといたしまして、ヒューマンエラー防止に係る物理的対策が不十分ということでございますけれども、こちらは後で出てきますけれども、IP無線の設置等を考えてまいりたいと思っております。
また、車両、設備の老朽化による不具合ということでございまして、今年11月に2台導入しましたような新車両というのを計画的に導入してまいりたい。また、軌条交換といって全部レールをやり換える工事というのを計画的にやってまいりたいと思っております。
続きまして、環境でございますけれども、モチベーションが低いということに関しましては、対策として乗務員の処遇改善、コミュニケーションの促進等を行ってまいりたいと思っております。
続きまして、管理に関しましては、安全について組織としてマネジメントができていないことに関しまして、1月1日付で設置しておりますような「安全対策チーム」など体制の強化を図ってまいりたいと思っております。
このように御提言いただいた対策のうち、「安全対策チーム」の設置等一部については既に実施済みでございますけれども、その他の取組についても可能な限り迅速に対応してまいりたいと考えております。
右側、2番、交通局職員への会長、委員のアンケート調査を踏まえた提言ということでございます。
現状の問題点として、3点指摘されております。1番として、リスク及び危機管理システムの問題、これは組織全体としてリスク管理ができていないんではないかという問題があるということです。2番といたしまして、組織におけるコミュニケーションの問題、3番といたしまして、職種間、事務職と技工職、運転士だとか、そういったところに壁があるんではないかという指摘があっております。
それで、問題解決に重要な2つの視点というので捉えられた提言というのが、下の7項目になります。
①番といたしまして、相互信頼の醸成、②番として、部署間の風通しの改善、③番で意識と行動の変革、④番で新しい視点からの教育・研修の充実、⑤番で第三者によるサポート、⑥番でバランスの取れた人材の確保、⑦番で仕事環境の整備、こういった組織風土の改善と組織の根幹に係る視点というのも含まれておりますため、今後の取組に適宜盛り込んでいくとともに、長期的に取り組んでまいりたいと考えております。
最後に、直近の取組でございます。次のページをお願いいたします。
検証委員会からの提言、また9月20日の九州運輸局からの改善指示というのを受けまして、取り組んでいる代表的な6項目について書いております。
①番として、「安全対策チーム」の設置、こちらは1月1日付で実施しております。乗務員の育成、資質管理、指導教育、事後防止対策に加え、各部門間の連携を図る目的で設置しております。
実際には写真にありますように、車内や交差点等、現地において、基本動作の実施状況の確認をはじめ、安全に係る取組などを実施中でございます。
②番といたしまして、JR九州を講師に迎えた安全教育講話の実施でございます。これは先々週の1月16日に実施したものです。安全に関する専門知識や安全意識に関する外部のノウハウというのを学びまして、基本動作の徹底や安全意識の向上を図るものです。
③番といたしまして、信号見落とし防止に係る補助表示装置の設置、こちら9月補正で上げていたものになりますけれども、写真の黄色枠の下にある信号がもともとついていた信号でして、そちらを見落として進行して冒進したことから、その上により明るく光る、点滅する信号を補助的につけまして、運転士に注意喚起をするものでございます。
右上、④番、ドア開け走行防止に係る注意喚起装置の設置、こちらも9月補正で上げておりましたものですが、車両の中間ドアが開いた状態で走るというインシデントが発生したことから、開いている間はポーン、ポーンとチャイムで知らせる装置を年度内に全対象車に設置する予定です。
⑤番で、軌道検測機の導入ということでございますけれども、現在、手検測で、大きな定規のようなものでレールのチェック、測定を行っておりまして、1,200ポイント、測定ポイントがありますことから、2か月ぐらいかかって測定していたところを、この新しい検測器でころころ転がした形で検測することで、二、三週間ぐらいで測定できるんではないかと考えておりまして、作業の効率化と点検頻度の向上を図りたいと考えております。今年度中に導入予定です。
⑥番でIP無線の導入、こちら運転士の要望1位でございまして、現在の無線は地形やビルなど障害物の多い場所で度々通信不能となっておりまして、安全面やストレス面でも負担が大きいものとなっております。そこで、既存無線は残しつつ、補助的な連絡手段としてIP無線を導入するもので、今年度中に全車に導入する予定です。
説明は以上です。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 資料都-1、市電延伸事業についてでございます。
市電延伸事業につきましては、これまで特別委員会をはじめ、市議会における議論を通じまして、着実に検討を進めてまいりました。第3回定例会におきましては、実施設計に関する補正予算を可決いただいたところでございます。
一方で、市電の運行につきましては、昨年からの相次ぐ運行トラブルを受けまして、上下分離の実施時期を延期すること、また、安心・安全の観点から軌道運送高度化実施計画を精査することを公表いたしまして、現在1月に設置しました「安全対策チーム」におきまして、安全管理体制の構築に全力で取り組んでいるところでございます。
しかしながら、そのような中におきましても、年末の脱線事故に続き、先日には一部区間の運休を余儀なくされるなど、現状としましては市電に対する市民の信頼は失墜し、信頼回復には程遠い状況にございます。
このような状況を鑑みまして、青囲みの部分でございますけれども、市電延伸事業につきましては、これまで安全対策と並行して進めてきたところではございますが、まずは運行の根幹である安全・安心の道筋を明らかにすることに最優先に取り組む必要があるとしまして、先週の市長記者会見で市長から申し上げましたとおり、市電延伸事業の今後のスケジュールについて再検討するよう指示があったところでございます。
なお、今後の進め方につきましては、下段に記載しておりますが、レールの点検や補修など足元の安全対策を早急に進めながら、今後の安全の再構築に向けた検討内容、方針について委員会にも適宜お諮りした上で、高度化計画へ反映し、延伸事業の再開につなげてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
○田中敦朗 委員長 以上で説明は終わりました。
それでは、質疑及び御意見等をお願いいたします。
◆齊藤博 委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
るる今御説明いただきました。冒頭ちょっと申し上げたいと思いますが、ぜひ今年に入りまして、1月ももう後半ということでありますが、安全・安心に市民の皆さん方が公共交通機関としてしっかりと電車を使っていただけるような環境を一日も早く、信用を取り戻していただければと、冒頭申し上げておきたいと思います。
その中で、あえて幾つか御質問申し上げたいと思いますが、交-1のインシデントですけれども、落ち葉によってブレーキ操作が思うように機能しなかったというような事例ですけれども、横断歩道を越えて停止線約33m先で停止したと。昨年、トータルでいうと16件のインシデント等の運行トラブルが発生していた中で、結果的に市民の方から、市民かどうか分かりませんが、外部からの通報を受けてこの事案が発覚をしたと。
要は、運転士が指令へ報告をしなかったと。33メートル停止線を越えて止まったという現実があったにもかかわらず、報告をされなかった理由ですね。当然いろいろな運行トラブルが実態として出ていたさなか、運転士の個人を責めているということではなくて、組織の風土として単純に疑問なんですが、こういった事例が起こった中で報告を上げなかったのか、まずここをちょっと教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 運転士に、この後にすぐヒアリングを行いました。ちょっとここにも記載しておりますけれども、滑走によるものであって、報告をしていなかったことに関しましては、申し訳なかったということは申しておりました。インシデントであるという認識がなかったということでございました。
◆齊藤博 委員 恐らく安全運行というものがいかなるものなのかという共有の認識が組織の中で図られていないと、多分そう言わざるを得ない事例なんではないかなと。これは安全運行に大きく逸脱した事例ではなかったというような、運転士の考え方といったようなものがひょっとしたら働いておったのではないかと。
そうするのであれば、安全運行というのは、一体どんなことを指して安全運行と捉えなければいけないのか。こういうところがやはり職員の皆さん方に共有できていなかったのではないかなと捉えられますので、後ほどちょっとまた申し上げたいと思いますが、検証委員会の指摘等々に対する組織、交通局としての姿勢、あるいは職員の皆さん方へのそういった安全運行に関する共有の認識、これをもう一回徹底していただければなと。
そういう意味では、参考となる事例ということになりゃせんかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続けてよろしいですか。
それから、交-2、これもお尋ねをしたいんですが、時系列にいうと12月7日に、これは予防策としてのということなんだろうと思いますが、レール整正工事を行っていると。その後の12月31日に、もともと12月7日に行った整正工事箇所に近いところ、挟まれたところという表現になっていますけれども、この整正工事を12月7日にやったことが原因なのか、今回脱線事故がそこで起こったしまいましたと。そしてその脱線事故が起こった後に近くを調べてみたら、今度また軌道が広がっていたところが発覚をしたというようなことで、一部交通を遮断して工事に入ったというような経緯だと思いますが、この12月7日にそもそも行ったレール整正工事、これは結果として適切に行われていたという認識を交通局として持っているのかどうなのか、そこを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 12月7日の整正工事でございますけれども、この緑色のところ、市役所付近で3点工事をしてございます。そのうち2点が脱線箇所の両脇のところでして、この工事方法というのが、その緑のポイントから前後3メートルのレールの回りだけを剥いで、軌間を調整するといったところになっております。この調整自体は適切に行われているという認識をしておりまして、その後も、脱線した後も測っても基準値内の値を保っておりました。
そういったことから、工事がまずかったとは考えていないところでございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 まずかったわけではないという回答ではあったんですけれども、でも挟まれたレール幅が広がって、そして結果として脱線事故につながっている点。要は2か所を犬釘でがちっと固定した。固定したがゆえに、結果としてそこのぐらつきがなくなったもんだから、ほかのところにひずみが出た。そしてそのひずみによって、今回脱線事故が起こったしまったというようなことであれば、この整正工事そのものが何か課題があったんではないかと、普通に考えれば捉えるべきなんだろうと思うんですよ。
こういうことはほかのところでも従前あっているはずですし、今回の検証が後々に生かされるためにも、予防のための整正工事が結果としてやはり不具合を生じさせてしまった、あるいは工事が終わったらほかのところの部分の影響も踏まえて、後々しっかり検証するとか、12月7日に行った工事そのものに全く問題なかったと言われると、同じような工事を今後したときに、その間の線路の幅の広がりとかの動きの検証につながっていかないんですよね。
だから、これそのものの捉え方というのをもう一回、交通局としてどんなふうに捉えるか、改めてお願いします。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどの、うちの見解としては、そうというお話をしたところでございますけれども、ここに関しては専門的な知識、知見がある方の意見を聞きたいと考えておりまして、鉄道総合研究所という鉄道で一番大手の研究をされているところに、こういった事象というのは適切だったのかというところも含めて、今相談しているところでございます。
また、今回みたいな工事、両脇で例えば工事をするところでひずみが発生したということが正しいとするならば、やはり先ほどお話ししたような、ちょっと円を切る工事だとかが適切な対応となってまいると思っておりまして、今後、するところに関しても、そういった工事をやっていかないといけないのかなと、そこも鉄道総研さんに相談したいと思っております。
以上です。
◆齊藤博 委員 起こってしまった事故というのは事実ですので、事故から導き出される検証のやり方とか、検証そのものをもう一回改めて確認していただければなと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 交-2に関してほかにありませんか。
◆齊藤博 委員 交-2の続きでいいですか。
○田中敦朗 委員長 はい。
◆齊藤博 委員 交-2の2ページ、次ページですけれども、今後の対応、一番下ですね、現時点で軌間の拡大が確認されている5か所の整正工事をやるということで、これはもう速やかに予防ということで行っていただきたいと思います。
これに関連して、ここは特別委員会ですので、予算がどうこうというのは都市整備分科会で検証されるべきものとは思いますけれども、あえてお尋ねを申し上げたいと思いますが、この5か所の整正工事に関してはどのように対応するのか、どのように対応するのかというのは、予算的にどうするのか、幾らぐらいかかるものなのか、あるいは今年度中の補正で対応するのか、あるいは新たな年度で補正するわけではないですよね。今年度中に完了するということですから。補正で対応するならそこのやり方を教えていただきたい、どれぐらいお金がかかるのか。
それから、軌道検測機を購入するであるとか、ドア開け走行防止の注意喚起装置をつけるとか、あるいはIP無線導入をやるとか、これは今年度中の予算であろうかと思いますが、当然事故が発生してから今後予防策ということですから、ここに補正が発生してくるのか、あるいは既存の予算で対応できるものなのか、そこを教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどのレールの整正でございますけれども、5か所ありまして、1か所は今回1月15日、16日の箇所に含まれているため、4か所今残っております。そこに関しましては、もう既に工事の業者さんと契約をしておりまして、早急にやってまいりたいと思っておりますし、それまでの間は運転の方で速度制限を設けたり、毎日広がっていかないか、検測をやっているところでございます。早急に対応してまいりたいと思ってございます。
また、金額ですけれども、契約の金額としては600万円程度です。4か所残りありますけれども、今回脱線のときがレール幅から39ミリ基準値から超過しているところでございまして、今回の箇所は一番小さいところで1ミリ程度、一番広いところで7ミリ程度超過しているという実証でございまして、基準値は当然オーバーしているんですけれども、値としてはそこまで大きくはない状況でございます。
そこで、速度制限とか毎日の検測だとかというところで対応してまいりたいと思ってございます。
あと機器ですけれども、先ほどの補助表示装置、一番最後の紙の③番のところになりますけれども、そちらが3か所で350万円、④番のドア開け注意喚起装置が1,020万円、こちらは9月補正で既につけていただいて、そちらで執行しております。
また、⑤番の軌道検測器が550万円、⑥番のIP無線が750万円、こちらはもともとうちの既存予算流用で対応してまいりたいと思っておりますので、2月補正で上げたりとか、そういったところは考えていないところでございます。
説明は以上です。
◆齊藤博 委員 IP無線の導入について、流用というのはどういう意味か、もう一回教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 IP無線自体は予算ついておりませんでしたけれども、工事の予算の残があったことから、そちらの残を生かしての執行ということを考えております。
以上です。
◆齊藤博 委員 それは予算の在り方として正当ですか。工事の予算をIP無線に流用するんですか。ちょっと想定を超えた答弁のように聞こえるんですが、ごめんなさい。
個人的には事故が起こった後の対処ですから、語弊があるといけませんが、補正でどんどん上げていただければいいんではないかなと思うんです。軌道検測器の導入、そもそも何でこれが今の時期に導入されるのかなというところもちょっと分からない部分もあるんですが、こういう脱線事故まで起こしてしまったから、早急に対応しなければいけない。それはそれで分かります。補正を起こすなら補正を起こしていただいて、僕は一委員としてオーケーなのではないかなと思います。
それから、IP無線の導入についても、今まで課題がありましたということで、対応していただくのは当然やぶさかではないし、その対応のやり方、これについては僕は個人的には補正で上げていただいた方がごく自然なのではないかなと思います。工事費を流用するというのは、ちょっと正直予算の使い方としてはいかがなものかと思いますが、いかがでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 すみません、先ほどの2件に関しては、私の認識誤りでございまして、補正で対応してまいりたいと考えております。申し訳ございません。
◆齊藤博 委員 確認ですが、すみませんね、交-3の資料に載っているもんですから、ドア開け走行防止に係る注意喚起装置はもともと予算計上していたということで大丈夫ですね。軌道検測器の導入とIP無線の導入については補正で上げる予定だという認識でございますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そのとおりでございます。
◆齊藤博 委員 もう一つ確認です。
あと残り4か所の整正工事について、これはトータルで600万円、これも補正で上げるということでようございますか。上げる予定ということでいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 このことに関しましては、昨年からもともと悪いところを把握しており、当初予算で計上しておりまして、それの分で対応してまいりたいと思っております。
以上です。
◆齊藤博 委員 すみません、何回も確認ですけれども、この5か所、残り4か所、1か所のもう既に修正した箇所、ここも含めて当初予算で上がっていた分なんですか。もう一回教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの維持補修として当初予算で計上していたものでございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 分かりました。
それでは、今年度に残り4か所の工事もやってということでありますので、検測の実施や安全運行に全力を尽くしていただきたいと思います。
それともう一つ、今後の対応として交-2のところで、検測間隔の基準の見直しを20メートルから10メートル間隔でやるということなんですが、軌道検測器を購入することで、10メートル間隔とかする必要というのは、これを導入すれば必要なくなるという認識でいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 委員おっしゃるとおり、測定間隔は短かめられまして何十センチ単位という、1メートルで例えば2ポイントだとかいう感覚で取ることは可能となります。
ただ、運輸局さんに提出する書類というのが20メートル間隔で出しておりまして、そこが例えば10メートル間隔で提出するのかというところを今後運輸局さんと相談してまいりたいと。代表的なポイントとして管理するというところの認識でございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 それでは、今回安全運行に伴って検測器を入れ、実態として交通局として管理していくのは、もっと間隔的には狭い、何十センチとか、10センチ、20センチ、場合によっては50センチ程度の間隔でずっと検査を行っていくと、そんな認識でいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 測定はできますので、そのデータは50センチとか、そういう間隔で取って管理してまいりたいと思っております。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
◆上野美恵子 委員 では、交-2の今の点についてお尋ねします。
私が思ったのは、今回、この交-2で軌道の不備ということで御報告があっておりました。こういう事故が発生してくるのは、一定施設の老朽化とか、そういうのも影響している面があるのではないかなと思っています。
そういう意味では、今回の対応についてのお尋ねがありましたが、こういう軌道整正について日常的な点検というのはこれまでどうなっていたのか、今回事故の発生によっての御報告になっていたんですけれども、日常的な点検がどうなっていたのか、それとその点検を行ったときに何らかの修正するとか、対応するとか、そのときの基準というのはどのようになっているのか、その基準に対して今の対応がどうなっているのかを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの点検でございますけれども、毎日整備長がトラックで確認をして、休みのときは代わりの職員が対応するということで確認をしております。
基準といいますか、点検、測定自体も年1回、測定しておりまして、その中で管理をしていくということにしております。オーバー値が出てくるときには適切に、今回ちょっと整備遅れというのがありましたけれども、値がオーバーしているところが見られたら適切に、早期に対応してまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 そのオーバー値という値を教えてもらっていいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 値について軌間がレールとレールの内側の距離が1,435ミリというのが、JRさんも含めて、通常のうちの標準軌という規格になります。うちの整備心得として管理値を設けており、1,435からマイナス5、プラス15ミリまでは許容するということになりますので、1,430~1,450までの間で管理するということになっております。
大概管理値を小さくいくのではなくて、オーバーする方向に出るというのが普通ですので、今回大みそかのときも、1月15、16日のときも超過ぎみに出ているものでございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 今の説明だと、ずっと点検を積んでいきながら、年に1回は点検をするというふうな形になっているみたいですけれども、減ることは少なくてオーバーすることが多いということなので、1,450をオーバーしたときにすぐに対応ができているのか、それともちょっとぐらいならいいかなとか、このぐらい超えたらでも最低しとかんと危ないかなとか、そういう交通局の判断によって、私たちからすれば、基本は基準値を超えた場合は、しかるべき対応をしないと安全が損なわれると思うんですけれども、そこの安全が損なわれないために、基準値を超えた場合の対応が100%行われていたのか、それとも全部は採用できないから、このぐらいはしとこうとか、ちょっと積み残しのある状態で対応されてきているのか、教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 9月20日に九州運輸局から改善指示というのが出まして、その中の一つとして、軌間の維持管理ができていないというところに関しましては、2年連続でオーバー値をそのまま積み残していたといったことから指摘が出るものでございまして、本来ならば早急に対応していかなければいけないところが、そのまま積み残されていたということで、今指摘を受けた後、すぐ取り組んでまいりたいということで対応しているところでございます。
説明は以上です。
◆上野美恵子 委員 ということは、今回こういう事案が発生するまで2年間オーバーした状態が続いていても、対応ができていないという状態を交通局がそのままにしていたということですかね。
◎荒木敏雄 運行管理課長 その点に関して、九州運輸局さんからの御指摘というのが改善指示で出されたものでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 これまで2年連続でも改善できていなかったように、かなり積み残しというのはどのぐらいあったのか。地点が多分決めてあると思うんですよ、20メートル間隔、今度は10になるけれども、20メートル間隔なので地点数が決まっているので、その決まった地点数に対して何地点ぐらいのオーバー状態であったのかを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどお話しした4か所プラス、市役所のところが軌間オーバーというところの値で出てございましたので、10か所までなかったかと、7か所ぐらいだったかなと認識しております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 では、普通の基準からいくならば、今おっしゃった7か所というのは、去年の計測があったときの時点から早くに手を打たなきゃいけなかったということなんですかね。
◎荒木敏雄 運行管理課長 本来ならば9月に検測して、また翌年までの1年間の間に対応していかなければならなかったことと思っておりまして、その対応が遅れたということでございます。申し訳ございません。
◆上野美恵子 委員 ということは、2年間というのは放置された状態なので、最低でも1年に1回は千何百か所の計測地点がきちんと計測をされて、そして場所によってはオーバーする値が出たときに、その時点で、その1年間のうちに修正がされていけば、2年間継続というのはなかったわけですね。
ということは、なぜ1年間のうちにせずに翌年に繰り越して2年間放置をして、要するに国から指導を受けるような状況になっていたのか、その理由は何ですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そこは管理不足というところ、九州運輸局からも指摘されておりますんで、そのとおりと思っております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 だったら、今回インシデントがたくさんこの特別委員会にも、そしてまた常任委員会にも報告をされて、私たちも本当に残念な気持ちでインシデントの報告があるたびに聞いてきたんですけれども、突き詰めていろいろ詳細に聞いていくと、交通局としてのいろいろな守るべき基準を守らないというところに、大きな原因があるんではないかなと思います。
また、後で国からの改善計画、最終報告も出ておりますので、それも含めて今後改善していかなきゃいけないかなと思いますけれども、そこはちょっと認識甘いですよね。
例えば認識していたけれども、予算が少なかったとか、ほかの事情があったならともかく、今のお答えだと、まあいいかなみたいな感じで放置をされていたという向きがありますので、それはちょっとどうでしょうかね。井芹事業管理者、それではやはり事故というのは起こってしまいますよね。どう思われますか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの委員の御指摘は、これはもっともでございますし、それに対して私たちは何も申すことがないという意味では、本当に申し訳なく思っております。
そういうことが、今話がるる出ました運輸局からの改善指示もそうですけれども、インシデントの検証委員会からも車両とか、レール、軌条も含めた施設の老朽化といったところも早くすべきではないかという御指摘につながっていると思ってございます。
なので、今5か所等についても早急に対応するということにしていますし、レールの検測器等についても、今まで買う予定もなかったというところで、これも反省をしているところでございますけれども、早急に買ってきちんと測って、そのほかの箇所等についてもきちんと測って対応していきたいと思ってございますし、御指摘いただいたことについては、本当に申し訳ないというお言葉しかお答えできませんけれども、今後についてはきちんと対応を進めていきたいと思ってございますし、その内容等については、この特別委員会の場でもきちんと御説明をしていきたいと思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 もう一点、私が心配していることがあるんですけれども、1つは、レールの整正ということを今言いましたけれども、老朽化が進んでいくので耐用年数というのがあると思うんですよね。さっき全面的に軌条を交換していくという御提案が説明の中ではありましたけれども、現状の問題として、交通局が管理しているレールの中で、そもそもレールの耐用年数はどうなっているのか、そして、交通局が管理しているレールの現状について、20年以下がどのぐらいあるのか、距離とかパーセントとか、20年~30年がどれぐらいあるのか、30年~40年がどれぐらいあるのか、40年以上に至っているものが幾らあるのか、数字を教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの耐用年数といたしましては、定められたものはございませんけれども、通常20年~40年程度といわれておりまして、都心の方のJRさんのところだとかというのは、20年で管理されていると。あとはちょっと郊外になってくると、30年、40年というのがあるという状況でして、うちは一般的に30年で考えて、経営企画上は30年で考えているところでございます。
ただ、今実際のレールの年数といたしまして、30年越えがだいたい40%ぐらいあるといったところ、あと40年越えが4%ぐらいあるというのが現状でございまして、そちらを計画的に早期に対応していかないといけないと考えておりまして、それが軌条交換でレールの更新というのを早期に対応していきたいと考えているところでございます。
説明は以上です。
◆上野美恵子 委員 今30年以上が40%、40年以上が4%あるということでした。40年ということは、10年前にもう既に基準というか、一応交通局が経営計画上で定めてある耐用年数というのを超えていたにもかかわらず、何とはなしに使ってきた、漫然と使ってきたという現状があったんだなと思います。
この点でも、例えば人為的なもの、人をどうにかするというのは、その人本人の向き合い方とか、人間というのは難しいけれども、こういう環境、ハード的なものについては、一旦決めた目標とか基準に対して、きちんと対応することが原則ではないかと思うんですよね。
さっきも整正という点でも、基準がありながらそうなっていなかった。そもそものレールそのものだって、確かに私たちも委員会で交通局が大変経営的に厳しいというお話をずっと聞いてきていて、その裏でこういうふうにもう少し安全ということを考えたときには、最低限ですよね。
レールの耐用年数が過ぎているのに4割以上も今現状にそこにあるということ、今回事故が起こって検証委員会があって、国からもいろいろな指導が入ってなったから、こんなふうに大問題だと言っているけれども、そういうことを抜きに、決めている基準に対しての日常的な交通局としての自身の管理ということに対する向き合い方そのものが問われてはいないかなと思います。
これちょっと駄目ですよね。それは予算なんかがついていなかったんですか、それともほかに理由があったんですか、こういうふうに過ぎても漫然と使っているという、その大元にある理由というのは何ですか。
これだと基準決める意味がなくなってきますよね。経営計画を立てながらその計画にのっとらない実態があるということについて、どのようにお考えなのか教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 うちが全線が12キロございまして、30年で割るとするならば、年間400メートルずつ工事するというのが平均的にやっていくというところでございますけれども、実際に過去10年ぐらいで二百数十メートル、ここ最近では360メートルぐらい、400メートルに近くやっているところでございますけれども、さらにちょっと加速して400メートルを超えていかないと、このような30年以内での管理というのができないと思っておりますので、そちらはやってまいりたいと思っております。けれども、なかなかメートル数だけではなく、例えば交差点のところでは距離はいかないけれども、工事は結構困難だとかというところもございまして、けれども、計画的に400メートル、500メートルというところを目指してやっていきたいと考えてございます。
説明は以上です。
○田中敦朗 委員長 できなかった理由は答えていないけれども、いいですか。
◆上野美恵子 委員 いやいや、それは聞きます。
今は現状だけ言われたんですけれども、できなかった理由ですよね。今おっしゃった計算でいけば、年間400メートルしないと30年間で更新していけないという具体的な数字を描きつつも、それが執行できずに以前は二百数十メートルがずっと続いて、多いときでも300メートル超えたぐらいだったという今御説明であったかと思いますけれども、その理由は何なのかというところです。
でなかったら、今課長がいや今後は頑張るとおっしゃったけれども、でもその理由をはっきりさせて、今までできなかった理由というのをクリアしていかないと、多分やると言っても難しいと思いますよ。そこの理由は何ですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 確かに軌条交換する箇所というのは計画的にしておりましたけれども、そこの箇所の計画というところが確かに遅れぎみになっていたところはあるのかなと思っておりますし、仮に上げておってもなかなか予算的に厳しいという面もあったのかなと思ってございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 遅れぎみは現状ということで、理由で今おっしゃったのは、予算は上げていて、予算はあったんですか、それとも要求したけれども少なかった。どっちですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 財務、財政も総務課で持っておりまして、その枠の中でやれるところをやっているというのが今までの現状でございました。
以上です。
◆上野美恵子 委員 その400メートルの交換を、年間400メートル実施できるだけの予算は確保できていたんですか、できていなかったんでしょうか。どちらでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そこに関してはできておりませんでした。
以上です。
◆上野美恵子 委員 長い交通局の歴史の中で、それができた年度があったんでしょうか。できなかったと言われましたけれども、たまにはそれだけの予算がついたのか、ずっと予算がつかなかったのか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 昨年、商業高校前とかをやっておった年には400メートルを超えてございますけれども、早々そんな何年もというところはございません。単年度で単発でクリアしたところはありました。
以上です。
◆上野美恵子 委員 その予算というのは、軌道の問題なので、予算そのものは財政局で査定されるんですか。要求はしていたんですか。要求していて査定で落ちていたのか、要求もしなかったのか。どちらでしょう。
◎荒木敏雄 運行管理課長 もともと上げるところは、うちの局内でやっておりまして、工事するときには基準外繰り出しとか、その辺のところの話もありますので、財政課と話をしているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 そうしたら、交通局としては、予算は要求をしていたわけですよね。財政局は、そういう市電の安全運行に関わる、こういう最低限守るべき基準についての予算を査定で落とすんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 すみません、今何度かやり取りをさせていただいておりますけれども、まず、そもそもこうなったというのは、先ほども言いましたように、必要な予算を必要なときにつけていなかったというのは事実であろうと思ってございますが、これにつきましては、過去に交通局は経営上よろしくなかったものですから、経営健全化というものを優先にするというところで、どうしてもそこに対する予算というものが少なかったのは事実だと思います。
例えば、うちは30年と決めておりますけれども、30年を1年でも超えたらそのレールが使えなくなるかというのは、そういうわけではないということではあろうかと思いますので、毎年毎年の測定等を基に、今年は使えるかな、来年はというふうにちょっと後送りといいますか、そういったことを積み重ねてきた結果だろうということであって、交通局の中でそういうふうにしていたというのが、基本的だろうと思ってございます。
そういう中で、それはいかんということで、令和3年にその経営計画を定めたときには、先ほど言いました400メートル等できちんとやっていくということをきちんとうたって、ここ数年はそれに対する予算も大きく取ってはいるところでございますが、いかんせんやはりレールも買わないといけませんし、工事も結構金額がかかるものですから、少し進捗として目に見えて1年間にとか、短縮でできるというような工事ではなかったかなと思ってございます。
今回、こういったことも踏まえまして、再度その経営計画について、400メートルということそのものについても見直していきたいと今思ってございます。そこには運輸局の今後指摘事項等に対する最終報告とかもありますので、運輸局とも相談をしながら、きちんと計画を見直していきたいと思ってございます。
その内容については、ここの特別委員会でもきちんと事前に計画の内容については考え方をお示しして御議論いただければと思ってございます。その上で、きちんとした軌条の整備というものをやっていきたいと思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 聞いていると、400メートルを交換するだけの予算はなかなか厳しいので、30年で更新していくという、その計画そのものを見直すと今言われたんですけれども、ということは30年で更新しないということになっていくんですか。そこを変えるんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 もう少し早めに、もう少し期間を短くしてどうにかできないかと思っております。
◆上野美恵子 委員 二十何年にするということは、もっと予算が要りますよね。
◎井芹和哉 交通事業管理者 予算もそうですけれども、一部輸入したレールとかも使っているということもありますので、予算がどんとつけば、その年にどんと、例えば1キロも2キロもできるというものでも当然ございませんし、事業者、工事をする業者等についても、専門的なところもありますので、そこも土木工事よりも少ないと思ってございますので、そういった兼ね合いも含めてきちんと計画を立て直したいと思っております。
◆上野美恵子 委員 見直しというのは、これからのことだと思いますので、このことで議論してもちょっと深まらないと思うので、私からぜひお願いをしておきたいのは、経営計画、今後見直してと言っておられますけれども、経営計画そのものをどこに視点を置くかという点では、いろいろなお金の面があるかと思いますけれども、何よりも安全重視、安全第一、そういう視点でしか見直しはしないというところを、局として毅然として立場を明確にしないと、どんなに見直しと言っても、ずるずるとなってしまいかねないと思うので、そこは絶対に譲らずにやっていただきたいなと思います。
そしてそういう立場でいろいろ今後検討していく中で、予算についても、幾ら企業だから、独立だからといいますけれども、安全運行そのものが担保できないんだったら、今度上下分離になっていきますけれども、その問題にも関わることとして考えないといけないと思いますよ。
改革といっていろいろな方針が出されるけれども、それをするときに本当に安全が確保できるのか、そこのところだけは、一歩も譲らずに考えていくという姿勢がいるし、そのことを交通局も頑張るけれども、市長がこの間の市電の100周年の式典の中で講演なさった、私はああいう場で市長が安全運行について講演されるというのは、異例のことだと思うんですよね。
でも、せざるを得なかった、そういう中にあったというのは、今いろいろ明らかになってきた、きちんとやるべきところやらないと、この市電のインシデント問題は解決しないという中にあって、そこのところしっかりしていかないといけないし、他局も交通局は企業だからということではなくて、安全運行のためには、一般会計からのいろいろな支援も含めて、安全が守られるような事業の運営に対しては、全庁を挙げて、市長があのときおっしゃったことは、確実に現実のものにするために、全庁が協力するというのが大事かなと思うので、そういう決意で頑張っていただきたいなと思いますが、いかがでしょう。
◎井芹和哉 交通事業管理者 安全というものを第一にということについては、私もしっかりと思っておりますし、改めて今の言葉も踏まえて、その認識を前提として今後努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 いいですか。
◆上野美恵子 委員 はい。
○田中敦朗 委員長 そのほかありますか。
◆上田芳裕 委員 今の井芹事業管理者からも、また上野委員、齊藤委員からの御指摘等もある中で、安全が第一だということで、今後取り組まれるということで、後ほどほかにも意見があるかと思いますが、市電の延伸の今後のスケジュールも変更する中で、安全管理の再構築を行っていくということで、言うならば今の話をずっと聞いていくと、課題がそこにあるのに手がつけられていなかった、予算立てがされていなかったということの積み重ね、それは人の配置もそうですね。積み重ねが今一気に来ているのかなと考えております。
そういった意味では、令和7年新たな年を迎えて、今年が、市長も言われた、安全・安心の元年にしたいというようなことであるんですけれども、いろいろ対策については、外部の検証委員会の中からヒューマン的なもの、施設整備的なもの、職場の環境、組織管理体制含めていろいろな御指摘があって、その中で交通局で「安全対策チーム」というのを1月1日につくられてすぐということになりますけれども、「安全対策チーム」の中でどのような安全対策をやっていくのか、その方向性、項目等々の検討が適切ですけれども、御答弁いただける範囲があれば教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 資料の交-3の2枚目のところで、「安全対策チーム」の設置ということを書いてございまして、今写真であるような交差点立哨だとか、添乗監査ということで、実際の運転士が基本動作をきちんとやられているかだとか、あとは速度だとか、当然ながら信号を守っているかとか、そういう基本的なところを確認していると、そこで指導をしているといったのがメインの仕事でございますけれども、そのほかに資質の管理とか、あとは指導教育、実際に新人の運転士もこの「安全対策チーム」で教育してまいりますし、事故防止対策というのも施設だとか、車両だとかという各部門間で連携しながら取り組んでいっているところでございます。
以上でございます。
◆上田芳裕 委員 今御答弁では、乗務員の育成、資質管理、指導教育、ヒューマン的なものと事故防止することでありますけれども、外部検証委員会から出されてある対策の中には、施設整備のところで軌道車両の予防保全の強化であったりとか、事故多発箇所の安全対策の再検討であるとか、様々に軌道と車両、いわゆる設備、施設のところとヒューマンケアのところが示されておって、対策チームの中で対策を検討し、講じなければならない課題というのは、物すごくたくさんあると思っています。
そういった意味では、今回、外部検証委員会の中から体制強化ということで、この資料からいくと専門チームの設置という、専門チームという表現されていますが、私から言わせていただくと、この課題になってから答弁を運行管理課長がずっとされておりますけれども、運行管理課長の守備範囲というか、それを超えているのではないかと思っています。
そういった意味では、運行管理課長が大変重たい職責に当たっていらっしゃると思いますけれども、「安全対策チーム」というよりも、交通局の中に総合安全管理課とか、きちんとした体制整備を構築した上で、今後進めていくべき課題ではないかなと思っておりますけれども、この点については事業管理者の御所見があればお願いいたします。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ありがとうございます。
今御指摘をいただいたことは大変重要だと思ってございまして、おっしゃるとおり、今までの反省といいますものが、そこの部署で全て完結していたということが、問題点が見えなくなってきていたという、一つの大きな要因でもあったのかなと思ってございます。
なので、まずは、諸規定等をきちんと見直す。また、今も課長が申しましたように、現場の指導であったりとか、そういったところからやならないといけないもんですから、現場に、しかもこのチームという名称で増員をしていただいて設置をしたところでございますが、御指摘のとおり、今後は法規とか、そういった点についてもきちんと整備を再度見直す必要もあると思ってございますので、そういった意味では、部署の新設というものも、私としては必要だと思ってございますので、今後の安全に対する検討の中で、そこについても含めて検討していきたいと思っております。
◆上田芳裕 委員 井芹事業管理者から、そういったことも含めて検討いただくということであります。今後は時期を見て上下分離することで、上物、下物とあって、施設、軌道とかの管理と交通社団法人ですか、公共交通公社と役割が変わってきますけれども、安全管理を総合的に行うという意味では、新しい、さっきの話ですけれども、交通公社も、また下物を管理する市も大事になってくると思いますので、十分な検討と具体的な設置に向けて御協議いただきたいと思っています。
もう一点心配なのが、そういった安全管理体制の構築をしてきちんとした安全対策を行う、先ほどから上野委員からもありました軌道の安全とか、車両を新しくどんどん変えていくということに関しては、物すごく予算がかかっていくと思っています。そういった意味では、安全体制の再構築の初めの段階で、たくさんの予算をかけていろいろな対策を打たなければならないと思っています。
一遍に何もかもできるとは思っていませんけれども、財政的な負担が交通局、また熊本市にも生じてくると思っていますけれども、そこら辺の考え方について、財政局長に御所見があればいただきたいと思います。
◎原口誠二 財政局長 今上田委員、また先ほど上野委員からもありました、先ほどの市電の延伸の話にもつながるんですが、延伸の前に既存の安全が保たれて延伸の話だと私ども思っております。既存のこちらの更新については、るるこれだけ重大な案件が出ている中で、これまで金がないからレールを交換したらいかんとか、そういう議論をしてきたことはございません。
ただ、全体としての基準外繰り出しをどうするかという議論は、これまでここ何年かもずっとあって、都市整備委員会でも多分るる議論があってきたと思いますけれども、先ほどお話があった中で、今後の安全対策については、命を守る公共交通でありますので、その辺の視点も、委員の方々からの御意見も含めて、繰り出し基準の考え方等についても御相談して、御議論いただければと思っております。
以上でございます。
◆上田芳裕 委員 御答弁ありがとうございます。
既存の施設の安全対策の上に延伸がなるという、なかなかうまくいくのかどうか非常に考えるところもあるんですけれども、ぜひそういった考え方を持って今後も財政局としても対応していただきたいと思いますし、上下分離になった以降も、そのことを十分引き継いで、財政面の支援含めて取り組んでいただきたいというふうに思います。
私からは以上です。
◆藤山英美 委員 資料交-1の件で質問したいんですが、この件については、電車でほかの車両もあるんですが、イチョウは油分が多くてスリップするという話は、相当以前から出ていた問題です。私もこの件について質問したときは、まだ電車通りが県の管理だったときです。
そういうときに、大体イチョウの落ち葉が、11月末までぐらいに剪定すれば落葉がないということで質問をして、答弁ではちょっと今まで2月、3月でやっていた剪定をそんな形でできないというような答弁だったと思いますけれども、それで熊本市の所管でないということで、私は県の土木事務所にお願いに行きました。そして県でも同じような答えだったんですが、私はせめて坂のある熊商前と大甲橋のところだけでもやってくれませんかと言ったら、そこでやってくれました。その後、何年か続いたと思いますけれども、今はちょっとうやむやになっているような感じがしているんですけれども、これは当時から、相当前から電車のスリップについては指摘されておりました。
しかし、さっき言いましたように県の管理ということでなかなか進まなかったんですが、今はもう市の管理になっておりますので、管理も高木は3年に一度剪定するということになっていると思いますけれども、落葉の時期に皆さんも御存じと思いますけれども、相当のイチョウの葉っぱが舞っているんですよね。だから、交通局としても本当に大変だと思います。砂をまいて、運転士さんはほこり対策でマスクを二重にしているとか、そういう話まで聞きますし、外的要因でいろいろな問題が出ているんではないかなという思いがありますので、これもたまたま相当長い距離が必要だったということですけれども、それまでにも短い距離があったんではないかなと思います。
そういうことで、外的要因を除去する方法も書いてもらえないかなという思いがしますし、交-3の外部検証委員会の最終報告についての課題と対策ということで載っていますけれども、この外的要因というのは載っていないもんですから、特別委員会の趣旨として調査研究というのがテーマになっておりますので、ぜひそういうことで入れて研究してもらえないかなという思いがしております。
今後も、膨大なイチョウの落ち葉対策は課題として残ると思いますので、そこのところを研究していただきたいし、事故防止で事業管理者が言われたように、安全第一というならば、そういうところまで考えてほしいなという思いがしていますので、そこのところどのように考えておられますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 12月、1月には結構イチョウの葉っぱが当然ながら落ちまして、土木センターにもお願いしながら、剪定だとか、スイーパーというか、掃除機みたいなもので横の車道を掃除していただいたりとかやっているところではございますけれども、本数が結構あるのと、市電の沿線沿いには結構ずっと植わっているものですから、その辺の管理体制だとか、その辺のところには、また土木センターと協議しながら、局としては進めてまいりたいと思ってございます。
以上です。
◆藤山英美 委員 よろしくお願いします。
これは電車だけの問題ではないんです。ほかのイチョウの高木があるところは、歩道の人も自転車も車も電車もみんな影響があるわけですよ。そして、高校生の自転車が転倒するという事故も何回か見ておりますので、そういう問題まではらんでおりますので、このイチョウ対策、高木対策は、本当は喫緊の課題ではないかなという思いがしますので、よろしくお願いします。
◆古川智子 委員 私からは1点確認をさせてください。
1月15日の始発から区画運休して緊急整正工事を実施されている件です。背景を見てみると、1月7日時点でレール幅の広がりを確認している。ただ、この時点では早急に脱線につながるような状況ではないと判断をしています。というところで、1週間後の14日、再検測及び夜間に試運転を実施したところ、自動車と市電の通行を妨げない工法では、100%安全性を確保できるとは言えず、実施困難と判断をして翌日の始発から運休しているというところですね。
市民への周知の方法が、朝5時のたしか公式LINEで伝わった。その方法を取られたと思うんです。もちろん安全運行、この安全を担保することが一番ということは、もう大前提となるお話の上でやり取りをさせていただきたいんですけれども、この説明からいうとレール幅の広がり確認して、早急に脱線につながるような状況ではないけれども、自動車、市電の通行を妨げない工法では、安全性を100%確保できるとは言えず、結局早急に翌日対応なんですよ。
だから、14日の時点でもう脱線につながるような状況ということを判断したのか、緊急度と優先順位がどれぐらい高かったのかというのかということを教えていただきたいんですね。
可能性とすれば、早朝というのは出勤、それから通学、多くの市民の方に御迷惑をかけるというタイミングであるので、例えばどのぐらいの余力というか、余裕があったのか、なかったのか、方法としては仮に半日遅らせたりできたんではないかというのもちょっと考えられるので、そこの緊急度をどのぐらい判断されたのかというのを確認したいです。お願いします。
◎荒木敏雄 運行管理課長 委員お尋ねの1月14日のところでございますけれども、そもそも自動車、市電の通行を妨げない工法というのが、例えば交差点を3分割、4分割しながら、夜間工事で少しずつ剥いではレールを整正して、埋め戻してという工事を4日間、5日間ぐらい繰り返す工事というのを想定しておりました。
そうしたときに、全てのレールをむき出しにして、今回実際にしたときの工事みたいに、交差点すべて舗装を剥してということができないのですから、1か所、1か所を整正して戻すとなってくると、脱線のときに考えたようなひずみというか、横から補修したのにまた開けたところからのずれだとか、そういったところも影響するのかと考えておりまして、全て交差点を封鎖してやるという判断をして、確かにおっしゃるように、判断がちょっと遅れたところがございまして、1月14日の夜間も、11時過ぎになったと記憶していますので、そういったときからなかなか連絡を回すのが、報道とかには投げたんですけれども、当然報道も朝方しか入れないというところになりますので、連絡が遅くなったことに関しては、すごく申し訳なく持っております。
ただ、先ほどの部分的にやっていく方法では、ほかのところ、やったところに対してまた剥いだところからの影響だとか、そういうところを考えたときにやむを得ない判断だったのかなと考えております。
説明は以上です。
◆古川智子 委員 ありがとうございました。
今課長おっしゃったのは、工法として一遍にやるしかなかったということで、翌日から工事を着工するという判断を取られたと思うんですけれども、その工法に関しては納得がいくんです。
ただ、タイミング、例えば全部やるとしても、翌日早急にというよりも、1日空けるとかできたんではないかなというところでお尋ねをしたわけですけれども、1つは、これからも努めてほしいというのは、もちろん安全対策一番というのは先ほども申しました。市民の方にこれだけ不便さをどうしても影響として与えてしまうので、市民の方への理解を努めなきゃいけないと思うんです。
もう脱線の可能性がとても高まった。だから、皆さんの安全を担保するために申し訳ないんだけれども、翌日運休しましたよというところをもうちょっと伝えないと、これ本当にこのタイミングでよかったのかなと、もうちょっと空けても全然支障なかったんではないかなという疑念は生まれかねないので、本当にやるときは安全のためということをきちんとお伝えしていく。御迷惑をかけたところは謝罪していくしかないんですけれども、そういった今後もこういったことが起こり得ると思うので、緊急度が高いものはもちろんすぐやらなきゃいけない。だけれども、その点に関しては、きちんと御理解をいただくような周知方法に努めていただきたいなと思っております。
以上です。
◆村上誠也 委員 交-3になりますけれども、最終報告の中で、②でJR九州さんを講師に迎えた安全教室講話というのを1月16日にやられたということをお伺いさせていただきましたけれども、この講話の中で運転士の皆さんたちが参加をされてその講話を聞かれたと思いますけれども、この講話を受けられた後に運転士の皆さんたちに気づきとか、思いとか、どう違ってきたのかという意識を持たれるようなアンケートとかを取られたことはございますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 1月16日に、実際に講師の方に来ていただきまして、講話をいただきました。実際に参加した人間が30人、運転士と監督30人でして、うちが120人ぐらいいることから、その後に関しましては動画を撮ってそれを流すと。それがあった後にアンケートを取りまして、気づきだとか、そういったところを書き込んでもらう。その中では、やはり基本動作が重要ということが改めて分かりましたとか、講話の中で講師の先生がおっしゃったのが、市電もパイロットとかJRの運転士も一緒で、命を預かって人生を運んでいるようなもんだからと、そこはきちんと心に銘じてくださいみたいなことをおっしゃって、そういったことが心にしみましたということを書かれているのもありました。
以上でございます。
◆村上誠也 委員 ありがとうございます。
今おっしゃったように、こういう講話を受けられて、これだけ大きなインシデント等を含めて発生しているという事実を、しっかり認識していただく必要性があるんだろうなと思います。JRからこういう講話を受けられたことで、自分たちが今まで気づいていなかったこと、感じていなかったことをしっかり感じ取っていただく、それを皆さんに共有していただくというのが物すごい大事なのかなと思います。
交-3の前のページになりますけれども、管理のところで、乗務員の意見が反映されていないというところも書いてございます。指摘の中でですね、各委員の皆さんからお話があったように、乗務員さんだけで解決するような問題だけではないと私、多分委員さん思っていらっしゃると思います。
先ほどから線路の問題でありますとか、いろいろな形で交通局全体が一つになって動いていかないと、なかなかこういうところはきちっと対応ができていけない、そして運転士さん皆さんたちだけが命を預かっているんだという認識ではなくて、交通局自体がそういう認識を持たないと、運営する側、そして実際乗務する側が一体とならないと、そこはなかなか解決しない問題ではないのかなと思うところでもあります。
その一番多分いい例が交-1であるように、落ち葉で80メートル手前から速度制限しながら、25メートル手前でブレーキ操作を始めた。そして33メートルオーバーした。これというのは、多分今までもあっていたんだろうな、80メートル手前でブレーキかけて、25メートルかけていたら多分オーバーするんではないかなというのは、想像がつく問題ではないのかなと、私はちょっと考えているところです。
これについて運転士の皆さんたちと今まで何年も運転をされてきて、こういう時期はここら辺では遅いのかなという認識も多分あられたんではないかな、もし新しく採用された方々は、実績としてなかった部分というふうな捉え方をしっかりやっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 当該の運転士は、ここに記載ありますけれども、7年8か月と比較的長い経験年数を持っておりますけれども、このように滑ったという経験はないと話しておりました。
ただ、他の運転士に聞くと、当然このイチョウの時期というのは、滑走した経験を持っている運転士がたくさんおりまして、そういったところでスピードの制限だったりというのを用心しながらやっているところでございます。
当然ながら、このイチョウの木が生えているところはそういうふうになるんですけれども、ここの箇所というのが実はあまりイチョウの木がないところでございまして、交通局前とかあるところのイチョウから恐らく風とかで吹いて、そちらに流れていったのかなというところ、位置的なところから運転士もあまりイチョウの影響はないと判断したのかもしれないですけれども、ドラレコを見ると確かにレールの上に結構イチョウの葉っぱが何十枚、100枚以上とかというところで乗っておりましたので、当然ながらそういう滑走が起こり得る状態だったのかなと。ただ、経験は、本人はちょっとそういったところが今まではなかったというところを申しておりました。
説明は以上です。
◆村上誠也 委員 確かに、そういうこともたくさんあるかと思います。しかしながら、そこでこういうインシデントが起こったという事実には変わりはないと思います。
そこで、もしこの前後で運転士さんが気づいたらば、次からあの辺は今日は危ないぞという注意喚起をする必要性は必ずあるんだろうなと思います。これを見ただけでも、25メートル手前でブレーキ操作して33メートルということは、60メートル近く手前からもう操作を始めないと、このときは、この時間帯含めてやらないと間に合わないぞという認識を持っていただく。それが必要かな。
でないと、我々も普通車を運転したりしますけれども、危ないところは注意して、あそこは危ないよという情報交換したりというのが多分出てくると思いますので、そういうところを認識づけというのをしっかりやっていただかないと、運行側、そして乗務していただく運転士の皆さんたちと一緒になってやっていただくというのを心がけていただきたいと思います。
以上です。
◆井本正広 委員 齊藤委員からも最初に指摘があったんですけれども、今の件でこれだけインシデントが続いているのに、運転士さんは信号冒進とは考えず、指令への報告を行わなかった。私はここが一番肝だと思います。これを受けて、事業管理者としてどういうふうにこれを思われたか、この後、どういう行動を取られたか、そこをお聞きしたいと思います。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今お話ですけれども、ヒヤリ・ハットという観点からも、今村上委員からも話がありましたけれども、そこは必要だったと思っています。
ちょうど落ち葉の時期に私も何度か乗車する中では、きちんとどこが滑ると無線で報告をしている運転士が何人もいました。そうすると、無線の中で分かったという話と、大至急砂まきをそこの場所に向かわせるからとか、今どこでやっているから、その後そこに行かせるからとか、人によってはどれくらい滑るのかとか、そういった緊急度を図るとかというやり取りも、電車と指令でやっているというのも、私何度も電車の中でそういうのは見聞きしました。
今回のことはインシデント云々もそうですけれども、ヒヤリ・ハットという観点からも、数分後には次の電車が来るわけですので、それをしとればそこは用心して、次の運転士は特に用心して運転したと。この運転士については、幸いにして事故等はありませんでしたけれども、その次に滑った場合にはそうとは限りませんので、そういった観点からも、重要だというお話は、この当該運転士も含めて話をしたところです。
確かに自分だけに考えてしまっていて、車の通行にも、当然事故も起こっていないし、車の通行にも影響がないからしなかったということは聞きましたけれども、そうではなくて、全体の安全を高めるという観点でも、あなたの報告というものは大事だったんではないかという点については、当該運転士と話をしたところでございます。
以上です。
◆井本正広 委員 今回の検証委員会の最終報告の中で、課題と対策の中で、人、もの、環境、管理、基本ルールの不徹底ですとか、視野が狭く偏った対策、ヒューマンエラーですとか、モチベーションが低いですとか、かなりすごい指摘があっております。
最終的に、組織風土の改善等ということが書かれているわけなんですけれども、そういう観点でヒヤリ・ハットはあるんですけれども、報告をしなかったということについて、これは組織として考えていかなければいけないというのが一番重要ではないかなと。様々原因はありますけれども、まずは風通しが悪い、組織報告がないということが大変一番重要だと思っております。
この報告書を受けて、6項目について書かれておりますけれども、これだけではちょっと足りないんではないかなと思います。ですから、またこの報告を受けてしっかり組織風土、風通し、モチベーション、本当にこれからもっともっと深く検討していただきたいと思います。すぐにできることではないかと思いますので、よく検討を深めていただきたいと思います。
以上です。
◆齊藤博 委員 延伸事業について簡潔にお答えいただければと思いますが、軌道運送高度化実施計画に関して、これは今までのインシデント等を勘案すれば、延期せざるを得んというのはよく分かります。
その中で、軌道運送高度化実施計画の中に直接的に盛り込まれておりますのは、例えば上下分離だったりとか、市電の延伸、こういったスケジュール感をこの計画に当然うたわれるわけでありますけれども、上下分離については、市長からも1年程度延期すると、それから延伸については、改めてスケジュールの再検討を行うというようなことが示されております。
ただ、そのほかにも上下分離やそういった延伸のスケジュールのみならず、例えば従前から議論が出ておりました職員の皆さん方の処遇改善、給与水準を引き上げましょうというような話が出ておりましたり、これは一応4月から予定をしているはずですけれども、それでありますとか、あるいは今年6月から予定をしましょうということで、運賃の200円への値上げ、こういったものに軌道運送高度化実施計画を見直すことで影響が出るのか出ないのか、特に職員の処遇、4月からの改善に向けた取組に変更はないのか、その確認と、それから6月をめどに200円の運賃に改定をしたいというような動きに、まだ確定ではないにしても、その動きに変更はないのか、そこ2点まずお聞きしたいと思います。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 まず1点目のお尋ねの処遇改善等による影響等についてでございますが、高度化実施計画自体は法定で定められている項目でございまして、高度化事業を実施する区域内容、それから高度化事業の実施の予定期間、そういったものが法定の項目として定められております。
処遇改善については、法定の項目ということではございませんが、高度化実施計画の中に参考資料として収支状況をお示しする形になりますので、処遇改善による人件費ですとか、あるいは車両の更新とか、そういったもので収支が変わったものについては、そこの収支状況の中で反映させていくという形になります。
2点目の今後のスケジュール感についてでございますが、まず処遇の改善につきましては、今年3月の定例会におきまして、条例改正等を上程させていただきたいと考えております。それで可決いただきましたならば、4月から乗務員等の処遇改善は、上下分離導入に先行して行ってまいりたいと考えております。
具体的には、給料表の拡充だったりとか、あるいは扶養手当、住居手当といった新たな手当の支給というところを予定しております。
それと運賃改定についてでございますが、運賃改定につきましても、直接的に高度化実施計画の項目ということではございませんが、ただ、これにつきましては、上下分離導入の有無にかかわらず、直近の交通局の経営状況、非常に人件費高騰や物価高騰で厳しい状況でございますので、上下分離実施の有無にかかわらず、導入すべき運賃改定を行いまして、処遇の改善、あるいは安全の再構築とか、そういった面に充てさせていただきたいと考えておりますので、これにつきましても、3月に条例案を上げさせていただきまして、その後、国への申請、認可を得て、6月に運賃の改定をさせていただければということで考えておりますが、また改めまして、3月の定例会でお示しをさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
職員の処遇は、予定どおり4月からということで改善を図っていただきたい。そんなふうに予定もスケジュールも変わらないということでありました。
それから、運賃の値上げについても6月から200円にということで、ここも変わらないということでありますけれども、今年に入ってからまた今後インシデントが起こるような事態に直面すれば、こういった計画に市民の皆さん方、あるいは利用者の皆さん方の御理解を得にくくなるというようなことにもつながってきますので、ぜひそういう意味においても、計画遂行できるような環境、安心・安全な運行に努めていただきたいと改めて思うところでもあります。
それともう一つようございますでしょうか。
○田中敦朗 委員長 どうぞ。
◆齊藤博 委員 市電延伸の実施設計、これ市電延伸そのものの計画を延期するということでありますので、今年度中に実施設計を行うとなっておりました予算です。今年度、令和6年9月に承認されている予算なんですけれども、4億2,000万円、これ補正かけますか、かけませんか。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今年度9月補正の中で、市電延伸の実施設計に係る補正予算可決いただきまして、今年度の契約を目指して事務を進めてきたところではございます。
ただ、こういった今の市電の状況を鑑みまして、スケジュールについて再考させていただきたいということで、今後の進め方についてお諮りしているところでございますけれども、今後議会からの意見も踏まえまして、最終的には判断したいと考えておりますが、延期ということになれば、今年度の予算については減額補正を行うという形になろうかと考えております。
以上です。
◆齊藤博 委員 もう一回ちょっと確認なんですが、減額補正でいくのか、あるいは繰越しというやり方もできんことはないかもしれませんが、それは担当局でお願いします。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今回の実施設計に係る予算につきましては、国からも交付金の内示をいただいているところでございます。市単独予算ということであれば繰越しということも考えられるんですけれども、今年度設計を実施しないということになると、なかなか国費の繰越しというところが難しくなると。そうなると、一旦全額ですね、減額せざるを得ないのかなと考えてございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 当時の説明資料の中に、今まさに出ました国庫補助金72億円程度が見込まれていると報告を受けております。延期することによって国庫補助金そのものの妥当性といいますか、いやいや延期するならちょっとそこまでは担保できんよと、当然国も今年度の予算として上げていたところでもあろうかと思いますし、その影響ですね。延長することによって、今まで令和6年度に示された総事業費が141億円と見込まれております。その中でその半分、国庫補助金が72億円というような見込みを上げていただいていますが、この総事業に大きな影響がないのかどうなのか教えてください。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今回の市電延伸の事業スケジュールの見直しにつきましては、計画内容そのものに何か問題があるということではございませんで、今の市電の状況を鑑みて、一旦立ち止まるべきではないかと考えているところでございます。
そういったことから、延伸事業の計画内容、総事業費141億円というところでお示ししていますけれども、そこについては変更はないといったところでございます。
国費の影響でございますけれども、まず前提としまして、今、国から内示をいただいている予算というのは、今年度実施する予定だった実施設計に対する予算4億2,000万円に対する国費の内示をいただいていたところでございます。その後の用地買収、工事実施に当たっては、その年度の必要な額をその都度要求していくという形になってございますので、この72億円という国費が担保されているというわけではございません。
ただ、今、国へ市電の状況というのを説明していく中で、国からも今の現状については御理解いただきまして、予算については今後市の方針を踏まえて調整をさせていただくというところで協議を進めているところでございます。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
今のところ延期はするけれども、総事業に変更はないというようなことで理解をさせていただきました。ありがとうございました。
◆上田芳裕 委員 延伸に関連しまして、今、国からの補助関係の影響はないというようなことでお聞きしましたけれども、昨年9月に実施設計の予算を可決して、熊本市でもいろいろな動き、募集とか、動きはあっていますけれども、そういったところで業者さんへの影響がないかというところが1点と、昨年、市電延伸の周辺の皆さん方へ住民説明会を行って、延伸の計画であったり、用地買収について大体どこら辺のエリアが計画されてあるとか、工事そのものの複線化、単線化とか、供用開始が令和13年度とかというところを詳しく説明をされていると思っていますけれども、住民の中から、その中には一日でも早く延伸をしていただいて、市電の効果、自分が乗ることへの効果、渋滞が減ることへの効果を含めて望まれている方がいらっしゃると思いますけれども、そういった方々への今回市長からのマスコミ報道で皆さん知られたと思うんですけれども、細かな説明であるとか、そういった部分は何かお考えございますでしょうか。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 まず、業者への影響、入札等に関することかと思いますけれども、発注業務に当たって設計業務に必要な見積り等を取っているといったところがございますけれども、まだ設計の委託の発注に係る公告等行っている段階ではございませんので、それについては今のところ影響はないかなと考えてございます。
2点目の住民説明会、あと地権者、中には進めてほしい方もいるといったお話でございますけれども、そのとおりかと思います。まだ延期ということを決定しているわけではないんですけれども、延期するということになれば、当然地域の住民の方々、地権者の方々に今の市電の現状を説明した上で、御理解を求めていく必要があるのかなと考えてございます。
以上です。
◆上田芳裕 委員 分かりました。
業者の方へは影響がない、住民の皆さん方へはスケジュールの変更を決定していないという言われ方をされるんですけれども、正式には決定ではないんでしょうけれども、そのような方向で進められていく、決定というのはどの場でされるか、今度の定例会になるのか含めて明確にお示しができればお願いします。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 まず、先週の金曜日に市長から、市長の考えとして、延期も含めたスケジュールの見直しを指示したという市長の考えを表明されたところでございます。
今回、今の現状を踏まえて、一旦立ち止まるべきではないかといったようなことについて、この委員会の中でもお諮りした上で、御意見をいただいた上で、最終的には判断していきたいと。その結果、延期するということになれば、今度の議会、第1回定例会の中で減額の補正予算案を上程させていただいて、分科会等で御議論いただくと。そこで可決されれば、そこで延期が決定ということになろうかと考えております。
以上です。
◆上田芳裕 委員 分かりました。
そのような心づもりで定例会に臨んでいきたいと思います。
◆上野美恵子 委員 今の延伸の件で、私から1つお尋ねは、さっき齊藤委員もちょっとお触れになったんですけれども、いろいろな交通局のインシデントが続いているので、すごく市電に対する市民の皆さんの不信というか、疑問というかが、とても過去にないくらい、心配も含めて高まっているかなと思います。
そういう中で、さっき運賃値上げは、財源にもなるから粛々とするのだという御答弁であったかと思いますけれども、市民感情からするなら、そこのところの理解というのは、局側はそうかもしれないけれども、市民の感覚としては、非常に理解し難いと私は思います。
値上げの理由も、これまでの一般会計の繰入れのこともあるし、もう一つは乗車人員のこともありますし、いろいろ理由はありますけれども、それをこれだけ市民の疑問が高まっているときに、いや、それはそれ、これはこれだから値上げはしますというのは、どう考えても納得しないのかなと思うんですよね。
それこそこんな時期だから、安全をきちんと確保して、担保した上で、そういう安全の条件が確保された上で、運賃についても提案をしますということならば、理解もあるかもしれないけれども、全然市民の感覚と交通局としての対応というのは、齟齬があるのではないかと思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 委員から御意見いただきましたとおり、現在市電におきましては、昨年16件のトラブル等がありまして、信用は失墜しているという状況かと思います。
ただ一方で、繰り返しになりますけれども、交通局の経営状況というのは非常に厳しい状況でございまして、こういった安全対策をしっかり再構築していくこと、それから乗務員の処遇改善を行っていくことということから運賃の改定をお願いするものでございまして、市民の方々へも丁寧に説明を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 いろいろおっしゃっても、なかなかそういうのには市民感情としてはついていけないんではないかなと私は思います。
運賃の件についてはもう少し丁寧な取組というか、今の繰り返しではなくて、市民に対しての丁寧な説明とか、意見聴取とか、そういうことを改めてしないと、利用にも関わってくるんではないかなと思いますので、その点はよろしくお願いします。
もう一つは、先ほどから意見が出ておりましたインシデント等に関する検証委員会の件で、いっぱい聞きたいことはあったんですけれども、1つに絞って聞きます。
概要版と本編と資料として以前いただいていましたので、拝見したんですけれども、いろいろ現状も明らかにしながら検証委員の方々が検討されて、そしてまとめをつくっておいでになったんですけれども、まとめに関わるところで、委員さんたちから、委員会としては問題解決に向けた視点が2つあるということで、1つは、相互尊重と理解を促進する視点の転換、もう一点が組織ぐるみの意識と行動の変革というこの2点を上げられて、提言としては、概要版では、次のページに7点の項目を上げられていたんですよね。
これも相互信頼から始まって部署間の風通しであったり、意識と行動の改革であったり、新しい視点からの研修や教育であったり、バランスの取れた人材確保とか、仕事環境の整備ということで、いかにこの事業に関わる交通局の方々の、交通局という組織そのもの、そしてそれを構成する職員のお一人お一人の在り方について問われていたのかなと思って拝見しました。
そういうのを基にして本編を読んだんですよね。それの77ページ~78ページのところに向けて気になること、提案したいことなどというのがあったんですよ。そこでハラスメントのことが述べてあったんですよね。職員からの多分御意見として、嘱託職員との格差がパワハラ、モラハラの温床になっているということと、それからパワハラ等が多くて毎年数名が心を壊しているという言葉があって、それに対する委員さんたちの所見なのかな、まとめみたいなものがあって、それについての範囲や程度は明らかではないが、ハラスメントをはじめとして職位間に軋轢が存在していることがうかがわれるという記載になっていたんですよね。
これを読んだときに、さっき紹介しました今回の検証委員会の提言、そのまとめに当たる部分が、この組織と一人一人の職員の在り方に関わる問題であっただけに、そしてこの本編には出てくるんだけれども、概要版にはパワハラなんて言葉は出て来ないんですよね。
そして、本当に交通局が今回のインシデントという重大な事態の多発を受けて、組織を改革して、お一人お一人の職員の皆さんが一丸となって、交通局の今後の運営について改善していこうと思うためには、こういうパワハラをたくさん訴えている人がいながら、こういうことを改善せずして先に進むというのは、私は難しいんではないかなと思うんですよね。
今はいろいろなところで、いろいろな場所でこういう問題が多発していて、問題になって、でもこの向き合い方をきちんとせずに、疎かにしてしまえば、先々に禍根を残していくことにもなるし、どんなに言葉ではいいことを言っても、結果的に何一つ改善にならないと思ったんです。
これがきれいな提言の概要版になったときに全くなくて、一体どうするんだろうと思ったんですけれども、この問題については、私はきちんと具体的な事実をそこの局の中では明らかにしていきながら、意見をおっしゃった方たちに対して、納得のできるような方向性として改善方向というのを見いだしていかないと、職員が一丸となってこのインシデント問題に取り組んでいく、改善させていくというふうにはなっていかないんではないかなと思ったんですけれども、どのように今受け止めておられますでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 検証委員会が5月から始まりまして、そこと併せて事業管理者、次長と運行管理課長、私、当時、副課長でしたけれども、4人で運転士の方の全員と、20人ずつぐらい面談をいたしました。
そういった中でも、確かに人間関係の話とかが出てきまして、運転士が大体10年ちょっと経験すると、監督職になるという、営業所の中の立場というのがございますけれども、運転士が今会計年度任用職員、こちらで嘱託と書いてありますけれども、そういったところの立場で、監督さんの中にはもともと交通局採用の監督さんがいらっしゃるといったところで、人間関係の中にちょっと壁というか、そういうのがあるというのは、そういう面談の中で感じ取れるところはありました。
ただ、それぞれの方ときちんと向き合って話をして、そこで自分たちができることというのをやっていて、進めていかないと何も変わらないのかなと思っておりますので、その後にも事業管理者は、例えば工場の技工さん全員と面談したりとかされていますし、そういったことを繰り返していって、聞いたことに関して対応していくということをやっていきたいと思っております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 全ての運転士さんと面談をなさったときには、おぼろげにそういう実態があるのではないかという程度での多分訴えであったと思うんですよね。はっきりパワハラがあるんですよとかと、個別に面談しているときに自分自身をさらして言えるような方というのは、多分おられなかったんだろうと思います。だけれども、あえてこの職員の調査の中で出てきているということは、事実があるけれども、名前を出してまでは言えないという、そういう問題だからですよね。
だから、ちゃんとした対応をしないと、これというのはうやむやになっていくし、改善していかないと思うんですよね。だから、どういうふうにしたら一番いいのかというのは、ここで具体的に私から言えないんですけれども、ただ、これをこのまま放置はしてはいけないと思います。
何らかの形でそれを改善していく、具体的、個別的にやっていけるようなことをしていかないと、このインシデントの改善の検討の提言そのものが上滑りしてしまうというか、上っ面のものになってしまって、本質的なところでは、職員が一丸になるということは、できないんではないかなと私は思いますので、この点については、さっき私が言った軌道とかハード面はもちろん基本ですけれども、その上によって立つソフト面における人というか、そこをきちんと束ねていって、みんなが本当に一丸となってやっていく、そこにおける取りまとめをしっかりしていく。そういう意味での交通事業管理者の役目というのがすごく大事かなと思いますので、ちょっと答えは出ることではないのかもしれないけれども、事業管理者の御意見を聞いておきたいと思います。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今御指摘いただいたことについてでございますけれども、確かに私も職員一人一人と話をする、ずっとしておりますけれども、そういった中でも、今委員の言われましたように、直接的にとかということはなくても、話というのは出ております。
そこにはどうしても、何というんでしょう、車両も古くて、運転士とかも減っていってということがあって、その中で回していかないといけない。運転を欠便することなく回していかなければならないということで、ちょっときつい言い方だったりとかということもあったのではないかなと思っておりますし、一人一人の話を聞いて全体としてどういったことがあったのかというものを突き止めることは当然ですけれども、そういう観点で減便とかもして、まずは働きやすい環境とかということに努めたところです。
といって、それが全てではありませんので、何がどこに、訴えられている方のところがどこなのかというのはきちんとしていく必要があると思っております。
すみません、先ほど本文と概要版の違いということも言われて、そこについては申し訳なく思っておりますけれども、その概要版のことをすればいいと思っているわけではなくて、きちんと報告書全体を精査して、そこに書かれている課題というものについては、全て対応していくということが基本であると思ってございますので、きちんと職員みんなで内容を精査して対応を考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
◆上野美恵子 委員 ここには、この問題については信頼関係だということが書いてあるんですけれども、そのことを抜きにして、今後の交通事業の改善とかはあり得ないなと私は思いますので、ぜひ心して対応していただくようにお願いをしておきます。
◆島津哲也 委員 交-2の裏面のところで、先ほど古川委員の質問がありましたけれども、1月15~16日に緊急の工事がなされたということで、非常に緊急で安全性が確保ができないということが書いてありますけれども、15日の始発から区間運休ということになったということで、市民の方にうまく伝わらず、利用者の方に混乱を招いたというニュース報道も流れていました。SNSでの発信をされたということですけれども、公式のLINEだけだったのでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 まず、報道に深夜だったかと思いますけれども、投げさせていただきました。あと、市のホームページ、局のホームページ、あとはXとデジタルサイネージ、使える手段というのは、こちらとしても使って広報したところでございます。
以上です。
◆島津哲也 委員 そうですね、いろいろなものを使って、学生さんだとインスタとか、そういうのも使われていますし、ちょっと調べましたら、交通局さんもXがありますけれども、交通局さんのXからは発信がなかったので、こういうのも使われたらいいのかなと思いました。
皆さんにできるだけ伝わるように御努力いただければなと思います。
私からは以上です。
◎荒木敏雄 運行管理課長 Xでもたしか投げ込みはしていたかとは思います。すみません。
◎井芹和哉 交通事業管理者 補足で。
ずっと出ているのが残りますと混乱しますので、次の局面になったときには、落としたりとかとしておりましたので、経緯が全部は出ていなかったかと思います。すみません。
○田中敦朗 委員長 ほかございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 ほかにないようであれば、本日の調査はこの程度にとどめたいと思います。
さて、前回の本委員会において決定しております参考人の意見聴取のための委員会開催につきましては、改めて参考人との調整が必要となりますことから、本職に御一任いただき、決定次第連絡をいたします。
これをもちまして、地域公共交通に関する特別委員会を閉会いたします。
午後 0時43分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 三 島 健 一 総括審議員 村 上 英 丈
総合政策部長 黒 木 善 一 政策企画課長 松 永 直 樹
〔財 政 局〕
局長 原 口 誠 二 財務部長 濱 田 真 和
財政課長 津 川 正 樹
〔都市建設局〕
局長 秋 山 義 典 技監 上 野 幸 威
都市政策部長 高 倉 伸 一 都市政策課長 飯 田 考 祐
交通政策部長 迫 本 昭 交通政策部首席審議員
濱 口 佳 久
交通企画課長 大 川 望 移動円滑推進課長 徳 田 隆 宏
移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 自転車利用推進課長酒 井 伸 二
太江田 真 宏
〔交 通 局〕
交通事業管理者 井 芹 和 哉 次長 松 本 光 裕
総務課長 吉 岡 秀 一 運行管理課長 荒 木 敏 雄
運行管理副課長 北 添 友 子
地域公共交通に関する特別委員会会議録
開催年月日 令和7年1月27日(月)
開催場所 特別委員会室
出席委員 12名
田 中 敦 朗 委員長 平 江 透 副委員長
木 庭 功 二 委員 村 上 誠 也 委員
古 川 智 子 委員 中 川 栄一郎 委員
島 津 哲 也 委員 齊 藤 博 委員
井 本 正 広 委員 藤 山 英 美 委員
上 野 美恵子 委員 上 田 芳 裕 委員
議題・協議事項
(1)持続可能な地域公共交通の実現に向けた諸問題に関する調査
午前10時30分 開会
○田中敦朗 委員長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから地域公共交通に関する特別委員会を開会いたします。
本日の議事に入ります前に、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可します。
◎井芹和哉 交通事業管理者 おはようございます。
まず、おわびでございます。
昨年12月21日に、大江5丁目交差点において、またも市電が信号冒進、いわゆる信号無視をするインシデントが発生いたしました。
また、12月31日には、熊本城市役所前停留所から花畑町停留所方面に向かう区間で、脱線という重大事故を引き起こしてしまいました。
さらに、運行再開後、脱線箇所付近のレール幅に広がりが確認されましたことから、緊急に軌道の修正する工事が必要と判断をいたしまして、1月15日から2日間区間運休をいたしました。
後ほど原因や対応につきましては、詳細な報告をさせていただきますが、度重なる事故やインシデントの発生を受け、局を挙げて再発防止に取り組んでいる中、また、インシデント等外部委員会での最終取りまとめの時期に前後して、このような事態を引き起こしてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
市電を御利用いただいている皆様をはじめ、市民の皆様に対しましては、年末年始の外出に御不便をおかけし、また、度重なる運行トラブルにより大変御迷惑と御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
それから、次に御報告でございます。
去る1月1日付の人事異動により、交通局運行管理課に北添副課長が着任いたしました。同時に、安全管理体制をより強固なものにするため、北添と同じく異動でまいった事務職員2名と運輸職員4名の計6名で構成する安全対策チームを運行管理課内に新設いたしました。安全対策を専門部署で一体的に実施する体制とすることで、より効果的な安全対策とノウハウの蓄積による人材育成を図り、一日も早い熊本市電の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○田中敦朗 委員長 発言は終わりました。
これより本日の議題に入ります。
本日は、執行部より申出のありました信号冒進(インシデント)について、熊本城・市役所前停留場付近の軌道の不備について、インシデント等外部検証委員会の最終報告について、市電延伸事業について説明聴取を行うため、お集まりいただきました。
それでは、調査の方法についてお諮りいたします。
調査の方法といたしましては、まず、執行部から説明を聴取した後、質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
それでは、執行部の説明を求めます。
◎荒木敏雄 運行管理課長 資料交-1をお願いいたします。
12月21日、土曜日に発生した信号冒進(インシデント)についてでございます。
経緯は、左下に書いております。場所が、交通局前電停から味噌天神電停に向かって発車した電車が、デイリーストアがある交差点、鎮西高校から出てくるところになりますけれども、そちらの交差点に差しかかったところで冒進したものでございます。
経緯といたしまして、信号が赤だったために、停止線の約80メートル手前から速度調整しながら、約25メートル手前でブレーキ操作を開始したものです。しかしながら、イチョウの落葉の影響により滑走しまして、横断歩道を越え、停止線約33メートルの交差点内で停止したものです。鎮西高校から出てくる自動車には、支障のない位置で停止したものでございます。
運転士は、滑走によるものであるため信号冒進とは考えず、指令への報告は行っておりませんでした。外部からの通報を受け、ドラレコで事実を確認したものでございます。けが人は発生しておりません。
右側2番、発生原因でございますけれども、イチョウの落葉の影響により滑走し、適切な位置に停止できなかったものでございます。
3番、再発防止策といたしまして、全運転士、監督に対して事案を周知、また、滑走が発生する12月、1月におきまして点呼等で周知いたしました。
また、運転士によるレール状況の報告、滑りやすいだとか、イチョウの葉っぱが落ちるだとかというところを、無線で指令に上げるということを徹底しております。
加えまして、以前からやっておったんですけれども、滑り止めの砂まきというのを始発前の5時ぐらいからと、当日も朝方に1回まいておりました。そういったもので、滑走を防止してまいりたいと思っております。
また、落葉が大量にある場合は、速やかに営業所から出向いて撤去してまいりたいと思っております。
さらに、全運転士に対して以下の2点を周知しておりまして、1点が落葉を確認した場合、早めのブレーキ操作を行うこと、2点目が滑走や信号冒進が発生した際、運転指令への報告を徹底することというのを指示しております。
交-1に関しては以上です。
続きまして、資料交-2をお願いいたします。
熊本城・市役所前停留所付近の軌道の不備についてでございます。
2項目ございまして、1番として12月31日、大みそかに発生した脱線事故(重大事故)でございます。
左側に経緯を書いておりますけれども、熊本城・市役所前電停から花畑町電停に向けて出発した電車が脱線したものでございます。乗客30名、乗務員2名にけがはございませんでした。
運転士が脱線を確認し、運転指令に報告の上、乗客を車外に誘導しております。脱線直後から水道町、辛島町間を上下線ともに区間運休しまして、レールの補修工事を行った上で試運転を行い、1月3日の始発から全線で運行を再開しております。
右上が現場の状況写真になります。奥の市役所方面から写真手前の花畑町方面に電車が進行している際に、「脱線痕」と書いてある緑色の矢印で示したところ辺りで脱線をしておりまして、進行方向の左側10センチぐらいずれたところをずっと走行しているというものでございます。
舗装を剥いだときの状況が右側の絵で描いておりまして、枕木の上にレールが乗っておって、そのレールを止めるのが犬釘という大きなくぎで止めているんですけれども、そちらが完全にずれて25ミリの隙間があって、完全にレールを抑えられていない状況というのが確認できました。
この要因といたしまして、軌間が基準値から最大で39ミリメートル超過していたというものでございます。
2番の発生原因でございますけれども、レール幅が基準値を超えた箇所があり、右カーブで左側に遠心力が加わりまして脱線につながったと推定しております。
次のページの資料を見ていただきますと、絵の左側のところが今回の12月31日の脱線箇所でございまして、右側の市役所方面から進行してきたときに、やや右カーブになっておりまして、それで左側、図でいう下の方に遠心力がかかりまして、脱線したものでございます。
また、この絵で緑の十字のところのポイントが青点線の横にありますけれども、そちらが脱線の3週間前、12月7日にレール整正、レールの幅を狭める工事というのを行っておりまして、その間隔が近すぎるということで、その間にレールのひずみが生じまして、また、車両の通過の振動によって徐々に広がったものと推定しております。
資料にお戻りいただきまして、3番、対策についてでございます。
広がった軌間というのを狭めるようにレール整正工事を実施、また加えてレールのひずみ、影響がないように円を切る形でレールを切断しまして、レールの長さを調整しております。
施工後もレール変位を定期的に観測いたしまして、変位が見られないことを確認できるまで、運行時上限15キロというのを設けております。
また、全面的な改修、下地から全部やり換える軌条交換というのを今年秋~冬にかけて実施する予定としております。
こちらに関しましては、先ほどの図の1月15日、16日の整正箇所も、同じく交差点部分のところは軌条交換を実施したいと考えております。
資料交-2の2枚目をお願いいたします。
1月15日、16日発生のレール緊急整正工事でございます。
先ほどの図の左側が大みそかの脱線箇所でございまして、その右側、市役所に近いところの交差点というのが今回の整正工事の場所になります。
図で描いておりますように、黄色の吹き出しに書いておりますように、1月7日、レール幅の広がりというのを確認しております。ただ、脱線箇所で見られたようなレールの動きだとか、レール横の舗装に車輪が接触した痕というのがございませんでしたことから、早急に脱線につながる状況ではないと局内で判断しておりました。
それで徐行運転に加えまして、運転士が通行中に異音、振動等が感じられた場合にはすぐ報告するように、また併せて自動車の通行や市電の通行を妨げない工法というのを合わせて検討しておりました。
1週間後の1月14日、再度検測いたしまして、また、夜間に実際に電車での試運転というのを実施したものの、このままだと安全性が100%確保できないと考えまして、自動車や市電の通行を妨げない工法で実施するのは困難と判断したものでございます。
そこで区間運休しまして、全対象区間の舗装を剥ぎ取った上で、整正する工法の選択を決定したものです。
1月15日始発から先ほどの大みそかの分と同じく水道町、辛島町間を区間運休いたしまして、緊急整正工事を実施しました。試運転後に1月17日の始発から全線運行再開しております。
3番、1月22日九州運輸局からの指摘事項及び今後の対応についてでございます。
この2回の工事等を受けまして、九州運輸局から文書で「軌道の安全輸送の確保について」というのが発出されております。もともと9月20日に改善指示が出ておりまして、それに加えまして指摘が2点ございました。
1番としまして、全線の軌道について安全性を再確認すること、2番といたしまして、軌道の維持管理の方法について検証を行うとともに、この2件の背後要因を含めた原因究明と再発防止策を策定すること。
今後の対策といたしましては、番号が対応しておりますけれども、1番といたしまして、今年度内に現時点で軌間拡大が確認されている5か所は、整正工事を実施するとともに、全線の軌道の検測を実施いたします。
また、その検測の結果、問題がある箇所に関しましては、早急に整正工事を実施したいと思っております。
②維持管理の方法についてでございますけれども、検測間隔の基準の見直し、今20メートル間隔で測定しておりますけれども、それを半分の10メートル間隔に狭める等を検討してまいりたいと思っております。こちらは、運輸局と相談して決定したいと思っております。
交-2の説明は以上です。
続きまして、交-3をお願いいたします。
インシデント等外部検証委員会の最終報告についてでございます。
1月10日に、検証委員会から市長に最終報告書が提出されました。6回にわたる会議での検証と対策、会長と委員が局職員に取られたアンケートの調査結果を踏まえた提言というのがなされました。それを受けまして、今後のインシデント等の再発防止に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
左側1番、課題と対策でございます。
ひし形で課題、四角囲みで対策を書いております。
ジャンルといたしまして、人、もの、環境、管理の4つに分けておりまして、人の代表的なところでいきますと、一番上の基本ルールの不徹底、指導・教育等の効果確認不足の対策といたしまして、初期教育の充実、個人教習の強化と効率的な効果確認等を行ってまいりたいと思っております。
続きまして、ものといたしまして、ヒューマンエラー防止に係る物理的対策が不十分ということでございますけれども、こちらは後で出てきますけれども、IP無線の設置等を考えてまいりたいと思っております。
また、車両、設備の老朽化による不具合ということでございまして、今年11月に2台導入しましたような新車両というのを計画的に導入してまいりたい。また、軌条交換といって全部レールをやり換える工事というのを計画的にやってまいりたいと思っております。
続きまして、環境でございますけれども、モチベーションが低いということに関しましては、対策として乗務員の処遇改善、コミュニケーションの促進等を行ってまいりたいと思っております。
続きまして、管理に関しましては、安全について組織としてマネジメントができていないことに関しまして、1月1日付で設置しておりますような「安全対策チーム」など体制の強化を図ってまいりたいと思っております。
このように御提言いただいた対策のうち、「安全対策チーム」の設置等一部については既に実施済みでございますけれども、その他の取組についても可能な限り迅速に対応してまいりたいと考えております。
右側、2番、交通局職員への会長、委員のアンケート調査を踏まえた提言ということでございます。
現状の問題点として、3点指摘されております。1番として、リスク及び危機管理システムの問題、これは組織全体としてリスク管理ができていないんではないかという問題があるということです。2番といたしまして、組織におけるコミュニケーションの問題、3番といたしまして、職種間、事務職と技工職、運転士だとか、そういったところに壁があるんではないかという指摘があっております。
それで、問題解決に重要な2つの視点というので捉えられた提言というのが、下の7項目になります。
①番といたしまして、相互信頼の醸成、②番として、部署間の風通しの改善、③番で意識と行動の変革、④番で新しい視点からの教育・研修の充実、⑤番で第三者によるサポート、⑥番でバランスの取れた人材の確保、⑦番で仕事環境の整備、こういった組織風土の改善と組織の根幹に係る視点というのも含まれておりますため、今後の取組に適宜盛り込んでいくとともに、長期的に取り組んでまいりたいと考えております。
最後に、直近の取組でございます。次のページをお願いいたします。
検証委員会からの提言、また9月20日の九州運輸局からの改善指示というのを受けまして、取り組んでいる代表的な6項目について書いております。
①番として、「安全対策チーム」の設置、こちらは1月1日付で実施しております。乗務員の育成、資質管理、指導教育、事後防止対策に加え、各部門間の連携を図る目的で設置しております。
実際には写真にありますように、車内や交差点等、現地において、基本動作の実施状況の確認をはじめ、安全に係る取組などを実施中でございます。
②番といたしまして、JR九州を講師に迎えた安全教育講話の実施でございます。これは先々週の1月16日に実施したものです。安全に関する専門知識や安全意識に関する外部のノウハウというのを学びまして、基本動作の徹底や安全意識の向上を図るものです。
③番といたしまして、信号見落とし防止に係る補助表示装置の設置、こちら9月補正で上げていたものになりますけれども、写真の黄色枠の下にある信号がもともとついていた信号でして、そちらを見落として進行して冒進したことから、その上により明るく光る、点滅する信号を補助的につけまして、運転士に注意喚起をするものでございます。
右上、④番、ドア開け走行防止に係る注意喚起装置の設置、こちらも9月補正で上げておりましたものですが、車両の中間ドアが開いた状態で走るというインシデントが発生したことから、開いている間はポーン、ポーンとチャイムで知らせる装置を年度内に全対象車に設置する予定です。
⑤番で、軌道検測機の導入ということでございますけれども、現在、手検測で、大きな定規のようなものでレールのチェック、測定を行っておりまして、1,200ポイント、測定ポイントがありますことから、2か月ぐらいかかって測定していたところを、この新しい検測器でころころ転がした形で検測することで、二、三週間ぐらいで測定できるんではないかと考えておりまして、作業の効率化と点検頻度の向上を図りたいと考えております。今年度中に導入予定です。
⑥番でIP無線の導入、こちら運転士の要望1位でございまして、現在の無線は地形やビルなど障害物の多い場所で度々通信不能となっておりまして、安全面やストレス面でも負担が大きいものとなっております。そこで、既存無線は残しつつ、補助的な連絡手段としてIP無線を導入するもので、今年度中に全車に導入する予定です。
説明は以上です。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 資料都-1、市電延伸事業についてでございます。
市電延伸事業につきましては、これまで特別委員会をはじめ、市議会における議論を通じまして、着実に検討を進めてまいりました。第3回定例会におきましては、実施設計に関する補正予算を可決いただいたところでございます。
一方で、市電の運行につきましては、昨年からの相次ぐ運行トラブルを受けまして、上下分離の実施時期を延期すること、また、安心・安全の観点から軌道運送高度化実施計画を精査することを公表いたしまして、現在1月に設置しました「安全対策チーム」におきまして、安全管理体制の構築に全力で取り組んでいるところでございます。
しかしながら、そのような中におきましても、年末の脱線事故に続き、先日には一部区間の運休を余儀なくされるなど、現状としましては市電に対する市民の信頼は失墜し、信頼回復には程遠い状況にございます。
このような状況を鑑みまして、青囲みの部分でございますけれども、市電延伸事業につきましては、これまで安全対策と並行して進めてきたところではございますが、まずは運行の根幹である安全・安心の道筋を明らかにすることに最優先に取り組む必要があるとしまして、先週の市長記者会見で市長から申し上げましたとおり、市電延伸事業の今後のスケジュールについて再検討するよう指示があったところでございます。
なお、今後の進め方につきましては、下段に記載しておりますが、レールの点検や補修など足元の安全対策を早急に進めながら、今後の安全の再構築に向けた検討内容、方針について委員会にも適宜お諮りした上で、高度化計画へ反映し、延伸事業の再開につなげてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
○田中敦朗 委員長 以上で説明は終わりました。
それでは、質疑及び御意見等をお願いいたします。
◆齊藤博 委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
るる今御説明いただきました。冒頭ちょっと申し上げたいと思いますが、ぜひ今年に入りまして、1月ももう後半ということでありますが、安全・安心に市民の皆さん方が公共交通機関としてしっかりと電車を使っていただけるような環境を一日も早く、信用を取り戻していただければと、冒頭申し上げておきたいと思います。
その中で、あえて幾つか御質問申し上げたいと思いますが、交-1のインシデントですけれども、落ち葉によってブレーキ操作が思うように機能しなかったというような事例ですけれども、横断歩道を越えて停止線約33m先で停止したと。昨年、トータルでいうと16件のインシデント等の運行トラブルが発生していた中で、結果的に市民の方から、市民かどうか分かりませんが、外部からの通報を受けてこの事案が発覚をしたと。
要は、運転士が指令へ報告をしなかったと。33メートル停止線を越えて止まったという現実があったにもかかわらず、報告をされなかった理由ですね。当然いろいろな運行トラブルが実態として出ていたさなか、運転士の個人を責めているということではなくて、組織の風土として単純に疑問なんですが、こういった事例が起こった中で報告を上げなかったのか、まずここをちょっと教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 運転士に、この後にすぐヒアリングを行いました。ちょっとここにも記載しておりますけれども、滑走によるものであって、報告をしていなかったことに関しましては、申し訳なかったということは申しておりました。インシデントであるという認識がなかったということでございました。
◆齊藤博 委員 恐らく安全運行というものがいかなるものなのかという共有の認識が組織の中で図られていないと、多分そう言わざるを得ない事例なんではないかなと。これは安全運行に大きく逸脱した事例ではなかったというような、運転士の考え方といったようなものがひょっとしたら働いておったのではないかと。
そうするのであれば、安全運行というのは、一体どんなことを指して安全運行と捉えなければいけないのか。こういうところがやはり職員の皆さん方に共有できていなかったのではないかなと捉えられますので、後ほどちょっとまた申し上げたいと思いますが、検証委員会の指摘等々に対する組織、交通局としての姿勢、あるいは職員の皆さん方へのそういった安全運行に関する共有の認識、これをもう一回徹底していただければなと。
そういう意味では、参考となる事例ということになりゃせんかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続けてよろしいですか。
それから、交-2、これもお尋ねをしたいんですが、時系列にいうと12月7日に、これは予防策としてのということなんだろうと思いますが、レール整正工事を行っていると。その後の12月31日に、もともと12月7日に行った整正工事箇所に近いところ、挟まれたところという表現になっていますけれども、この整正工事を12月7日にやったことが原因なのか、今回脱線事故がそこで起こったしまいましたと。そしてその脱線事故が起こった後に近くを調べてみたら、今度また軌道が広がっていたところが発覚をしたというようなことで、一部交通を遮断して工事に入ったというような経緯だと思いますが、この12月7日にそもそも行ったレール整正工事、これは結果として適切に行われていたという認識を交通局として持っているのかどうなのか、そこを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 12月7日の整正工事でございますけれども、この緑色のところ、市役所付近で3点工事をしてございます。そのうち2点が脱線箇所の両脇のところでして、この工事方法というのが、その緑のポイントから前後3メートルのレールの回りだけを剥いで、軌間を調整するといったところになっております。この調整自体は適切に行われているという認識をしておりまして、その後も、脱線した後も測っても基準値内の値を保っておりました。
そういったことから、工事がまずかったとは考えていないところでございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 まずかったわけではないという回答ではあったんですけれども、でも挟まれたレール幅が広がって、そして結果として脱線事故につながっている点。要は2か所を犬釘でがちっと固定した。固定したがゆえに、結果としてそこのぐらつきがなくなったもんだから、ほかのところにひずみが出た。そしてそのひずみによって、今回脱線事故が起こったしまったというようなことであれば、この整正工事そのものが何か課題があったんではないかと、普通に考えれば捉えるべきなんだろうと思うんですよ。
こういうことはほかのところでも従前あっているはずですし、今回の検証が後々に生かされるためにも、予防のための整正工事が結果としてやはり不具合を生じさせてしまった、あるいは工事が終わったらほかのところの部分の影響も踏まえて、後々しっかり検証するとか、12月7日に行った工事そのものに全く問題なかったと言われると、同じような工事を今後したときに、その間の線路の幅の広がりとかの動きの検証につながっていかないんですよね。
だから、これそのものの捉え方というのをもう一回、交通局としてどんなふうに捉えるか、改めてお願いします。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどの、うちの見解としては、そうというお話をしたところでございますけれども、ここに関しては専門的な知識、知見がある方の意見を聞きたいと考えておりまして、鉄道総合研究所という鉄道で一番大手の研究をされているところに、こういった事象というのは適切だったのかというところも含めて、今相談しているところでございます。
また、今回みたいな工事、両脇で例えば工事をするところでひずみが発生したということが正しいとするならば、やはり先ほどお話ししたような、ちょっと円を切る工事だとかが適切な対応となってまいると思っておりまして、今後、するところに関しても、そういった工事をやっていかないといけないのかなと、そこも鉄道総研さんに相談したいと思っております。
以上です。
◆齊藤博 委員 起こってしまった事故というのは事実ですので、事故から導き出される検証のやり方とか、検証そのものをもう一回改めて確認していただければなと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 交-2に関してほかにありませんか。
◆齊藤博 委員 交-2の続きでいいですか。
○田中敦朗 委員長 はい。
◆齊藤博 委員 交-2の2ページ、次ページですけれども、今後の対応、一番下ですね、現時点で軌間の拡大が確認されている5か所の整正工事をやるということで、これはもう速やかに予防ということで行っていただきたいと思います。
これに関連して、ここは特別委員会ですので、予算がどうこうというのは都市整備分科会で検証されるべきものとは思いますけれども、あえてお尋ねを申し上げたいと思いますが、この5か所の整正工事に関してはどのように対応するのか、どのように対応するのかというのは、予算的にどうするのか、幾らぐらいかかるものなのか、あるいは今年度中の補正で対応するのか、あるいは新たな年度で補正するわけではないですよね。今年度中に完了するということですから。補正で対応するならそこのやり方を教えていただきたい、どれぐらいお金がかかるのか。
それから、軌道検測機を購入するであるとか、ドア開け走行防止の注意喚起装置をつけるとか、あるいはIP無線導入をやるとか、これは今年度中の予算であろうかと思いますが、当然事故が発生してから今後予防策ということですから、ここに補正が発生してくるのか、あるいは既存の予算で対応できるものなのか、そこを教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどのレールの整正でございますけれども、5か所ありまして、1か所は今回1月15日、16日の箇所に含まれているため、4か所今残っております。そこに関しましては、もう既に工事の業者さんと契約をしておりまして、早急にやってまいりたいと思っておりますし、それまでの間は運転の方で速度制限を設けたり、毎日広がっていかないか、検測をやっているところでございます。早急に対応してまいりたいと思ってございます。
また、金額ですけれども、契約の金額としては600万円程度です。4か所残りありますけれども、今回脱線のときがレール幅から39ミリ基準値から超過しているところでございまして、今回の箇所は一番小さいところで1ミリ程度、一番広いところで7ミリ程度超過しているという実証でございまして、基準値は当然オーバーしているんですけれども、値としてはそこまで大きくはない状況でございます。
そこで、速度制限とか毎日の検測だとかというところで対応してまいりたいと思ってございます。
あと機器ですけれども、先ほどの補助表示装置、一番最後の紙の③番のところになりますけれども、そちらが3か所で350万円、④番のドア開け注意喚起装置が1,020万円、こちらは9月補正で既につけていただいて、そちらで執行しております。
また、⑤番の軌道検測器が550万円、⑥番のIP無線が750万円、こちらはもともとうちの既存予算流用で対応してまいりたいと思っておりますので、2月補正で上げたりとか、そういったところは考えていないところでございます。
説明は以上です。
◆齊藤博 委員 IP無線の導入について、流用というのはどういう意味か、もう一回教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 IP無線自体は予算ついておりませんでしたけれども、工事の予算の残があったことから、そちらの残を生かしての執行ということを考えております。
以上です。
◆齊藤博 委員 それは予算の在り方として正当ですか。工事の予算をIP無線に流用するんですか。ちょっと想定を超えた答弁のように聞こえるんですが、ごめんなさい。
個人的には事故が起こった後の対処ですから、語弊があるといけませんが、補正でどんどん上げていただければいいんではないかなと思うんです。軌道検測器の導入、そもそも何でこれが今の時期に導入されるのかなというところもちょっと分からない部分もあるんですが、こういう脱線事故まで起こしてしまったから、早急に対応しなければいけない。それはそれで分かります。補正を起こすなら補正を起こしていただいて、僕は一委員としてオーケーなのではないかなと思います。
それから、IP無線の導入についても、今まで課題がありましたということで、対応していただくのは当然やぶさかではないし、その対応のやり方、これについては僕は個人的には補正で上げていただいた方がごく自然なのではないかなと思います。工事費を流用するというのは、ちょっと正直予算の使い方としてはいかがなものかと思いますが、いかがでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 すみません、先ほどの2件に関しては、私の認識誤りでございまして、補正で対応してまいりたいと考えております。申し訳ございません。
◆齊藤博 委員 確認ですが、すみませんね、交-3の資料に載っているもんですから、ドア開け走行防止に係る注意喚起装置はもともと予算計上していたということで大丈夫ですね。軌道検測器の導入とIP無線の導入については補正で上げる予定だという認識でございますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そのとおりでございます。
◆齊藤博 委員 もう一つ確認です。
あと残り4か所の整正工事について、これはトータルで600万円、これも補正で上げるということでようございますか。上げる予定ということでいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 このことに関しましては、昨年からもともと悪いところを把握しており、当初予算で計上しておりまして、それの分で対応してまいりたいと思っております。
以上です。
◆齊藤博 委員 すみません、何回も確認ですけれども、この5か所、残り4か所、1か所のもう既に修正した箇所、ここも含めて当初予算で上がっていた分なんですか。もう一回教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの維持補修として当初予算で計上していたものでございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 分かりました。
それでは、今年度に残り4か所の工事もやってということでありますので、検測の実施や安全運行に全力を尽くしていただきたいと思います。
それともう一つ、今後の対応として交-2のところで、検測間隔の基準の見直しを20メートルから10メートル間隔でやるということなんですが、軌道検測器を購入することで、10メートル間隔とかする必要というのは、これを導入すれば必要なくなるという認識でいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 委員おっしゃるとおり、測定間隔は短かめられまして何十センチ単位という、1メートルで例えば2ポイントだとかいう感覚で取ることは可能となります。
ただ、運輸局さんに提出する書類というのが20メートル間隔で出しておりまして、そこが例えば10メートル間隔で提出するのかというところを今後運輸局さんと相談してまいりたいと。代表的なポイントとして管理するというところの認識でございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 それでは、今回安全運行に伴って検測器を入れ、実態として交通局として管理していくのは、もっと間隔的には狭い、何十センチとか、10センチ、20センチ、場合によっては50センチ程度の間隔でずっと検査を行っていくと、そんな認識でいいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 測定はできますので、そのデータは50センチとか、そういう間隔で取って管理してまいりたいと思っております。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
◆上野美恵子 委員 では、交-2の今の点についてお尋ねします。
私が思ったのは、今回、この交-2で軌道の不備ということで御報告があっておりました。こういう事故が発生してくるのは、一定施設の老朽化とか、そういうのも影響している面があるのではないかなと思っています。
そういう意味では、今回の対応についてのお尋ねがありましたが、こういう軌道整正について日常的な点検というのはこれまでどうなっていたのか、今回事故の発生によっての御報告になっていたんですけれども、日常的な点検がどうなっていたのか、それとその点検を行ったときに何らかの修正するとか、対応するとか、そのときの基準というのはどのようになっているのか、その基準に対して今の対応がどうなっているのかを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの点検でございますけれども、毎日整備長がトラックで確認をして、休みのときは代わりの職員が対応するということで確認をしております。
基準といいますか、点検、測定自体も年1回、測定しておりまして、その中で管理をしていくということにしております。オーバー値が出てくるときには適切に、今回ちょっと整備遅れというのがありましたけれども、値がオーバーしているところが見られたら適切に、早期に対応してまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 そのオーバー値という値を教えてもらっていいですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 値について軌間がレールとレールの内側の距離が1,435ミリというのが、JRさんも含めて、通常のうちの標準軌という規格になります。うちの整備心得として管理値を設けており、1,435からマイナス5、プラス15ミリまでは許容するということになりますので、1,430~1,450までの間で管理するということになっております。
大概管理値を小さくいくのではなくて、オーバーする方向に出るというのが普通ですので、今回大みそかのときも、1月15、16日のときも超過ぎみに出ているものでございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 今の説明だと、ずっと点検を積んでいきながら、年に1回は点検をするというふうな形になっているみたいですけれども、減ることは少なくてオーバーすることが多いということなので、1,450をオーバーしたときにすぐに対応ができているのか、それともちょっとぐらいならいいかなとか、このぐらい超えたらでも最低しとかんと危ないかなとか、そういう交通局の判断によって、私たちからすれば、基本は基準値を超えた場合は、しかるべき対応をしないと安全が損なわれると思うんですけれども、そこの安全が損なわれないために、基準値を超えた場合の対応が100%行われていたのか、それとも全部は採用できないから、このぐらいはしとこうとか、ちょっと積み残しのある状態で対応されてきているのか、教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 9月20日に九州運輸局から改善指示というのが出まして、その中の一つとして、軌間の維持管理ができていないというところに関しましては、2年連続でオーバー値をそのまま積み残していたといったことから指摘が出るものでございまして、本来ならば早急に対応していかなければいけないところが、そのまま積み残されていたということで、今指摘を受けた後、すぐ取り組んでまいりたいということで対応しているところでございます。
説明は以上です。
◆上野美恵子 委員 ということは、今回こういう事案が発生するまで2年間オーバーした状態が続いていても、対応ができていないという状態を交通局がそのままにしていたということですかね。
◎荒木敏雄 運行管理課長 その点に関して、九州運輸局さんからの御指摘というのが改善指示で出されたものでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 これまで2年連続でも改善できていなかったように、かなり積み残しというのはどのぐらいあったのか。地点が多分決めてあると思うんですよ、20メートル間隔、今度は10になるけれども、20メートル間隔なので地点数が決まっているので、その決まった地点数に対して何地点ぐらいのオーバー状態であったのかを教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 先ほどお話しした4か所プラス、市役所のところが軌間オーバーというところの値で出てございましたので、10か所までなかったかと、7か所ぐらいだったかなと認識しております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 では、普通の基準からいくならば、今おっしゃった7か所というのは、去年の計測があったときの時点から早くに手を打たなきゃいけなかったということなんですかね。
◎荒木敏雄 運行管理課長 本来ならば9月に検測して、また翌年までの1年間の間に対応していかなければならなかったことと思っておりまして、その対応が遅れたということでございます。申し訳ございません。
◆上野美恵子 委員 ということは、2年間というのは放置された状態なので、最低でも1年に1回は千何百か所の計測地点がきちんと計測をされて、そして場所によってはオーバーする値が出たときに、その時点で、その1年間のうちに修正がされていけば、2年間継続というのはなかったわけですね。
ということは、なぜ1年間のうちにせずに翌年に繰り越して2年間放置をして、要するに国から指導を受けるような状況になっていたのか、その理由は何ですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そこは管理不足というところ、九州運輸局からも指摘されておりますんで、そのとおりと思っております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 だったら、今回インシデントがたくさんこの特別委員会にも、そしてまた常任委員会にも報告をされて、私たちも本当に残念な気持ちでインシデントの報告があるたびに聞いてきたんですけれども、突き詰めていろいろ詳細に聞いていくと、交通局としてのいろいろな守るべき基準を守らないというところに、大きな原因があるんではないかなと思います。
また、後で国からの改善計画、最終報告も出ておりますので、それも含めて今後改善していかなきゃいけないかなと思いますけれども、そこはちょっと認識甘いですよね。
例えば認識していたけれども、予算が少なかったとか、ほかの事情があったならともかく、今のお答えだと、まあいいかなみたいな感じで放置をされていたという向きがありますので、それはちょっとどうでしょうかね。井芹事業管理者、それではやはり事故というのは起こってしまいますよね。どう思われますか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ただいまの委員の御指摘は、これはもっともでございますし、それに対して私たちは何も申すことがないという意味では、本当に申し訳なく思っております。
そういうことが、今話がるる出ました運輸局からの改善指示もそうですけれども、インシデントの検証委員会からも車両とか、レール、軌条も含めた施設の老朽化といったところも早くすべきではないかという御指摘につながっていると思ってございます。
なので、今5か所等についても早急に対応するということにしていますし、レールの検測器等についても、今まで買う予定もなかったというところで、これも反省をしているところでございますけれども、早急に買ってきちんと測って、そのほかの箇所等についてもきちんと測って対応していきたいと思ってございますし、御指摘いただいたことについては、本当に申し訳ないというお言葉しかお答えできませんけれども、今後についてはきちんと対応を進めていきたいと思ってございますし、その内容等については、この特別委員会の場でもきちんと御説明をしていきたいと思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 もう一点、私が心配していることがあるんですけれども、1つは、レールの整正ということを今言いましたけれども、老朽化が進んでいくので耐用年数というのがあると思うんですよね。さっき全面的に軌条を交換していくという御提案が説明の中ではありましたけれども、現状の問題として、交通局が管理しているレールの中で、そもそもレールの耐用年数はどうなっているのか、そして、交通局が管理しているレールの現状について、20年以下がどのぐらいあるのか、距離とかパーセントとか、20年~30年がどれぐらいあるのか、30年~40年がどれぐらいあるのか、40年以上に至っているものが幾らあるのか、数字を教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 レールの耐用年数といたしましては、定められたものはございませんけれども、通常20年~40年程度といわれておりまして、都心の方のJRさんのところだとかというのは、20年で管理されていると。あとはちょっと郊外になってくると、30年、40年というのがあるという状況でして、うちは一般的に30年で考えて、経営企画上は30年で考えているところでございます。
ただ、今実際のレールの年数といたしまして、30年越えがだいたい40%ぐらいあるといったところ、あと40年越えが4%ぐらいあるというのが現状でございまして、そちらを計画的に早期に対応していかないといけないと考えておりまして、それが軌条交換でレールの更新というのを早期に対応していきたいと考えているところでございます。
説明は以上です。
◆上野美恵子 委員 今30年以上が40%、40年以上が4%あるということでした。40年ということは、10年前にもう既に基準というか、一応交通局が経営計画上で定めてある耐用年数というのを超えていたにもかかわらず、何とはなしに使ってきた、漫然と使ってきたという現状があったんだなと思います。
この点でも、例えば人為的なもの、人をどうにかするというのは、その人本人の向き合い方とか、人間というのは難しいけれども、こういう環境、ハード的なものについては、一旦決めた目標とか基準に対して、きちんと対応することが原則ではないかと思うんですよね。
さっきも整正という点でも、基準がありながらそうなっていなかった。そもそものレールそのものだって、確かに私たちも委員会で交通局が大変経営的に厳しいというお話をずっと聞いてきていて、その裏でこういうふうにもう少し安全ということを考えたときには、最低限ですよね。
レールの耐用年数が過ぎているのに4割以上も今現状にそこにあるということ、今回事故が起こって検証委員会があって、国からもいろいろな指導が入ってなったから、こんなふうに大問題だと言っているけれども、そういうことを抜きに、決めている基準に対しての日常的な交通局としての自身の管理ということに対する向き合い方そのものが問われてはいないかなと思います。
これちょっと駄目ですよね。それは予算なんかがついていなかったんですか、それともほかに理由があったんですか、こういうふうに過ぎても漫然と使っているという、その大元にある理由というのは何ですか。
これだと基準決める意味がなくなってきますよね。経営計画を立てながらその計画にのっとらない実態があるということについて、どのようにお考えなのか教えてください。
◎荒木敏雄 運行管理課長 うちが全線が12キロございまして、30年で割るとするならば、年間400メートルずつ工事するというのが平均的にやっていくというところでございますけれども、実際に過去10年ぐらいで二百数十メートル、ここ最近では360メートルぐらい、400メートルに近くやっているところでございますけれども、さらにちょっと加速して400メートルを超えていかないと、このような30年以内での管理というのができないと思っておりますので、そちらはやってまいりたいと思っております。けれども、なかなかメートル数だけではなく、例えば交差点のところでは距離はいかないけれども、工事は結構困難だとかというところもございまして、けれども、計画的に400メートル、500メートルというところを目指してやっていきたいと考えてございます。
説明は以上です。
○田中敦朗 委員長 できなかった理由は答えていないけれども、いいですか。
◆上野美恵子 委員 いやいや、それは聞きます。
今は現状だけ言われたんですけれども、できなかった理由ですよね。今おっしゃった計算でいけば、年間400メートルしないと30年間で更新していけないという具体的な数字を描きつつも、それが執行できずに以前は二百数十メートルがずっと続いて、多いときでも300メートル超えたぐらいだったという今御説明であったかと思いますけれども、その理由は何なのかというところです。
でなかったら、今課長がいや今後は頑張るとおっしゃったけれども、でもその理由をはっきりさせて、今までできなかった理由というのをクリアしていかないと、多分やると言っても難しいと思いますよ。そこの理由は何ですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 確かに軌条交換する箇所というのは計画的にしておりましたけれども、そこの箇所の計画というところが確かに遅れぎみになっていたところはあるのかなと思っておりますし、仮に上げておってもなかなか予算的に厳しいという面もあったのかなと思ってございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 遅れぎみは現状ということで、理由で今おっしゃったのは、予算は上げていて、予算はあったんですか、それとも要求したけれども少なかった。どっちですか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 財務、財政も総務課で持っておりまして、その枠の中でやれるところをやっているというのが今までの現状でございました。
以上です。
◆上野美恵子 委員 その400メートルの交換を、年間400メートル実施できるだけの予算は確保できていたんですか、できていなかったんでしょうか。どちらでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 そこに関してはできておりませんでした。
以上です。
◆上野美恵子 委員 長い交通局の歴史の中で、それができた年度があったんでしょうか。できなかったと言われましたけれども、たまにはそれだけの予算がついたのか、ずっと予算がつかなかったのか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 昨年、商業高校前とかをやっておった年には400メートルを超えてございますけれども、早々そんな何年もというところはございません。単年度で単発でクリアしたところはありました。
以上です。
◆上野美恵子 委員 その予算というのは、軌道の問題なので、予算そのものは財政局で査定されるんですか。要求はしていたんですか。要求していて査定で落ちていたのか、要求もしなかったのか。どちらでしょう。
◎荒木敏雄 運行管理課長 もともと上げるところは、うちの局内でやっておりまして、工事するときには基準外繰り出しとか、その辺のところの話もありますので、財政課と話をしているところでございます。
以上です。
◆上野美恵子 委員 そうしたら、交通局としては、予算は要求をしていたわけですよね。財政局は、そういう市電の安全運行に関わる、こういう最低限守るべき基準についての予算を査定で落とすんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 すみません、今何度かやり取りをさせていただいておりますけれども、まず、そもそもこうなったというのは、先ほども言いましたように、必要な予算を必要なときにつけていなかったというのは事実であろうと思ってございますが、これにつきましては、過去に交通局は経営上よろしくなかったものですから、経営健全化というものを優先にするというところで、どうしてもそこに対する予算というものが少なかったのは事実だと思います。
例えば、うちは30年と決めておりますけれども、30年を1年でも超えたらそのレールが使えなくなるかというのは、そういうわけではないということではあろうかと思いますので、毎年毎年の測定等を基に、今年は使えるかな、来年はというふうにちょっと後送りといいますか、そういったことを積み重ねてきた結果だろうということであって、交通局の中でそういうふうにしていたというのが、基本的だろうと思ってございます。
そういう中で、それはいかんということで、令和3年にその経営計画を定めたときには、先ほど言いました400メートル等できちんとやっていくということをきちんとうたって、ここ数年はそれに対する予算も大きく取ってはいるところでございますが、いかんせんやはりレールも買わないといけませんし、工事も結構金額がかかるものですから、少し進捗として目に見えて1年間にとか、短縮でできるというような工事ではなかったかなと思ってございます。
今回、こういったことも踏まえまして、再度その経営計画について、400メートルということそのものについても見直していきたいと今思ってございます。そこには運輸局の今後指摘事項等に対する最終報告とかもありますので、運輸局とも相談をしながら、きちんと計画を見直していきたいと思ってございます。
その内容については、ここの特別委員会でもきちんと事前に計画の内容については考え方をお示しして御議論いただければと思ってございます。その上で、きちんとした軌条の整備というものをやっていきたいと思ってございます。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 聞いていると、400メートルを交換するだけの予算はなかなか厳しいので、30年で更新していくという、その計画そのものを見直すと今言われたんですけれども、ということは30年で更新しないということになっていくんですか。そこを変えるんですか。
◎井芹和哉 交通事業管理者 もう少し早めに、もう少し期間を短くしてどうにかできないかと思っております。
◆上野美恵子 委員 二十何年にするということは、もっと予算が要りますよね。
◎井芹和哉 交通事業管理者 予算もそうですけれども、一部輸入したレールとかも使っているということもありますので、予算がどんとつけば、その年にどんと、例えば1キロも2キロもできるというものでも当然ございませんし、事業者、工事をする業者等についても、専門的なところもありますので、そこも土木工事よりも少ないと思ってございますので、そういった兼ね合いも含めてきちんと計画を立て直したいと思っております。
◆上野美恵子 委員 見直しというのは、これからのことだと思いますので、このことで議論してもちょっと深まらないと思うので、私からぜひお願いをしておきたいのは、経営計画、今後見直してと言っておられますけれども、経営計画そのものをどこに視点を置くかという点では、いろいろなお金の面があるかと思いますけれども、何よりも安全重視、安全第一、そういう視点でしか見直しはしないというところを、局として毅然として立場を明確にしないと、どんなに見直しと言っても、ずるずるとなってしまいかねないと思うので、そこは絶対に譲らずにやっていただきたいなと思います。
そしてそういう立場でいろいろ今後検討していく中で、予算についても、幾ら企業だから、独立だからといいますけれども、安全運行そのものが担保できないんだったら、今度上下分離になっていきますけれども、その問題にも関わることとして考えないといけないと思いますよ。
改革といっていろいろな方針が出されるけれども、それをするときに本当に安全が確保できるのか、そこのところだけは、一歩も譲らずに考えていくという姿勢がいるし、そのことを交通局も頑張るけれども、市長がこの間の市電の100周年の式典の中で講演なさった、私はああいう場で市長が安全運行について講演されるというのは、異例のことだと思うんですよね。
でも、せざるを得なかった、そういう中にあったというのは、今いろいろ明らかになってきた、きちんとやるべきところやらないと、この市電のインシデント問題は解決しないという中にあって、そこのところしっかりしていかないといけないし、他局も交通局は企業だからということではなくて、安全運行のためには、一般会計からのいろいろな支援も含めて、安全が守られるような事業の運営に対しては、全庁を挙げて、市長があのときおっしゃったことは、確実に現実のものにするために、全庁が協力するというのが大事かなと思うので、そういう決意で頑張っていただきたいなと思いますが、いかがでしょう。
◎井芹和哉 交通事業管理者 安全というものを第一にということについては、私もしっかりと思っておりますし、改めて今の言葉も踏まえて、その認識を前提として今後努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 いいですか。
◆上野美恵子 委員 はい。
○田中敦朗 委員長 そのほかありますか。
◆上田芳裕 委員 今の井芹事業管理者からも、また上野委員、齊藤委員からの御指摘等もある中で、安全が第一だということで、今後取り組まれるということで、後ほどほかにも意見があるかと思いますが、市電の延伸の今後のスケジュールも変更する中で、安全管理の再構築を行っていくということで、言うならば今の話をずっと聞いていくと、課題がそこにあるのに手がつけられていなかった、予算立てがされていなかったということの積み重ね、それは人の配置もそうですね。積み重ねが今一気に来ているのかなと考えております。
そういった意味では、令和7年新たな年を迎えて、今年が、市長も言われた、安全・安心の元年にしたいというようなことであるんですけれども、いろいろ対策については、外部の検証委員会の中からヒューマン的なもの、施設整備的なもの、職場の環境、組織管理体制含めていろいろな御指摘があって、その中で交通局で「安全対策チーム」というのを1月1日につくられてすぐということになりますけれども、「安全対策チーム」の中でどのような安全対策をやっていくのか、その方向性、項目等々の検討が適切ですけれども、御答弁いただける範囲があれば教えていただきたいと思います。
◎荒木敏雄 運行管理課長 資料の交-3の2枚目のところで、「安全対策チーム」の設置ということを書いてございまして、今写真であるような交差点立哨だとか、添乗監査ということで、実際の運転士が基本動作をきちんとやられているかだとか、あとは速度だとか、当然ながら信号を守っているかとか、そういう基本的なところを確認していると、そこで指導をしているといったのがメインの仕事でございますけれども、そのほかに資質の管理とか、あとは指導教育、実際に新人の運転士もこの「安全対策チーム」で教育してまいりますし、事故防止対策というのも施設だとか、車両だとかという各部門間で連携しながら取り組んでいっているところでございます。
以上でございます。
◆上田芳裕 委員 今御答弁では、乗務員の育成、資質管理、指導教育、ヒューマン的なものと事故防止することでありますけれども、外部検証委員会から出されてある対策の中には、施設整備のところで軌道車両の予防保全の強化であったりとか、事故多発箇所の安全対策の再検討であるとか、様々に軌道と車両、いわゆる設備、施設のところとヒューマンケアのところが示されておって、対策チームの中で対策を検討し、講じなければならない課題というのは、物すごくたくさんあると思っています。
そういった意味では、今回、外部検証委員会の中から体制強化ということで、この資料からいくと専門チームの設置という、専門チームという表現されていますが、私から言わせていただくと、この課題になってから答弁を運行管理課長がずっとされておりますけれども、運行管理課長の守備範囲というか、それを超えているのではないかと思っています。
そういった意味では、運行管理課長が大変重たい職責に当たっていらっしゃると思いますけれども、「安全対策チーム」というよりも、交通局の中に総合安全管理課とか、きちんとした体制整備を構築した上で、今後進めていくべき課題ではないかなと思っておりますけれども、この点については事業管理者の御所見があればお願いいたします。
◎井芹和哉 交通事業管理者 ありがとうございます。
今御指摘をいただいたことは大変重要だと思ってございまして、おっしゃるとおり、今までの反省といいますものが、そこの部署で全て完結していたということが、問題点が見えなくなってきていたという、一つの大きな要因でもあったのかなと思ってございます。
なので、まずは、諸規定等をきちんと見直す。また、今も課長が申しましたように、現場の指導であったりとか、そういったところからやならないといけないもんですから、現場に、しかもこのチームという名称で増員をしていただいて設置をしたところでございますが、御指摘のとおり、今後は法規とか、そういった点についてもきちんと整備を再度見直す必要もあると思ってございますので、そういった意味では、部署の新設というものも、私としては必要だと思ってございますので、今後の安全に対する検討の中で、そこについても含めて検討していきたいと思っております。
◆上田芳裕 委員 井芹事業管理者から、そういったことも含めて検討いただくということであります。今後は時期を見て上下分離することで、上物、下物とあって、施設、軌道とかの管理と交通社団法人ですか、公共交通公社と役割が変わってきますけれども、安全管理を総合的に行うという意味では、新しい、さっきの話ですけれども、交通公社も、また下物を管理する市も大事になってくると思いますので、十分な検討と具体的な設置に向けて御協議いただきたいと思っています。
もう一点心配なのが、そういった安全管理体制の構築をしてきちんとした安全対策を行う、先ほどから上野委員からもありました軌道の安全とか、車両を新しくどんどん変えていくということに関しては、物すごく予算がかかっていくと思っています。そういった意味では、安全体制の再構築の初めの段階で、たくさんの予算をかけていろいろな対策を打たなければならないと思っています。
一遍に何もかもできるとは思っていませんけれども、財政的な負担が交通局、また熊本市にも生じてくると思っていますけれども、そこら辺の考え方について、財政局長に御所見があればいただきたいと思います。
◎原口誠二 財政局長 今上田委員、また先ほど上野委員からもありました、先ほどの市電の延伸の話にもつながるんですが、延伸の前に既存の安全が保たれて延伸の話だと私ども思っております。既存のこちらの更新については、るるこれだけ重大な案件が出ている中で、これまで金がないからレールを交換したらいかんとか、そういう議論をしてきたことはございません。
ただ、全体としての基準外繰り出しをどうするかという議論は、これまでここ何年かもずっとあって、都市整備委員会でも多分るる議論があってきたと思いますけれども、先ほどお話があった中で、今後の安全対策については、命を守る公共交通でありますので、その辺の視点も、委員の方々からの御意見も含めて、繰り出し基準の考え方等についても御相談して、御議論いただければと思っております。
以上でございます。
◆上田芳裕 委員 御答弁ありがとうございます。
既存の施設の安全対策の上に延伸がなるという、なかなかうまくいくのかどうか非常に考えるところもあるんですけれども、ぜひそういった考え方を持って今後も財政局としても対応していただきたいと思いますし、上下分離になった以降も、そのことを十分引き継いで、財政面の支援含めて取り組んでいただきたいというふうに思います。
私からは以上です。
◆藤山英美 委員 資料交-1の件で質問したいんですが、この件については、電車でほかの車両もあるんですが、イチョウは油分が多くてスリップするという話は、相当以前から出ていた問題です。私もこの件について質問したときは、まだ電車通りが県の管理だったときです。
そういうときに、大体イチョウの落ち葉が、11月末までぐらいに剪定すれば落葉がないということで質問をして、答弁ではちょっと今まで2月、3月でやっていた剪定をそんな形でできないというような答弁だったと思いますけれども、それで熊本市の所管でないということで、私は県の土木事務所にお願いに行きました。そして県でも同じような答えだったんですが、私はせめて坂のある熊商前と大甲橋のところだけでもやってくれませんかと言ったら、そこでやってくれました。その後、何年か続いたと思いますけれども、今はちょっとうやむやになっているような感じがしているんですけれども、これは当時から、相当前から電車のスリップについては指摘されておりました。
しかし、さっき言いましたように県の管理ということでなかなか進まなかったんですが、今はもう市の管理になっておりますので、管理も高木は3年に一度剪定するということになっていると思いますけれども、落葉の時期に皆さんも御存じと思いますけれども、相当のイチョウの葉っぱが舞っているんですよね。だから、交通局としても本当に大変だと思います。砂をまいて、運転士さんはほこり対策でマスクを二重にしているとか、そういう話まで聞きますし、外的要因でいろいろな問題が出ているんではないかなという思いがありますので、これもたまたま相当長い距離が必要だったということですけれども、それまでにも短い距離があったんではないかなと思います。
そういうことで、外的要因を除去する方法も書いてもらえないかなという思いがしますし、交-3の外部検証委員会の最終報告についての課題と対策ということで載っていますけれども、この外的要因というのは載っていないもんですから、特別委員会の趣旨として調査研究というのがテーマになっておりますので、ぜひそういうことで入れて研究してもらえないかなという思いがしております。
今後も、膨大なイチョウの落ち葉対策は課題として残ると思いますので、そこのところを研究していただきたいし、事故防止で事業管理者が言われたように、安全第一というならば、そういうところまで考えてほしいなという思いがしていますので、そこのところどのように考えておられますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 12月、1月には結構イチョウの葉っぱが当然ながら落ちまして、土木センターにもお願いしながら、剪定だとか、スイーパーというか、掃除機みたいなもので横の車道を掃除していただいたりとかやっているところではございますけれども、本数が結構あるのと、市電の沿線沿いには結構ずっと植わっているものですから、その辺の管理体制だとか、その辺のところには、また土木センターと協議しながら、局としては進めてまいりたいと思ってございます。
以上です。
◆藤山英美 委員 よろしくお願いします。
これは電車だけの問題ではないんです。ほかのイチョウの高木があるところは、歩道の人も自転車も車も電車もみんな影響があるわけですよ。そして、高校生の自転車が転倒するという事故も何回か見ておりますので、そういう問題まではらんでおりますので、このイチョウ対策、高木対策は、本当は喫緊の課題ではないかなという思いがしますので、よろしくお願いします。
◆古川智子 委員 私からは1点確認をさせてください。
1月15日の始発から区画運休して緊急整正工事を実施されている件です。背景を見てみると、1月7日時点でレール幅の広がりを確認している。ただ、この時点では早急に脱線につながるような状況ではないと判断をしています。というところで、1週間後の14日、再検測及び夜間に試運転を実施したところ、自動車と市電の通行を妨げない工法では、100%安全性を確保できるとは言えず、実施困難と判断をして翌日の始発から運休しているというところですね。
市民への周知の方法が、朝5時のたしか公式LINEで伝わった。その方法を取られたと思うんです。もちろん安全運行、この安全を担保することが一番ということは、もう大前提となるお話の上でやり取りをさせていただきたいんですけれども、この説明からいうとレール幅の広がり確認して、早急に脱線につながるような状況ではないけれども、自動車、市電の通行を妨げない工法では、安全性を100%確保できるとは言えず、結局早急に翌日対応なんですよ。
だから、14日の時点でもう脱線につながるような状況ということを判断したのか、緊急度と優先順位がどれぐらい高かったのかというのかということを教えていただきたいんですね。
可能性とすれば、早朝というのは出勤、それから通学、多くの市民の方に御迷惑をかけるというタイミングであるので、例えばどのぐらいの余力というか、余裕があったのか、なかったのか、方法としては仮に半日遅らせたりできたんではないかというのもちょっと考えられるので、そこの緊急度をどのぐらい判断されたのかというのを確認したいです。お願いします。
◎荒木敏雄 運行管理課長 委員お尋ねの1月14日のところでございますけれども、そもそも自動車、市電の通行を妨げない工法というのが、例えば交差点を3分割、4分割しながら、夜間工事で少しずつ剥いではレールを整正して、埋め戻してという工事を4日間、5日間ぐらい繰り返す工事というのを想定しておりました。
そうしたときに、全てのレールをむき出しにして、今回実際にしたときの工事みたいに、交差点すべて舗装を剥してということができないのですから、1か所、1か所を整正して戻すとなってくると、脱線のときに考えたようなひずみというか、横から補修したのにまた開けたところからのずれだとか、そういったところも影響するのかと考えておりまして、全て交差点を封鎖してやるという判断をして、確かにおっしゃるように、判断がちょっと遅れたところがございまして、1月14日の夜間も、11時過ぎになったと記憶していますので、そういったときからなかなか連絡を回すのが、報道とかには投げたんですけれども、当然報道も朝方しか入れないというところになりますので、連絡が遅くなったことに関しては、すごく申し訳なく持っております。
ただ、先ほどの部分的にやっていく方法では、ほかのところ、やったところに対してまた剥いだところからの影響だとか、そういうところを考えたときにやむを得ない判断だったのかなと考えております。
説明は以上です。
◆古川智子 委員 ありがとうございました。
今課長おっしゃったのは、工法として一遍にやるしかなかったということで、翌日から工事を着工するという判断を取られたと思うんですけれども、その工法に関しては納得がいくんです。
ただ、タイミング、例えば全部やるとしても、翌日早急にというよりも、1日空けるとかできたんではないかなというところでお尋ねをしたわけですけれども、1つは、これからも努めてほしいというのは、もちろん安全対策一番というのは先ほども申しました。市民の方にこれだけ不便さをどうしても影響として与えてしまうので、市民の方への理解を努めなきゃいけないと思うんです。
もう脱線の可能性がとても高まった。だから、皆さんの安全を担保するために申し訳ないんだけれども、翌日運休しましたよというところをもうちょっと伝えないと、これ本当にこのタイミングでよかったのかなと、もうちょっと空けても全然支障なかったんではないかなという疑念は生まれかねないので、本当にやるときは安全のためということをきちんとお伝えしていく。御迷惑をかけたところは謝罪していくしかないんですけれども、そういった今後もこういったことが起こり得ると思うので、緊急度が高いものはもちろんすぐやらなきゃいけない。だけれども、その点に関しては、きちんと御理解をいただくような周知方法に努めていただきたいなと思っております。
以上です。
◆村上誠也 委員 交-3になりますけれども、最終報告の中で、②でJR九州さんを講師に迎えた安全教室講話というのを1月16日にやられたということをお伺いさせていただきましたけれども、この講話の中で運転士の皆さんたちが参加をされてその講話を聞かれたと思いますけれども、この講話を受けられた後に運転士の皆さんたちに気づきとか、思いとか、どう違ってきたのかという意識を持たれるようなアンケートとかを取られたことはございますか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 1月16日に、実際に講師の方に来ていただきまして、講話をいただきました。実際に参加した人間が30人、運転士と監督30人でして、うちが120人ぐらいいることから、その後に関しましては動画を撮ってそれを流すと。それがあった後にアンケートを取りまして、気づきだとか、そういったところを書き込んでもらう。その中では、やはり基本動作が重要ということが改めて分かりましたとか、講話の中で講師の先生がおっしゃったのが、市電もパイロットとかJRの運転士も一緒で、命を預かって人生を運んでいるようなもんだからと、そこはきちんと心に銘じてくださいみたいなことをおっしゃって、そういったことが心にしみましたということを書かれているのもありました。
以上でございます。
◆村上誠也 委員 ありがとうございます。
今おっしゃったように、こういう講話を受けられて、これだけ大きなインシデント等を含めて発生しているという事実を、しっかり認識していただく必要性があるんだろうなと思います。JRからこういう講話を受けられたことで、自分たちが今まで気づいていなかったこと、感じていなかったことをしっかり感じ取っていただく、それを皆さんに共有していただくというのが物すごい大事なのかなと思います。
交-3の前のページになりますけれども、管理のところで、乗務員の意見が反映されていないというところも書いてございます。指摘の中でですね、各委員の皆さんからお話があったように、乗務員さんだけで解決するような問題だけではないと私、多分委員さん思っていらっしゃると思います。
先ほどから線路の問題でありますとか、いろいろな形で交通局全体が一つになって動いていかないと、なかなかこういうところはきちっと対応ができていけない、そして運転士さん皆さんたちだけが命を預かっているんだという認識ではなくて、交通局自体がそういう認識を持たないと、運営する側、そして実際乗務する側が一体とならないと、そこはなかなか解決しない問題ではないのかなと思うところでもあります。
その一番多分いい例が交-1であるように、落ち葉で80メートル手前から速度制限しながら、25メートル手前でブレーキ操作を始めた。そして33メートルオーバーした。これというのは、多分今までもあっていたんだろうな、80メートル手前でブレーキかけて、25メートルかけていたら多分オーバーするんではないかなというのは、想像がつく問題ではないのかなと、私はちょっと考えているところです。
これについて運転士の皆さんたちと今まで何年も運転をされてきて、こういう時期はここら辺では遅いのかなという認識も多分あられたんではないかな、もし新しく採用された方々は、実績としてなかった部分というふうな捉え方をしっかりやっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 当該の運転士は、ここに記載ありますけれども、7年8か月と比較的長い経験年数を持っておりますけれども、このように滑ったという経験はないと話しておりました。
ただ、他の運転士に聞くと、当然このイチョウの時期というのは、滑走した経験を持っている運転士がたくさんおりまして、そういったところでスピードの制限だったりというのを用心しながらやっているところでございます。
当然ながら、このイチョウの木が生えているところはそういうふうになるんですけれども、ここの箇所というのが実はあまりイチョウの木がないところでございまして、交通局前とかあるところのイチョウから恐らく風とかで吹いて、そちらに流れていったのかなというところ、位置的なところから運転士もあまりイチョウの影響はないと判断したのかもしれないですけれども、ドラレコを見ると確かにレールの上に結構イチョウの葉っぱが何十枚、100枚以上とかというところで乗っておりましたので、当然ながらそういう滑走が起こり得る状態だったのかなと。ただ、経験は、本人はちょっとそういったところが今まではなかったというところを申しておりました。
説明は以上です。
◆村上誠也 委員 確かに、そういうこともたくさんあるかと思います。しかしながら、そこでこういうインシデントが起こったという事実には変わりはないと思います。
そこで、もしこの前後で運転士さんが気づいたらば、次からあの辺は今日は危ないぞという注意喚起をする必要性は必ずあるんだろうなと思います。これを見ただけでも、25メートル手前でブレーキ操作して33メートルということは、60メートル近く手前からもう操作を始めないと、このときは、この時間帯含めてやらないと間に合わないぞという認識を持っていただく。それが必要かな。
でないと、我々も普通車を運転したりしますけれども、危ないところは注意して、あそこは危ないよという情報交換したりというのが多分出てくると思いますので、そういうところを認識づけというのをしっかりやっていただかないと、運行側、そして乗務していただく運転士の皆さんたちと一緒になってやっていただくというのを心がけていただきたいと思います。
以上です。
◆井本正広 委員 齊藤委員からも最初に指摘があったんですけれども、今の件でこれだけインシデントが続いているのに、運転士さんは信号冒進とは考えず、指令への報告を行わなかった。私はここが一番肝だと思います。これを受けて、事業管理者としてどういうふうにこれを思われたか、この後、どういう行動を取られたか、そこをお聞きしたいと思います。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今お話ですけれども、ヒヤリ・ハットという観点からも、今村上委員からも話がありましたけれども、そこは必要だったと思っています。
ちょうど落ち葉の時期に私も何度か乗車する中では、きちんとどこが滑ると無線で報告をしている運転士が何人もいました。そうすると、無線の中で分かったという話と、大至急砂まきをそこの場所に向かわせるからとか、今どこでやっているから、その後そこに行かせるからとか、人によってはどれくらい滑るのかとか、そういった緊急度を図るとかというやり取りも、電車と指令でやっているというのも、私何度も電車の中でそういうのは見聞きしました。
今回のことはインシデント云々もそうですけれども、ヒヤリ・ハットという観点からも、数分後には次の電車が来るわけですので、それをしとればそこは用心して、次の運転士は特に用心して運転したと。この運転士については、幸いにして事故等はありませんでしたけれども、その次に滑った場合にはそうとは限りませんので、そういった観点からも、重要だというお話は、この当該運転士も含めて話をしたところです。
確かに自分だけに考えてしまっていて、車の通行にも、当然事故も起こっていないし、車の通行にも影響がないからしなかったということは聞きましたけれども、そうではなくて、全体の安全を高めるという観点でも、あなたの報告というものは大事だったんではないかという点については、当該運転士と話をしたところでございます。
以上です。
◆井本正広 委員 今回の検証委員会の最終報告の中で、課題と対策の中で、人、もの、環境、管理、基本ルールの不徹底ですとか、視野が狭く偏った対策、ヒューマンエラーですとか、モチベーションが低いですとか、かなりすごい指摘があっております。
最終的に、組織風土の改善等ということが書かれているわけなんですけれども、そういう観点でヒヤリ・ハットはあるんですけれども、報告をしなかったということについて、これは組織として考えていかなければいけないというのが一番重要ではないかなと。様々原因はありますけれども、まずは風通しが悪い、組織報告がないということが大変一番重要だと思っております。
この報告書を受けて、6項目について書かれておりますけれども、これだけではちょっと足りないんではないかなと思います。ですから、またこの報告を受けてしっかり組織風土、風通し、モチベーション、本当にこれからもっともっと深く検討していただきたいと思います。すぐにできることではないかと思いますので、よく検討を深めていただきたいと思います。
以上です。
◆齊藤博 委員 延伸事業について簡潔にお答えいただければと思いますが、軌道運送高度化実施計画に関して、これは今までのインシデント等を勘案すれば、延期せざるを得んというのはよく分かります。
その中で、軌道運送高度化実施計画の中に直接的に盛り込まれておりますのは、例えば上下分離だったりとか、市電の延伸、こういったスケジュール感をこの計画に当然うたわれるわけでありますけれども、上下分離については、市長からも1年程度延期すると、それから延伸については、改めてスケジュールの再検討を行うというようなことが示されております。
ただ、そのほかにも上下分離やそういった延伸のスケジュールのみならず、例えば従前から議論が出ておりました職員の皆さん方の処遇改善、給与水準を引き上げましょうというような話が出ておりましたり、これは一応4月から予定をしているはずですけれども、それでありますとか、あるいは今年6月から予定をしましょうということで、運賃の200円への値上げ、こういったものに軌道運送高度化実施計画を見直すことで影響が出るのか出ないのか、特に職員の処遇、4月からの改善に向けた取組に変更はないのか、その確認と、それから6月をめどに200円の運賃に改定をしたいというような動きに、まだ確定ではないにしても、その動きに変更はないのか、そこ2点まずお聞きしたいと思います。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 まず1点目のお尋ねの処遇改善等による影響等についてでございますが、高度化実施計画自体は法定で定められている項目でございまして、高度化事業を実施する区域内容、それから高度化事業の実施の予定期間、そういったものが法定の項目として定められております。
処遇改善については、法定の項目ということではございませんが、高度化実施計画の中に参考資料として収支状況をお示しする形になりますので、処遇改善による人件費ですとか、あるいは車両の更新とか、そういったもので収支が変わったものについては、そこの収支状況の中で反映させていくという形になります。
2点目の今後のスケジュール感についてでございますが、まず処遇の改善につきましては、今年3月の定例会におきまして、条例改正等を上程させていただきたいと考えております。それで可決いただきましたならば、4月から乗務員等の処遇改善は、上下分離導入に先行して行ってまいりたいと考えております。
具体的には、給料表の拡充だったりとか、あるいは扶養手当、住居手当といった新たな手当の支給というところを予定しております。
それと運賃改定についてでございますが、運賃改定につきましても、直接的に高度化実施計画の項目ということではございませんが、ただ、これにつきましては、上下分離導入の有無にかかわらず、直近の交通局の経営状況、非常に人件費高騰や物価高騰で厳しい状況でございますので、上下分離実施の有無にかかわらず、導入すべき運賃改定を行いまして、処遇の改善、あるいは安全の再構築とか、そういった面に充てさせていただきたいと考えておりますので、これにつきましても、3月に条例案を上げさせていただきまして、その後、国への申請、認可を得て、6月に運賃の改定をさせていただければということで考えておりますが、また改めまして、3月の定例会でお示しをさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
職員の処遇は、予定どおり4月からということで改善を図っていただきたい。そんなふうに予定もスケジュールも変わらないということでありました。
それから、運賃の値上げについても6月から200円にということで、ここも変わらないということでありますけれども、今年に入ってからまた今後インシデントが起こるような事態に直面すれば、こういった計画に市民の皆さん方、あるいは利用者の皆さん方の御理解を得にくくなるというようなことにもつながってきますので、ぜひそういう意味においても、計画遂行できるような環境、安心・安全な運行に努めていただきたいと改めて思うところでもあります。
それともう一つようございますでしょうか。
○田中敦朗 委員長 どうぞ。
◆齊藤博 委員 市電延伸の実施設計、これ市電延伸そのものの計画を延期するということでありますので、今年度中に実施設計を行うとなっておりました予算です。今年度、令和6年9月に承認されている予算なんですけれども、4億2,000万円、これ補正かけますか、かけませんか。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今年度9月補正の中で、市電延伸の実施設計に係る補正予算可決いただきまして、今年度の契約を目指して事務を進めてきたところではございます。
ただ、こういった今の市電の状況を鑑みまして、スケジュールについて再考させていただきたいということで、今後の進め方についてお諮りしているところでございますけれども、今後議会からの意見も踏まえまして、最終的には判断したいと考えておりますが、延期ということになれば、今年度の予算については減額補正を行うという形になろうかと考えております。
以上です。
◆齊藤博 委員 もう一回ちょっと確認なんですが、減額補正でいくのか、あるいは繰越しというやり方もできんことはないかもしれませんが、それは担当局でお願いします。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今回の実施設計に係る予算につきましては、国からも交付金の内示をいただいているところでございます。市単独予算ということであれば繰越しということも考えられるんですけれども、今年度設計を実施しないということになると、なかなか国費の繰越しというところが難しくなると。そうなると、一旦全額ですね、減額せざるを得ないのかなと考えてございます。
以上です。
◆齊藤博 委員 当時の説明資料の中に、今まさに出ました国庫補助金72億円程度が見込まれていると報告を受けております。延期することによって国庫補助金そのものの妥当性といいますか、いやいや延期するならちょっとそこまでは担保できんよと、当然国も今年度の予算として上げていたところでもあろうかと思いますし、その影響ですね。延長することによって、今まで令和6年度に示された総事業費が141億円と見込まれております。その中でその半分、国庫補助金が72億円というような見込みを上げていただいていますが、この総事業に大きな影響がないのかどうなのか教えてください。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 今回の市電延伸の事業スケジュールの見直しにつきましては、計画内容そのものに何か問題があるということではございませんで、今の市電の状況を鑑みて、一旦立ち止まるべきではないかと考えているところでございます。
そういったことから、延伸事業の計画内容、総事業費141億円というところでお示ししていますけれども、そこについては変更はないといったところでございます。
国費の影響でございますけれども、まず前提としまして、今、国から内示をいただいている予算というのは、今年度実施する予定だった実施設計に対する予算4億2,000万円に対する国費の内示をいただいていたところでございます。その後の用地買収、工事実施に当たっては、その年度の必要な額をその都度要求していくという形になってございますので、この72億円という国費が担保されているというわけではございません。
ただ、今、国へ市電の状況というのを説明していく中で、国からも今の現状については御理解いただきまして、予算については今後市の方針を踏まえて調整をさせていただくというところで協議を進めているところでございます。
以上でございます。
◆齊藤博 委員 ありがとうございました。
今のところ延期はするけれども、総事業に変更はないというようなことで理解をさせていただきました。ありがとうございました。
◆上田芳裕 委員 延伸に関連しまして、今、国からの補助関係の影響はないというようなことでお聞きしましたけれども、昨年9月に実施設計の予算を可決して、熊本市でもいろいろな動き、募集とか、動きはあっていますけれども、そういったところで業者さんへの影響がないかというところが1点と、昨年、市電延伸の周辺の皆さん方へ住民説明会を行って、延伸の計画であったり、用地買収について大体どこら辺のエリアが計画されてあるとか、工事そのものの複線化、単線化とか、供用開始が令和13年度とかというところを詳しく説明をされていると思っていますけれども、住民の中から、その中には一日でも早く延伸をしていただいて、市電の効果、自分が乗ることへの効果、渋滞が減ることへの効果を含めて望まれている方がいらっしゃると思いますけれども、そういった方々への今回市長からのマスコミ報道で皆さん知られたと思うんですけれども、細かな説明であるとか、そういった部分は何かお考えございますでしょうか。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 まず、業者への影響、入札等に関することかと思いますけれども、発注業務に当たって設計業務に必要な見積り等を取っているといったところがございますけれども、まだ設計の委託の発注に係る公告等行っている段階ではございませんので、それについては今のところ影響はないかなと考えてございます。
2点目の住民説明会、あと地権者、中には進めてほしい方もいるといったお話でございますけれども、そのとおりかと思います。まだ延期ということを決定しているわけではないんですけれども、延期するということになれば、当然地域の住民の方々、地権者の方々に今の市電の現状を説明した上で、御理解を求めていく必要があるのかなと考えてございます。
以上です。
◆上田芳裕 委員 分かりました。
業者の方へは影響がない、住民の皆さん方へはスケジュールの変更を決定していないという言われ方をされるんですけれども、正式には決定ではないんでしょうけれども、そのような方向で進められていく、決定というのはどの場でされるか、今度の定例会になるのか含めて明確にお示しができればお願いします。
◎太江田真宏 移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 まず、先週の金曜日に市長から、市長の考えとして、延期も含めたスケジュールの見直しを指示したという市長の考えを表明されたところでございます。
今回、今の現状を踏まえて、一旦立ち止まるべきではないかといったようなことについて、この委員会の中でもお諮りした上で、御意見をいただいた上で、最終的には判断していきたいと。その結果、延期するということになれば、今度の議会、第1回定例会の中で減額の補正予算案を上程させていただいて、分科会等で御議論いただくと。そこで可決されれば、そこで延期が決定ということになろうかと考えております。
以上です。
◆上田芳裕 委員 分かりました。
そのような心づもりで定例会に臨んでいきたいと思います。
◆上野美恵子 委員 今の延伸の件で、私から1つお尋ねは、さっき齊藤委員もちょっとお触れになったんですけれども、いろいろな交通局のインシデントが続いているので、すごく市電に対する市民の皆さんの不信というか、疑問というかが、とても過去にないくらい、心配も含めて高まっているかなと思います。
そういう中で、さっき運賃値上げは、財源にもなるから粛々とするのだという御答弁であったかと思いますけれども、市民感情からするなら、そこのところの理解というのは、局側はそうかもしれないけれども、市民の感覚としては、非常に理解し難いと私は思います。
値上げの理由も、これまでの一般会計の繰入れのこともあるし、もう一つは乗車人員のこともありますし、いろいろ理由はありますけれども、それをこれだけ市民の疑問が高まっているときに、いや、それはそれ、これはこれだから値上げはしますというのは、どう考えても納得しないのかなと思うんですよね。
それこそこんな時期だから、安全をきちんと確保して、担保した上で、そういう安全の条件が確保された上で、運賃についても提案をしますということならば、理解もあるかもしれないけれども、全然市民の感覚と交通局としての対応というのは、齟齬があるのではないかと思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
◎吉岡秀一 交通局総務課長 委員から御意見いただきましたとおり、現在市電におきましては、昨年16件のトラブル等がありまして、信用は失墜しているという状況かと思います。
ただ一方で、繰り返しになりますけれども、交通局の経営状況というのは非常に厳しい状況でございまして、こういった安全対策をしっかり再構築していくこと、それから乗務員の処遇改善を行っていくことということから運賃の改定をお願いするものでございまして、市民の方々へも丁寧に説明を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆上野美恵子 委員 いろいろおっしゃっても、なかなかそういうのには市民感情としてはついていけないんではないかなと私は思います。
運賃の件についてはもう少し丁寧な取組というか、今の繰り返しではなくて、市民に対しての丁寧な説明とか、意見聴取とか、そういうことを改めてしないと、利用にも関わってくるんではないかなと思いますので、その点はよろしくお願いします。
もう一つは、先ほどから意見が出ておりましたインシデント等に関する検証委員会の件で、いっぱい聞きたいことはあったんですけれども、1つに絞って聞きます。
概要版と本編と資料として以前いただいていましたので、拝見したんですけれども、いろいろ現状も明らかにしながら検証委員の方々が検討されて、そしてまとめをつくっておいでになったんですけれども、まとめに関わるところで、委員さんたちから、委員会としては問題解決に向けた視点が2つあるということで、1つは、相互尊重と理解を促進する視点の転換、もう一点が組織ぐるみの意識と行動の変革というこの2点を上げられて、提言としては、概要版では、次のページに7点の項目を上げられていたんですよね。
これも相互信頼から始まって部署間の風通しであったり、意識と行動の改革であったり、新しい視点からの研修や教育であったり、バランスの取れた人材確保とか、仕事環境の整備ということで、いかにこの事業に関わる交通局の方々の、交通局という組織そのもの、そしてそれを構成する職員のお一人お一人の在り方について問われていたのかなと思って拝見しました。
そういうのを基にして本編を読んだんですよね。それの77ページ~78ページのところに向けて気になること、提案したいことなどというのがあったんですよ。そこでハラスメントのことが述べてあったんですよね。職員からの多分御意見として、嘱託職員との格差がパワハラ、モラハラの温床になっているということと、それからパワハラ等が多くて毎年数名が心を壊しているという言葉があって、それに対する委員さんたちの所見なのかな、まとめみたいなものがあって、それについての範囲や程度は明らかではないが、ハラスメントをはじめとして職位間に軋轢が存在していることがうかがわれるという記載になっていたんですよね。
これを読んだときに、さっき紹介しました今回の検証委員会の提言、そのまとめに当たる部分が、この組織と一人一人の職員の在り方に関わる問題であっただけに、そしてこの本編には出てくるんだけれども、概要版にはパワハラなんて言葉は出て来ないんですよね。
そして、本当に交通局が今回のインシデントという重大な事態の多発を受けて、組織を改革して、お一人お一人の職員の皆さんが一丸となって、交通局の今後の運営について改善していこうと思うためには、こういうパワハラをたくさん訴えている人がいながら、こういうことを改善せずして先に進むというのは、私は難しいんではないかなと思うんですよね。
今はいろいろなところで、いろいろな場所でこういう問題が多発していて、問題になって、でもこの向き合い方をきちんとせずに、疎かにしてしまえば、先々に禍根を残していくことにもなるし、どんなに言葉ではいいことを言っても、結果的に何一つ改善にならないと思ったんです。
これがきれいな提言の概要版になったときに全くなくて、一体どうするんだろうと思ったんですけれども、この問題については、私はきちんと具体的な事実をそこの局の中では明らかにしていきながら、意見をおっしゃった方たちに対して、納得のできるような方向性として改善方向というのを見いだしていかないと、職員が一丸となってこのインシデント問題に取り組んでいく、改善させていくというふうにはなっていかないんではないかなと思ったんですけれども、どのように今受け止めておられますでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 検証委員会が5月から始まりまして、そこと併せて事業管理者、次長と運行管理課長、私、当時、副課長でしたけれども、4人で運転士の方の全員と、20人ずつぐらい面談をいたしました。
そういった中でも、確かに人間関係の話とかが出てきまして、運転士が大体10年ちょっと経験すると、監督職になるという、営業所の中の立場というのがございますけれども、運転士が今会計年度任用職員、こちらで嘱託と書いてありますけれども、そういったところの立場で、監督さんの中にはもともと交通局採用の監督さんがいらっしゃるといったところで、人間関係の中にちょっと壁というか、そういうのがあるというのは、そういう面談の中で感じ取れるところはありました。
ただ、それぞれの方ときちんと向き合って話をして、そこで自分たちができることというのをやっていて、進めていかないと何も変わらないのかなと思っておりますので、その後にも事業管理者は、例えば工場の技工さん全員と面談したりとかされていますし、そういったことを繰り返していって、聞いたことに関して対応していくということをやっていきたいと思っております。
以上です。
◆上野美恵子 委員 全ての運転士さんと面談をなさったときには、おぼろげにそういう実態があるのではないかという程度での多分訴えであったと思うんですよね。はっきりパワハラがあるんですよとかと、個別に面談しているときに自分自身をさらして言えるような方というのは、多分おられなかったんだろうと思います。だけれども、あえてこの職員の調査の中で出てきているということは、事実があるけれども、名前を出してまでは言えないという、そういう問題だからですよね。
だから、ちゃんとした対応をしないと、これというのはうやむやになっていくし、改善していかないと思うんですよね。だから、どういうふうにしたら一番いいのかというのは、ここで具体的に私から言えないんですけれども、ただ、これをこのまま放置はしてはいけないと思います。
何らかの形でそれを改善していく、具体的、個別的にやっていけるようなことをしていかないと、このインシデントの改善の検討の提言そのものが上滑りしてしまうというか、上っ面のものになってしまって、本質的なところでは、職員が一丸になるということは、できないんではないかなと私は思いますので、この点については、さっき私が言った軌道とかハード面はもちろん基本ですけれども、その上によって立つソフト面における人というか、そこをきちんと束ねていって、みんなが本当に一丸となってやっていく、そこにおける取りまとめをしっかりしていく。そういう意味での交通事業管理者の役目というのがすごく大事かなと思いますので、ちょっと答えは出ることではないのかもしれないけれども、事業管理者の御意見を聞いておきたいと思います。
◎井芹和哉 交通事業管理者 今御指摘いただいたことについてでございますけれども、確かに私も職員一人一人と話をする、ずっとしておりますけれども、そういった中でも、今委員の言われましたように、直接的にとかということはなくても、話というのは出ております。
そこにはどうしても、何というんでしょう、車両も古くて、運転士とかも減っていってということがあって、その中で回していかないといけない。運転を欠便することなく回していかなければならないということで、ちょっときつい言い方だったりとかということもあったのではないかなと思っておりますし、一人一人の話を聞いて全体としてどういったことがあったのかというものを突き止めることは当然ですけれども、そういう観点で減便とかもして、まずは働きやすい環境とかということに努めたところです。
といって、それが全てではありませんので、何がどこに、訴えられている方のところがどこなのかというのはきちんとしていく必要があると思っております。
すみません、先ほど本文と概要版の違いということも言われて、そこについては申し訳なく思っておりますけれども、その概要版のことをすればいいと思っているわけではなくて、きちんと報告書全体を精査して、そこに書かれている課題というものについては、全て対応していくということが基本であると思ってございますので、きちんと職員みんなで内容を精査して対応を考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
◆上野美恵子 委員 ここには、この問題については信頼関係だということが書いてあるんですけれども、そのことを抜きにして、今後の交通事業の改善とかはあり得ないなと私は思いますので、ぜひ心して対応していただくようにお願いをしておきます。
◆島津哲也 委員 交-2の裏面のところで、先ほど古川委員の質問がありましたけれども、1月15~16日に緊急の工事がなされたということで、非常に緊急で安全性が確保ができないということが書いてありますけれども、15日の始発から区間運休ということになったということで、市民の方にうまく伝わらず、利用者の方に混乱を招いたというニュース報道も流れていました。SNSでの発信をされたということですけれども、公式のLINEだけだったのでしょうか。
◎荒木敏雄 運行管理課長 まず、報道に深夜だったかと思いますけれども、投げさせていただきました。あと、市のホームページ、局のホームページ、あとはXとデジタルサイネージ、使える手段というのは、こちらとしても使って広報したところでございます。
以上です。
◆島津哲也 委員 そうですね、いろいろなものを使って、学生さんだとインスタとか、そういうのも使われていますし、ちょっと調べましたら、交通局さんもXがありますけれども、交通局さんのXからは発信がなかったので、こういうのも使われたらいいのかなと思いました。
皆さんにできるだけ伝わるように御努力いただければなと思います。
私からは以上です。
◎荒木敏雄 運行管理課長 Xでもたしか投げ込みはしていたかとは思います。すみません。
◎井芹和哉 交通事業管理者 補足で。
ずっと出ているのが残りますと混乱しますので、次の局面になったときには、落としたりとかとしておりましたので、経緯が全部は出ていなかったかと思います。すみません。
○田中敦朗 委員長 ほかございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 ほかにないようであれば、本日の調査はこの程度にとどめたいと思います。
さて、前回の本委員会において決定しております参考人の意見聴取のための委員会開催につきましては、改めて参考人との調整が必要となりますことから、本職に御一任いただき、決定次第連絡をいたします。
これをもちまして、地域公共交通に関する特別委員会を閉会いたします。
午後 0時43分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 三 島 健 一 総括審議員 村 上 英 丈
総合政策部長 黒 木 善 一 政策企画課長 松 永 直 樹
〔財 政 局〕
局長 原 口 誠 二 財務部長 濱 田 真 和
財政課長 津 川 正 樹
〔都市建設局〕
局長 秋 山 義 典 技監 上 野 幸 威
都市政策部長 高 倉 伸 一 都市政策課長 飯 田 考 祐
交通政策部長 迫 本 昭 交通政策部首席審議員
濱 口 佳 久
交通企画課長 大 川 望 移動円滑推進課長 徳 田 隆 宏
移動円滑推進課審議員兼市電延伸室長 自転車利用推進課長酒 井 伸 二
太江田 真 宏
〔交 通 局〕
交通事業管理者 井 芹 和 哉 次長 松 本 光 裕
総務課長 吉 岡 秀 一 運行管理課長 荒 木 敏 雄
運行管理副課長 北 添 友 子